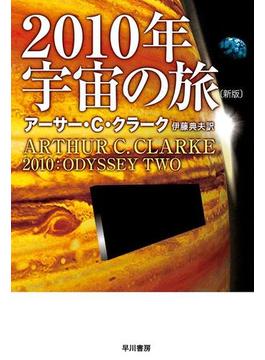クラークによる続編
2020/05/07 07:24
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:のび太君 - この投稿者のレビュー一覧を見る
映画「2001年宇宙の旅」についてのクラークによる続編で、ハラハラドキドキする場面の連続で最後まで飽きずに読める。
投稿元:
レビューを見る
この題名の年になっちゃいましたね。まったくこのお話のような宇宙生活は実現できていませんが。せっかくなので記念に今年中にもう一度読んでおきたいと思います。
投稿元:
レビューを見る
1982年の大学3年生の皆さんごめんなさい。2010年の僕たちの悩みは未だに狭い地球の中で、いかに食いっぱぐれないようにするかとか、夢をとるか安定をとるかとか、どうやったらあいつを彼女に出来るかだとか、自分の魅力って何なんだろうかとか、なんであんなやつがとか、世の中結局金なのかとか、社会が悪いとか、自分が悪いとか、顔か性格か金かとか、学歴とか、才能はあるけど運がないだけとか、本気出してないだけとか、あんなもん本当は意味ねえよとか、高校時代に戻りたいとか、中学時代に戻りたいとか、ええい生まれ変わりたいとか、愛って何とか、生きるのはめんどくさいとか、考えすぎだよとか、人生って何だろうとか、まぁそんなとこなんです。でも結構、すごく大事なことじゃないかと思うんです。4年生ときたらそれを冷めた目で見てくるのです。
1982年の大学3年生の皆さんごめんなさい。そうです。そのへんは変わらんのです。宇宙とかそんなん、ちょっとよくわかんないっす。まだまだあなた達とやけ酒で盛り上がることができてしまうんです。同じグチを抱えておるのです。楽しく飲もうぜ!
ああ、でもあなた達ほど景気良くないし、80年代のプラザ合意には恨みがあるのであしからず。
時は2010年。今年読むしかないだろうと、買った。帯には茶番な宣伝文句。
≪巨匠クラークが描いた未来に人類は到達できたのか?≫
しばらくの沈黙の後、ハルは答えた。
「すまないデイブ、世界経済にモノリスが立ちはだかっている。着陸不可能だ。」
―と、いう皮肉が浮かんでしまうわけだが、いやいや、この本から学ぶべきものはそういう話じゃない。クラークの科学技術の発展に対する純粋な希望に目を向けるべきなのだ。いつか人類が宇宙の神秘に出会うであろうということを信じるのだ。
それが今世界の腫瘍を鮮明に映し出すかもしれない。光を当てなければ見えるものも見えない。今も昔も変わらぬ宇宙の法則である。(10.09.22)
投稿元:
レビューを見る
2010年が始まったとき、〆はこの小説で決まっていた。
2001年が綿密な設定と謎にわくわくしていく古典的な名作だったのに比べ、
この作品はどちらかというとそれの詳しい解説やエンターテイメントの面を強調している。
実際に2010年になってもこの時代の科学力はこの小説に追いついて来れないし、明らかな矛盾が見つかるまでも無い。
そして古臭くもない。
人間の、クラークの想像力にただただ感服するばかりである。
投稿元:
レビューを見る
2001年宇宙の旅の続編…と言わなくてもタイトルでわかりますね(^^;)。
あれで終わりかと思いきや、さらにその後日談が前作の登場人物と新登場人物で繰り広げられます。
前作は映画と小説で設定が違うよ、という前提で話が作られていたのに対し、今作は前作の設定は設定だけど映画の設定を踏まえて今回は書くよ、というスタンスなので初めは若干混乱します。
あんまり詳しく書くとアレなのですが、2001年で映画→小説と進めると「あ、設定が違うんだ、小説はこうなんだね」と納得して終わるわけです。
で、その影響下にあって続きのつもりで読み始めると2010年は「映画はこうだったからやっぱり映画の設定で続けるよ」と宣言して始まるわけですがやっぱり小説のつもりで読んでるので「アレ?小説は違うよね?」という疑問があちこちに出てきて序盤は集中できませんでした。二回同じ事を言いましたかね?
まぁ内容的には大事なところは前作の設定でもっと広げた状態になるので面白いのは面白いです。あぁこういうところに持っていくんだ、という感覚というか…でもイメージは『幼年期の終わり』と同じですよねぇ(ぉ
投稿元:
レビューを見る
2001年より面白かった.
ちょうど「幼年期の終わり」をもっと洗練させた感じの内容.
途中のHALとのからみもどうなるのか気になって一気に読んでしまった.
投稿元:
レビューを見る
もはや説明の要すらない大傑作「2001年宇宙の旅」の9年後を舞台とした続編。設定上は、小説版ではなく映画版の続編となっており、遺棄されたディスカバリー号が漂流しているのは木星衛星群の宙域です(この辺りのいきさつは、クラーク自身による「作者のノート」に詳しいです)。
宇宙飛行士4人が死亡、1人が行方不明となったディスカバリー号事件から9年後、木星衛星群探検のきっかけを作ったヘイウッド・フロイド博士は、ディスカバリー号回収のためにHAL9000の生みの親・チャンドラ博士と共にロシアの宇宙船に乗って木星へと旅立つ。9年前と何ら変わらぬ政治的な駆け引きに翻弄されつつも、ボーマン船長が残した謎のメッセージを頼りに木星周辺での探索を続けるフロイド博士が観た事件の真相、そして更なるモノリスの企みとは?
前作の小説版は、いわゆる「ハードSF」としてきっちりと作り込まれた物語的ダイナミズムが最大限の効果を発揮した傑作だと、鴨は思っています。映画を観る限りだと何が何だかよくわからないんですけどねヽ( ´ー`)ノ小説版では、TMA-1の存在理由もHAL9000が発狂する過程もボーマン船長が変容したものが「何か」もSFとして全てちゃんと説明されており、SFとしての(実にクラークらしい)オチも付いています。
続編である「2010年」も、前作のテイストを引き継ぎ、「ハードSF」として隙のない、きっちりと美しく構成された物語世界が展開されています。まぁ、モノリスによる変容後のボーマン船長(であったもの)が登場したり、コンピュータであるHAL9000の「意識」がディスカバリー号消滅後にも精神体として生き残ったり、多分にオカルティックかつスピリチュアルな描写もそこかしこに見られるのですが、クラークのスゴいところはそれがハードSF世界の一風景として何ら違和感なく存在しうるというところ。ボーマン船長(であったもの)がクルーにとある警告を発して以降の物語の緊迫感は、タダものではないです。最終的に警告を受け入れたクルーが危機一髪で木星圏を脱出する描写に、鴨は痺れましたね。これぞハードSF!
この「ハードSFっぽさ」に加えて、いかにもこの作品がクラークらしいポイント。それは、地球人類の未来に対するニュートラルな視点です。
物語の途中で、どこかで読んだような気がする一章が挿入されます。実はこれ、前作「2001年宇宙の旅」と全く同じテキストによる、モノリスの存在理由を説明する一章なのです。地球人類のちっぽけな自尊心など全く意に介さない、巨大な存在の提示。そして、物語の最後の最後に登場する、モノリスによって選ばれた「地球人類以外の知性」。地球人類の存在意義を徹底して客観的に見つめる、「幼年期の終わり」にも通じるクラークの冷徹な視線を感じます。
そんな壮大なヴィジョンを提示しつつも、その一方でフロイド博士の離婚騒動とか宇宙船クルー内の恋愛模様とか、ものすごく卑近な地球人類ならではの人間模様も描いてみせたりして、あぁもぅこれだからクラークやめられないのよヽ( ´ー`)ノ
面白いです!
投稿元:
レビューを見る
友人から「蛇足」と聞いていたが
後日談?くらいにのんびりと読めば良いと思う。
取り敢えず彼と和解出来たのは本当に良かったと思う。
良かった、本当に良かった。
投稿元:
レビューを見る
やっと読み終わったーー。
アメリカとソビエトの対立と和解なんかが話の視点にかなり入ってきてて2001年とはだいぶ雰囲気が違う感じ。
何か2001年からひたすらハルが不憫なのう…。あんなに純粋でいい奴やのに…。
投稿元:
レビューを見る
2016/11/09-2016/11/10
星4.3
『2001年宇宙の旅』の続編。この後に2061年、3001年と続く。
2001年に比べて随分ダイナミックな文章になっていて、すぐ読めた。2001年の方で投げっぱなしだった疑問点がいくつか解消するような、そういう話だった。ここからどうやって2061年へと時代が移るのだろう?
投稿元:
レビューを見る
壮大すぎてなにがなんだかわからないといったところはあるが、やはり今回もSFらしいSFで、満ち足りた読後感。
ハルとの最後のやりとりは緊張感がある、そして小さなどんでん返しもチャンドラ博士のユーモアが垣間見られて愛おしい。偏屈な人がここぞという時に見せる笑顔って恐ろしく魅力的だよなーと。
そして、ハルとボーマンの和解もよかった。ボーマンの独白部分の描写や2人?の会話はできる短く抑制が効いているが、ボーマンがハルに対し懐かしさや親愛の情を感じていることが、よくわかった。意識生命体となった彼は、言葉以外の手段でそういったものを伝えて来た。著者の手腕だなー。
投稿元:
レビューを見る
このSF小説は、第二部であり、前書の「2001年宇宙の旅」でコンピューターの原因不明事故の解明するために、主人公の科学者が乗り出すがそこで意外な人物が。
投稿元:
レビューを見る
読んだ後に映画も鑑賞。前作のHALの反乱の謎は解けるが、新たな謎というか展開。新たな展開で、地球を含む惑星の軌道や気候が変わってけっこう大変なコトになりそうだけど、その辺は無かったことになるのかな。""
投稿元:
レビューを見る
これも、結構前に購入したのだが、なぜかそのまま積ん読になっていた。2001年宇宙の旅を読んでから10年以上経っており、内容も忘れていたので、最近また2001年を再読してから読んでみた。
続編だと聞いていたのだが、(新販)ということもあってか、色々と手直しをしたと書かれていた。旧版の方は読んだことはないのだが、やはりその時代を反映した形で書き直されるのだろう。2001年では米国とソ連という大国が出ているが、今回はすでにソ連はなくなっている。この小説での国際情勢の変化はよくわからないが、今回の内容は、米国とロシアの協力がテーマに書かれていたように思う。
主人公が、ボーマンからフロイド博士に変わっている。ボーマンが星の子になった後にどうなったかは、残念ながら今回もよくわからなかったが、まあ、このわからないところが魅力的なのかもしれない。
今回は、HALとチャンドラ博士の会話はあるものの、どちらかというと人間同士のやりとりがメインのドラマのように感じた。所々わからなくなったり、前回は土星がターゲットだったはずが、いつの間にか木星に焦点が当てられていたり、流れがなかなか複雑だが、物語は楽しかった。
もう2010年は一昔前になろうとしているが、未だ人類は有人ということでは木星にたどり着いていない。実際、「ザガートカ」みたいなものってあるのだろうか。昔はそういうものに憧れて、良く空想にふけったりしたが、今でもこんな小説を読むと、当時の高揚感が蘇って来る。
しかし、結局TMA1とかザガートカについては、決着していない。これは続編で明らかになるのだろうか。まだ続編を読んでないので楽しみである。
投稿元:
レビューを見る
ストーリーが映画の続きだったので、ちょっと混乱しながら読み進めた。
全体的にもうちょっとすっきりしててもいいかなと思わなくもなかった。
映画も観たけど、まぁなんというか観なくても別に良かった。
2010: Odyssey Two(1982年)