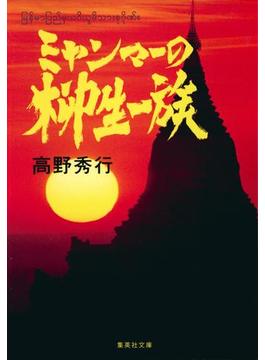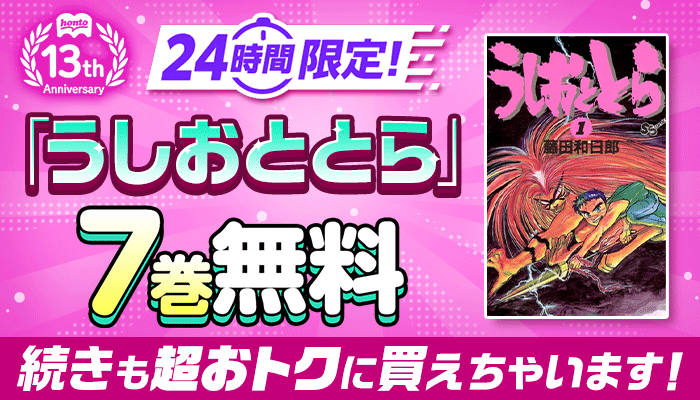ミャンマーを江戸時代にたとえるというその発想、お見事ですぞ。
2006/07/16 14:14
11人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:サトケン - この投稿者のレビュー一覧を見る
「ミャンマーの柳生一族??? なんじゃこりゃ、際物めいた代物だな・・・」と思い、書店の店頭で何度も目にしたが手にとってみることもしなかった。結局、ひまつぶしのために買って読んでみることとしたのだが、中身は、っていうと、笑える、笑える。ミャンマー珍道中なのであった。
私自身、今から10年前にミャンマーを一人旅したことがあるので(その当時はなんとANAの直行便が関空とヤンゴンを結んでいた)、高野氏がミャンマーという国の本質を的確に描いていることに大いに感心した。ミャンマーを江戸時代にたとえるというその発想、お見事ですぞ。
またディテールが実に観察力鋭く、これまた面白い。ミャンマーに関心をもつ人は、だまされたと思って手にしてください。面白くてためになる好著ですよ。
ミャンマーの柳生一族
2021/03/05 13:50
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:雄ヤギ - この投稿者のレビュー一覧を見る
高野秀行が大学の探検部の先輩・船戸与一の小説執筆取材の通訳としてミャンマーに動向するのだが、その監視として政府の情報部から役人が派遣されるのだが、その情報部が軍と対立する首相直属の機関で、軍の弱みを握っているという事から江戸幕府初期に各大名の監視をした柳生一族みたいだということがタイトルの由来。ただ監視に来た男が英語もしゃべれない頼りないやつで、柳生っぽくなかった。
内容的には、ミャンマーの首相が高野さんの本を読んでいると言う点が驚きだった。そして高野さんの他の本でも似たような事があったと思うが、本文でミャンマーの首相と軍の対立を解説したあとに、あとがきで後日談として、政変が起きたと書いて会って驚いた。このあとがきを読んでからもう一度読み返すと、また違った見方が見えてくる。
ミャンマーの人々の生き方を感じさせてくれる貴重な情報に触れられました
2017/03/20 21:11
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:大阪の北国ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者のミャンマー3作である西南シルクロード、アヘン王国と本書の3冊を読破。前2作が著者自身による体験記であり、じっくり現地の人々の風俗や地誌を炙り出していたのに対して、本作は残念ながら船戸与一氏に随行した記録に過ぎずやや表面的な観察記録に留まったところが残念である。日本の江戸期になぞらえ、無味乾燥な他国の歴史を身近なストーリーとして判りやすく説こうとした著者の努力は買うが、柳生一族を持ち出してまでミャンマーの政治動向を解説するのは語呂合わせの域を出ず、あまりに無意味であった。
数点貴重な現地情報を提供してくれたのは 〇空港のゴミ箱をひっくり返すとキンマの噛み滓で床が真っ赤に染まったこと 〇シャン料理も雲南と同じく照葉樹林文化の形跡を色濃く残す食文化であること 〇ミャンマーの一般大衆も極めて人の好い正直な人々であること(これまでの著者の著作では、少数民族目線で書かれていたため、多数派ミャンマー人は敵視目線で描かれていることが多かった)等である。
生きた情報が少ないミャンマーの一般大衆情報に触れられたことが貴重であった。
比喩冴えわたるミャンマー柳生
2023/12/05 13:51
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ブラウン - この投稿者のレビュー一覧を見る
恥ずかしながら江戸時代の勢力図についてはとんと無知なので、著者の比喩がクリティカルなのか判断がつかない。が、登場人物の本名を並べられてもごっちゃになってしまうことがある身としては、見分けがつきやすいだけでも大変ありがたかった。
先輩の取材旅行に現地知ったる通訳として同伴する著者。現地の政治勢力図を展開しながら、描かれる情景は素朴な現地民との交流に相違なく、どこかのいざこざも別世界の出来事のように思えてしまう。日本に住んでいても似たものだろう。政治の話はするけれど実感を持って話題を広げている人は一体何人いることだろう。ミャンマーの市民感覚と言うべきか、そのエッセンスがユーモラスな語りで綴られている。愉快な旅行記である。
投稿元:
レビューを見る
<探検部の先輩・船戸与一と取材旅行に出かけたミャンマーは武家社会だった!二人の南蛮人に疑いを抱いたミャンマー幕府は監視役にあの柳生一族を送り込んだ。しかし意外にも彼らは人懐こくて、へなちょこ。作家二人と怪しの一族が繰り広げる過激で牧歌的な戦いはどこへ…。手に汗握り、笑い炸裂。椎名誠氏が「快怪作」(解説)と唸り仰天した、辺境面白珍道中記。>
ミャンマーって普通の人は行けないとこなんだなー。
投稿元:
レビューを見る
読んだらきっとミャンマーに行きたくなる。
当時の軍情報部を柳生一族にたとえた珍道中。
奇想天外というか面白いというか・・・ガイドブックとは一味違ったミャンマー
この本より前にミャンマーへ行ったことがあるけれどどこかに柳生がいたんだろうか(笑)
投稿元:
レビューを見る
高野秀行に外れなし。
ズバリタイトルそのものにもなっている、この本全体をパッケージしているその設定が秀逸を通り越して芸術。
ミャンマーの軍事政権を江戸時代の徳川幕府に、その中で公安的な役割を担う一団を柳生一族になぞらえている喩えが絶妙すぎてもう笑ってしまう。
もちろん笑っているばかりではなくて、ミャンマーという国を、行かずともできる限り理解するという点において、これほど分かりやすくためになる書籍もないのではないだろうか。
日本で普通に生活していても、「アウン・サン・スー・チー氏が自宅に軟禁されました」などというニュースを見聞きして「ほおー」なんて分かった風に無知のままうなずくことはあるが、その裏に潜む本当の事情や内実(その一部に過ぎないのかもしれないが)に、この本を読むことによって初めて触れた気がして、何だか目から鱗。
冗談じゃなく、学校などの教育現場で、東南アジアの歴史の一端を教える際の教材として使ったらいいんじゃないか、と思ったぐらい。
とてもじゃないが私はきちんと知っているとは言いがたかったミャンマーという国家が持つ特殊性が、とてもスムーズに脳内で咀嚼されたような気がする。
無論いつもの高野節も冴え渡り、ノンフィクションの体をとりながら綴られる物語は読者を惹きつける。
著者のあとがきも含め、現在進行形で混沌が止まないミャンマー国内の政情は、地べたに沿った彼の語り口だからこそ我々にもとても身近に感じられ、特に本編を読み終わる頃にはおそらくほとんどの読者が親近感を抱いているであろう三十兵衛ことマウン・マウン・ジョーを始め、愛すべき柳生一族の行く末は、高野氏ならずとも非常に気に掛かるところである。
投稿元:
レビューを見る
この旅のメンバーが面白い。
著者もだけど、著者の先輩の作家さんも、柳生の一味も…、笑える。
ミャンマーの政治権力者の相関図が柳生一族の系譜に当てはめられていて、そもそも柳生一族についてそんなに知らなかったけど、ミャンマーの政治の状況が結構理解できました。
良くも悪くも強力な指導者が存在しないと国はまとまらないということが分かり、考えさせられました。
投稿元:
レビューを見る
(2007.11.21読了)(2007.11.03購入)
アマゾンで「ミャンマー」をキーワードにして検索したら表示されてきた本の一冊です。題名を見たときは、タイで活躍した山田長政のように、ビルまでは、柳生一族が活躍したという話なのかと勝手に想像して、よく調べる気にはなりませんでした。
ところが、朝日新聞の書評コラムで、最近読んで面白かった本の一冊として「ミャンマーの柳生一族」を取り上げているのを見て、読んでみる気になりました。
現代のミャンマーを日本の江戸時代に見立て軍情報部を柳生一族になぞらえて、日本人に分かりやすく説明しようという本でした。
作家の船戸与一氏から、ミャンマーを舞台にした小説を書くために、取材旅行に行くのでガイド兼通訳兼相談役として同行して欲しいと頼まれ、同行した際の旅行記でもあります。
船戸与一氏の成果は「河畔に標なく」として出版されている。
「もっとミャンマーのことを深く、そして楽しく知りたいと願う方は、高野秀行著「ビルマ・アヘン王国潜入記」と「西南シルクロードは密林に消える」をお読みいただきたい。」(229頁)ということです。
●2004年のヤンゴン(34頁)
ヤンゴンは十年前と比べて、びっくりするくらい変わっていなかった。確かに、高層ビルはいくつもある。車も何倍にも増えた。だが、逆に言えば、それだけである。
●服装(35頁)
ジーンズ姿の若者もいるのだが、正装としても私服としてもロンジー(ビルマ式腰巻き)を着用し続けているというのは驚くべきことだ。ロンジーはさっと洗えて、しかもすぐ乾く。日向に置けば、15分くらいではけるようになる。
●大学(55頁)
1997年にヤンゴン大学を市内から追い出し、郊外へ移転させた。しかも、大学院だけを残し、学部はもう学生をとらないことにしたという。ヤンゴン大学だけではない。マンダレー大学も同じ処分を受けたという。
●豆鉄砲(57頁)
タクシー運転手、ゾウ・ティンの話
「この豆はマ・ペというんだけど、10年くらい前まで政府が栽培を許さなかった。これは銃弾になるからだよ」
●中国国境ムセー(128頁)
ヤンゴンをはじめ、ミャンマーのどこにも売ってないようなしゃれた衣服が店の軒先から、露店からあふれている。仔細に見れば、それは私が中国で見慣れた「箸にも棒にもかからない安物の化学繊維」なのだが、どういうわけか、ここではそれらが光り輝いて見える。
電気製品にしても、DVDプレーヤーのほか、CDラジカセ、ビデオデッキ、液晶テレビ、パソコン、デジタルカメラまで何でもある。
●ビルマ人が日本の会社で働くときのストレス(138頁)
「日本の会社では上司が自分に意見を聞く。会議でもどんどん発言して欲しいといわれる。それが辛い」
●民主主義の恐怖(144頁)
徳川幕府がキリスト教を恐れたのと同じくらい、ミャンマー幕府は民主主義を恐れている。そして、それが排外主義=孤立化=鎖国へとどうしても発展してしまうらしい。
●読書大国(192頁)
ミャンマーは知る人ぞ知る、読書大国である。
ヤンゴンやマンダレーはもちろん、地方のどんな小さな町にでも貸し本屋がある。実際に、ミャンマーでは電池やライターといった日用品を売る店より、貸し本屋のほうがたやすく見つかるくらいだ。それくらい、ミャンマー人はよく本を読む。
現代ミャンマーがよく分かる。ミャンマーについて知りたい方にお勧めです。
著者 高野 秀行
1966年10月21日 東京都八王子市生まれ
1989年 早稲田大学探検部在籍時に『幻獣ムベンベを追え』でデビュー
2006年 「ワセダ三畳青春記」で酒飲み書店員大賞受賞
(2007年11月29日・記)
☆関連図書(既読)
「アウン・サン・スーチー 囚われの孔雀」三上義一著、講談社、1991.12.10
「ビルマ 「発展」のなかの人びと」田辺寿夫著、岩波新書、1996.05.20
(「BOOK」データベースより)amazon
探検部の先輩・船戸与一と取材旅行に出かけたミャンマーは武家社会だった!二人の南蛮人に疑いを抱いたミャンマー幕府は監視役にあの柳生一族を送り込んだ。しかし意外にも彼らは人懐こくて、へなちょこ。作家二人と怪しの一族が繰り広げる過激で牧歌的な戦いはどこへ…。手に汗握り、笑い炸裂。椎名誠氏が「快怪作」(解説)と唸り仰天した、辺境面白珍道中記。
投稿元:
レビューを見る
いやあ面白いナァ。
何だか始終ドタバタしていますが、東南アジア近辺ってこんな感じかもしれません。本好きが多いというミャンマーに興味を覚えた一冊。
投稿元:
レビューを見る
著者が早稲田大学探検部の先輩である船戸与一のミャンマー取材旅行のガイドとして同行した際の紀行文。ミャンマーの軍政を徳川幕府の初期の執政体制になぞらえて解説。面白い。
投稿元:
レビューを見る
異国の政権に武家社会って例えを当てはめる。
すると本当に不思議と同じに見えてくる。遠い国の理解出来ない価値判断で動いていると思ってしまいがちな政治情勢が、あっさり抵抗なく理解できる(つもりになる)
投稿元:
レビューを見る
高野作品で実は一番好きな本!
作家の船戸先生がこんなひとだったのか!という笑いもこみ上げます。なにより、歴史観や民族感が高野さんのフィルターを通してみたとき、すごく魅力的である部分どうしようもなくて、愛おしいような、不思議な気分になるのです。
そして切なさも少々。
投稿元:
レビューを見る
「アヘン王国潜入記」を読んで、その先が気になっていたので。
ミャンマーを柳生一族に準えるなんて、凡人には絶対できない業。
非常にわかりやすく読み込みやすい。
内容は冴えまくりの笑いまくり。あーおもしろかった。
投稿元:
レビューを見る
ミャンマーの支配構造は日本の江戸時代に酷似している。
アウン・サン・スーチーさんはあの人に似ていたのか!