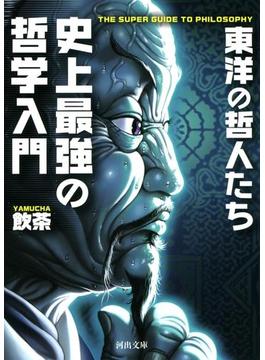史上最強の哲学者シリーズ第2弾、東洋哲学を解説した興味深い一冊です!
2020/05/13 10:09
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、東洋における古代の哲学者たちの思想、真理を追い求める姿を描いた興味深い書です。同書は、『史上最強の哲学入門』の第2弾で、前巻の西洋哲学に対して、同巻は東洋哲学に焦点が当てられています。同書は、「第1章 インド哲学 悟りの真理」(ヤージュニャヴァルキヤ、釈迦、龍樹)、「第2章 中国哲学 タオの真理」(孔子、墨子、孟子、荀子、韓非子、老子、荘子)、「第3章 日本哲学 禅の真理」(親鸞、栄西、道元、十牛図)となっており、多数の哲学者とその思想が学べます!
理想的な東洋哲学入門書。
2020/12/09 14:13
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ゲイリーゲイリー - この投稿者のレビュー一覧を見る
冒頭から驚かされた。
なぜなら本書を読んでも、東洋哲学を理解することは不可能であると述べているからだ。
なぜ理解不能なのかという問いから、まずは東洋哲学と西洋哲学との違いについて本書は幕を開ける。
私は全くの哲学初心者なので、この東洋哲学と西洋哲学との違いも全く知らなかったが、
著者のとても分かりやすい説明のため、東洋哲学と西洋哲学が根本的に異なることを学べた。
東洋哲学と西洋哲学との違いを学ぶことで、論理的思考に基づく西洋哲学(本書では「階段」と形容される)を本で学ぶことが可能なのは理解できたが、
対してゴール(真理)に達した人物の思想に解釈を重ねていく東洋哲学(本書では「ピラミッド」と形容される)を本で学ぶことができるのかという疑問が残る。
しかしそれは杞憂に終わる。
本書では、論理的思考とは真逆に位置する難解な東洋哲学の歴史を辿り、
どういう経緯を経て今の形態へと至ったかを分かりやすく言語化している。
それにより私たちは、なぜ東洋哲学を理解することが不可能であるかを理解することができる。
東洋哲学の発祥から日本へと辿り着き、そして日本独自の仏教へと変貌していくまでの過程を時系列順に記すことで、
東洋哲学の推移が非常に分かりやすく述べられている。
と同時に、前作の「史上最強の哲学入門(西洋哲学)」を読んでいたことで、西洋哲学との比較も楽しめた。
「色即是空や「無為自然」、「朝三暮四」や「南無阿弥陀仏」といった誰もが一度は聞いたことのある言葉に、
とても深い意味があり背景には思想家たちによる幾年もの努力がある。
それらを前作同様とてもユニークな例を用いて(ガンダムやピーナッツ等)、面白く哲学を学ぶことができるのも本作の魅力の一つであろう。
哲学といえば難解で堅苦しいなどのイメージがあるかと思うが、本作ではそういった負の先入観を取っ払ってくれ、哲学の面白さを存分に私たちに教えてくれる。
本作は、これ以上ない程理想的な哲学入門書だ。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
難しそうなイメージの哲学が、わかりやすく解説されていてよかったです。東洋の哲人の思想に親しめそうで楽しみです。
投稿元:
レビューを見る
哲学入門シリーズの2冊目。今回は東洋に絞った内容。前作(西洋編)の序盤はものすごく盛り上がったけど、今作は淡々と記述してある印象。ただ、わかりにくい東洋の哲学をものすごくわかりやすく紐解いており、何度も何度も例示を使用することで東洋哲学の本質に迫っていく手腕は本当に圧巻。哲学の入門書としては非常に良い内容だと思う。哲学に興味がある人は、前著と併せて読んでみると「なるほど哲学というのはこういう学問なのか」が分かって面白いと思う。
投稿元:
レビューを見る
文句なしの五つ星。読んでいて著者の頭の良さが伝わる。東洋の哲学者をここまで一つのストーリーのように綺麗に説明する人は他にいないだろう。たとえもわかりやすく、言葉も少し荒いのがとても良かった。
投稿元:
レビューを見る
あらゆる東洋哲学は、東へ東へと伝わり、この日本にたどり着いた。修行という実践に専心していくと、やがてその根底にある思想への関心が強くなっていく。本書は東洋哲学全般への入門として奨められる。
投稿元:
レビューを見る
わかりやすい、ここから哲学名著を読もうかと思ったが、やはり内容が難解らしい(ので挑戦しない)。概要と自分の哲学があればいいので。
「私(アートマン)については「に非ず、に非ず」としか言えない。それはとらえることができない。なぜなら捉えようががないからである。どうやっても認識するものを認識できるのであろうか。妻よ、不死というのは、こういうことなのである」
・釈迦:アートマン(私)は存在しない」という主張が無我。
・般若心経:物語が「空(関係性の中で成り立っているだけの実体のないもの)」であることを踏まえつつ、無分別(智慧)の行を実践して真言を唱えながら、えいやと悟りの境地に至りましょう」これが般若心経の内容。
・道(タオ)とは、要するに梵我一如(万物と私がひとつ)の境地である
・あるがままに物を見ている。「あれ」「これ」といった相対するものを超えることが「道(タオ)の要
投稿元:
レビューを見る
「史上最強の哲学 入門東洋の哲人たち」飲茶
あらゆる先入観を排除し、疑って疑って疑いつくして、厳密に確実に正しいと言えることを限界ギリギリまで追究するのが哲学。
「私」とは「赤や痛みなどを見たり感じたりする意識現象があること」である。
認識するものは認識できない。無限遡行
「私」とは「認識するものである」という定義を受け入れるならば、同時に「私は私自身を認識対象にできない」という論理的帰結も受け入れなくてはならない。
「私」とは「○○ではない」という否定的な言葉でしか記述できない特殊な存在である。
「私(アートマン)」については「に非らず、に非らず」としか言えない。それは捉えることができない。なぜなら捉えようがないから。それは破壊することができない。なぜなら破壊しようがないから。それは執着することができない。なぜなら執着しようがないから。それは束縛されることもなく、動揺することもなく、害されることもない。どうやって認識するものを認識するできるであろうか。不死とはこういうことである。この事実に気づいた瞬間、この世のあらゆる不幸は消え去り、自己は無敵の存在となる。
本当に知ったと言えるのは、本当がどうかを試した時。
知識として知っているだけの人と体験的に本当にわかった人は、言葉の上では全く同じことを話すが、本質的には全く違う。
古代インドで苦行が重視された理由は、苦しみに耐える事が、映画(鑑賞物)と観客(鑑賞者=私)は別物だという真理を悟り、無敵の境地に到達した事の客観的証明になると考えられていたから。
人生は苦しみだらけだが、その苦しみは執着という原因があり、それを無くせば苦しみを消す事ができる。
物理法則なんて人間が経験的慣習から「そういう絶対の法則性がある」と勝手に思い込んで信仰化しただけであり自明などではない。-ヒューム
言葉とは、なんらかの価値基準に従って世界に引いた、区別のための境界線。つまり言葉は区別そのもの。
無分別智とは、分別しないで物事を直感的に理解する事。真理とは無分別智でしか理解する事ができない。仏教はそこへ到達する方法論を提示する。
般若心経とは、物事が空(関係性の中で成り立っているだけの実体のないもの)であることを踏まえつつ、無分別智(智慧)の行を実践して真言を唱えながら、えいやと智の境地にいたりましょうというもの。
孔子から学ぶべきことは、戦国時代にたった一介の学士にすぎなかった男が、歴史を正気に戻そうと国家権力にも神秘的権威にも屈せずに立ち向かったという心意気にある。
「物はない」とするのが最高の境地であり、その次が「物はあるがそこには境界を設けない」という境地。その次は「物と物の境界があるが善悪などの価値判断による是非がない」という境地。価値判断による是非を行うことが道(タオ)が失われる原因。
論理を基盤とする西洋哲学は言語による伝達可能を前提とした体系。東洋哲学は論理ではなく体験���よるものであり、伝達不可能。
言葉や論理でしか理解できない、それが「知る」為の唯一の方法なのだと思い込むと永遠に理解できない。外に出ること。
東洋哲学は、悟りの体験を引き起こす方法論の体系として発展していった。
戒律は欲望を止める為にあるのではなく、欲望を自覚させ、苦しめる為に存在する。
本当の問題は戒律の対象に特別な価値を見出していた自分自身の心の動き(分別)にある。
価値を作り出したのも自分、価値によって苦しんでいたのも自分。これがあらゆる不幸の正体。
戒律とはこのバカバカしさを体験させる為の一つの方便。
知識や説明を与えることが良い結果を生むわけではないので、東洋哲学の師匠は何も説明しない。
方便自体は重要ではなく、方便を通して得られる体験が重要。
東洋哲学の様々な方便は、体験的理解を引き起こす為、2500年かけて洗練され続けた人類の偉大な哲学体系。
悟りとは、分別で作られた虚像の世界から目を覚まして無分別の智慧を取り戻し、無我の真理を体験すること。
ウパニシャッド哲学を背景として始まったインド仏教が中国に伝播し、老荘思想と融合して成立したものが禅。
禅の語源は、サンスクリット語の「ディヤーナ」であり、これが中国で「禅那」に音写され、最後に省略された「禅」になった。ディヤーナとは瞑想の事。
世界では中国語の「チャン」ではなく「ZEN」として知られている、日本が誇るべき文化の一つ。
「不安」は脳が物理的な作用によって排出された化学物質の刺激情報にすぎない。その感覚に「不安」という名前(分別)を与え、それに「悪いもの」という価値を付与し、さらにはそれを「私自身(心)」だとして同化している。だが、そもそも心など存在しないのだからその心が不安になることもない。
どんなものでも問題にしてしまう「問題視」という日常的な癖を減らすこと。
思考で表現できないものを思考で表現してわかった気になる。
禅は問題を破壊し、革命し、飛び越える。問題を分析して解き明かすのではなく、問題から飛躍し、「答え」を直接体験する。
十牛図の10番目は、彼は市場へと出かける。仏教で禁止されている酒を飲み、魚を食べ、普通に楽しく暮らしていく。ときには昔の自分と同じように牛を探している別の牧童と会うこともあるだろう。しかし、だからと言って、悟りすました態度で教え導くのではなく、ただその出会いを楽しむ。彼はそういう境地を生きる。
起こるに任せる、身体が動くに任せる、脳が考えるに任せる。たとえどんな映画が上映されようと、それが観客を傷つけるものではないことをもう知っているから。
「それ」を知った人は、何が起ころうと起きたままに起きたものを感じ、「それ」を味わい尽くす。
投稿元:
レビューを見る
すごく面白い本でした。いきなりこちらからでなく、先に(実際の出版順に)「西洋哲学」から読むと、両者のアプローチの違いがよく分かる…いや、分かった気になる。そして、「禅」の思想が、どういった思想の系譜の先に位置するものなのかもよく分かる…いや、分かった感じがする。
ややこしい。「東洋哲学」が分かった気がした時点で何も分かっていないということも分かってしまう…(苦笑
…ということで、自分は実は分かっていないということも分かってしまう…が、そんなことを言う時点で東洋哲学のアプローチからしたら自分は全く分かっていないということも分かって…いや、ややこしい。
投稿元:
レビューを見る
西洋の方も読み終わっていたが、こちらも大変読みやすい。時代の流れを追っているので、思想のベースを理解した上で次々読み進めることが出来、これまで苦手だった東洋哲学への興味が増した。
哲学入門としては、(西洋の哲学入門も含めて)大変な名著だと思う。哲学をもう一度学び直したい方、興味はあるけどなかなか手が出なかった方の1冊目として、大変オススメです。
投稿元:
レビューを見る
「哲学には最後、バキが足りない」という斬新なコンセプトで書かれていた前作は
哲学をお手軽に知る上では良書だったが、今回は東洋哲学の真髄+バキ分という内容。
思想は世の中のあるべき姿を語り、哲学は世界の真理に迫る。
西洋哲学は理論で真理に迫るため、万人に「なるほどね」と言われることを目標としている。
が、古代インドに端を発し、老荘、そして日本の禅で完成する(と作者は論じている)
東洋哲学は、体験で真理に到達する為、悟っていない他者に対しては結局は
「うーん、あれだよ、あれ、あの感覚」
としか言いようがないらしい。。(「汝、それなり」←インド古代哲学の真髄らしい)
悟りとは、この世で起こるすべての相関関係を分別なく捉え、理解し、映画と鑑賞している人との関係のように日々に起こることを見て平静でいられる境地のことを言うらしい。
確かに前に一度だけ座禅を組んだときに感じたのは、「1秒も無心でいられない自分を笑う」という二元的な感覚があったような気がしたので、まあ、そういうことを修行する為に仏教のいろんな流派はあるんだなーと言うのはよく理解できた。
相変わらず文章が平易でドラマチックなので、哲学に興味ある方は、ぜひ。
投稿元:
レビューを見る
史上最強の哲学入門 東洋編
飲茶
2021年12月22日読了。
西洋の哲学は階段型。
ソクラテスは「我々は無知である」という所からこの世の真理を追求しようとした。
西洋の哲学は先人達の哲学を足踏みにさらなる真理追求を模索する階段型であった。
東洋の哲学はピラミッド型。
東洋の哲学はいきなり「我、真理を知り得たり」みたいないきなり究極の答えに到達したと言う。
つまり、西洋はゴールを目指すのに、東洋哲学はいきなり「ゴールした」所からスタートする。
しかも、後世の人間達は先人の東洋哲学を間違っているとはせず、「自分達の解釈の仕方が間違っているんだ」と考え、「新しい解釈の仕方」を作り出し、その解釈の体系を発展させていく。
すると、様々な解釈から宗派が生まれる事になり哲学から宗教へと発展するのである。
この辺り非常に例えが分かりやすい。
そして東洋哲学に関する入門書等は結局のところ、「釈迦や老師のタオなどその境地に達し体得して初めて分かるものだから、言葉だけ学んでもホントウの所は分かりませんよー。」みたいな事が多いとズバッと書いてあったりもして忖度なくて面白い。
それでも東洋哲学(インド哲学、中国哲学、日本哲学)を網羅的に、主要な哲人を分かりやすく説明しているので読み物として秀逸だと思います。
投稿元:
レビューを見る
悟りの境地とは何か?という、捉え処のないテーマを、何となく分かった風に仕立ててくれている本でした。
なんだか言葉を尽くしても始まらないので、とりあえず座ります。
投稿元:
レビューを見る
東洋哲学は「ゴール(真理)を目指す」のではなく、「ゴールした(真理に到達した)」ところからスタートする。よって、東洋哲学者の哲学を引き継いだ後世の人間たちは、西洋のように、その哲学を批判したり打ち砕くことに躍起になったりはしない。
認識するものを認識することはできない。
あらゆる不幸は勘違い。
私(アートマン)については「に非ず、に非ず」としか言えない。
それは捉えることが出来ない。なぜなら捉えようがないからである。
それは破壊することが出来ない。なぜなら破壊しようがないからである。
それは執着することが出来ない。なぜなら執着しようがないからである。
それは束縛されることもなく、動揺することもなく、害されることもない。
どんな雑念が浮かぼうと、それらはただの「認識の対象物」にすぎない。どんな認識の対象物が現れようと、純粋な観察者である自己には何の関わりもない。
私(アートマン)は概念ではない。認識の対象物とすらなりえない。私(アートマン)は存在しない。
「歩く」という現象1つとっても、とてつもなく大量で複雑な縁(間接的原因)の絡みによって成り立っており、単独で引き起こすことは決して出来ない。それと同様に、どのような物事や現象であろうとそれは単独で存在出来るものではなく、沢山の縁(間接的原因)の絡み合いによって起こり、浮かんでは消えていく実体のないものである。
物理法則は人間が経験的習慣から勝手に思い込んで信仰化しただけのものであり、本当にそのような法則があるかどうかなどわかったものではない(デイビット・ヒューム)。
我々が「存在している」と認識しているものはすべて、我々自身がそういうふうに存在するように区別しているからこそそのように存在しているのであり、決して「そのような実体が存在している」というわけではない。
人間がなんらかの価値基準(人それぞれの勝手な区切り方)に照らし合わせない限り、この世界に「長いもの」「短いもの」といったものが存在しえないのと同様、「汚いもの」「綺麗なもの」といったものも存在しえない。さらには、「自転車」も「鉄原子」も「銀河系」も同様に存在しえない。なぜなら、それらもなんらかの価値基準によって切り出されたものであり、「長いもの」「短いもの」といったものと同レベルの存在と言えるからである。
眼も、耳も、鼻も、舌も、身体も、意識も無い。それらが感知する色も、音も、匂いも、味も、感触も、意識の対象も無い。眼で見た世界から、意識で思われた世界まで、その全てが無い。
明確に切り分けられる「物事の境界」など世界のどこにもない。だが人間はその切り分けられないはずの世界を強引にサクッ、サクッ、と切り刻み、世界を「これ」と「これ以外」に分けてしまう。そして「これ」に「A」という名前をつけて「Aがある」などと語り始めるわけだが、当然その「A」という言葉が指し示す「これ」に実体があるわけではない。なぜなら、「これ」なるものは何もないところに無理やり境界線を引いて「これ」と「これ以外」に分けることによって生じたものにすぎないからである。
つまるところ、いっさいの言葉は「世界にあるモノ(実体)」を指し示しているのではなく、何らかの価値基準に従って世界に引いた境界線を指し示しているのである。よって、言葉とは「区別(境界線)そのもの」だと言ってよい。これを分別智という。人間のあらゆる知的活動は分別智である。
人間には分別智以外にも無分別智という理解の仕方がある。無分別智とは物事を直感で理解することである。釈迦が悟った「真理」とはこの「無分別智(智慧)」でしか理解することが出来ないものである。
仏教とは釈迦の哲学を知識として伝えるための教団ではない。仏教とは釈迦、そして古代インドの哲人たちが到達した「あの境地」を人々に体験させようとその方法を何千年も研鑽し続けた学徒の集団である。
もし釈迦が到達した「真理」を知りたければ、釈迦と同じ「ああ、そういうことか!」という強烈な体験、悟りの体験をすることが前提となる。東洋ではリアルな体験としての「理解」を味わって初めて「知った」と言えるのである。
ある特定の物質なり概念自体に固有の価値があるのではなく、個人個人の「思い込み」によって「そのような価値」が作り出されているに過ぎない。
釈迦はあらゆる先入観をなくし、自分の欲望に善悪の評価をすることを止め、浮かび上がる思考をただ「無い、無い」と否定し、自分の中で起きていることをしっかりと見続けた。そしてついに思考が途切れ、分別が消え去ったその瞬間に「智慧」が現れた。
人間が勝手に分別して名前をつけない限り、この世界は「すべてが混じりあった混沌としたドロドロの海」としてあり、その意味において「万物」は存在していない。「万物(リンゴや机、ハンマーなど私達が普段存在していると言っているモノ)」が存在するのは人間が「名前をつけた」からであり、そのように分別して名付けたからこそそのような形で「(私達にとって)存在する」のである。
何の価値観も持たずに無欲になれば万物が存在する前の混沌とした世界を見ることが出来る。何らかの価値観を持ち込んで有欲になり分別を始めれば、万物の境界線がはっきりとした世界を見ることが出来る。だが、その世界は両方とも同じ世界である。
私達の身体的な動作をよくよく観察してみれば、「細かいことは何も決めていないにも関わらず、いつの間にか筋肉が勝手に収縮して指が動いており、私自身はその一連の行動にまったく関わっていない」ということに気づくはずである。これはすなわち日常的に「私が自分でやっている」と思い込んでいる行為でも、実は身体が自動的に勝手にやっているのであって「私」はそれをただ「見ているだけ」に過ぎないということである。
身体を動かしたり思考したりするのはそれぞれの専門家(身体や脳)に任せた方が断然うまくいく。仮にうまくいかないにしても、少なくとも本来持っている能力を最大限に発揮した行いが出来るはずである。「私」は行動や思考の複雑なカラクリを理解していない素人であるのだから、事は専門家に任せ邪魔にならないよう静かに見守っているのが吉である。
東洋は論理や知識というものをそれほど���効だとは信じていない。なぜなら、東洋にとって「真理」とは「ああ、そうかわかったぞ!」という体験として得られるものであり、体験とは言葉では表せられないものであるからだ。そのため「思考を磨き続ければいつか真理に到達出来る。言語の構造物で真理を表現出来る」といった幻想を東洋哲学は最初から持っていないのである。
東洋哲学は「とにかく釈迦と同じ体験をすること」を目的とし、「その体験が起こせるなら理屈や根拠なんかどうだっていい!ウソだろうと何だろうと使ってやる!」という気概でやってきた。なぜなら彼らは「不可能を可能にする(伝達できないものを伝達する)」という絶望的な戦いに挑んでいるからだ。そういう「気概」でもなければ、とてもじゃないがやってられない。
突然宇宙から巨大な隕石が落ちてくることがわかった。それは地球よりも大きく、あまりに巨大で人類の叡智を持ってしても避けようもないことが明らかとなった。その隕石は地球に近づくにつれ気温を上昇させ、すでに地上は灼熱地獄と化している。そんな苦痛の中では、ニーチェもカントも全て吹き飛ぶ。どれほど学問を積み重ね、深淵な哲学を脳内に蓄えていようとその生き地獄の瞬間においては何の役にも立たない。そのような瞬間でも、「今起きていること」を受け入れ、その瞬間瞬間を「真っ直ぐに生き抜いていく」にはどうすればよいか。きっとその時には「念仏」−暴れる思考を静め、他力に委ねて今を生きる親鸞の哲学−しかないのではないか。
慧可は達磨に対して自らの覚悟と決意を言葉ではない方法(自らの腕を切り落とし、達磨に向かって投げつける)で示してみせた。それによって、達磨への弟子入りを果たすのである。
不安とは脳が出しているただの信号、物理的な作用によって排出された化学物質の刺激情報に過ぎない。
そもそも思考とは肉体が持っている機能の1つに過ぎない。だが、たいてい私たちはその機能をとても重要視し、それどころかそれこそが「私」なのだと「同化」してしまうのである。
私たちはどうしても思考(言葉、論理、理屈)でどんな物事でも表現可能であり、理解可能であると思い込んでしまう。「分別を停止して無分別智の境地に達した状態が『仏』なのですね」「思考ではなく体験することでしか『悟り』には到達できないのですね」と言葉で表現して思考の一部とし、一度も体験したことのない「それ」を「わかったつもり」になるというあり得ない愚を犯してしまうのである。
禅は「問題」に対して論理的な思索をもって関わらない。禅は「問題」を破壊し、革命し、飛び越える。禅とは「問題を分析し解き明かす」のではなく、「問題から飛躍し『答え』を直接体験する」ことを目指して洗練されてきた哲学体系なのである。
投稿元:
レビューを見る
史上最強の哲学入門を読了後、こちらの本も読ませていただきました。前作が西洋哲学だったのに対し、今作は東洋哲学を取り扱っています。
前作同様哲学という曖昧なものを面白く、かつ簡潔に説明できている本だと思います。
2冊とも読めばある程度哲学について理解することができるのではないでしょうか。