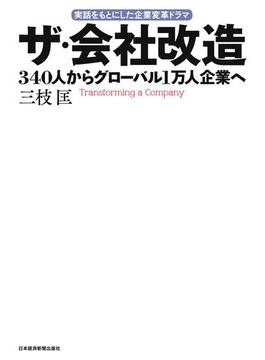会社経営者への思いが伝わってくる
2016/11/06 18:10
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Freiheit - この投稿者のレビュー一覧を見る
会社経営の重要場面をドキュメンタリー風にし、コンサルタントとしての解説を加えている。さらにコラムを入れるなど読ませる工夫をしている経営書であると思う。
事業改革の真髄がわかる良書です!
2018/06/19 08:57
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、数々の事業改革を行い続け、ようやく事業モデルの革新に成功した現役経営者によるビジネス書です。多くの組織で事業改善や企業改革が進められていますが、なかなかうまくいっていないのが実態です。どうすれば企業改革が上手くいくのか。本書は、そんな素朴とも言える、しかし、誰もが知りたい疑問に丁寧に答えてくれます。企業の経営者の方々はもちろん、組織の管理者には、ぜひとも読んでいただきたい一冊です。
投稿元:
レビューを見る
読んでて取り組みの大変さが胸にしみて痛い。頭が下がる。改めて、自分も自分なりに初心に帰って愚直に取り組もうと思いました。
投稿元:
レビューを見る
ターンアラウンドマネージャーの実話はとてもリアルで面白い。更に腰を据えて会社を大きくして際の苦労がとてもよく伝わってくる。
投稿元:
レビューを見る
職場の先輩のおすすめ。
組織を変えるために必要な視点。ただし改造を目的にせずに、成果を出す。
◯惰性に任せてきた 「経営の流れ 」を切断し 、組織の新しい方向性を導き出し 、それを実行する
◯修羅場の原因の多くは戦略系だが 、その苦しさを増幅させるのは人間系 、政治系の動き
◯過去のほとんどの例で 、会社が用意してくれた社内資料は役に立たなかった 。ものの見方や切り方が違うのだ 。だから 、待ちの姿勢でいると何も見えてこない 。
◯自社の事業モデルが優れているのに 、その 「構造 」が整理されていない会社は 、 「事業モデル 」という切り口で議論することを忘れ 、事業モデルを強化するための総合戦略を放置している可能性が高い 。
◯経営者の優劣はフレ ームワ ークの有無で決まる 。フレ ームワ ークとは 、物事の本質や構造を理解し 、わかりやすく説明するための 「枠組み 」のことだ 。
◯事業のシナジ ーが得られるのは 、 ①事業 ・商品に関連性がある 、 ②共通の技術を使っている 、 ③市場 ・顧客が重なっている 、 ④販売チャネルが重なっている 、 ⑤既存のブランドイメ ージを利用できる 、 ⑥競争相手が同じなので戦略上の連動効果がある 、 ⑦勝ち戦に至る重要な競争要因が同じで 、こちらはその戦いに慣れている 、 ⑧必要とされる社内組織の強みが同じなのでそれを使える
◯頑張りは非常に重要だ 。しかし 、立ち上げ初期の壁を乗り切ることができても 、長丁場の勝負を経て本当の勝ち戦を収めるにはそれだけでは足りない 。事業戦略が生み出す 「仕組みによる強さ 」が必要なのだ 。それがないと 、ベンチャ ーの成長は頭打ちになる 。
◯大切なことは 、狙う市場は小さくてもいいから 、そのなかで圧倒的なナンバ ーワンを目指すこと
◯《 1枚目 》は 、複雑な状況の核心に迫る 「現実直視 、問題の本質 、強烈な反省論 」 。 《 2枚目 》は 、 《 1枚目 》で明らかにされた問題の根源を解決するための 「改革シナリオ 、戦略 、計画 、対策 」 。 《 3枚目 》は 、 《 2枚目 》に基づく 「アクションプラン 」
以下、kindleメモ
投稿元:
レビューを見る
この人の本は、まさしく明日から使える言葉ばかりで、何度読んでも発見や、再確認がある。
実践、実証からの言葉は説得力が違う。
投稿元:
レビューを見る
今年ベスト。そしてライフタイムでもトップ10に入る本。星を5つにしたが本当は10、いや100個でも足りないくらい。
まず圧倒的な熱量、テンション、情報量、具体的な事例。確かにもっと知りたいところもたくさんあるが、知的財産的な部分もあるだろうし、そこは自分で考えるところだという、筆者の思いも感じる。これはある意味、筆者からの挑戦場であり、課題を提示された形とも取れる。
そのため一度だけ読むのでは到底筆者の真意を汲み取ることは難しいので、二度、三度と読み込むことが求められる。また、幾度となく過去作からの引用があるため、過去作を改めて読むたくなる衝動に駆られる。
しかし読んでいるうちになんとなく、筆者の経営者としてのcapabilityやperformanceの自慢?のように感じることがあるのがたまに傷。
投稿元:
レビューを見る
三枝匡の企業再生奮闘記。
著者曰く「プロ経営者」の定義は、
1.どんな状況の会社に行っても、短期間で「問題の本質」を発見できる人。
2.それを幹部や写真に「シンプル」に説明できる人。
3.それに基づいて幹部や社員の心と行動を「束ね」、組織の前進を図れる人
4.そしてもちろん、最後に「成果」を出せる人
ではミスミの再生をトップの立場からどう実践して会社を再生したのかを、その人となりが浮かんでくるくらいエネルギッシュに描く。再生の過程において直面した幾多のチャレンジを「いつか見た景色」と書く。言葉を換えれば修羅場にどう立ち向かって克服したかの引き出しの数が難局を乗り切るヒントとなる。内野目線で企業再生を書いた良書。
投稿元:
レビューを見る
三枝戦略3部作のあの三枝匡が十数年ぶりに返ってきた。ミスミでの12年間のCEO在籍中に策定してきた戦略、そして改革してきた様を詳細に綴った一冊。多少物言いが偉そうで鼻につくことはあるもののそりゃそんだけ実績あればそりゃそうかと。内容は痺れます。最高です。
投稿元:
レビューを見る
三枝3部作に続く企業改革ストーリ
今回の主人公は三枝さんその人で、企業名「ミスミ」も実名で登場。
しかしながら、改革にかかわった人物たちは仮名で登場で、今まで同様の小説形式でのストーリ展開です。
自身の話という事からなのか、生産革新での停滞や、カスタマーセンターでの2度ものミスも赤裸々に語られていて、プロの経営者でも簡単に企業改革は出来ないんだなぁって感じられる物語となっています。
そのプロの経営者として、筆者は7つ定義しています。
1.どんな状況の会社に行っても、短期間で「問題の本質」を発見できる人
2.それを幹部や社員に「シンプル」に説明できる人
3.それに基づいて幹部や社員の心と行動を「束ね」、組織の前進を図れる人
4.そしてもちろん、最後に「成果」を出せる人
5.業種、規模、組織カルチャー等の違いを超えて、どこの企業に行っても通じる「汎用的」な経営スキル、戦略能力、企業家マインドを蓄積している
6.その裏付けとしてプロ経営者は、過去に、修羅場を含む「豊富な経営経験」積んでいる。難しい状況に直面しても、これは「いつか来た道」「いつか見た景色」だと平然としてられる
7.プロには自然に「それなりの高いお金」がついてくる
とのこと。
そして会社改造には3枚のフレームワークで語る
1枚目:複雑な状況の核心にに迫る「現実直視、問題の本質、強烈な反省論」
2枚目:1枚目で明らかにされた問題の根源を解決するための「改革シナリオ、戦略、計画、対策」
3枚目:2枚目に基づく「アクションプラン」
としていて、それに結びつく変革の3つの原動力として
戦略、ビジネスプロセス、マインド行動をチャートとして表しています。
今回のストーリの目玉は大きく3つ
(1)30歳の若手に託した中国事業の立ち上げ
(2)3年もの停滞期間を持ちながらも実現した生産革新
(3)2度の挫折を乗り越えて実現したカスタマーセンター改革
いずれも現場の本音や泥臭い作業、混乱が伝わって来て、それらをどう乗り越えてきたかがポイントとなっています。
結果的に実績自慢が出てくるところが嫌味なところがありますが…
そして、それらの改革の中で人材育成・組織活性も合わせて実現していく、そこがまたすごいところです。
ただし、生産革新やカスタマーセンター改革の具体的な中身までは語られていません。それがミスミの戦略的優位を保つ重要な企業秘密なのでしょう。
それも赤裸々に語ってくれればいいのに(笑)
一方で、「問題の本質」や「改革のシナリオ」「戦略、計画」などの立案に至るまでの過程、膨大な資料作成や、追いつめられる幹部。さらに、実際に責務を果たす事が出来ずに辞めていく幹部など、改革を実現するための影の部分も語られています。
それらも全部ひっくるめて、企業改革という事なのでしょう。
ある意味、企業改革の光と影を赤裸々に語っている物語と言えると思います。
これも必読!
投稿元:
レビューを見る
三枝匡の集大成とされる渾身の一作。三部作のような火事場の経営改革ではなく、資本も業績も良好な一部上場企業を「日本の次世代経営者育成の場」ととらえて、大幅に躍進させた実話、実名の物語。
火事場の立て直しは、ある意味、簡単だ。ダメでもともと、うまくいけばヒーローなのだから、モチベーションも保ちやすいし、急場のこととて思い切った手も打ちやすい。本当に難しいのは、火事場になる前、ジリ貧に陥る前に変革することだ。三枝匡は、これを小さな組織による社員の活性化と、全体最適のための「束ね」との二極間の揺り戻しに解を求むる。
ミスミという(仕事の関係で)個人的にも親しみのある企業が題材となっているからか、教科書然とした感じも薄く、ノンフィクションとして読んでも過去の著作より面白い。
投稿元:
レビューを見る
・危機感を訴えるだけでは何も起きない。たった一人のリーダーが変化を生み出す。優秀な経営者はひとりで危機感を人為的に創り出す。
・プロの経営者とは、「短期間で『問題の本質』を発見できる人」「幹部・社員にシンプルに説明できる人」「幹部や社員の心と行動を束ね、組織の前身を図れる人」「最後に成果を出せる人」「汎用的な経営スキル、戦略能力、起業家マインドを蓄積している」「豊富な経営経験を積み、難しい状況に直面しても『いつかきた道』『いつか見た景色』と平然としていられる」。
投稿元:
レビューを見る
著者自身は経営人材に参考にしてほしい意向が強いようだが、中小の一従業員に過ぎない私にも多くの気付きを与えてくれた。それは甘言をもって読者を喜ばせるものからは遠く、著者の会社運営に多大な緊張が伴う、その感覚が私にも強く伝わってきたので、時には私の仕事人生を否定しかねない強烈な反省を迫るものだった。例えば、野党さながらに澄ました顔で会社の悪口ばかり言ってはいないか、あるいは、前の会社を辞めた理由として己の能力不足を棚上げしていないか、私の方にも緊張が生まれた。一方で、会社組織に表れがちな病気が明確な言語で浮き彫りにされており、経営の立場でなくとも、業務への客観的な見方を得た気がする。主として、経営の立場から進むべき航海図を示しているので、私の一従業員の立場からとるべき行動は、またこの著書の視点とは別に、構想を必要とする。つまり、私には私の生き方を追求していく当たり前の事実があるが、それでもこの本の知的資源の有用性は私にも十分に適用できるので、素直にこの本との出会いに感謝したい。
投稿元:
レビューを見る
会社の人が対談に同席、というので知って読んでみた。
考え方や進め方など、とても共感できる内容だった。
なぜ、星4つかというと、わからない。本能的なぶぶんで奮い立たない。
以下内容の自己備忘メモ。
とにかく経営人材がどう戦略を描くか、そして経営人材をどう育てるか、という人間が介在する問題、組織の作り方の問題が肝要。
経営人材は、ただしいワークスタイルをもったうえで多くの事例を経験しフレームワークを蓄積しつづけ、再利用し続け、成長しつづける必要がある。
会社改造においては、まず現状を強烈に反省すること。
そこから戦略をねりあげ、伝播させていくこと。
安易なリストラは遠ざけている印象(過去の経験からか)。
いまあるものの強みを最大化、別次元化させる話だったのはミスミという土台があったからなのだろうか。どれも同じではないはず。
戦略をねりあげるためのデータがなければ探し出す。それをベースにする。
うちの会社で本書を題材に戦略を、やることを考えるワークショップをしたい。数字をベースにしたやつやってみたい。
投稿元:
レビューを見る
HBRで本の存在知り遅ればせながら読みました。実体験がドラマにように書かれていて一気に読める。経営者次第で会社は如何様にも変容する事、その覚悟、学ぶこと共感することが多い一冊