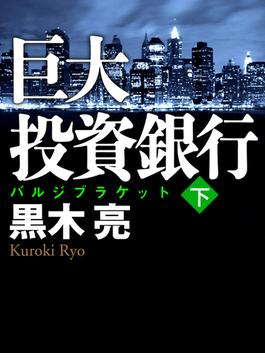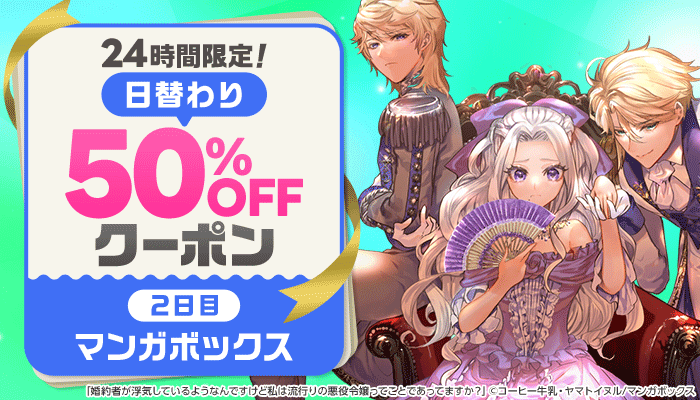日本経済の栄光と転落
2010/02/11 19:16
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:yjisan - この投稿者のレビュー一覧を見る
バブル経済、バブル崩壊、金融危機、金融ビックバン……日本と世界の経済が劇的に転変した激動の20年を、外資系投資銀行で活躍した日本人インベストメント・バンカーたちの目を通して圧倒的なリアリティで描く経済小説。史実に基づく企業買収劇や経済犯罪事件の全容は圧巻で、金儲けのためには手段を選ばない「狩猟民族」たるインベストメント・バンカーたちの闘争心が浮かび上がる。日系以上に上司が絶対でゴマすりが横行、手柄の横取り、部門間の激しい対立など、外資系投資銀行の企業文化も垣間見えて興味深い。
ソロモンの敏腕トレーダー、ソルトこと竜神宗一(シュガーこと明神茂がモデル)はバブル崩壊を見越して、金融工学を駆使した大規模なアービトラージ(裁定取引)を敢行、巨額の儲けを出し、ついにはソロモンの副会長にまで上り詰める。
ソロモンの藤崎清治はバブルに踊り財テクにのめり込む無知な日系企業にデリバティブ(金融派生商品)を売りつけてボロ儲けしていたが、バブル崩壊後、大幅な赤字となった日系企業につけ込む損失先送りビジネス(という名の犯罪)に嫌気がさして、独立する。
桂木英一は旧態依然とした日本の都市銀行にあいそをつかして退職し、ウォール街の巨大投資銀行モルガン・スペンサー(モルガン・スタンレーがモデル)に転職した。「結果が全て」である外資流のビジネスに翻弄されながらも、巨額のM&Aや証券引受で勝機をつかみ、昇進を重ねていく。やがて、その運命は日本の金融再生と劇的に絡み合い、桂木は外資での高収入を捨てて、今まで培った手腕を邦銀再生のために捧げようと決意する(りそなをモデルとした「りずむHD」会長、という形で貢献することになる)。実際、世界を股にかける国際派ビジネスマンは、実は愛国心が強いらしく、意外なような納得できるような。
金融工学の暴走が生み出した「リーマン・ショック」で傷を負った世界経済が未だ癒えず、そしてオバマ米大統領による金融規制強化法案が論議を呼ぶ現在、欧米投資銀行の果敢すぎるリスクテイクのあり方について、本書から学ぶべき点は多い。
壮大な現代史の大河ドラマ
2020/09/10 10:42
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コアラ - この投稿者のレビュー一覧を見る
バブルの発生から崩壊までを描いた壮大な大河ドラマだ。ちょうど評者の社会人生活と重なっていたので,とても身近に感じられ,「うんうんそうだったよな」と思いながら,どうしてあんなに株式投資で損失を出したのかもよくわかった。裁定取引に特化したファンドの成績がなぜ落ちたのかも理解できた。バブル崩壊について検証したより学術的な書籍もあるが,興味をもたれた読者は,とりあえずこの小説から入るとよいと思う。小説フィクションといいながら,誰が誰だかわかりまくりなのだから,きっとここに描かれたとおりなのだろう。ここで学んだことを教訓に賢く生きたいものだ。それにしても桂木英一かっこよすぎ!
投稿元:
レビューを見る
読了。下巻では投資銀行の中でなんとかサバイブした桂木が、投資銀行での経験を活かして新たな領域に挑戦していく話。ここでも1990年代後半から2005年あたりまでの経済環境が緻密に描かれている。投資銀行および経済の教科書的にも結構いいのではないか。ハードカバーのときはなかなか手が出なかったが、文庫本になった今としては投資銀行にこれから就職しようと考えている人は必読ではないだろうか。[2008/11/10]
投稿元:
レビューを見る
下巻です。かっこいい。。。
投資銀行とか商業銀行とかって何かと考えると、
結局は客のために何ができるかって話なんですわ。
最近自分が考えるのは、客のためになにかできるかと
いうことも大事なんだけど、自分が大好きな周りの人の
ために働きたいなーと思うこともしばしば。
そろそろ職種転換か!と思いきや、現在の仕事は
業界全体見れるからそれはそれで楽しいので
もうしばらく頑張りたいと思います。
今の上司がいなくなる or 自分が転勤する
を転機にちょいと考えますわー。
投稿元:
レビューを見る
フィクションとノンフィクションがうまく混じり合って小説として大変面白い。
日系金融の泥臭さや外資金融の実態が生々しく描かれている。
投稿元:
レビューを見る
以前真山氏の作品を読んで、ビジネス小説って面白いな。と感じたので、
その他の小説で、良さそうなものがないかamazonで探したら、なかなか良い評価を
得ているので、読んでみた。
小説なので、内容をまとめて書く無粋真似はしないが、読み終わった感想としては、
かなり面白かったと言える。どの点が良かったか、それは、
1.投資銀行が行っている業務や仕事内容がありありと描かれている。
2.ある程度史実に関連づけて、リアリティが高まっている。
3.微妙に主人公が何人かいるという事。
以前映画で流行っていたマルチストーリーとまではいかないが、数人のトレーダーの
人生が重なりはせずとも描かれていて、主人公の桂木以外の竜神や藤崎という人物の
生き方や人となりに惹かれた。
しかし、投資企業の現場はこれほどまでに凄まじいものなのだろうか。
まぁ、下巻最後の辺りではクオンツという人種が増えてきて、体育会系や賭場士的な
人は減ったと描かれているので、現状はそんな感じなのか。。。
ただし、一番下っ端の激務は・・・事実だと思う。これは投資銀行だけでなく、
コンサル系もそうだろう。
また、小説内には頭の切れる人物が何人か登場し、その性格と頭の良さが描かれているが、
その凄さを見習いたいと思う。というか、見習えるというレベルのものか?という疑問が
あるが、勝手に目指すだけだし、問題はないだろう(笑)
最後に、主人公の桂木は大きな決断をするが、その心境になるには多くの事が成し遂げられ
ての事であったりする。自分も将来は、そのような決断が出来る程、心身共に成長して
いきたい。
投稿元:
レビューを見る
前回の続編。
けっこういったことあるオフィスの話とか、元その会社にいた人の話とか聞いたことあって、リアル感漂ってました!
特に興銀(本の中では産銀)のM&A部隊のレベルの低さという話は、前に元興銀で今は外資IBのヘッドやってる人の話を聞いたときに竹やりと大砲で戦争してるレベルだったって話を聞いてたから、ちょっと感慨深かった。
総評としては、この20~30年の投資銀行の歴史を読めるし、単純に読み物としても面白いから暇があれば是非読んで見て欲しい本です。
社会貢献ってなんなのか、自分のキャリアを含めて考えさせられる本でした。
全然関係ないけど、リーマン日本法人の最後の社長ってこの本の主人公と同じ名前だった気がする笑
そしてこの竜神ってトレーダーは明●さんのことだよね?
奥が深い楽しめる小説でした!
投稿元:
レビューを見る
黒木亮の長編小説。
下巻の半ばくらいまでは面白かった。
『白い巨塔』の財前みたいに、主人公がどんどん昇りつめていくところが。
投稿元:
レビューを見る
(日経ビジネス 2006/02/20 Copyright©2001 日経BP企画..All rights reserved.)
出版社/著者からの内容紹介
旧態依然とした日本の都市銀行を飛び出し、ウォール街の巨大投資銀行モルガン・スペンサーに転職した桂木英一。
外資流のビジネスに翻弄されながらも、巨額のM&Aや証券引受で勝機をつかみ、一流のインベストメント・バンカーへと駆け上っていく。
やがて、その運命は日本の金融再生と劇的に絡み合い、桂木は外資で培った手腕を邦銀再生のために捧げようと決意する…。
日米企業間で繰り広げられる巨大買収劇の裏側、伝説のトレーダー・竜神宗一が仕掛ける巧妙な裁定取引(アービトラージ)、…ヴェールに包まれた米系投資銀行の内幕を圧倒的なリアリティで描き切った金字塔。
2008/12/1
投稿元:
レビューを見る
2009年5月27日に読み終わった本
http://hydrocul.seesaa.net/article/120494660.html
投稿元:
レビューを見る
上巻に続いて、すらすら読んでいた。次はどうなるんだろう、と読者の心をつかんで話さない著者は素敵です。
投稿元:
レビューを見る
■概略
元・投資銀行マンである著者が、複雑な投資銀行業界を半分実話に基づいて描いた作品。
■感想
非常に難解な解説が多かったものの、投資銀行という業界の雰囲気をつかむには非常に参考になりました。
投資銀行におけるイベントメントバンキング、セールス、トレーダーという3つの主な業務をそれぞれ個性的なキャラクターを起用して描いているため、比較的難解な内容にも関わらずサラッと読めてしまいました。
(ただ、個人的にはストーリーにもうひと捻り欲しかったところです)
とはいえ、やはりより金融の知識をもって読むと、もっと違った一面が見えてくるのかもしれません。
■一般的見解
臨場感・リアリティがあって面白いという意見が多い一方で、逆に「投資銀行の本当の厳しさが描かれていない」という声もありました。
確かに、主な3人の登場人物は作中で三様に成功を収めたという内容になっているため、「投資銀行でドロップアウトする恐ろしさ」は強くは感じ取れなかった気もします。
■総括
金融商品や歴史上の人物について本当に良く取材されており、投資銀行という業界の雰囲気をつかむには間違いなく最良の本だと思います。
投稿元:
レビューを見る
【上下巻同一レビュー・ネタばれ含】
トップレフトとどう違うのか?と問われれば、うーん、と悩んでしまうだろう。。この小説でためになったのは、変わりつつあった外資投資銀行の姿がありのままに描かれていたこととかかなぁ。
あと、読んでいて、ナイポールの「自由の国で」を思い出させるようなタッチだと感じた。というのも、彼の帰る場所が邦銀であったこと(また、上巻の中盤か下巻の最初の方にあった、モルガン・スペンサーに勤める事への恩師の無念がる様子、そして最後の邦銀CEO就任時の恩師の祝電がそれを裏付ける。)また、外銀を渡り歩く中での降格・解雇・取引の失敗やかつての古巣の邦銀の元同僚・上司からの陰口などが、「自由の国で」で主人公が受ける暴行に似ている。著者自体、英国在住だし。パッチワーク的な部分も多いし。まぁ、とてつもなく可能性の低い推論だが。
投稿元:
レビューを見る
日本でM&A業務を行っている桂木英一。
しかし、日本ではバブルが崩壊し、不況のどん底にある中で案件数は減少傾向にあった。そんな中でも桂木はもがき、かつての人脈等を頼りながら、またM&Aからカバレッジに移動になりながらも必死で仕事をした。そんな中、産銀からの投資銀行部門長への打診があり、桂木はそれを引き受けた。しかし、その後の金融再編のなかでの不毛な権力闘争の中で、桂木は純粋に日本に貢献するという思いを道半ばであきらめることになる。桂木は古巣モルガンスペンサーに戻ることを決意した。しかし、桂木は国有化されたりそな銀行の会長就任を打診された。再び、国家のために働けるチャンスを得た桂木は、外資で得た経験を基に、自分の金融人生を締めくくるため、最期の挑戦を始めるのであった。
時を同じくして、竜神や藤崎といったマーケットサイドの人間も市場の非効率をついた裁定取引や法外なデリバティブなどを駆使し、日本で暴れていたが、そんな時代もやがて終止符が打たれ、ひとつの時代が終わったのである。
投稿元:
レビューを見る
バブルが崩壊し、外銀が利益ために買いあさった宝の山、日本の市場が一気に冷え込む。
そんな中、桂木は日本の金融力を底上げするためにモルガンを去り産銀へ。
バブルから邦銀の大合併まで一気に進む。一時代を築いた伝説のトレーダー達の幕が今降りようとしている… 世の中はリスクを取って大きく利益を上げる裁定取引を行う投資銀行ではなく大型顧客に安定的に貸し付けを行う商業銀行への道を歩もうとしている。(小説はメガバンクの誕生で終わるが、リーマンショックを経て純粋な投資銀行はほとんど消えていった)
これはフィクションの経済小説としてではなくて、これまで日本の金融の世界を辿った金融経済史としての読み方もある。
非常に勉強になった。
本書のスタートでは邦銀を去った桂木は37才であったが、最後に邦銀に戻るのは56才と、一人の金融マンの人生を追いかけるのも非常に面白かった。
1980年代に後ろ指をさされながらも外銀へ行き、生き残りをかけて戦い、再び邦銀に戻るという山あり谷ありの人生であるもの非常に生々しい。
そして桂木のように悩みながらも自分の強い思いを持って生きていきたいと思った。