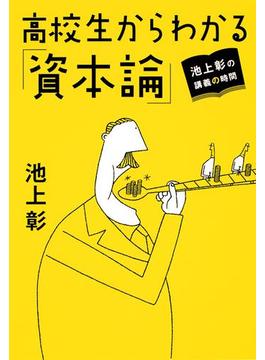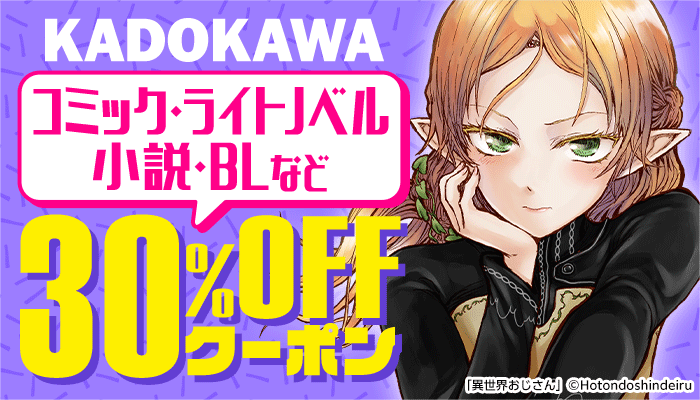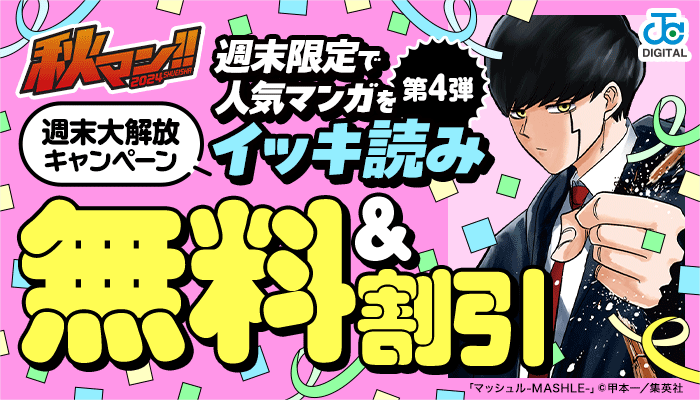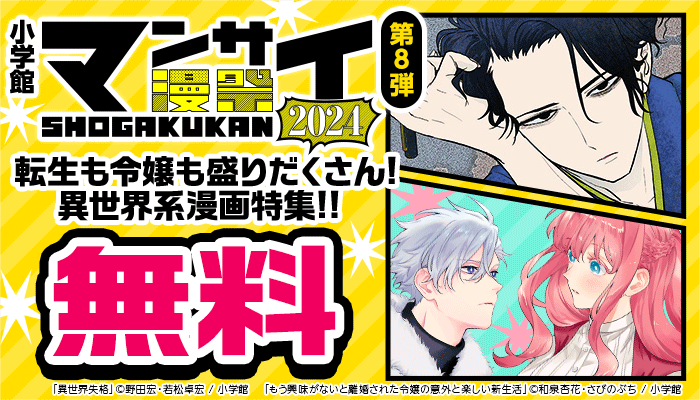池上さんの口語調の解説でわかりやすい!
2016/04/30 20:24
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:森のくまさんか? - この投稿者のレビュー一覧を見る
タイトルにも書きました通り、池上さんの解説で
資本論が非常に理解しやすかったです。
140年前の内容が今現在のことと同様のことが起こっていることを
マルクスが資本論にて 資本主義を分析したんだと思いました。
共産主義国は現状ほぼ崩壊してしまいました。一方、西側諸国は
資本主義の勝利と浮かれてしまって、急激な新自由主義によって
140年前の状況に戻ってしまったとのこと。資本主義がまた
行き過ぎてしまっています。
繰り返しますが、大変わかりやすい内容でした。
概要がつかめます
2015/08/29 11:18
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:tow - この投稿者のレビュー一覧を見る
難解な資本論1巻目の概要がつかめます。これを読んでから、資本論を読むと
理解が深まると思います。
たいへん分かり易い資本論のついての講義です!
2018/12/09 13:54
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、マルクスの『資本論』をとても分かりやすく講義した書です。『資本論』と言えば、経済学では非常に重要な位置を占める理論ですが、なかなか理解するのは難しく、原著を読んでもなかなか頭に入らないという人は多いと思います。そこで、マスコミなどで世界のニュースを非常に分かり易く説明してくれると注目されている池上氏が、『資本論』のエッセンスをとても簡潔に教えてくれるのが同書です。ぜひ、一度、読んでみてください。きっと「資本論ってこういうことが書かれていたんだ!」と分かるようになりますよ。
投稿元:
レビューを見る
読みやすくてよかった。
なんつかお金の仕組みって不思議よね。
行き過ぎた資本主義の構造こそが現在叫ばれる貧困の問題や
経済危機の問題に大きく関わっている。
投稿元:
レビューを見る
学生時代を思い出した。
経済学部の私は当然資本論にも挑戦したが、理解出来なかった部分が多かった。
分かりやすく書いてあり、十分理解できた。
成程、著者の言うように、現在の新自由主義とやらは、マルクスの想定した資本主義の末期に近いのかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
(2010.01.18読了)
「学生時代には、「『資本論』が読み進めないのは自分の力がないからだ」と思っていたのですが、いまになって読みなおすと、単にマルクスがわかりやすい説明をしていなかったからだと思うようになりました。」と池上さんは、「おわりに」に書いています。
的場昭弘さんの「超訳資本論」全3巻を読んだのですが、簿記を使って説明してくれたら随分わかりやすくなるのでは、と思ったりしたのですが、どうなのでしょうか?
的場さんの本を読んでもよくわからないので、池上さんならわかるかと思って読んでみたのですが、それなりのまとまりをもった構成にはなっているようですが、あまりにも現代に引きつけ過ぎているように思います。高校生にもわかるように、という狙いなので、やむを得ないことなのでしょう。もう一冊ぐらい別の本にあたってみましょう。
「資本論」は、全三巻になっているのですが、この本では、第一巻だけを扱っています。使用したテキストは、筑摩書房刊のマルクス・コレクションⅣ・Ⅴ「資本論 第一巻」(上・下)2005年発行です。
●金融恐慌は、新自由主義のため(21頁)
マルクスが「資本論」を書いていたころの時代には、恐慌というのがひっきりなしに起きていた。東西冷戦時代で社会主義にならないようにと資本主義の国々が労働者の権利を守り、経済がひどい状態にならないようにといろんな仕組みを作ったことによって、恐慌というのは起きなくなっていたのに、新自由主義によって、すべてを自由にした途端に、再び恐慌が起きるようになってしまったのではないか、ということなのです。
●「資本論」を要約すると(41頁)
人間の労働があらゆる富の源泉であり、資本家は、労働力を買い入れて労働者を働かせ、新たな価値が付加された商品を販売することによって利益を上げ、資本を拡大する。資本家の激しい競争により無秩序な生産は恐慌を引き起こし、労働者は生活が困窮する。労働者は大工場で働くことにより、他人との団結の仕方を学び、組織的な行動ができるようになり、やがて革命を起こして資本主義を転覆させる。
●使用価値(57頁)
人間の労働が受肉されて使用価値を持っているということは、人間の労働こそが尊いもので、人間の労働があってこそ世の中すべての商品には価値があるものなんだよ、労働が受肉されているから使用価値なんだよ、とマルクスは言いたいのです。
●貨幣の機能(81頁)
貨幣には三つの機能があります。
貨幣は、まずは価値尺度になります。
それから、お金の価値は保存することができます。
それから支払い手段になります。
●金儲けの仕組み(106頁)
資本家というのは、工場を建てたり、機械を買ってきたり、原材料を買ってくるのと同じように、労働力を買ってきてここで製品を作らせる。するとその製品は、買ってきたものよりも高くなる。こうやって資本家は金をもうけているんだ
●先のことなど(147頁)
洪水は我れ亡き後に来たれ!これがあらゆる資本家と資本主義国家の合言葉である。だからこそ資本は社会によって強制されない限り、労働者の健康と寿命に配慮することはない。
●労働者の能力を高める(210頁)
資本主義というのは、何も悪いことばかりではない。みんなが一緒になって働く、協力して世の中を動かしていく、協力して働くとそういう力を身につける、そういう生きがいを身につけると同時に、子どものころから様々な教育を受けられるようになってくる。資本主義というのは資本家は金儲けのためにいろいろやるんだけど、それは結果的に労働者が能力を高めていくことにもなる
☆池上彰の本(既読)
「池上彰のこれでわかった!政治のニュース」池上彰著、実業之日本社、2006.09.15
「池上彰の「世界がわかる!」」池上彰著、小学館、2007.10.01
(2010年1月19日・記)
投稿元:
レビューを見る
○2010/03/22
それでも少し難しかったなあ。これ直接高校生が講義を受けていてかつそれを飲み込んで理解できていたなら羨ましい。
たしかにマルクスの引用文を読んでいると目が滑って滑ってしょうがない。まあまず手に取ることのなさそうな本だけど、こういう形で触れる程度でも知っておければいいかなあ。世界のしくみ、経済の仕組み、政治にも触れていたり、知らないことをたくさん読んだ。でも書き方もあるし、特別難しいことを題材にしているとは感じなかった。砕き方がうまいのか。すごいなあ。まあ言ってることは簡単でも内容は難しかったけど。
もう一度時間をかけてゆっくり読み込んでいきたいと思った。この本を理解したと自信を持って言えるくらいになったら、資本論の元の方にも手が出せそう。…いや、でもないかな(笑)
現代のこの情勢について、池上さんはフォローもしてるけどどうしてもバッシングが先行しているイメージ。投げかけをするのは講義だからなの?
昔の人は内も外も無駄に着飾るのが好きだったんだろう。最後に池上さんが、読みにくいのはマルクスの書き方が悪いって断言しているところに笑った。
投稿元:
レビューを見る
実際に資本論を引用しながら講義してくれているので、おお、資本論読んでるー!って感じられました笑
でも書いてあることは他の概説書で勉強したことと同じなのですんなり入ってきました。
昔は日本人はたくさんマルクス勉強した人がいたらしい。
そういう人が官僚になったり、政治家になったり、資本家になったりしてたから労働者を守るための規制とかもよく進められたらしい。
別にマルクシズムに走らなくてもいいんやけど、資本主義っていうのがどういうものなのかっていうことは私たちもっと知っておかなくちゃいけないと思った。じゃないと「規制緩和」とか言われてもそれが何を意味するのかとかわからないまま何となく新聞読んで「ああ、いいことなのね」って賛成しちゃって。
革命論はともかくとして、マルクスの資本主義分析はすごいし、資本主義を学ぶっていう意味でももっと大学の般教とかで教えるべきじゃないかなーー
とりあえず資本論自分でも読みたい!!!
ていうか池上さんになりたい!!!
投稿元:
レビューを見る
非常にわかりやすい解説。太字で書いてある原文の訳は気合いを入れないと解読できない難解な文章だった。もともとマルクスの理論には賛成的な立場。資本主義が成熟して共産主義に移行するというのはなるほどと思った。
マルクスは資本主義を否定しているのかと思ったら必ずしもそうではなくきちんといいところを認めていることがわかった。
140年前の人間がここまで資本主義の弊害を見事に指摘しているその慧眼に驚かされた。今の時代にはわかりやすい理論だなと思う。好景気のときは考えもしないことだろうが。
投稿元:
レビューを見る
資本論に出て来る重要な概念をこんなにわかりやすく解説した本が他にあるだろうか。池上さん本人が学生の頃に挫折した本であるってところもあるし、高校生に講義したのを本にしたものであるってのもあるし、とにかくわかりやすい。もちろんあくまで入門書であって時間や興味のある人は原典に当たっていくべきですけど。
さらにマルクスが述べたことが現代をどれだけ予見していたかってことも改めて感じてマルクスの天才さにはちびるばっかりです。
一般にはマルクス主義ってばソ連やチャイナを思い浮かべるんでしょうが、それが誤解であることもこの本を読んでいただければすんなりわかってもらえると思う。
投稿元:
レビューを見る
「メモ」
派遣労働者に払う費用=物件費
⇒モノ扱い
「資本主義が発展すればするほど労働者の労働条件はどんどん悪くなっていって、労働者が人間として扱われない。まるでモノみたいに扱われることに耐えられなくなってくる。そうなると、労働者の不満が高まって、労働者がこの社会を変えようという動きが高まり、やがて革命が起きる。」
東西冷戦時代で社会主義にならないようにと資本主義の国々が労働の権利を守っていた
⇒終身雇用、年功序列、社会福祉、雇用保険
⇒談合的な体質
第二次世界大戦
⇒反省
⇒マルクス経済学者「戦争はいけない」主張していた
⇒マルクス経済学見直し
⇒全国の大学の主流に
⇒新自由主義が入ってくる
⇒マルクス経済学が教えられなくなる
マルクスの誕生日⇒子供の日
ヘーゲル哲学
1917年ロシア革命
⇒レーニン
⇒まだ早かった
⇒民主主義、自由な選挙は実現できなかった
資本主義経済が発展することで社会が豊かになる
⇒労働者は貧困
⇒大工場での労働者→団結
⇒革命へ
チャベス
ベネズエラの大統領
⇒資本主義体制を社会主義体制へ
⇒別に革命を起こす必要はない
マルクス・レーニン主義
⇒マルクスの理論に基づいてレーニンが革命
⇒両者は一体として考えるべき、思想
世の中は商品であふれている
⇒1つ1つの商品を解析
⇒資本主義全体を見る
⇒使用価値と交換価値
⇒使用価値だけ→商品ではない
⇒誰かのため→初めて商品になる
⇒等価な労働力という基準(A=B=C)
⇒労働力=労働時間
⇒労働時間:社会全体としての平均的な労働時間
労働力が受肉している
⇒キリスト教的な表現
⇒それだけ貴重な尊いものが商品の中に含まれている、と読む
「自分が働くことによって誰かに喜んでもらえるという働きがい、生きがい」
日本:稲「ネ」→値
中国:子安貝
ローマ帝国:塩→サラリウム→salary
全ての商品とイコールで結ぶことのできる商品
⇒貨幣
⇒貨幣の価値が半分に→インフレ
貨幣の価値が2倍に→デフレ
⇒W-G-W G-W-G’
お金ではなく、お金といつでも交換しますよ
⇒預り証
⇒遠くに持っていくのが大変、腐る
⇒紙幣
⇒金本位制
⇒「本当にあの銀行金持ってるの?」
⇒取り付け
⇒日銀のみ紙幣発行可能
お金の昨日
1価値尺度
2価値の保存
3支払い手段
4世界貨幣
⇒全く違うお金の単位を使っている国との取引
⇒金に戻る
⇒ブレトン・ウッズ体制
⇒アメリカグループに入っているとこんなに豊かになるんだよ
⇒マーシャルプラン
⇒ドルばらまき
⇒フランスやイギリスによる取り付け→ニクソン声明
⇒ドル価値は下がったけど、流通していたので、そのまま世界のお金へ
旧約聖書、新約���書、コーランは読むべし
GでWを買い、付加価値をつけてからGに
⇒資本の誕生
⇒資本の人格化、資本を増やすことへの欲求
⇒使用することで価値の源泉となるような性質を持つ商品
⇒労働力
⇒使うことによって新しい価値が生まれる
⇒お金を持つ資本家=労働力を持つ労働者
労働力の価値
⇒労働者が元気になって再び働けるようになるための費用
⇒給料
⇒労働力の再生産費用
⇒必要労働費
⇒必要労働+剰余労働=労働日
⇒剰余労働→搾取
不変資本と可変資本
⇒固定資産と流動資産??
⇒不変資本:機会 可変資本:労働力
労働者がどうやって人間として扱われて、人間的に働いて、
⇒新たな価値
⇒社会全体が豊かに
⇒これをどう実現するか
⇒工場法
⇒労働者をあまり働かさせすぎてはいけない
⇒剰余労働を生み出すため、非人道的な労働
⇒「洪水は我れ亡きあとに来たれ!」
⇒剰余価値を増やす→労働時間を長くする×
⇒相対的な剰余価値を増やす
⇒機械の導入
⇒家族全員で働く→1人分の給料down
⇒労働力が安くなる→売る商品が安くなる、→買う商品が安く
→労働力再生産費用が安くなる→給料が安くなる=労働力が安くなる
私たちが普段気づかないところに何か規則性があったり、法則性のようなものがある。それを見つけて体系的にまとめる
⇒学問
ウォールマート
⇒なんでも安い、他の店をつぶす
⇒他の店の従業員、職を無くす
⇒ウォールマートで働くしかない
⇒他にも働いてくれる人はいる
⇒給料下げ
みんなで一緒に働く
⇒人間の本質、一緒に働くことによる喜び
⇒みんなで達成したときの喜び
⇒資本主義悪いことばかりではない
⇒労働者が固まる
学生時代に分からない
⇒社会を経験していないから
機械が導入される
⇒人が集まる
⇒婦人労働、児童労働
⇒労働力の価値が下がる、商品の価値が下がる
⇒再生産費が下がる
⇒機械導入によって労働の密度が上がる
⇒相対的な剰余価値が増える
⇒機械がどんどん増える
⇒労働者が切られていく
⇒労働市場(失業者)があふれる
⇒現在働いている人にプレッシャー
⇒給料が下がる
⇒労働している人の人数が減る
⇒労働者の能力upが必要になってくる
⇒教育の必要性
これだけ時間外労働すれば住宅ローンが返せるな
⇒時間外労働も含めてローンを組む
⇒景気が悪くなって残量ができなくなる
⇒ローンが返せなくなる
出来高賃金
⇒基本的には時給と一緒
⇒労働者がつい頑張ってしまう
⇒相対的な剰余価値up
労働者をさらに雇いたいという時(景気がいいとき)が来る
⇒労働者をさらに雇うために賃金up
プロレタリアート
⇒労働力しか持っていない労働者
生産性の向上
⇒労働力(可変資本)↓ 機械(不変資本)↑
⇒絶対数で労働力が増えても機械の方が割合的に多���なってくる
⇒産業予備軍(失業者)が増える
⇒給料を上げることができない
資本主義経済は必然的に失業者を生む
産業予備軍=派遣労働者
⇒給料が安くても働く
⇒正社員の給料がupしない
「一方の極における富の蓄積は、同時のその対極、すなわち自分自身の生産物を資本として生産している階級側における窮乏、
労働苦、奴隷状態、無知、残忍化と道徳的退廃の蓄積である。」
唯物史観
⇒下部構造(経済的な関係)が発展すると上部構造(下に対する法律や思想)が押さえ込もうとし、
結果的に上部構造が爆破される
「協同の社会的労働の生産手段として利用されることによるあらゆる絵資産手段の経済化が進み、すべての民族が
世界市場ネットワークに組み込まれ、それとともに資本制の国際的性格が発展する」
資本家同士の虐殺
⇒資本家の数が減っていく
⇒1つの場所で働く労働者の数up
⇒不満を持つ労働者が増えてくる(生産内か生産外かは分からない)
⇒搾取に対する反発
一部の企業が独占
⇒社会的に見た生産力の発展が妨げられてくる
ジョン・メイナード・ケインズ
⇒国債発行すればええやん!
ロシア、中国、北朝鮮
⇒社会主義 w/ マルクス
ヨーロッパの国々、日本、アメリカ
⇒資本主義 w/ ケインズ
■大事■
「歴史に十分に学ばないことによって再び失敗を繰り返したのが、このところの金融不安だと思います」by池上彰
⇒愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ
⇒歴史=他人の経験
投稿元:
レビューを見る
資本論が平易に書かれている。実際に高校生と「わかりやすいか」考えあったということもあり、読みやすい。しかし、池上彰流に平易に解釈されているので、意見の押しつけのように見えるところは見える。池上彰氏の「こう思う!」というのと「事実はこうだ」というのを意識して読めば、さくさくと資本論の概要があたまの中に入ってくる、優れた資本論の入門書、の入門書。
投稿元:
レビューを見る
「資本論」を身近な例を交えながらわかりやすく読み解いています。途中、読み進めた内容をまとめてくれているので、資本論を知らない私でも頭にすっと入ってきました。
投稿元:
レビューを見る
資本論を読んでみようと思ってみたわけではなく、池上さんの本だから読んでみようと思ったのだが、読んでみて正解!自分の専門は経済じゃないし、全然経済のこと、世の中のことを知らなかったけど、興味が出てきた。原文だと絶対読めなかったはず。池上さん、解説ありがとう!
投稿元:
レビューを見る
「そうだったのか!」シリーズでけっこう池上節になれたので、本書を図書館で借りた。
そうだったのかシリーズでは丁寧語だったが、本書は高校生にした講義をもとに構成されているためか、お父さんが子供に解説するような口調だった。
本書は「資本論」第一巻だけを扱い、各章ではじめにマルクスの文言を引用した後、それを著者が解説していくスタイルをとっている。
ただ、分量が287ページということもあって、さすがに「そうだったのか!」シリーズのように一気に読むことはできなかった。具体的には1週間強かかってしまった。
マルクスの難解な語り方に、著者はかなり批判的なコメントを残しているが、彼がそのような語り方をしてくれたおかげで、著者は一冊の本を出すことができた、ということも言える。