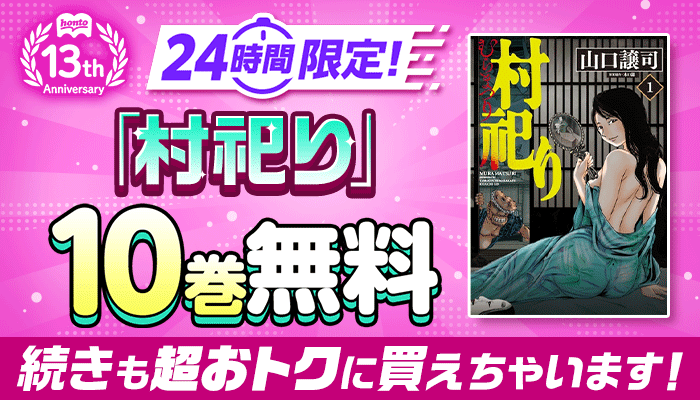理想国家とは、哲学者統治国家
2006/10/06 05:47
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:濱本 昇 - この投稿者のレビュー一覧を見る
上巻から続いて対話が続く。話す内容個々は、スムーズに読めたが、その内容は、難解で著者の主張を理解出来たとは言えない。良き国家とは、良き人間の集合である。良き人間とは、哲学的思考により、魂を磨く(知を求める)人間であり、すなわち、哲学者による国家統治を理想として説き伏せる。
本書のような難解な哲学書を読むのは、意味は理解出来ないが、自己満足的欲求満足感が得られる。それで良いと思う。文章が頭に残らずとも、自らの魂に読みこまれ、血となり肉となると、私は、考えている。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Ottoさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
岩波文庫の上下巻の内、実は下巻しか読んでいない。
誰かが下巻で十分だと書いていたからだが、10巻を上下巻に分けて、確かにまず正義論に始まり、教育論、知恵、勇気などの徳、哲学者の話が続き、ようやく第6巻(下巻)から、哲学的認識で有名な「太陽」、「線分」、「洞窟」の比喩、哲人の治める理想国家、君主制、民主制、寡頭制など国家論の主題が語られる。
「国家」は、プラトンの対話扁の中でも主著とされており、下巻も500頁を越える大部だが、解説が80頁、訳注が60頁あり、本文はお決まりのソクラテスが中心の対話なので読みやすいと言えばそのとおりだ。
民主主義の原点、国家論、正義論を考えるなら下巻だけでも読んでおきたい。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ポージー - この投稿者のレビュー一覧を見る
国家の支配者は権力や名誉に溺れることなく良い政治をしなければならないから、支配者というポジションはそれに着任する人にメリットがいかないように設定する必要がある、とかなるほどなと思った。
投稿元:
レビューを見る
内容に入る前に一言…「長いんじゃ、ボケ!」 そして、対話のテーマが、柱である「国家論」「正義論」に留まらず、あらゆる方向に伸びてるのに巻数ごとのテーマ別の分類などが一切無いため、非常に読みづらい。まぁ、解釈書じゃないから原典に忠実でなければならないのはわかるけど…苦しかった。
さて、下巻では上巻の最後で登場した「哲人統治」の続きから。結局は真理や実在を愛する哲学者が、国を守る…というか支配するのに相応しいということでファイナルアンサー。トラシュマコスさんが陥落した今となっては、誰もソクラテスの意見に異を唱えません。「アナタノイウコトハタダシイデス」…そんな言葉ばかり繰り返してないでもっと食い付いていかないと対話篇とした意味が無いような…。
そして、出ましたイデア論。哲学的な素質を育てるために必要な「善」のイデアについて、有名な洞窟の比喩などを用いての説明。個人的にはこのイデア論の考え方、「(元々は良い素質を持っているはずの)魂の向く方向を変えればいいんだ!」的な発想は大好き。
また、国家の五種類の形態・国制の話をとても面白く感じた。まずはソクラテス達が上巻で作り上げた完璧な国家「優秀者支配制」。そして、そこから生じてくる不完全な四種類の国家、すなわち「名誉支配制」「寡頭制」「民主制」「僭主独裁制」。これらの国制について、そこに存在する人間の性格をも検討しながら語り出す。ちなみに幸福という観点から見て順位をつけると、ここに挙げた順に素晴らしい国家であるそうだ。…民主制がやたら低い順位にあるのをソクラテスが(直接)民主制国家の下で殺されたことを受けてのプラトンの情報操作かと疑ったり、優秀者支配制と僭主独裁制を対極に位置するものとしているけど両者は非常に紙一重の関係…というかほとんど同じでは?なんて批判的に見てしまったりもしたが、まぁ面白かった。
締めくくりは、イデア論と密接な関係を持つ「魂の不死」について説いた後、「エルの物語」という話で魂の行く先について語ってお終い。だんだん普段自分達が認識できる範囲の世界から離れるようにして語られてきた、国家篇の最後としては綺麗な形で終われてる気がする。
読み終えて…自分はどうもこの本を批判的に見てしまったことに気付き、反省した。「法は国家全体に幸福を行き渡らせるように存在すべき」としながらも「正しい人は望むなら国を支配し、どこからでもすきなところから妻を貰い、誰でも好きな者と子供達を結婚させることができる・・・」云々、ソクラテスの基準での「徳のある者」「善い魂を持つ者」…すなわち「哲学者」がほとんど独裁者と化すことを喜ばしいことだとしている(ようにも思える)下りがどうも現代人たる自分にはマッチしなかったみたいで…。
もう少し大人になったら読み返したい一冊。…これ以上歳をとってからだと、こんな長い本は読む気力が無くなりそうだと不安に思いながらも、今はそう思いながらこの本を本棚にしまうことにしよう。
投稿元:
レビューを見る
若いころに政治に熱心だったプラトンは、ソクラテスの裁判以後哲学に傾倒していくが、それでも政治に対して完全に決別できず、どこかで、ソクラテス的哲学と、政治の融合できる方法を探していた。しかしこの両極の二つが融合するには、そこに揺るぎない理論的支柱がなければならない、その確信が得られたのは、プラトンがアカデメイアを創設してから10年もの歳月を要した。
その哲学と政治の融合、哲人政治をこの「国家」によって明らかにしたのである。
投稿元:
レビューを見る
上巻を読み終えてからしばらくたちました、ようやく読み終えたプラトンの『国家』。イデア論を中心に、ソクラテスとグラウコン、アディマントス兄弟の答弁は続きます。知ること、知識こそが真理を見出す唯一の道といい、感情がいかに芸術を求めようともそれを切って捨てることが正義。ホメロス批判が響きます。上巻で取り上げられた『ギュゲスの指輪』に対する答えも一応答えられています。結局は本心の問題。死後の世界が巻末に広がりますが、当時の価値観としては意味がある答弁だったのでしょう。黄泉の有無よりも、そういった恐怖信仰以前の人間の本性としての正義を追及した点で哲学のすばらしさを感じます。今より2500年ほど昔に、このような道徳の語らいがあったのは驚きです。ソクラテス、プラトン、やはりすばらしい。
09/5/8
投稿元:
レビューを見る
有名な「洞窟の比喩」が出てきます。
私のゼミでは「洞窟」=「現代の映画館」論へ強制的に持って行かされます。
投稿元:
レビューを見る
哲学の授業で読んだ本
「洞窟の比喩」が出てくる。
私がプラトンに興味を持ったのは
洞窟の比喩が引用されている
「アルジャーノンに花束を」
を読んだから。
難しいけど哲学を、人の考えを学ぶのは面白い
投稿元:
レビューを見る
正義とは何か、正しい国家とは何かについて語られる。哲人王の統治や有名な洞窟の比喩もコンテクストの文脈で語られると意義深い。広範に渡って語られるため全貌を掴むにも何度も読み込む必要がありそうだ。理想の国家から堕落していく国家のあり方はアテネだけでなく、古代ローマ、フランス革命などと照らし合わせても正しいと感じられ洞察力には舌を巻いた。また、魂の不死を説いたエルの物語は現代人にも説得力を持つように感じられた。
投稿元:
レビューを見る
『国家』の第6巻~第10巻までを収録。プラトンの正義論については、ポパーはじめ多くの批判的意見が提出されてきた。しかし、洞窟の比喩、エルの物語など、いまなお人の精神にゆさぶりをかける優れてアクチュアルな内容が含まれていることは間違いない。その意味で、やはり『国家』は第1級の古典と言えるだろう。
投稿元:
レビューを見る
古典から正義について知るにはプラトンの『国家』の右に出るものは無いでしょう。いきなり理想の国家の設計図を描こうとするのではなく、「老年の平和と自由」をめぐる意見交換から始めて、「正義と幸福」は果たして両立するものなのかと言う難題に立ち向かっていきます。
投稿元:
レビューを見る
プラトンが国家で、ソクラテスに哲人王として君臨すべき人物として彼を想起させるような論理展開をさせたことはやはり、『ソクラテスの弁明』の結果処刑されたソクラテスに対する複雑な感情と、民衆のみならず、都市の頭脳たちに対する不満と怒りの念が会ったからであろう。
教育論も語られていて、読み物として面白いのでぜひ一読してはいかがだろうか。
投稿元:
レビューを見る
プラトン以降の歴史は全て、彼の手の平の中だったのかもしれない-そんなことを痛切させれらる。とにかく国家の形態とその推移に関する分析は圧巻だった。ここでプラトンは自由と平等を愛する民主主義というのを決して優れた国家形態とはみなしていない。またこの制度は富者が支配する寡頭制に対する反発として、寡頭制の次に必然的に現れるものと考察している、正に歴史がそれを証明している通りに。そして何より恐ろしいのは、この民主制というのが自由と平等を愛する結果、守るべき秩序も失われ僭主独裁制、つまりファシズムを必然的に生み出すものと描かれているのだ。そう、歴史は今まさに、その事実を証明しようとしつつある。
投稿元:
レビューを見る
最初、哲学史を理解するための教養として読むつもりで手に取ったのだけれど、その気高い思想に触れるうちに読むこと自体が快楽になってしまった。たとえ、本書で語られている内容がほとんど理解できなかったとしても、著者がこれを書かざるをえなかった動機のようなものは感じ取れると思う。そして、それだけでも本書を読んだ価値はあると断言したい。
個人的には、これまで頭の中でばらばらの点として存在していた数々の思想が、一応弱いながらも一定の線を描きつつあるように感じられたことも含めて非常に満足のいく読書となりました。
投稿元:
レビューを見る
言葉が何者だというのですかと以前先生に尋ねた。わたしには言葉がどうしても単なる音であってそのパフォーマンスを心得たものが理知あるとみなされているように思えていたから。
この本を読んでその答えを見つけられたように思う
「画家は手綱やはみを描くであろう、しかしそれを作るのは革職人や鍛冶家だろう」作家であるホメロスも音楽家も女優も実際には、語るそのものについての知識を、技術を、持ってはいない。それは神から数えて三番目の職となる。(二番目は実際にそれを作り出す人のこと。)しかし
言葉の意味に対する共通理解がなければ勘違いといざこざが絶えないだろう。そのうえで共通認識を持たせるために文化、文芸が発達したのであり快い音とは、美とは統治に欠かせないものだろう。しかし現代ではより多くの富を得ることが快いとされるために自ら創り出すよりもそれを演じる人たちをうらやましいと思うのである。やはりここでも形骸化が起こっているといえると思った