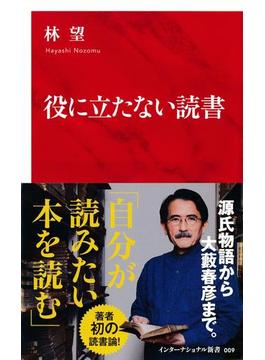リンボウ先生の「読書について」
2017/09/27 05:45
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る
ショウペンハウエルの『読書について』という本にこうある。
「読書は、他人にものを考えてもらうことである。(略)だから読書の際には、ものを考える苦労はほとんどない。(略)読書にいそしむかぎり、実は我々の頭は他人の思想の運動場にすぎない」と。
読書好きにとっては何とも耳のいたい文章だ。
そして、この本。作家で国文学者でリンボウ先生と親しまれている著者の読書論のタイトルが「役に立たない読書」というのも、痛烈だ。
ただショウペンハウエルもリンボウ先生も、読書をするなと云っているわけではない。
リンボウ先生の言を借りれば、「内的な契機のない読書には意味はない」ということだ。
さらに、リンボウ先生は「読書量と人格はなんら関係がない」と云う。要は、「一冊の本をいかに深く味わい、そこから何を汲みとり自らの栄養にしたか」だと。
この本の前半部分はこのような読書に関してのご意見鋭く、読んでいて小気味いいぐらい。
ただ中盤あたりから、ご自身の職業的な話と関係して、古書とのつきあいとか古典の話になって、中だるみ(自分には合わない箇所なのでしょう)ですが、最後の章「書物はどこへ行くのか」となれば、さすがにリンボウ先生、本の特長をよくご存じで、興味が蘇る。
リンボウ先生は、紙の本を内容だけでなく全体の装幀や紙質といった「オブジェクトとしての書物の形」を私たちは愛してきた経緯があるとみている。
確かに、新刊を買ってその手触りを愛で、匂いをかぐなんてことは電子書籍にはできまい。
本を愛するリンボウ先生ならではの、読書論である。
本当に役立たない
2017/07/13 00:40
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ヤマキヨ - この投稿者のレビュー一覧を見る
筆者の本は所有すべきだという意見には一方で賛同する自分がいます。自分も、今後もう読まないだろうと思う本を捨てられずにいます。でも、その一方で「本は自分で買って、自室でじっくり読むのがよい」と言われると反発も覚えます。誰もが静かに読書ができる自室を持っていて、書籍代をまかなえる余裕がある人ばかりではありません。現実はシビアです。どんな読者を想定して書かれたのか知りたいところです。
投稿元:
レビューを見る
読書への愛情を感じます。
・役に立つかどうかでなく、自分の娯楽として読書しなさい。
・本は自分の一部だから、本当に自分の支えや血や肉となった本は手元に蔵書しよう。
・無理に読む必要はないが、関心を持った所から古典に入ると不易な人間の営みが理解できる
こんな感じでしょうか。
投稿元:
レビューを見る
リンボー先生の読書論である。リンボーさんが読書についてこれまで何も書いてこなかったわけではない。『時間の作法』でもそういうことを書いていた記憶がある。しかし、読書の仕方、本の買い方、古本屋さんとのつきあい方等々まで書いたのは本書が初めてだろう。リンボーさんの基本は本は借りず自分で買え、である。ぼくもそう思うが、これはだれにでも実行できることではない。本に費やすだけのお金の余裕があってできることである。本を読むことをなりわいとしていない人にこれを求めるのは難しい。ぼくの妻などは、本は二度読むことなどほとんどないから、借りて読むのがいいという。これはお金がもったいないという以外に、ものを貯め込みたくないという考えからだ。にもかかわらずぼくは本をどんどん買っていくので、いつも妻との争いが絶えない。それはともかく、リンボーさんは人の家にいけばまず本棚を見せてもらうという。同じことは内田樹さんも言っていた。そういうものがなければ、その人との接点がなく、とりつくしまがないというのである。たとえ、そこにある本をすべて読んでいなくても、この人がどんなことに関心をもっているかがわかる。そこから共通の話題がみつかったりする。読んだから売ってしまえば、まさにとりつく島がなくなってしまう。本棚は自分にとっても過去の記録なのである。/リンボーさんは本は楽しく読むことで、感想をもとめたり書いたり要求してはいけないという。これは教師としてはなかなか実行できないが、子どもに本を読んでやって、では感想は?というのも実はおろかな質問なのだとわかる。楽しいと思うことが大事なのである。そこで、感想文となると、楽しさも半減してしまうのである。だから、読書会も必要ないとリンボーさんは言う。徹底している。ただ、リンボーさんは古典の先生で源氏や平家を翻訳するくらいだから、古典については感想を書いたり、注釈を調べたりせざるをえない。だから、リンボーさんの読書論が一般にも通用するかは少し問題ではある。
投稿元:
レビューを見る
人生はできるだけ楽しく、豊かに(^_^)豊かに楽しく生きることの秘鍵が、すなわち自由な読書♪\(^o^)/自由に読み、ゆっくり味わい、深く考える、絶対の自由と自主、それこそが読書にとってもっとも大切!!(^o^)
投稿元:
レビューを見る
題名がいい.仕事で読まなきゃいけない本は読書じゃないだろうから,ここで取り上げられているのは広い意味での娯楽としての読書.その点に関しては.読みたい本だけを読めばいい,という著者の主張は正しい.著者の主張を知るには最初の50ページくらいを読めばいい.あとは自分の仕事,趣味に関する話で好きな人は好きだろうが,この本の趣旨からすれば蛇足.20,30分立ち読みをすれば十分な内容.
それにしても,たくさんの自分の本から引用.こうでもしないと一冊分の新書の原稿がうまらないのか.
投稿元:
レビューを見る
20170802 ついつい本を買ってしまい、気付くと何がどこにという状態になるのでタイトルから参考に買ってみた。結局は本を読む事に対しての気構えとして、
「自由に読み、ゆっくり味わい、そして深く考える。」
事だと理解しました。
投稿元:
レビューを見る
ひとそれぞれに読書スタイルがある。しかしながら、読書を楽しむ人にとって、いくつか共通点が存在する。それを見つけるのもこんな本を読んだ時の楽しみになる。読書家は、えてして蔵書家でもある。楽しめました。
投稿元:
レビューを見る
「(読書だけしても)問題意識がなければ始まらない」、「課題図書をあたえて感想文を書かせても意味がない」など、おおいに首肯する部分もあるし、電子書籍と紙の図書の比較など、そうかなあ、と思う部分もあり。古典についての語りはさすがに面白く、ちゃんと古典を読んでおきたい、とあらためて思わされた。
でも結局、何かの役に立てようと思って本を読むときもあり、そうではないときもあり、色んな役割があるよね、という自分の基本姿勢について、補強するようなところしか頭に残ってないです。
あと、ちょいちょい著者の書いた他の本の宣伝が出てくるのには「ん?」となった。
投稿元:
レビューを見る
月に〇冊読んだ→そういう人に限って深みのない人物
インテリジェンスを涵養するのではなくペダントリー(pedantry 学問、知識をひけらかすこと)へ
書物の価値は時間が決める 芥川賞、直木賞を30年後に読む人がいるか?
実用書はそれなりに役に立つ→○○に合格する、料理本→マニュアルを読むのと同じ
図書館で借りた本の知識はしょせん借り物の知識☆座右に備えておく本なら買うべき 本の定義が違う?福澤諭吉の「福翁自伝」、古典全集
本との出会い 神田、本郷、早稲田
☆筆者は作家 出版社から本が送られてくる環境の人の意見→本は買うべきという発想になる/図書館ですぐに何回も利用可であれば所有と同じ/本が売れなくなるから勧めないだけ
発見をカードに書いておく☆ブクログ 本を買うこととは関連なし・図書館ですぐにまた読める環境であれば買ったことと同じ
論語 顔淵編「礼にあらざれば聴くことなかれ」 アマゾンのレビューは信頼しない
翻訳書の限界 ディスカウントストアでデオドラントを買った→大割引の店で匂い消しを買った ☆外国との差がなくなって状況を理解できる現代
本棚は脳みその延長☆ブクログ・ネット上で再現可能
ネットで自分の本が1円で売っている→日本文化の衰退局面の一つ
日本古典文学全集
恋は日本ではタブーではない 古事記 国生み神話 男女が尋常にみとのまぐわいをなして子供が産まれる。
耳で読む 源氏物語 平家物語 朗読データ参照
漱石「夢十夜」 お前がちょうど俺を殺したのはちょうど百年前だね。☆漱石の短編・有名ではないからあまり知らない
日本では電子書籍は普及しないだろう→日本語独自の問題 文字の種類 世界一同音異義語が多い
投稿元:
レビューを見る
紙の書籍にこだわり、古典を愛する著者の本に対する愛情は十分に伝わりました。実際に著者と同意見の方も多いと思います。
しかし、一方でもう少し現代における読書形態を受け入れてもいかがでしょうか。
アマゾンのレビューに関しては、匿名であるがゆえに、”まったく信頼するに足りない”と切って捨てていいます。本当にそうでしょうか?ネットが普及した現代において、レピュテーション等の集合知はますます価値を高めていると私は考えます。
著者はベストセラーを読む価値がなく、古典にこそ価値がある。なぜなら長い間人々の評価をくぐり抜けて生き残ったものであるからだと説きます。レビュテーショントは、まさに古典の様に優れたものをより優れる現代の発明だと考えます。
古典が発表された時代においては、それを読むことができる人はごく一部の人たちであったでしょうし、古典を愛でている現代とは読書形態も異なっていたと想像できます。古典を愛すればこそ、もう少し時間軸を取り入れた読書法へと議論を展開して欲しかったと思います。
投稿元:
レビューを見る
私はリンボウ先生の著書が好きなので、バイアスが掛かっている事が前提となりますが。概ね(全面的にではない)読書家としての私の理想像です。読書が何の役に立つのか?読書なんて娯楽なんだから好きな時に好きなモン読ませろやというのがスタイル。勉強のために読むのは勉強であり読書ではない。私も本の山に囲まれることに幸せを感じる方なので、買った本は基本捨てない。電子書籍は本を買うほどではない、又は紙で入手が困難な場合に限る。私もKindleは活用してますが、基本は紙の本です。思ったほどKindleに移行しませんでした。
なお、タイトルについては「読書なんて役に立たない」という意味ではなく、「読書は役に立てようと思って行うことではない」という意味でしょう。リンボウ先生が最終的に古典に行き着くのは先生がそういう趣味趣向であっただけで、世にはミステリ狂もいますし、マンガしか読まない人もいますし、中には哲学書を娯楽(知識欲)の境地で読む人がいる。それでいいじゃないか。電子書籍がダメだとはイッていない。「自分には合わない」と言っているだけ。本は捨ててはいけない、ではなく「自分は捨てない」と言っているだけ。ただそれだけのこと。
投稿元:
レビューを見る
タイトルに反して、読書の楽しさ、本を所有する楽しみなどが書かれていて、もっと本を読みたいと思わせてくれる本だった。
実用的に、役立たせるだけが読書ではない。
何冊読んだとひけらかすのではなく、読んでどんなことを感じたかが大切。
あと、自分の本棚の整理がしたくなった。
投稿元:
レビューを見る
書かれていることほぼ全て自分に当てはまって、最初から最後まで「そうそう」って感じで読了。
ただ一点、林望先生と異なり、書き込みはしない。
でも、古書で誰かの書き込みとか見つけると、どんな人が何で書いたのか、思いを巡らすのは同じ。
投稿元:
レビューを見る
林望さんの本は今までも少しばかり読んでいるのですが、語っている内容は結構すっと腹に落ちるんですね。本書もそうでした。
「ベストセラーは読まない」「速読はしない」「同時並行的に何冊も読み進める」等々は、まったく同感です。
ただ、「本は借りて読む」というスタイルの私なので、「本は自分で買って読め」という勧めは実践できそうにありません。できるだけ乱読・雑読でいきたいので、読んでみたいと思った本をすべて買っているとあまりにも“無駄打ち”が多くて、お金も保管場所もついていかないのが正直なところです。