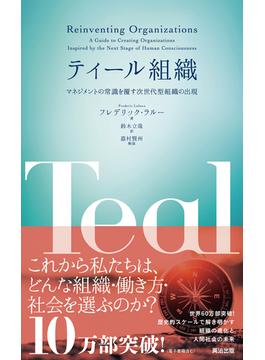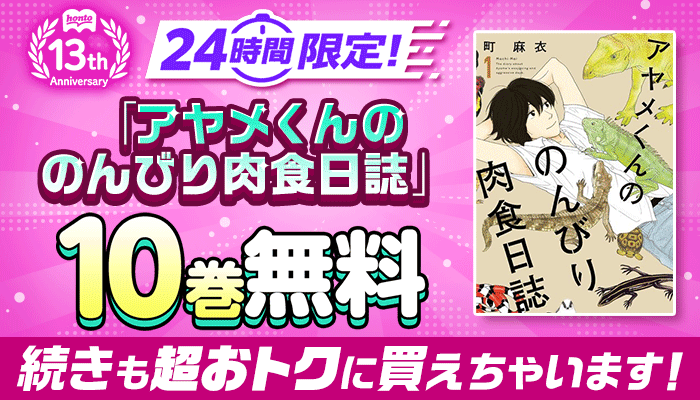新しい「進化型(ティール)」組織についての解説した書です!
2018/07/29 11:40
2人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、これまで普通のことと考えられてきた組織内の上下関係も、業績目標も、予算も何もなく、それでいて一定の成果を上げている組織の実例をもとに、新しい「進化型(ティール)」組織について詳細に、丁寧に解説した書です。本書は、販売以来、全世界でたちまちベストセラーになったという人気の書で、ようやく日本語訳も出されて、日本でも反響を巻き起こすのではないかと言われるくらいの書となっています。今、世界に現れてきている「進化型」の組織について、この機会を利用して、勉強してみるのもよいかもしれません。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みらい - この投稿者のレビュー一覧を見る
今一人ビジネスをやっているのですが、いいかげん一人では回らなくなってきたので、この本で勉強して組織づくりしたいです。
2人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
権限の分散と組織階層の欠如よりも組織としての全体性を実現する自主経営組織の影響力に重点を置くことが内部統制システムと相反せず、投資家の支持を得られるものであるならば、短期的な利益最大化を目指さなくてもよい世界が到来するのか。十年後に本書の内容を振り返ってみたいものだ。
投稿元:
レビューを見る
<自主経営(セルフ・マネジメント)>
<全体性(ホールネス)>
<存在目的> p482
全体性(wholeness)
弱みよりも強みに、問題よりも機会に注目する p388
組織は生命力を持った有機体
進化型(ティール)組織の成果を理解するもう一つの方法がある。組織は人々の意志の力ではなく、進化というはるかに大きな力、生命自体のエンジンによって勢いづいていると考えるのだ。進化はきわめて美しく、そして複雑なプロセスだが、これは特定の全体構想の下に進行するのではなく、同時に進む数多くの、小規模な実験を執拗に繰り返して成し遂げられる。進化はトップダウンのプロセスではない。全体に貢献するためにだれもが招かれ、必要とされる。生態系に棲むあらゆる生命体(あらゆる細胞、感覚のある生物)は、自分の環境を感じ取り、他の生命体と調和し、新しい道を模索する。解決策が繰り返しすばやく試される。うまくいかなければ即座に捨てられ、うまくいくシステム全体にすぐに広まる。生命は混沌の中で、より多くの生命、美、複雑性、秩序を断固として求める。生命と連携し、自分の意志を他人に押しつけようとしなくなれば、もっとはるか先まで旅することができる。p485
https://newspicks.com/news/2882782
https://twitter.com/kensuu/status/987864036065738757
https://corp.netprotections.com/thinkabout/1486/
投稿元:
レビューを見る
発達進化する組織パラダイムに呼応して
新しい組織モデルを提言。
自主経営、全体性、存在目的という3つの軸
からなる、構成員一人一人が自律的に
判断実行する、有機的な新しい組織の形。
実行ハードルも高いが具体的な事例や
実現のための示唆もありとても興味深く
思いました。
学習する組織やマインドフルネス等とも
繋がっている感じもしました。
一回読んだだけでは掴みきれないので
再読しなくてはならないと思いました。
投稿元:
レビューを見る
組織開発関係の本は、いろいろ読んで、最近は、なんとなくどこかで読んだような話が多い感じがしていて、以前ほどは熱心にいろいろ読むエネルギーが出てこない感じ。
というなかで、久しぶりに、心を揺さぶられるというか、「これを実現したい」という熱い思いがわき上がってくる本だったな〜。
要素に分解すると、どこかで読んだ話ではある。
例えば、「ああ、これはアプリシエイティブ・インクワイアリーと一緒だ」とか、「NVCと一緒」とか、「社会システム的なアプローチだな」とか、色々、元ネタは見えるんです。
でも、「それが単に色々なツールを組み合わせているだけ」とは全然感じなくて、「ああ、このツールはこういうコンテクストの中で本当に活きるんだな」と頭が整理されつつ、自分の中にすでにリソースがあることに気づき、力が出てくる感じ。
もちろん、そういうツール的なことを超えて、この本は、なんだか思いが伝わってくるんだよね。
例えば、自律型の組織論である「ホラクラシー」は、読んでも、そこまで感動はしなかった。どちらかというと仕組み系の話だからかな〜。
それに対して、「ティール組織」には、人と組織が「全体性」として存在する、そしてそれが自律的に進化していく、という思想があって、そこに大きな希望というか、夢というか、解放があるんだよね。
現実的に、じゃあ何をやるのかと考えると、障害だらけで(やはり、組織のリーダーのメンタルのパラダイムシフトが必要条件)、全く困ってしまうのだけど、それでも、なんかやりたいという気持ちが高まる。
投稿元:
レビューを見る
つながり研究シリーズ。目標達成型でもなく、多元多様性尊重型でもない、変化の激しい時代における生命体型組織。自主経営、全体性、存在目的を重視する慣行、の3点が特徴。アントレプレナーシップに通ずるものがあるが、リーダーシップの出番は少ないという、なかなか理解も実践も難しそうな形態。例えるなら同窓会組織でSFCで運営してきたコミュニティと共通点がある気がする。会社経営というより、産学連携やオープンなコミュニティの運営に役立つのではないか。それにしても分量が多すぎてへこたれそうになったよ。
投稿元:
レビューを見る
「ティール組織」Frederic Laloux
青年は幼年に比べて「良い」人間というわけではない。それと同じように、高い発達レベルにいる方が本質的に「良い」わけでは全くない。けれども、青年の方が幼児よりも多くの事が出来るという事実は残る。それは、幼児よりは高度に物を考えられるから。
どのような発達レベルでも、問題はそのレベルが目の前の仕事に適切かどうかということ。
どんな組織もリーダーの発達ステージを超えて進化することはできない。
人々をその気にさせて実力以上の能力を引き出し、自分だけではできなかったはずの結果を成し遂げさせてしまう事が組織の真髄。
恐れに置き換わるものは、人生の豊かさを信頼する能力。
生き方の本質は二通りある。「恐れと欠乏感にまみれた人生か、信頼と潤沢に満ちた人生か。」
ティールでは、意思決定の基準が外的なものから内的なものへと移行する。
ティールでは、人生とは自分たちの本当の姿を明らかにしていく個人的、集団的な行程と見る。
職業とは何かを突き詰めていくと、「エゴ」の本音を覗く事になる。それは誰もが日々意識している「自分」ではなく器としての「自分」を通して人生を送ろうとしている事実。我々が「自分の人生」と呼ぶ、表面的な職業の型にはまった経験の下には、実はもっと深い、もっと真実の、本来なりたい自分が送るべき人生がある。この違いを感じ取るには、時間と過酷な経験が必要。
内なる魂の声を聞き、目的の深い意味に到達する個人は、恐れを全く知らずに自分の使命を追求できる。自分のエゴを抑制し、挑戦せずに後悔するくらいなら失敗する方がましだと考える。「大志を抱いているが野心的ではない人。」
自分の深い内面と結びついていない人生の目標を設定する、つまり他人の顔を身にまとっていると、私たちは自分自身の強さの中に立っていない事になる。必然的に、自分には何か欠けており、自分の弱みを克服しようとするが、あるべき自分になっていないのは自分または他人のせいだと非難する。
人生を自分の本当の姿を明らかにする行程だと捉えれば、自分の限界を現実のものとして冷静に見つめ、目に入るものを心穏やかにとらえる事ができる。人生とは元々素養がないものに無理してなろうとする事ではない。
周囲の人々や状況には何が足りないか、何が間違っているかという事ではなく、そこに存在するもの、美しいもの、可能性に注意を向けるようになる。
決めつけよりも思いやりと感謝を優先する。
人、社会は、他人から解決してもらう事を待っている「問題」ではなく、本質が明らかになる事を待っている「可能性」である。
ティール以前のステージでは、人生に立ちはだかる障害物は不運と見なされる。怒りや恥ずかしさ、他人を責める気持ちでこれに向き合うと、他人ばかりでなく自分自身からも離れてしまう。一方、ティールでは、人生における障害物とは、自分自身とは何か、世界とは何かを学べるよい機会と捉える。
グリーンまでは、変化を恐れるが、ティールになると楽しい緊張となる。
オレンジ的現代科学視点は、感情を警戒する合理還元主義。グリーンはその対極であるポストモダン。ティールはあらゆる領域を積極的に利用する全体論。
ティール以前のステージでは、人と意見が異なると、対峙するか、寛容の名の下に意見の違いを取り繕ってすべての真実は等しく価値があるとする。ティールでは、自分の信念が優れている事を知るが、同時に他の人も等しい価値の人間として受け入れる。
人は自己に誠実に向き合うと、自分がもっと大きな何か、人生と意識がお互いに結びついた一つの織物のようなものの一部、その一表現にすぎない事がわかる。
どの組織形態でも組織の上位にいる人々がステージを上れば上るほど業績が伸びる。
大企業の組織変革プログラムの成否は、CEOの発達ステージが大きく影響する。
ティールの人は、自分の人生の使命を探す事に忙しいので、明確で崇高な目的を持った組織のみが密接な関係を築きやすい。収益性や成長、市場シェアよりも存在目的が組織の意思決定を導く原則となる。
ティールは全体性とコミュニティを目指して努力し、職場では自分らしさを失う事なく、人と人との関係を大事に育てる事に深く関わっていく。
権力をトップに集め、同じ組織に働く仲間を権力者とそれ以外に分けるような組織は問題を抱えて病んでいく。
ティールは上下関係はないが、代わりに自然発生的な階層、つまり評判や影響力、スキルに基づく流動的な階層はある。
コーチの役割は、
・予想できる問題を防ぐ事ではなく、問題解決しようとするチームを支援する。
・自分が優れた解決方法を知っていても自分たちで選択させる。
・考えるヒントになる問いをぶつけたり、自分の目に映ったチームの様子をそのまま見せる。
・情熱と強みと能力を引き出す
ビュートゾルフでは、
・チームメンバーは12名を超えてはならない。
・特定のテーマに関する専門知識をどの看護師が身につけているかを社内SNSで確認できる。
・専門知識を蓄えるタスクフォースがボランティアで立ち上がる。
スタッフ機能を大きくして実現できる規模とスキルによる利益よりも、モチベーションの低下による不利益の方が大きい。
モチベーションの圧倒的な向上が生産性をはるかに高める方策。確実とされてきた規模の経済の方策は捨てる事。
本当に素晴らしく心を高揚させてくれるものは全て、自由に仕事に励む個人によって創造される。
-アインシュタイン
グーグルの20%ルールが、ティールでは100%ルール。
ティール人口は西側社会の5%。
ティール社会はGDP成長率はなくなるが、人間関係、感情面、精神面でははるかに豊かになる。
教育は、学習者一人一人が他社と協働しながら独自の学びの旅を創り出すような方式へと生まれ変わる。
金融システムは、自分で貯めておいた資産があるからではなく、様々な共有関係が織りなす揺るぎない信頼があるからこそ安心できる社会、そして、何か必要性が生じた時にはお互い助け合える事を知っている社会。
友情や関心のネットワークが真にグローバル化する。
人類史上初めて、幸せな一握りの人々だけでなく、誰もが自分の使命感に従って、創造的に自己表現する人生を自由に選べる時代。
ティールでは、宗教上の教義(アンバー)にも、現代の物質的な見方(オレンジ)にも満足せず、個人的な経験と慣行を通じて統合と超越を求める。宗教対立を解消し、非宗教的な精神性を通じて現代の物質的見方を変え、喜びと幸せをもたらそうとする。
株主や寄付者はスチュアードシップホルダー(管理責任所有権者)に変わる。ホルダーは余ったお金がすぐに必要でなければ自分たちが大切だと思える目的に使う事ができる。配当はないが、資金提供者が不運に見舞われた時は、その人の貢献額等に応じて支援する。違いを助け合う仕組み作り。
ティールに到達すると、将来を支配しようとする欲望よりも、豊かさへの信頼を高めるようになる。
ティールの場合、存在目的の達成に向けて努力することの方が、組織の為に働く事よりも重要なので、組織同士が境界をまたいで協力する可能性が拡がる。
人間の活動を体系化する簡単な方法は、世界は本質的に秩序だっていると認識する事。
我々はこの世界を巨大な機械として見るように教えられてきた為、自分たちも機械なのだと考えるようになった。
人間はとてつもなく生産性が高く、情熱的で、目的意識の明確な組織を作るだけでなく、社会全体さえ変える事ができる。
もし私たちが人間性にあふれた世界に存在する事ができれば、一体何を実現できるだろう?
ティールでは、これまでの階層関係が仲間同士のコミットメントに置き換わる。
ティールの限界は現実の一側面、つまり顕在意識における具体的な経験の範囲に限られている。この先、情熱と精神の世界と直接協力できるティールを超えた組織が現れる。
投稿元:
レビューを見る
ただの概念の提示だけではなく、そもそも社会学的なアプローチから組織の発展を説明し、実際自然とティール型組織を実現している複数の企業の実例を記載。また解雇や給与など多くの人々が疑問に思う点についても実例をベースに記載されており、大変面白い本であった。
以下一部要約
ヒトの意識が時代とともに進化、成長、発展を遂げており(マズローの欲求段階など多くの研究が示すように)、意識の発展により組織のあり方も実は変わってきている、という前提、背景から、ティール型の組織について説明されている。
今を生きる人々からイメージしやすい発達の歴史としては、マフィアやヤクザをメタファーとしたレッド型組織。恐怖により集団を目的達成へと導く。
アンバー型を飛び越え、オレンジ型組織になると、科学的、論理的な考えから効率性を重視したピラミッド型組織で目的達成を図る。これは日本の多くの企業が該当するだろう。
グリーン型組織に進むと、欧米的な価値観、個人の意思重視し、ワークライフバランスといった価値観がここに該当するだろう。トップダウンの意思決定よりはボトムアップでの目的達成を目指す。
最後にティール型組織になると、行き過ぎた個人尊重の姿勢から一気にホールネス(全体性)を持った組織が生まれ、階層は無く、権限、肩書きもない、また達成目標もない。
ある工場の例では、毎年機械的に設定される改善目標15%を廃止した所、目標設定していた時よりも良い結果が出たとのこと。
徹底的な性善説に基づき運営される組織になるが、この組織を実現するには、社員の自己啓発的な研修や組織のための議論をするための訓練を施し、ティール型組織を維持することが要とのこと。
投稿元:
レビューを見る
現代の人々がこれまで属してきた組織-学校、部活動・サークル、会社、NPO、父兄会等-の常識を覆しながら、組織に属する人間の幸福と組織の生産性を共に両立させる夢のような組織モデル、それが本書で語られるティール組織である。
既存の組織の常識はティール組織において、以下のように覆される。
・CEOのようなリーダーの下で、ピラミッド状の上下関係から成立する
→リーダーはおらず、全ての意思決定は分散的な各チームにより行われる
・組織の各人は事前に定められた職務内容(欧米のHRでいうところのJob Description)に沿った分業体制を取る
→直接業務であれ間接業務であれ、各人は自らの仕事を自分で定義する
・組織では自らの人間性を表出することは極めて困難であり、仮面を付けた状態で組織にいる時間を過ごさざるを得ない
→ティール組織では既存組織で喪失されがちな人間性を取り戻すことを強く意識することで、各人の生産性が最も高い状態で組織の仕事をこなすことができる
本書はそうした新たな組織モデルであるティール組織の成立要件、中央集権/ピラミッド型の既存組織との違い、もたらすメリット、ティール組織の立ち上げ方/既存組織の変革プロセス等が、先行事例たる複数の企業/NPO団体への調査を踏まえてまとめられている(そういう点では、組織論版の”ビジョナリー・カンパニー”という感じがする)。
さて、インターネット/ITの特徴の一つに中央集権から分散型へのシフトという点が挙げられるように、確かにこのような分散型の組織モデルは確実に求められているのは間違いがない。ただし、本書でも既存組織をティール組織に変革させるには非常に困難であり、むしろスタートアップのようにこれから組織を作るような場合の方がティール組織は向いているのでは、と書かれているように、この組織モデルをいざ作り運用するというのは、相応の覚悟がないとできないという印象。また、戦略面との相性で言うと、やはり新規事業創出系の方が相性は良さそうに感じる。
そういう点で、ティール組織が帯にあるような「次の組織モデルはこれだ」というほど普及するとは全く思わないが、新たな価値を生むモデルであるということは同意できる。
投稿元:
レビューを見る
(1)マッキンゼーの7Sモデルを想起させる。
システムを変えることで価値観や人材、文化を変える。
昔は、組織構造をいじって、文化などのソフトを時間をかけて変えようとする。
そのために、目標管理制度や成果主義型賃金制度などを導入して、失敗した。
今は、心理的安全性を重視し、個人のパフォーマンスが発揮できる環境づくりに力を入れる。
ハーズバークの衛生要因を整備し、動機づけ要因を刺激するような仕組みを取り入れる。
(2)ティール組織はIT発達の恩恵も受けている。
限界費用ゼロの世界では、有形資源のリソースは溢れてる。
しかし、人の能力という無形資源が最後の制約。
だから、人やチームに任せた方が速い。
投稿元:
レビューを見る
実際にセルフ・マネジメント組織でやってきている中でうなずく部分が多々あり、ドッグイヤー祭りだった。大企業病の処方箋にも
投稿元:
レビューを見る
実例を交えながら次世代型の組織を描くといった内容。実現したい組織を現実にするために必要なプロセスや要素がまとめられている。
投稿元:
レビューを見る
これまでの常識的なマネジメント、組織論の進化系として自主運営、全体性を肝とする「ティール組織」というものを実例を挙げながら解説している。こういう組織を築く事ができれば、心地よく従業員が働くことができ、高いパフォーマンスを発揮できるなぁーと思うが、既存組織を変革するのはハードルが高く、創業段階からのアプローチが必要であると思った。
投稿元:
レビューを見る
繰り返しが多くもったりとしているが、それに至った背景や文脈は面白い。少し先の組織のカタチ、個人に求められる力。
#ティール組織 #teal #読書記録