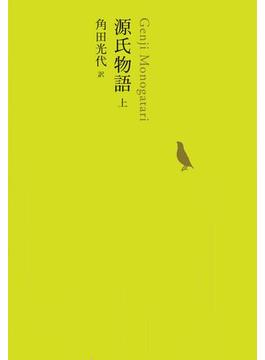主語がはっきりしていて、現代小説のように読むことができます。
2018/02/08 20:06
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぴんさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
何とかこの長い物語を俯瞰するような面白さ、運命がこんなにもねじれていく面白さというのを全体で見渡すことができないか。一帖ずつ読んでいって見えなくなるようなことがわかるためにはどうしたらいいか。そのためにはやっぱりわかりやすくプレーンな文章で書いていったほうがいいんじゃないか。そんな考え方から紡ぎだされた源氏物語の現代語訳。「格式がない」。「日本語の美しさ」だとか「王朝文学の優雅さ」だとか、そういうものはもうこの際ないことにして、とりあえずシンプルで読みやすくて、がんがん進めるものを、という人におすすめです。
読みやすい現代語訳
2025/05/03 09:21
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:kisuke - この投稿者のレビュー一覧を見る
現代語訳をされた角田さんがあとがきに書かれている通り、とても読みやすいです。それでいて格調の高さもあり、おすすめです。
源氏物語は様々な現代語訳を読んできましたが、正直言って良さは今ひとつ分かりません。今回思ったのは、容姿端麗で頭も良く、和歌も楽器も舞も何でも一流、更に大金持ちで愛人や家来にも湯水のようにお金を遣う。不遇期ですら味方が大勢…それでいて心は満たされず出家を考える。恵まれすぎた人の不幸、一見完璧に見える人の中にある暗く大きな穴を描いたのか…ということです。
女性に対する振る舞い、その場しのぎの口の上手さには辟易しました。「他所から耳に入っては」との配慮?から、紫の上に愛人達のことを話したり手紙を見せたりするけれど、こんなことをされる紫の上の気持ちまでは考えられない。
深く関わった女性はことごとく不幸にされる。どんなに口説かれても距離を保ち続けた朝顔の姫は賢かったな、と思いました。
最初から、ちゃんと。
2019/06/23 09:51
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ROVA - この投稿者のレビュー一覧を見る
源氏物語(の、もちろん翻訳版)を始めから最後まで読んだことが
一度も無かったので、ここでひとつ読みやすそうな版が発刊されて有難いです。いざ挑戦。
当たり前ですがとても読みやすいです。それにしてもすごいボリューム。
投稿元:
レビューを見る
世に優れて魅力ある男の物語がたくさんの登場人物を連ねて際限なく広がる。その一方で人の心の奥へも深く沈んでゆく。いうまでもなく日本文学最大の傑作。
投稿元:
レビューを見る
光君に心奪われ、惑わされ、近づいたり、離れたり、そんな女性心理を角田光代風に鮮やかに読ませてくれるだろうと、首を長くして出版を待っていた本。
とにかく読み易さを求めたと訳者は言っている。
確かに他の訳本よりもストーリーテーリングな感じかして、ぐいぐいと引き込まれていく。
しかしそれ以上に期待通り、女性達の微妙な心の動きがきちんと書かれているし、驚いたのは光君の心情までも丁寧に訳されていることだった。
早く次作を読みたい!
投稿元:
レビューを見る
===qte===
源氏物語 現代のリズムに
角田光代「歯切れよく、わかりやすく」
2017/9/5付日本経済新聞 夕刊
作家の角田光代が「源氏物語」の現代語訳(全3巻)に挑んでいる。歯切れよく、わかりやすい文章にすることで読み通しやすい訳書を目指したという。上巻が近く刊行される。
「源氏物語」は約1千年前、紫式部によって書かれた。光源氏が様々な女性と繰り広げる恋愛を中心に、生と死、権力闘争など平安貴族社会の内実を描いたもので、「桐壺(きりつぼ)」から「夢浮橋」まで54帖(じょう)ある。
これまで与謝野晶子、谷崎潤一郎らが現代語訳に取り組んできた。角田訳「源氏物語」(河出書房新社)は2014年に刊行が始まった「池澤夏樹個人編集 日本文学全集」の一つだ。
感情表現に共感
「『源氏物語』は学生時代にいくつかの帖を読んだだけで、特に好きなわけではなかった。すでに立派な現代語訳もあるのに、との思いもあった。でも私が唯一持っている作家のサイン本は、池澤さんの『海図と航海日誌』。そんな方に(訳者に)指名されたら引き受けざるを得ませんでした」
思い入れがない分、プレッシャーはなかったが、どんな立ち位置で現代語訳に取り組むかは迷った。「私に求められているのは何だろうと考えた。そこで思い当たったのがわかりやすさ。原文は一文が長いので切る。逆に(現代の読者にとって)言葉足らずと感じる箇所は補いました」
例えば「桐壺」冒頭の部分。帝に寵愛(ちょうあい)され、後に光源氏の母となる女性の地位は「女御より劣る更衣」であり、「与えられた部屋は桐壺」という説明を加えた。一方、地の文の敬語はできるだけ削り、頭に入ってきやすい歯切れのよい文章を心がけた。
文末は「自分が書き慣れていることと、やはり読みやすさを考え、『だ・である』調を選んだ」という。
現代語訳を進めていくうち、「源氏物語」の魅力にも改めて気づいた。「登場する女性たちは感情表現によって顔を与えられていると感じました。それは現代でも『ああ、分かるなあ』と思う感情です」
中でも胸にひしひしと迫ってきたのが上巻最後の「少女(おとめ)」の帖。光源氏の子である夕霧と、幼なじみの雲居の雁(かり)との初恋を描いている。「2人が引き裂かれたときは、思わず泣いてしまった。それは現代語訳に取り組んで初めての経験でした」
小説執筆は休止中
「――ところで光君という名は、高麗人の人相見が源氏を賞賛してそう名づけた、と言い伝えられているとのこと……」(「桐壺」)とあるように、「源氏物語」には「草子地の文」と呼ばれる作者とおぼしき声が登場する。「(人物や和歌を)いちいち挙げるのはやめておきますと宣言する箇所を読むと、面倒と感じていたのだろうと思う。作者が身近に感じられて興味深い」と述べ、その部分を目立たせるようにした。
「源氏物語」に取り組むため、15年春から小説執筆は休止中。「現代語訳が小説にどんな影響を及ぼすかは自分では分からない。でも周囲の方々が『必ず役立つはず』と言ってくれるので、それを信じています。確かに“小説心”を��こさせる要素はたまっています」。中巻は18年5月、下巻は18年末~19年の刊行を予定している。
(編集委員 中野稔)
===unqte===
投稿元:
レビューを見る
源氏物語を、初めて通しで読んだ。
読みやすい訳で、各話ごとに登場人物の相関図が書かれているので、私のような初心者にはぴったりだと思う。
大体のあらすじは学生の時に授業で習っていて、プレイボーイの話だということは知っていたけど、これほどまでに節操ないとは…驚いた!
でも、どの女の人も大事に想う気持ちに偽りはなく、こまめに手紙を送ったり、贈り物をしたりする心配りは、大したものだと感心する。
投稿元:
レビューを見る
高校生の時、教科書で「若紫」を読み、これっておもしろいよなと思って古文読解テキストを購入。でも序盤で飽きて挫折。
大学生の時、実家で母が買っていた瀬戸内寂聴訳を読むも雨夜の品定めあたりで頓挫。
働き始めた頃ふと購入した文庫の円地文子訳も同様。
嫁さんが持っている「あさきゆめみし」でさえ明石から先は読めず。
こんなわけで多分生涯読み通せまいと思っていた「源氏」だが、角田光代の新訳を買おうかどうか逡巡。今回も読めるか分からないし、なにせ本にしては高額で・・・。
しかし梅田の書店で角田さんのサイン本を見て、えいやと購入しました。彼女のコメント、「読みやすい訳を心掛けた」という言葉を信じました。
結果は意外なほどすいすい読み進められました。
尊敬語・謙譲語で身分関係を表すというこの小説の特徴をあえて無視したとのこと。
角田さんの仕事は本当に素晴らしい。
今まで読めなかった人もぜひ手にとって欲しいです。
よく考えれば、上中下巻(既刊はこの上巻のみですが)全部買っても、新幹線の東京・大阪片道に及ばないくらいの額です(本って他のエンターテイメントに比べたらホントに廉価)。
男だから光君の気持ちも分かると以前は思ってましたが、この小説に描かれている男女はそれぞれがそれぞれの地獄を抱えているように思えます。
結局、簡単になびく女性には興味がなく、いろいろな理由から返事がなかったり会えなかったりする女性のことばかり考えて悶々としている源氏の姿がずっと描かれている。
返歌がないと思い悩むのはLINEの既読スルーと変わらず、いつの世も変わらないのだなとも。
ちょっと落ち着いたと思ったら事件が起こって、エンターテイメントとして完成されている作品のように思います。
余談ですが、毎日通勤で通ってる道中に紫式部が住んでこの本を執筆していた場所(廬山寺)があることも最近知りました。
投稿元:
レビューを見る
国語の授業なんて覚えていないので、知識ゼロベース。
読み始めた時は、馴染めない世界観と分厚い紙束に後悔してた。気づいたときには、滅茶苦茶面白くなってた。
光君が破天荒。
歌で雅にごまかしてるけど、女性と寝ることしか考えてない。老いも若きも、美しいのも醜いのも誰でもあり。時代背景あるんだろうけど、理解が追い付かない。そんな超美男天才も凋落したり復権するから、また面白みが出るんだろうな。ワンチャンだけじゃなくてきちんとフォローしてるし。
歌が数えきれないくらい詠まれる。
この物語の一番すごいところって、長大なストーリーの構成力らしい。確かにすごい。そのストーリーをフルカラーで彩ってるのは、登場人物が詠み続ける和歌だと思った。日本の風景に重ねて歌われる恋心は、なんだかしんみりくる。一番印象に残ったのは、澪標(身を尽くし)の歌。好き。
角田光代の技量も大きいんだろうけど、1000年残っている物語の深さ、度量の大きさのようなものを感じました。中巻下巻も楽しみです。全部読みます。
投稿元:
レビューを見る
やっと読み終わった。圧倒的ボリューム。
600ページ超えの長編。これで上中下の上巻というのだから、源氏物語のスケールの大きさが計り知れない。角田光代さんの訳は非常に読みやすかった。注釈がなくてもスラスラと読めた。ただ、やはり昔の言葉独特の読みづらさがあるので、普通の現代小説みたいには読めない。でも与謝野晶子よりは断然読みやすかった。
光源氏の息子夕霧が幼い恋をする「少女」までが収められている上巻。「花散里」の終わり際、昼ドラめいた会話で面白さが際立ったと思った。
二条の東の院で姫君たちを集めて住まわせるなんて、大奥みたい。でも一人ひとりに愛情があって、財力もあるから光君って恵まれてる。それをしてもおかしくない実力があったw
投稿元:
レビューを見る
うーん。個人的には、文体が簡潔すぎて(…した。とか…だった。とか。あとセンテンスも割と短め)
読みやすいのかもしれないけど、情緒に欠けるというか。
現代語訳は、田辺聖子のほうが好みであった。
人物相関図がところどころで差し込んであるのはとてもいい。
投稿元:
レビューを見る
文章が現代の小説のようで読みやすい。
状況がよくわかるから、始めは家系図にするとわかる血の濃さに驚いたし、一夫多妻制に慣れるまで光君の浮気性に苛々した。若紫では子供を相手にほぼ誘拐で気味悪いし、葵の上が陣痛で苦しんでいる時には「あなたはひどいよ。私をつらい目にあわせるんだね」と泣き出すし。産後の体調不良で横になっている時には「子どものように甘えているから、こんなにいつまでもよくならないのだよ」と言ったり。現代の感覚なら有り得ない!クソ野郎!!という印象だった。特に帚木で男友達と、最高なのはどんな女か、と女性批評しているのは眉を顰める。
しかし慣れてくると、マザコン(藤壺)、ツン(葵の上)、人妻(空蝉)、ロリ(若紫)、不細工(末摘花)、不倫(明石の君)とバリエーション豊かで、まるで恋愛シミュレーションゲームのようだと思えた。
自然の描写や和歌は凝っていてとても美しいし、絵合や六条のお庭造りも面白い。また光君も容姿や服のセンス、血筋や知能や財力もステータスカンストで申し分ない上に、大変な筆まめで相手の心をくすぐるようなものを作るから確かにすごい。よく泣くけど、乱暴なところがないのも好印象。ただ、さらっと昇進するけど仕事はしてる?とは思ってる。
一冊が長いけれど楽しく読めた。
最後の池澤夏樹さんの解説も興味深かった。
投稿元:
レビューを見る
古典なので、読みづらいのではと思っていたが
とても読みやすく、登場人物の感情がよくわかるため
分厚いのに最後まで読み進めることができた
投稿元:
レビューを見る
淡々と現代語に訳された源氏物語。初めは物足りなく感じたけれど、淡々としているおかげで当時の風習や人々の考え方がよくわかる。
投稿元:
レビューを見る
2021113
ずっと読もう読もうとしていてやっと読み始めました。誰訳かも含めて。
4月に友人と感想を言い合う予定でよんでて楽しいです。よめるかなぁ〜
そして、すでに身分制度と今も変わってない女性の地位の低さにうんざりしてる。和泉式部日記のラジオ古典購読も並行して、きいてます。
20210126
ひとまず読み終わりました。643p。
光の君の恋物語。
なんでも許される人。
藤壺や桐壺や朧月夜や明石の君なんかは完璧すぎて、末摘花や花散里がでてくることで当時の人たちは自分もいつかって喜んだのかなぁ。なんて。
六条御息所が夕顔や葵上に取り憑く生き霊のところとかちゃんとはじめて読みました。
須磨に流された時、何の罪も犯してないっていってて、右大臣一派が病気になるんだけど、そうかなぁ。
まぁ、あとで藤壺との秘密が自分に返ってくるんだけど。
天網恢恢疎にしてもらさず、か。
当時は一夫多妻制で天皇の皇子である光は好き放題に見えるけど、どれくらいの頻度で女たちにあいにいつたんだろう。そして筆マメだなぁ。
紫の上にお子が出来なかったってのがなー。
3巻ある内の1巻目だけど一番ヒカルが栄華を極めるしょうで、角田さん訳狙い通り読みやすかったです。たいした思いもなく訳されたってのもとってもわたしには良かったです。
さて、中をよむかな。