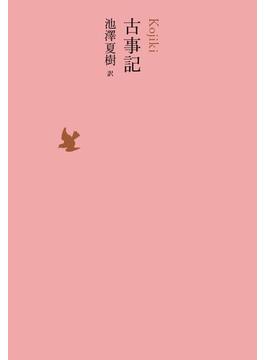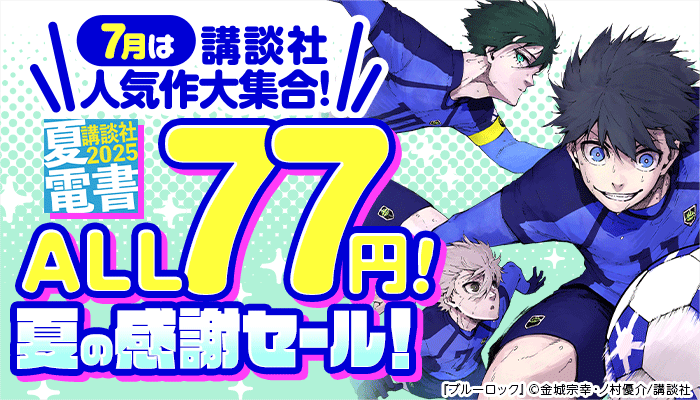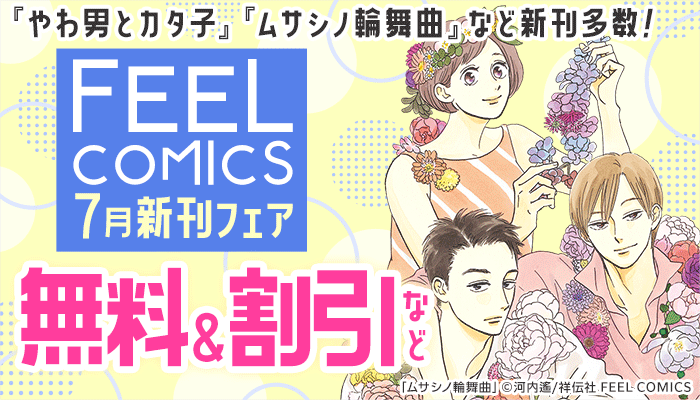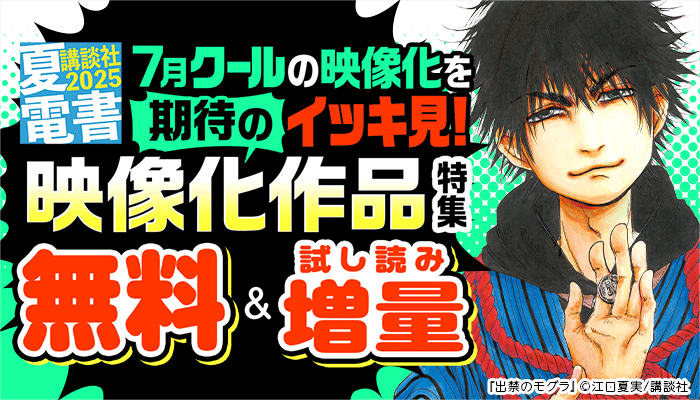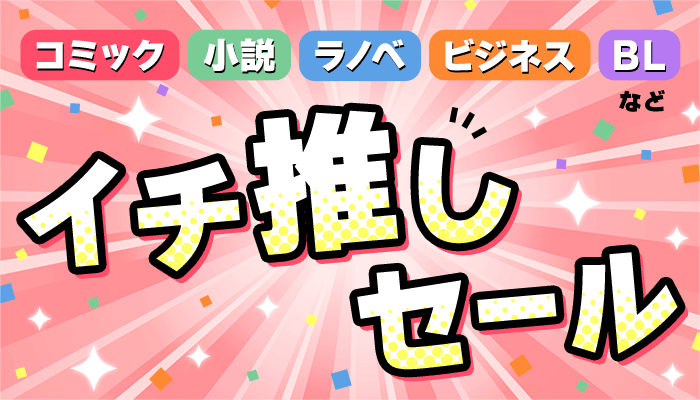- みんなの評価
 50件
50件
池澤夏樹=個人編集 日本文学全集
日本最古の文学作品を作家・池澤夏樹が新訳。原文の力のある文体を生かしたストレートで斬新な訳が特徴。画期的な池澤古事記の誕生!
【新訳にあたって】
なにしろ日本で最初の文学作品だから、書いた人も勝手がわからない。ごちゃごちゃまぜこぜの中に、ものすごくチャーミングな神々やら英雄やら美女が次から次へと登場する。
もとの混乱した感じをどこまで残すか、その上でどうやって読みやすい今の日本語に移すか、翻訳は楽しい苦労だった。(池澤)
解題=三浦佑之
解説=池澤夏樹
月報=内田樹、京極夏彦
日本語のために
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは


この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
日本文学全集 09 平家物語
2017/10/26 20:30
結構面白かった。
12人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:たまがわ - この投稿者のレビュー一覧を見る
訳者は前語りで、
『 つまらない挿話は省いたのか。無意味だと判断した書き足しを削ったのか。
すっきりさせて「ダイエット版の現代語訳 平家」を生んだ?
否だ。
私はほとんど一文も訳し落とさなかった。敬語だって全部訳出した(むしろ増やした)。
章段の順番もいっさい入れ換えなかった。』
『 私は全身全霊でこの物語を訳した。
鎮魂は為せたと思う。』
こう言っているので、安心して読めた。
原文ではとても読む気になれないし、どうにかこの訳で、途中飛ばし飛ばししながらも
何とか読み通せたので、良かった。
この訳によって、登場人物たちがより生き生きと描かれているのだと思う。
結構面白かった。
現代でも馴染みのある神社仏閣が、物語の舞台として結構出てきて、これも良かった。
試しに一部分を、手元にあった原文(版が違うかも?)と併せて載せてみた。
薩摩の南方の洋上にある鬼界が島についての描写の部分。
嶋の中にはたかき山あり。とこしなへに火もゆ。硫黄と云物みちみてり。
かるがゆへに硫黄が嶋とも名付たり。いかづちつねになりあがり、なりくだり、
麓には雨しげし。一日片時、人の命たえてあるべき様もなし。
島の中には高い山がございます。
永久に火が燃えております。
硫黄というものがいっぱいです。
そのために硫黄が島とも称されるのですが、まあ噴火の轟がいつも鳴り上がること、
そして山頂より鳴り下ること、それから麓では雨がしきりです。
一日片時といえども人が生きていられるところとは思えません。
壇ノ浦の合戦中の出来事。
「けふは日くれぬ、勝負を決すべからず」とて引退く處に、おきの方より尋常にかざっつたる小舟一艘、
みぎはへむいてこぎよせけり。磯へ七八段ばかりになりしかば、舟をよこさまになす。
「あれはいかに」と見る程に、船のうちよりよはひ十八九ばかりなる女房の、まことにゆうにうつくしきが、
柳のいつづれぎぬに、紅のはかまきて、みな紅の扇の日いだしたるを、舟のせがいにはさみたてて、
陸へむいてぞまねひたる。
とはいえ「今日はもう日が暮れてしまう。決戦は無理だ。」というわけで、引き揚げはじめた。
そのときだった。
沖のほうから立派に飾り立てた小舟が一艘、汀をめざして、来る。
漕ぎ寄せる。
と、磯へ七、八段ほどの距離となったところで、船の向きを横にする。
「あれは、なんだ」源氏の軍兵たちは訝る。
目を離さないでいると、船屋形から年のころ十八、九の女房が現れる。
柳の五衣に紅の袴を着て、優美なことこの上ない。紅の地に金箔でもって日輪を描いた扇を持っている。
いや、扇は竿の先についていて、その竿を持っている。その竿を船乗りたちが足場とする船の縁板に建てる。
それから、陸にーー源氏の武士たちにーー向かって手招きをする。
日本文学全集 04 源氏物語 上
2018/02/08 20:06
主語がはっきりしていて、現代小説のように読むことができます。
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぴんさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
何とかこの長い物語を俯瞰するような面白さ、運命がこんなにもねじれていく面白さというのを全体で見渡すことができないか。一帖ずつ読んでいって見えなくなるようなことがわかるためにはどうしたらいいか。そのためにはやっぱりわかりやすくプレーンな文章で書いていったほうがいいんじゃないか。そんな考え方から紡ぎだされた源氏物語の現代語訳。「格式がない」。「日本語の美しさ」だとか「王朝文学の優雅さ」だとか、そういうものはもうこの際ないことにして、とりあえずシンプルで読みやすくて、がんがん進めるものを、という人におすすめです。
2021/08/19 18:15
古典とは…
6人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ワシ - この投稿者のレビュー一覧を見る
…セックスだそうである。エロいのは男の罪…それを許さないのは女の罪…なのだが、それ自体は人類の宝である。
もちろんそれだけじゃないのだが、なにぶん娯楽の少ない時代の話だしそういう面が強いのも事実である。
わが国で初めて「霊」の字を使った『日本霊異記』
ここのエピソードは知らずとも『今昔物語』『宇治拾遺物語』『発心集』が説話集というのはなんとなく認識されていると思う。
仏法説話のように見えて現世利益にこだわったり、勧善懲悪のようでいて聖人がアレだったり、若くきれいなお姉さんのアソコに蛇がささってセッ(略。
エロ、ギャグ、オチ無し、訓話、ヤマ無し、悲喜劇、恋愛、ありとあらゆる物語の要素・本質が詰まっている。
ここを全くかすめずにお話を書くのは不可能ではないの?と思うほど。
作者も歌人も不明の名作は数知れず、日本文学は意外に深くておっかない。
町田康訳にはゲラゲラ笑わせてもらったが、町田は“現代語訳”だからとデタラメや好き勝手を書いてるわけじゃない。
音韻や雰囲気や空気感にリズム感、現代の我々と当時のノリの差を埋める事に徹底してこだわっており忠実そのものの「訳」だ。
ぜひ原文にも当たっていただきたい、元のお話が最高に面白いから。
宇治拾遺の「孔子倒れ」は傑作。
儒学に傾倒した支那王朝、朝鮮王朝は著しく柔軟さも活気も失ってしまい、国家そのものが停滞した。
わが国では、儒学から朱子学までの盛衰をみると、一時的なミニブームになりこそするも根を下ろすことはなかった。
実に笑けるのは、ヒマさえあれば儒者は倭国を見下していたが、しかしその倭人(我々のご先祖様)は儒者の本質を結構簡単に見抜いていたというところだ。
隙が出来たのでセックス!とねじ込んでみる。

実施中のおすすめキャンペーン