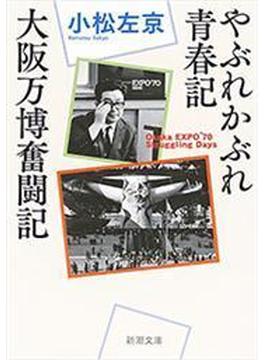小松実盛さんの「「青春記」には書かれなかったこと」では漫画家としての小松さんを紹介。漫画『怪人スケレトン博士』の一場面も見開きで。
2018/10/16 18:52
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぴんさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
自身のSFの原点となった戦中戦後の混乱の青春時代。当時最大の国家プロジェクトであったEXPO'70大坂万博の理念創りに深く係わった壮年時代。二つの時代の記録から、小松左京の本質と目指していた未来に迫ります。今では直感的に分かりにくくなった戦時中の食べ物や衣服の細かい描写、経験した人でないとわからない理不尽なメカニズムや生活の惨めさ楽しさ、栄養失調のときの無気力、戦後にあらわれた民主主義、闇市、一年間の本物の青春など、盛り沢山。
合本にした意図が良くわからないんですが、ファンは必読です
2020/08/15 23:15
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:忍 - この投稿者のレビュー一覧を見る
なんで今更、こんな本が新刊で発売されるのか、と思いながらも、とりあえず購入だけして積読状態だったのですが、ようやく読みだしたところ、やぶれかぶれ青春起にびっくり。ユーモラスな文章の合間に垣間見える陰惨な戦時中の小松実少年のエピソードを読むと、その後の作家小松左京がどうやって生まれてきたか、なぜ「地には平和を」が書かれなければならなかったのか、なぜ希望と絶望、光と闇を追い続けたのかが少し解けた気がします。大阪万博奮闘記のほうは、次の大阪万博の関係で出版されたのかと思いますが、意図が良くわかりません。関係者による(聞き書きの)解説文がついていますが、できれば第三者から見た解説文をつけていただいて、小松左京の果たした役割や功績を客観席に評価してもらえるとよいかと感じました。
次の大阪万博に備えよ
2018/11/01 20:29
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:しゅんじ - この投稿者のレビュー一覧を見る
小松さんの新刊とは! 『やぶれかぶれ青春記』は旺文社文庫版を中学生の頃に読んで、スゴく面白かった記憶があるが、万博関係の手記は初めて読んだ。小松さんの作品に出てくる役人には優秀な人が多いんだけどな。現実の役人に苦労させられた反動なのかしらん。理念のない商売先行の万博なんかやるもんじゃないよなあ。小松さんも梅棹さんも居ないのに大丈夫なのか。
投稿元:
レビューを見る
巨人、スーパーマン小松左京の肉声の雰囲気があふれでる。北杜夫『どくとるマンボウ青春期』に通じる終戦直後の高校生のドタバタ青臭さと、高度成長期に京都学派の重鎮たちと未来を刻印しようとするコーディネーターあるいはプロデューサーもしくはエバンゲリストとしての顔。SF小説家という括りにいれるには大きすぎる小松左京に圧倒され、共感する。
投稿元:
レビューを見る
前半は、戦中期を中心とした学生時代の話。正直あまり愉快な話ではないが、旧制中学時代のエピソードなどからは、著者の怪物ぶりが伝わってくる。漫画家としてのエピソードが一切出てこないことは、ご子息の解説にもあるが、ブルドーザーとも称される著者の意外な屈託が感じられ、興味深い。後半の万博の話は、大阪万博の影の部分とも言え、後世に残す意義は大きい。著者の感じた万博の難しさは、次の大阪博にも生きるものと思う。これを機に、著者のノンフィクションを含む膨大な著作が、もっと入手しやすくなることを切に願います。
投稿元:
レビューを見る
筆者である小松左京の、エネルギッシュで熱量溢れる書きっぷりが感じられます。
戦中時代を生き抜いた筆者による回顧録と体験談で、万博の裏事情がよく分かった。
投稿元:
レビューを見る
小松左京。「日本沈没」があまりにも有名なSF作家。漫画を描いたり、サブテーマ委員等で1970年大阪万博に深い関わりを持った万能の人だった。万博を単なる国際見本市にするのでなく、理念を大切にした。2025年開催が決まった大阪万博を進めるにあたっての遺産となった。多忙な中で、著者含め仲間たちがエネルギッシュに活動する様子に疲れや倦怠感は感じられない。義務でなく興味本位で取り組んだ由縁である。その器質は、青春時代に培われたこともわかった。2020.3.12
投稿元:
レビューを見る
小松左京氏のといえば、日本SF界の巨匠、ベストセラー作家とか知の巨人とか称される。その小松氏がまだ若かりし頃のお話。
この本の前半は、蛍雪時代に掲載された「やぶれかぶれ青春期」。旧制中学、旧制高校、そして新制大学の学生時代を振りかえっている。連載当時は、戦争体験者というか実際に戦場に赴いた人も多かった時代。ホントーに貴重な話が載っている。あと小松氏のご子息の一文『「青春記」に書かれなかったこと』は必読。
後半の「大阪万博奮闘記」も、これまた貴重な話が載っている。小松氏のか「限りない知性」とでもいうべきものが見てとれる。もとネタのひとつ「万国博覧会資料」は、現物が確認できていないとのこと。やっぱり貴重だ。
投稿元:
レビューを見る
SF界の怪物、小松左京を形成したものはこの戦中戦後の動乱期の経験にあることを確信した。また、御子息がなぜか漫画家小松左京の話を封印していることについての身内ならではの解説が必見。
投稿元:
レビューを見る
近年、再評価の小松左京氏。
短編と中篇の間の小品を、無理矢理くっつけたっぽい一冊。
でも感謝したい、こうして書籍化していただけたことに。
それだけ二作共に楽しかったです。
投稿元:
レビューを見る
1月3日の新聞朝刊に『EXPO2025開幕まで100日』の一面広告。その文言を読んで「おやおやこれは?」となる。本書の第二部では、1970年大阪万博開催当時、著者氏らが行った、万博理念の研究、テーマづくりへの取り組みが書かれている。翻って件の広告の文言。この第二部をそっくりそのまま丸写ししたかのような謳い文句なのだった。これはつまり、著者氏らの導き出した結論が、いつの時代のあらゆる万博についてでも通用し得る優れた理念であったことの証であろうか。まさかEXPO2025の手抜きではあるまいな。
投稿元:
レビューを見る
SF作家として有名な小松左京さんの本。
前半は戦争中の話が中心。
後半は大阪万博の話。
前半の方が圧倒的に面白い。
後半はどこそこの誰それと何しをした〜みたいな、よくある交遊抄風。
でも、時代性もあり、興味のある人には参考になるのでは?
投稿元:
レビューを見る
石毛直道さんの「座右の銘はない」に小松左京さんについて、たぐいまれな独創力と構想力を備えて、考えたことを実現できる天才として梅棹忠雄と並び称されている。
万博公園に民族学博物館ができた経緯に岡本太郎さんや小松さんの思いがあったことを知った。
さて、本書。
前半は戦中戦後の青春期。
昭和ヒトケタの僕の父母も戦中に軍国主義で平気で生徒を殴っていた教師が戦後「元々民主主義の人間です」と云っていた奴を罵っていた。そんな卑怯な教師は沢山いたんだな。
恐ろしいのは戦災孤児。僕はテレビ漫画のタイガーマスクぐらいしかイメージがなかったが、4つから7つぐらいのチビ達が大人にタバコの火をおっつけ、驚いた大人に因縁をつけ、レンガで頭を殴り、鉄棒で突き倒され、身ぐるみはがしてしまう。
小松さん自身も6つの男の子と4つの女の子からピストルで撃たれたそう。
もう二度とこんなことがないようにという文に同感する。
前半の最後はたった1年の旧制三高のある意味傍若無人な自由な日々を素晴らしく豪華なものと誇ってページを終わる。
後半は万博との関わり記。元々は梅棹忠夫氏、加藤秀俊氏との私的な勉強会「万国博を考える会」。京大人脈から拡がりを見る。通産省からは反体勢力と認識されるが、のちに取り込まれる。
小松氏達のテーマづくりが無かったら、万博はつまらない見本市になったんだろうな。そして今大阪がやろうとしている万博はつまらいものになるだろうし、観に行こうとも思わない。
とり・みきさんの漫画に小松が登場する。交友範囲の広い人なんだなと思っていたが、自身もマンガをかいていたということが明らかにされている。
知的ブルドーザーという評も聞いたことがある。もっと小松さん周辺の人脈をあさってみようかな。
投稿元:
レビューを見る
「大阪万博奮闘記」は今こそ読まれるべきだと思われます。世評の高い70年の大阪万博はどのように準備されてきたのか、その一面(あくまで一面ですが)を知ることができるでしょう。そして万博開催の年、小松左京はまだ30代です。いやはや。