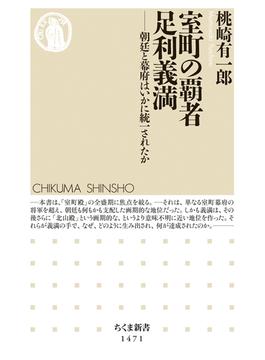目から鱗が・・・
2020/05/09 03:55
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:通りすがりの風来坊でござんす - この投稿者のレビュー一覧を見る
鎌倉・江戸の比べて、違和感のあった室町の幕府、その答えが解りました!!そもそもが、将軍の地位の在り方だったんですね。鎌倉・江戸は将軍が創業者でしたが、室町は(副)将軍が立ち上げたモノだったんですね。そう考えると、歴代足利将軍の名前が、初代尊氏(というより、その前から)の『氏』ではなく、弟の(副)将軍直義の『義』を通字としているのが理解できます。もっとも、源氏嫡流をアピールする為に、頼朝以前の源氏本流の通字を用いているのかもしれませんが・・・。
「室町殿」の栄衰
2020/04/24 08:31
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:雄ヤギ - この投稿者のレビュー一覧を見る
足利義満を中心に、「室町殿」の形成と栄衰について記している。軽快な筆致にグングン読み進められるが、時々わかりやすく伝えようとして、すこし違和感を覚えるところもある。他の研究にも目を通して、勉強したい。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:にま玉子 - この投稿者のレビュー一覧を見る
義満は絶頂で呆気なく死んでしまうので、その後の幕府のイメージがどうなっていくのか、室町ファンの想像を掻き立てますよね。
楽しく読ませていただきました。
金閣の構造が彼のメッセージだとしたら、武家と公家を超越した仏様として世を治める、そんな構想だったのでしょうか。
4人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オタク。 - この投稿者のレビュー一覧を見る
「後円融・後小松・称光の三代には、自暴自棄・精神崩壊を起こしやすい遺伝的な個性が否めない」という個所がある本だ。偏見を助長しかねない「個性が否めない」記述があると、他の個所でもありそうだ。
さすがに後光厳天皇には「遺伝的な個性」云々とは書いていないが、それは後光厳朝には見られないという事もあるが、崇光・後光厳両帝は生母が同じだからで、もし、そう書いたら伏見宮家も「遺伝的な個性」云々があると見做しうるのもあるだろう。
それでいくと足利義満は「遺伝的な個性」の「元凶」になる後円融天皇の生母と母方が同じだから義満一代限りの「バーチャルリアリティ」政治や足利義教の恐怖政治も同根だと言う事も出来る。
何となく「異形の王権」や「室町の王権」に戻った感じもする。
投稿元:
レビューを見る
<目次>
プロローグ 規格外の男・足利義満
第1章 室町幕府を創った男の誤算~足利直義と観応の擾乱
第2章 足利義満の右大将拝賀~新時代の告知イベント
第3章 室町第<花御所>と右大将拝賀~恐怖の廷臣総動員
第4章 <力は正義>の廷臣支配~昇進と所領を与奪する力
第5章 皇位を決定する義満と壊れる後円融天皇
第6章 「室町殿」称号の独占と定義~「公方様」という解答
第7章 「北山殿」というゴール~「室町殿」さえ超越する権力
第8章 虚構世界「北山」と狂言~仮想現実で造る並行世界
第9章 「太上天皇」義満と義嗣「親王」~北山殿と皇位継承
第10章 義持の「室町殿」再構成~調整役に徹する最高権威
第11章 狂暴化する絶対正義・義教~形は義持、心は義満
第12章 育成する義教と学ぶ後花園天皇~二人三脚の朝廷再建
エピローグ 室町殿から卒業する天皇、転落する室町殿
<内容>
340ページ余りの大作。足利義満が題だが、初代尊氏・直義から6代義教までが結構詳細される。そして斬新な解釈で面白い。というか、、室町時代面白い。近年のベストセラー『応仁の乱』(呉座勇一)から始まり、この時代の混沌とその中で生きた人の発想の仕方が面白い。桃崎さんはその応仁の乱も書きたいそうなので、待っていたいね。しかし、かつての今谷明の『室町の王権』は全否定されているらしいが、この本は発想的には似ている(本人は全面的に違うと言っているが)。
投稿元:
レビューを見る
「武士の起源をときあかす」の桃崎有一郎氏の新著。内容が足利義満だけにかつての「室町の王権」から中公の「足利義満」を経てどういう話にアップデートされているか強い興味を持って読んだ。
いつもながら多量の史料収集と卓越した筆致、軽妙な?ツッコミでぐいぐい読ませてくるのには感心しかない。これまたいつもどおり、核心的な主張については必ずしもピースが揃っていない部分も感じられるが、それを差し引いても「義満以前」の尊氏・義詮から「義満以後」の義持・義教を含めて足利義満とはなんだったのかを描き出している。
紙の新書だと妙に分厚く仕上がっているが、これは論を進めるにあたっての前提、例えば「室町殿」「北山殿」を説明するために鎌倉殿までさかのぼって説明することもあったりするためで、無駄な部分ではなかったと思う。
著者の次作が今から楽しみである。
投稿元:
レビューを見る
謎多き室町時代の本質を描いた名著。なぜ京都に幕府があったのか、なぜ義満が絶対権力者になったのか、といった問いに明快に解答を与えてくれる。そして、その後なぜ戦国時代が始まったのか、という問いに対しても、本書で示唆を与えつつ、次の著書で明確な答えを示してくれることを大いに期待させる。
投稿元:
レビューを見る
本の感想(http://www.books-officehiguchi.com/?p=1923)
「この本は「室町殿」の全盛期はどこにあったのかを考察した本である。
この本の意外な評価は、初代室町幕府の将軍足利尊氏は一門に政治を丸投げしたということである。実際に室町幕府をつくったのは足利尊氏の弟・足利直義であるという説を出している。
初代尊氏と2代義詮は三条殿と呼ばれていたが、3代将軍足利義満の代で、北山に花の御所ができ、北山殿と呼ばれるようになった。
足利義満は北山殿と呼ばれただけでなく、御所の中を牛車で移動するなど朝廷を支配できるくらいの権力もあったと筆者は考察している。足利義満が将軍になるまでと南北朝合一までの過程を知りたい人に薦めたい本である。
なぜ4代目以降室町幕府が弱体化したのか。筆者は要因として後継者を決めずに死んだことや幼くして将軍になったことを挙げていることにも注目したい。」
内容(「BOOK」データベースより)
足利一門大名に丸投げして創立された室町幕府では、南北朝の分断などに後押しされて一門大名の自立心が強すぎ、将軍の権力が確立できなかった。この事態を打開するために、奇策に打って出たのが足利義満である。彼は朝廷儀礼の奥義を極め、恫喝とジョークを駆使して朝廷を支配し、さらには天皇までも翻弄する。朝廷と幕府両方の頂点に立つ「室町殿」という新たな地位を生み出し、中世最大の実権を握った。しかし、常軌を逸した彼の構想は本人の死により道半ばとなり、息子たちが違う形で完成させてゆく。室町幕府の誕生から義満没後の室町殿の完成形までを見通して、足利氏最盛期の核心を描き出す。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
桃崎有一郎
1978年、東京都生まれ。2001年、慶應義塾大学文学部卒業。2007年、慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程単位取得退学、博士(史学)。現在、高千穂大学商学部教授。専門は、古代・中世の礼制と法制・政治の関係史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
目次
規格外の男・足利義満
室町幕府を創った男の誤算―足利直義と観応の擾乱
足利義満の右大将拝賀―新時代の告知イベント
室町第(花御所)と右大将拝賀―恐怖の廷臣総動員
“力は正義”の廷臣支配―昇進と所領を与奪する力
皇位を決める義満と壊れる後円融天皇
「室町殿」称号の独占と定義―「公方様」という解答
「北山殿」というゴール―「室町殿」さえ超越する権力
虚構世界「北山」と狂言―仮想現実で造る並行世界
「太上天皇」義満と義嗣「親王」―北山殿と皇位継承
義持の「室町殿」再構成―調整役に徹する最高権威
凶暴化する絶対正義・義教―形は義持、心は義満
育成する義教と学ぶ後花園天皇―二人三脚の朝廷再建
室町殿から卒業する天皇、転落する室町殿
投稿元:
レビューを見る
「室町の王権」で義満の天皇位簒奪計画説を読んだときはショックを感じたが、現在はこの説はほぼ否定されている。ただ、近年、義満や室町幕府に関して興味深い著作が多く出ており、本書もその一冊である。
本書は、義満の作り上げた室町殿について、1 京都との関係、2天皇との関係、3将軍と大名との関係に焦点を当てて、その魅力を教えてくれる。
投稿元:
レビューを見る
絶大な権力を誇り、南北朝を統一させるなど辣腕を振るい、室町時代の絶頂期を築き上げた足利義満の考察ではあるが、むしろ足利政権誕生の過程から、義満の死後の政権まで加える事で、日本史上類を見ない不安定だった室町幕府の所以や、何故義満が強大な権力を持つに至ったのか、そして何故その強力な権力体制が長続きしなかったのかがとても良く理解できた。
そして室町幕府の肝は足利直義という説明が、見事に腹落ちした。
投稿元:
レビューを見る
足利義満とは「強きを助け、弱きを挫く」男という説を何度か読んだことがあったが、表現としては面白いが曖昧な印象しか残らなかった。本書はその曖昧な部分に光を通して、そのような説が生まれた背景を解き明かしてくれる。
論旨が明快で文に勢いがあるのは、著者の頭脳と行動力の産物であろう。若さみなぎるエネルギーが痛快である。
投稿元:
レビューを見る
足利義満を中心に尊氏・直義の祖業から義持・義教までの黄金期の終焉までを「室町殿」という概念と朝幕関係の変遷を詳述。
義満が如何に朝廷を支配し、足利家が天皇家を乗っ取ろうとした説の背景の考察は白眉。
投稿元:
レビューを見る
終わった・・・忘備兼ねてA4を2ページ書いた感想が消えた・・・保存したWordの文書も白紙が登録・・・悪夢じゃ
気を取り直してうろ覚え
本書は新進気鋭の学者で、亀田俊和先生も推奨(ある方に)されていたので借りてよんだ
言葉に対して最初から説明してくれるのは、追及する学者の性(さが)だろうが、室町殿という呼称が日本人特有の建物を貴人の尊称に使う文化に由来していることを説明があったので、戦国時代の書状が書札礼に基づく事を最近知った身としては嬉しい
時には〇〇宿泊様方のようにホテル名に託すことも礼に叶うことなのだろうか
義満の朝廷へマウントとるやり方がエグイ
彼を説明するのに、直義(実は幕府を作った方)の時代(後継者は斯波高経・義将、そして義持だろうか)や、義教の凄みを発揮できたのは、朝廷の格式を破壊しかけた義満の路線を義持が丁寧に再構成した成果の上だということをしった
書いた事の20%で、大事な事も抜けているが以上です!( `ー´)ノフン!!
投稿元:
レビューを見る
室町時代の最盛期を築いたと思っていた義満だが、彼の時代が不安定で幕府の未来も定かではなく、彼の任期に型をつくり、それを堅固なものにしたのが義持、義教の時代であった。特に義教と後花園の蜜月な関係は、この頃が幕府の最盛期なのでは、と思わせた。しかし、室町幕府の弱点が嘉吉の変で改めて露わにされ、その後の不安と動乱の時代に突入していく。
投稿元:
レビューを見る
今年10冊目
出てこなかったやつ
9冊目
j.c.ブラウン著
ルネサンス修道女物語
ー聖と性のミクロストリアー
永井三明/松本典昭/松本香 訳
ミネルヴァ書房