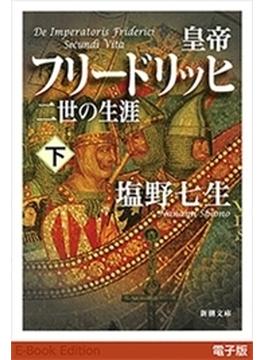法王の権威を恐れず、聖地を手中にし、学芸を愛した。時代を二百年先取りした「はやすぎた男」の生涯を描いた傑作歴史巨編
2020/01/22 17:15
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぴんさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
シチリア、プーリア、アーヘンなどでのこと。ロンバルディア同盟締結の時代背景とか
サヴォイア伯との同盟。アラビア数字の説明をピサでフィボナッチから聞きそして56歳のフィボナッチに生涯年金を与え始めて2年後の1228年にに「算術論」復刊とか。面白すぎる。中世ヨーロッパ、13世紀頃。日本だと執権政治とほぼ同時期か。物語を読み、この頃のローマ教皇、そして天皇についてより知りたくなった。まずは承久の乱あたりになるのかな。彼のかいたメルフィ憲章や鷹狩の書を読んでみたい。復活伝説のある彼の祖父バルバロッサは、孫の彼と混同されたが故に伝説化されたのではないかと。ドイツ諸侯にとっては『戦争』を引き起こしたバルバロッサよりも『平和』を維持した孫の方が良い主君だし。ローマ・カトリックに『蛇蝎の如く』嫌われているフリードリッヒ二世を大っぴらに追慕する事なんて、できませんし。
投稿元:
レビューを見る
下巻は、築いたものが無に帰していく展開なので、なかなかつらい展開。フリードリヒ二世を巡る女性の話で間を持たせているが、なかなかにつらい展開。まあ、どうして「早すぎた人」扱いなのかと言えば、無に帰したからなのですが……
投稿元:
レビューを見る
★★★2020年1月★★★
無血十字軍
法による政治体制(カプア憲章)
ナポリ大学の創設・・・
フリードリヒ2世による「中世打破」の行動はすさまじい。だからこそ、教皇庁や北イタリアの自治都市とへ激しく対立した。また息子や信頼する家臣の裏切りにもあい、神経をすり減らす日々であったろう。不屈の精神をもつ男とはまさにフリードリヒ2世のものだろう。
「生ききった」と、塩野氏があとがきで述べている。その言葉がしっくり来る。これほど筋を通した人生はないだろう。
投稿元:
レビューを見る
「ローマ人の物語」のカエサルの時もそうだったが、著者は、好きな男の女の話題は実に詳しくしかも楽しげに書いている。本書のフリードリッヒ二世の女たちの章には笑ってしまった。この男は実に愉快ないい男ではないか。
本書は主人公がハッキリしているだけに、読んでわかりやすく楽しい。しかもそのままヨーロッパ中世史の知識も得られる本だ。
本書が読んで楽しいのは過去の「歴史的事実」を知る事ができるからだけではない。後世でなければ得ることができない「歴史認識」をもって過去を読み解けるからだろう。そういう書を書ける著者の力を絶賛したい。
しかし、フリードリッヒ二世が偉大な政治家だったことは言うまでもないが、それでも近世の扉を開くには200年ほど早かったのだろう。彼が目指した「法による支配の国家」は死後崩壊し、子らもほとんどが歴史のなかで消え去っている。歴史というものは残酷なものであるとも思った。
投稿元:
レビューを見る
中世のイタリアにこんな興味深い皇帝がいたとは知らなかった。小説ではなく、歴史書として書かれているんだが、ときどき著者の思い入れの強さのせいか、想像による解釈が断定調に書かれてたりするので、その点は注意したほうが良いかも。
まぁ、その辺を割り引いてとても面白い。
投稿元:
レビューを見る
私にとって本書は、歴史を詳しく知るための参考書ではなく、著者の他の作品と同様に、実在した人物のドラマティックな人生をワクワクしながら覗き見る大河ドラマのような読み物だ。著者のオトコを見る目の厳しさをクリアした人物が、魅力的でないわけがない。
投稿元:
レビューを見る
ローマ法王との闘争に明け暮れた後半生。死後も嫡出子と庶子が助け合い、内紛が起こらなかったのは敵がいたからかもしれないが、素晴らしい。
投稿元:
レビューを見る
フリードリッヒ2世は、長じて<神聖ローマ皇帝>となって行くのだが、結局は当時のイタリアに在っても少し独特であったシチリア王国の中、残念ながら両親が早くに他界してしまったために「独立独歩」で育つ。そうした中で「時代の遥か先を往く」というような、当時は独特とされた考え方を育み、それを実践して行くことになるのであろう。
「中世」とは、「祈る人」、「闘う人」、「働く人」が在って、“領主”である「祈る人」や「闘う人」に“領民”である「働く人」が納税する仕組みだった。その納税等が恣意的に行われがちであった中、フリードリッヒ2世は「法治主義」というような概念を打ち出し、自らの権威が及び易いシチリア王国の版図では、後の時代の君主制国家に見受けられるような仕組みを整備していたのだった。
圧巻なのは、軍勢を率いて出動することはしたものの、交戦らしい交戦に及ぶことなく、イスラム勢力を代表するスルタンとの交渉で、イェルサレムでのキリスト教徒の権益を勝ち取ってしまったという<第6次十字軍>の経過だ。
多様な文化が渦巻いたシチリア王国の中で、非常に多くのモノを吸収して育ったフリードリッヒ2世…「何百年か生まれるのが早かった?」というような人物であったのかもしれない。
本作はそういうユニークな人物と出くわすことが出来る、なかなかに興味深いモノである。「1200年代の前半」と言えば、日本史では鎌倉時代と「かなり古い」という時期ではあるが、意外に「現代に向けて示唆に富む?」というようにも思える。
投稿元:
レビューを見る
著者にとって本当に書きたかった本。
過去の200頁程度の掌編ではなく渾身の歴史小説。これをどう捉えるかは読者の自由だが素晴らしい仕事であることに疑いはない。
投稿元:
レビューを見る
「物語 イタリアの歴史」を読んだ時に一番魅力的だった人物がこのフェデリーコ二世だった.中世ヨーロッパを代表する政治家であり教養人.その当時は専門書以外の評伝も邦訳がなく詳しく知りたくても知りようがなかった.誰か彼を主人公にした小説をかかないかなと思っていた.
そういう意味でこの本は待望の本.ちょっと長すぎるけれど,読みやすい.この機会に上掲の本も読み直したが,依拠した文献の違いか,人物の捉え方がずいぶん違う.イタリア統一や法王の地位に関する考え方など.
塩野七生の本は久しぶりだった.以前より文章がゆるく,明晰な感じが後退したように思う.同じような表現がなんどもあったり.読みやすくはなったけれど,ちょっと薄味にもなったように感じる.
投稿元:
レビューを見る
「鷹に始まり、鷹に終わった」
そんな空気感いっぱいの読後感!
ここまで封建社会の真っただ中で、「人の気持ち」と戦った「王様」はいなかったんだろうな、そう思います。
現代社会とは、すさまじく「常識」が違う。
今生きる私の目線だけで、一概にフリードリッヒ二世を見ることはなかなかできないし、人権無視した目を覆いたいような事も実際はやっている。それを含めて、当時は生活や政治の一つだった。
それを踏まえても、人類歴史の多くの部分を一段階上げる施策をしようとした一人の人間だったんだと、思う。
なかなか出来ることじゃないなー、と思う。
「マグナカルタ」に埋もれてしまったが、「メルフィ憲章」は、歴史上の大偉業。
キリスト教という権威に挑戦した、王様だった。
勝者とか敗者ではなく。
改革者、の話だった。
為政者になった人に、「文化、教養」などがその人自身に伴っていると、政治が進むことが凄くある。
平時でも乱世でも。
教養が必要なのは、その影響力を持つことになる為政者が。
歴史を一歩すすめる、そんな栄養に成り得るからなんだと。
フリードリッヒ二世を見て、改めて感じた雑感になりました!
人として、魅力あります。
投稿元:
レビューを見る
日本の世界史の講義では抜け落ちがちな第一次十字軍からルネサンスまでのヨーロッパの状況がよく理解できました。
ローマ教皇の力が絶大な時代に、「皇帝のものは皇帝のものに、教皇のものは教皇のものに」なる世界の実現に向かって突き進む力に勇気をもらいました。既存権力者(本書では教皇)に立ち向かう中で、度重なる困難に直面し失敗しても挽回する姿勢が特に印象的でした。
下巻ではフリードリッヒ二世を取り巻いた環境、特に人間関係についての記述が多く、彼のことをより理解できました。
しかし、何が彼をそこまで突き動かしたのかまでは本書からは分かりませんでした。読み終わって考えるに、青年期にシチリア王国の王、神聖ローマ皇帝になったことから周りには彼を利用したいと考える人や先代・先々代の皇帝と比較する人が多くいたと思います。皇帝を思い通りに操って利を得ようとする人の思い通りにはさせない、ならない反骨精神から歴史に名を遺す皇帝になってやるという気概が生まれてきたのではないかと感じました。
印象的だった文章
・苦難に出会うのは、何かやろうとする人の宿命である。苦難を避けたければ、何ごともやらない生き方を選ぶしかない。ゆえに問題は、苦難に出会うことではなく、それを挽回する力の有無になる。
テーマとした人物がなぜその行動をとったのか。と考える歴史小説の面白さを教えてくれる名著でした。フリードリッヒ二世といえばプロイセンでしょと思うなじみが薄い人に読んでほしい一冊です。
投稿元:
レビューを見る
封建社会から法に基づいた君主制国家の確立を目指し、ローマ法王の破門に屈せず政教分離を貫き、十字軍に行きながらもイスラムとの共存を考え和解の道を進む、中世ヨーロッパの先駆者・フリードリッヒ二世の生涯を塩野ワールドで描く後編。
上記の通り、フリードリッヒ二世はあまりにもいろんなことを同時代にやっていたので、頭の整理ができないところ、下巻では「間奏曲」として、女・子供・協力者など、いわゆる各論をまとめた章があったので読みやすかったです。
驚くのはフリードリッヒ二世の協力者を集める人たらしぶりと、女たらしぶり。
嫡子も庶子も一緒に教育させて自身、そして家臣の後継者を育成するなんてあらゆる意味で合理的すぎる。コーエーでシミュレーションゲーム化してほしいですが、PTAからクレームが入りそうだ(笑)
印象に残った文章を三つ。
「苦難に出会うのは、何かをやろうとする人の宿命である。」
「人間には誰にもある自己防衛本能は、科学的に証明されなくても肌では感じるカンを呼び覚ます働きはする。そして科学的な証明とは、カンが正しかったことを示してくれる場合が意外にも多い。」
そして
「不安からは何も生れないが、危機からは生れるのだ。
ただしそれは、危機を自覚した人にとって、ではあるけれど。」
新型コロナウイルスで不安に押しつぶされそうですが、自分、そして自分の愛するものへの危機に対して何を生み出せるのか、今一度考えてみたいと思いました。
投稿元:
レビューを見る
在宅勤務で電車に乗らなくなると、本を読むタイミングも結構難しくなる。
本書のような歴史大作は面白いのだけど、なにぶん読み進めるのに時間がかかるタイプ。
間隔あけちゃったけど、2週間でようやく終わった。
フリードリッヒ二世は本当にお手本のような統治者。それと対比されるローマ法王はまったく尊敬もできないし、勝手に怒りすら感じてしまう。この対立を見るだけで、現代に続く宗教観の争いが良くわかる。中世は(その前もその後もかもしれないけれど)もはやローマ法王には人の言葉は全く通じないうえに嫌な粘着質タイプばかり。自分の意に沿わないフリードリッヒをどうにか排除すべく、暗殺まで試みるという卑劣さ。彼が亡くなったと知って、大手を広げて欧州中に喜びを露わにする人としての小ささ(もはやキリストのトップといえるような雰囲気ではない)。
ある意味恐ろしい時代。フリードリッヒが目指した法治国家と、法王が作った異端裁判。片や正当な裁判にもかかわらず、異端裁判は訴えられる=有罪。魔女裁判の基になった裁判であるから、権力をかざしてもうやりたい放題。これはもう本当に、フランス王が70年にも渡り法王を牢獄に入れない限り続いていたであろう地獄の時代。
こんな歴史を垣間見て、無神論者の自分には敬虔な信者の気持ちがわからない。
同じように法王とフリードリッヒ
彼の死後の衰退感が、非常に切なくなる。優秀な息子たちも偉大な父あってこそ、になってしまう。
本書の帯に「圧倒的先駆者」ってあったけど、圧倒的過ぎて死後には目指した法治国家から封建社会に戻ってしまうという。新しいことを成し遂げたとしても、定着するには安定した社会が必要だと認識。
現代は、将来どういう目で見られるんだろうな。
投稿元:
レビューを見る
中世では、異端ともされてしまうくらいの圧倒的な先駆者。神聖ローマ帝国の皇位とともにシチリア王国の王位までももちながら、イェルサレムを無血開城してしまい、ローマ法王に破門されてしまったりもする。彼の信念は貫かれており、「皇帝のものは皇帝に。神のものは神に。」であった。だからこその、イスラムのスルタンと学問での友達にもなれたのだろう。
時代が時代ならば、もっと名君として君臨できたのではないだろうか。
彼の一生を描くには、ローマ人の物語やヴェネツィアの物語、十字軍の物語などなどの前段階がないと書けないような濃厚な作品に感じられた。