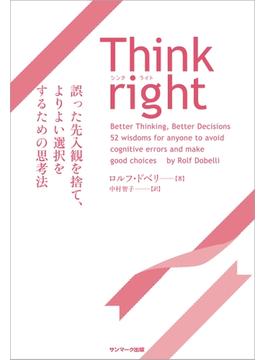正しく考えるヒント集
2020/12/31 22:11
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mistta - この投稿者のレビュー一覧を見る
読み進めるうちに「本当にその通りだな」「そんな風に考えるように気をつければ判断ミスを防げる
かもしれない」そんな教訓の数々に引き込まれた。
「確証の罠」「値引きされていれば値段はどうでもよくなる」「確率の無視の罠」etc.。
改めて、思考する際に陥りやすい罠を指摘してくれる。そして、その予防策も授けてくれる。
読んで一つ賢くなったような錯覚だけでは終わらず、本書の教えを反芻して役立てたい。
迷える日常を導く
2020/07/28 10:28
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Todoslo - この投稿者のレビュー一覧を見る
何となく選んできた道の積み重ねに、今の自分があることを実感します。心理学的な見地からの対処法は役に立ちそうです。
投稿元:
レビューを見る
誤った先入観を捨ててより良い選択をする為の考え方をまとめた本。全部で52の思考の落とし穴をまとめている。
ロルフドベリの本は、なぜ間違えたのか?Thinkシリーズ前2作も読んでいたので、正直言ってn増ししただけの感じにしかならなかったが、考え方を復習出来たのは良かったと思う。
投稿元:
レビューを見る
人間がハマってしまう「思考の落とし穴」について、実例を多く使いながら、解説している本。
解説の内容は、どんな落とし穴があるのか?、なぜハマるのか?、どうすればハマらないようにできるのか?の3点に触れられているため、全体的に具体的にイメージしやすかった。
ただ翻訳書ということもあって自分にはスッと理解できない言い回しもあった。
「誤った考え方」を普段意識していなかったので、1つ1つの思考のワナを『自分の場合はどうか?』と考えながら読めた。
投稿元:
レビューを見る
ドベリ氏の新作かと思って読んだら、過去に出版されていた本の再出版でした。
それにしてもうまいな。題名も変えちゃって、こういう商売の仕方はありだと思います。本当にうまいです。
本書の内容は過去の2冊と同じように行動経済学等に基づいた心の迷いを面白おかしく書いたもの。
この本が好きなら
ダン・アエリー氏の『予想どおりに不合理』
は必ず読んでみるべき。
投稿元:
レビューを見る
本書は、2013年に刊行された「なぜ、間違えたのか?」の改訂版にあたります。
「Think clearly」「Think Smart」と並ぶ「52の思考法シリーズ」第一弾にあたり、2020年に発刊されました。
人間の思考はけっして合理的ではない。思いもよらぬ不合理な行動をとってしまい、それが失敗や想定外の間違いを引き起こすものであり、失敗を招きかねないそうした思考の落とし穴は、行動経済学や社会心理学、進化心理学の分野で研究されており、著者によると、現在わかっているだけでおよそ120のワナが存在しているとのことです。本書では、その「思考の落とし穴」52を紹介しています。
ハロー効果やすっぱいブドウの木のように有名なものから、言われてみればそういう風に考えてしまいがちと納得してしまうもの、本当にそうだろうかと思ってしまうものまで、多岐に渡っており、様々な研究や経験を通して紹介されていますので、ショートストーリーをいくつも読んでいる感覚になります。
たとえば、
「回想のワナ」:ものごとが起きてしまってから、あとになって、それは予測可能だったと考えてしまうこと
取り除くのがもっとも難しいワナの1つ
「自分はうまく予測できるはずだ」と自己過信し、わたしたちを思いあがらせ、誤った決断に導く
アドバイスは、日記をつけること
また、「お抱え運転手の知識のワナ」
お抱え運転手とは、知ったかぶりをする人、自分を実際以上に誇示する人
「本物の知識」と「お抱え運転手の知識」を区別するのは難しくなっている。
「お抱え運転手の知識」を信用してはならない。見極めるサインは、本物の知識をもちあわせている人は、自分が知っていることと知らないことをよくわかっている
というように、思考の落とし穴を紹介したあと、その対処法をのべているので、自分がよく引っ掛かりそうな話を中心に読んでいけば正しい判断を下せるようになるのかもしれません。
一方で、そのように思考してしまう背景に、進化の歴史があり、間違ってしまうことは仕方ない、ということもたびたび指摘していることから、最初から完璧を目指すのではなく、失敗したら、少し修正し、次の機会に備える、その繰り返しこそ豊かな人生につながる、ということなのだと思います。
▼本書は「思考の落とし穴」に陥らないためのリスト
「思考の落とし穴」とは、「合理的に考えたり、論理的で理性的な行動をとろうとしたりするときに、一定の法則にしたがって陥る推論の誤りのこと」
▼「社会の中で、一般的な考え方にしたがいながら生活するのは簡単だ。
孤立して、自分の考え方だけで生きることも難しくない。
しかし、偉大な人間とは、社会の中にいながらも
自立した考え方を保ち続けることができる人である。」
(ラルフ・ワルド・エマーソン(思想家))
▼人間というものは、そもそも論理的に考えずに間違いをおかしやすい。それは、すべての人に当てはまると考える。優れた知性をもちあわせている人ですら、同じ落とし穴に何度もハマりこんでは、試行錯誤をくり返している、こうした誤りは偶然に起こるのではない。ハマった落とし穴の種類によって、決まった方向に間違いをおかすのである。そのことを理解すれば、過ちを予測でき、ある程度、行動を修正することができる。それでも、あくまである程度にすぎず、決して完璧には修正できない。
▼わたしたちは生物学的には、原始人となんら違いはなく、どんなにブランドの服に身を固めても、脳をはじめとする肉体は、狩猟と採集をする人間にすぎないのである。変化したのは「人間そのもの」ではなく、わたしたちが暮らす「環境」のほうだ。
▼人間は「間違い」をおかすようにできている
①進化はわたしたちを決して”最善の状態”、つまり完璧にはしてくれていないのだ。つまり、わたしたちがほかの生き物よりも環境に適応している限りは、行動に間違いがあっても許される。
②人間の脳は、「真実を追求」するためではなく、「繁殖を目的」として機能している。
③「直感的な決断」は、それが完璧に合理的ではなくても、特定の状況においてこそ価値がある。
▼失敗してもそれほど大きな問題にならない状況では、論理的に考えるのをやめて、自分の直感に任せている。論理的に考えるのは骨が折れる。だから、大きな損害が出ない場面では、頭を使って悩まずに、間違いをおかすことを自分に許すのである。そのほうが生きやすい。わたしたちがそれほど大きな危険をおかさずに生きている限りは、わたしたちの決断が正しくても間違っていても、自然にとってはそれほど大きな問題ではないのだ。しかし、重要な場面では、どのような決断を下すべきかよく考えることが必要なのである。
投稿元:
レビューを見る
私たちが思考する際に無意識のうちに犯してしまう過ちを「○○のワナ」という形で紹介してくれている。論理的な決断を下すために参考になるポイントが多数あった。
ただ記憶には残りづらかった(本書内で52個のワナについて述べられている)。また読み返したい。
投稿元:
レビューを見る
前回(Think Smart)以上に記憶に残りづらく、印象も薄くなってしまった。Audibleという性質も手伝うのか、数ページごとに論旨が切り替わる構成の書籍は、その数ページのボリュームでよっぽど「アハ体験」的な感覚を抱かないと自分の頭には残りにくいのかも。。。Think RightやThink Clearlyもそうだが、強く共感できるテーマがあったら自らの血肉になるまで実践と本著での振り返りを繰り返さないと、物にもならないように思う。この3つの書籍を通じて、小さな共感や軽い追体験だけでは、無理やりにでも自らの習慣を変えない限り、娯楽としての読書の域を超えないということが身に染みた。
以下、参考になった点のメモ。
・自己啓発系の書籍にはできる限り近づかない。そういった書籍はもともと幸せを感じやすい人が書いている。それで成功しない人がいる。不幸な人はそもそも書籍を書かない。
→これは、全面的に同意するわけではないが、そういった類の書籍もあることに留意して、合理性を感じる物とそうでない物の取捨選択を心掛ける気づきを得たという観点でメモ。
・ストーリーの罠:事実を分かりやすく捉えるため話を単純化、脚色するため、真実や問題点が抜け落ちやすくなる。
・メディアは聞き手が効きやすい覚えやすいストーリー構成を取りやすい。
投稿元:
レビューを見る
本書は日常生活で陥りがちな「思考の落とし穴」が題材で、○○のワナという形で52個の思考の落とし穴と、それに嵌らないためのアドバイスをしてくれている。
一つ紹介すると、「生き残りのワナ」は、「成功者」は表舞台に上がり、「挫折した人」は登場しないため、日常においては「成功」が「失敗」よりもはるかに目立つために、成功への見通しを甘く見て過大評価してしまうことを指す。
成功を収めたコーチングセミナーのトレーナーやベストセラー本に書いてあることも疑った方が良い。
というのも、失敗した人は自分の失敗について本を書いたり講演をしないため、成功法則通りに行動したにも関わらず失敗に終わってしまった人がごまんといるという事実は浮き彫りにならないからである。
だからといって「リスクをおかさない方が良い」ということではなく、「生き残りのワナ」は確かに存在していて、成功の可能性を歪めて見せているということは常に意識して行動をするべき。
「生き残りのワナ」に嵌ることを防ぐには、かつては有望視されていたプロジェクトや投資、輝かしい経歴を持った人々の失敗に目を向けることである。
こんなことが52個程書いてある。
本書を読むと、いかに自分が合理的な選択をしたつもりでも、錯覚や感情に左右されて非合理的な選択をしているかが思い知らされる。
「FACTFULNESS」にも近しい内容に感じた。
投稿元:
レビューを見る
20200830 人間が正しく判断できない理由について色々なパターンで説明されている。そう言うことかと納得させられる事と個人でできない事を明示されて悩まされる事、結局、この本をベースに判断が必要な場面が発生した時にどうしたらよいかをリスト化していこうと思う。
投稿元:
レビューを見る
日々決断の連続だが直感的な思考に頼ってる部分が多いと思う!
本書は物事を論理的な視点でみるための思考法が書かれている!
「偉大な人間とは社会の中にいながらも自立した考え方を保ち続けることが出来る人である」
そしてこの人の本はやはり面白い♪
投稿元:
レビューを見る
行動経済学や社会心理学などから明らかにされている、人間の認知エラーについて書かれた52のコラムをまとめたもの。
著者はスイス人で、初版はドイツで2011年に出ていたらしい。
フレーミングのワナ、確証のワナ、権威のワナ、希少性の錯覚のワナ、選択のパラドクスのワナ、あなたが好きのワナ、お返しの法則のワナ、生き残りのワナ、サンクコストのワナ、コントラストのワナ、イメージのワナ、いったん悪化してからよくなるのワナ、スイマーズボディ幻想のワナ、自信過剰のワナ、社会的証明のワナ、ストーリーのワナ、回想のワナ、お抱え運転手の知識のワナ、報酬という刺激のワナ、平均への回帰、共有地の悲劇、結果による錯覚、集団思考、確率の無視、基準比率の無視、ギャンブラーの錯覚、アンカリング、機能的推理、マイナスの過大評価……
感情を抑えたからといって回避できない不合理な行動を人間はとってしまう。それは人間の脳のつくりなので仕方のないこと。それを知った上で少しでもよい決断を下すにはどうするかを考えないとだな。
人間の幸福も不幸も3か月しかもたないとか、自分の影響の輪のもっとも重要なことに集中すべしとか、所有意識をなくすために持ち物は宇宙からの借り物と考えるようにするとか、carpe diemは週一に留めよとか、直観と論理思考を適切に使い分けるとか、ヒントが満載だった。
投稿元:
レビューを見る
ダンアリエリー氏の不合理シリーズと重複する部分は多かったが、読みやすい構成であり、様々なな思考のクセについて理解する事ができた。
興味深いのは、著者自身も全ての思考の落とし穴を避ける事はできないと考えており、重要な決断の前だけはできるだけ論理的に考えるようにし、そうでない時は直観で判断するとしていた部分。
投稿元:
レビューを見る
120のワナのうち52を紹介し、我々がいかに誤った選択をしているかについて記載している一冊。
正直読み終えた今、ワナに陥らず正しい選択をして生きていけるかと言われると、全くそんな自信はなく、不可能だろう。
なんらかの選択に迫られた際、今自分がすべき選択は何かを考えて、その結果がどうだろうと受け入れる覚悟を持って生きるしかないのだろうな。
環境がどうであれ、幸せは自分のこころで作り出せる。選択の結果によらず、幸せにはなれるらしい。自分の考え方、生き方を見つめ直していければと思う。(がんこだから素直にできるとは思えないけど。)
投稿元:
レビューを見る
ドドド、ドベリさん勉強になります!
我々人間は思い込みに惑わされて生きているだけなんだ!
普通に生きているだけだとワナワナワナ
に掛かるのだ、だから勉強して罠に掛からないようにしていく必要があるのだ!
人間の固定観念ってのは生きていく上でそれなりに定着してしまう。親、近所のおじさん、学校の先生、友達、TV・・・そのような情報だけですっかり頭の中はいっぱいになってしまう。最初に押し戴いた情報ってのはなかなか手放す事ができないものよ。
だから我々人間は勉強してどのような罠に掛かっているかを洗い出すべし。洗い出したら何が正解かを考えるべし。常に変化すべし。無知の知を持たないと罠にかかるのね。罠を無くすのは不可能だから常に罠を意識すべし!