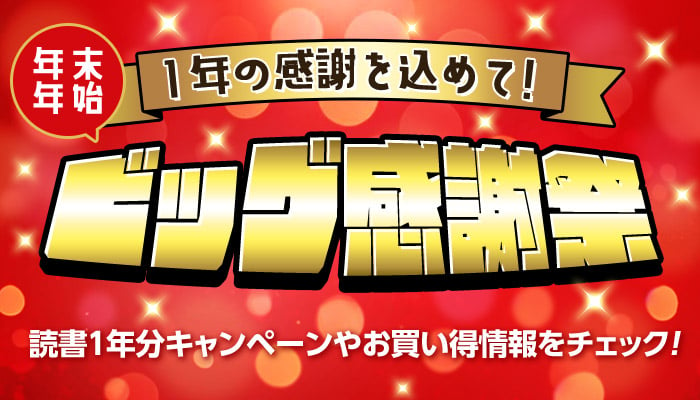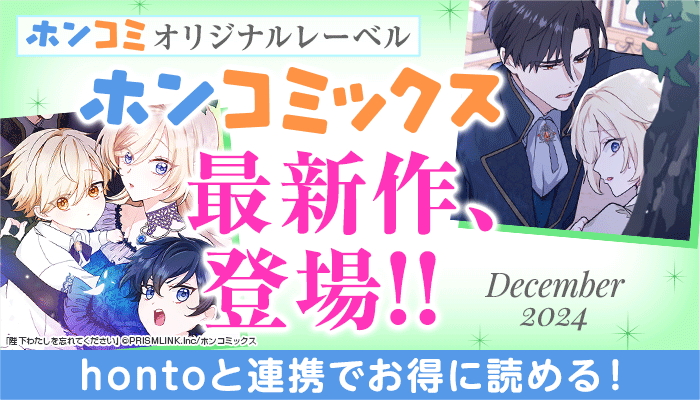外国語学習者必携の書
2015/08/23 10:25
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ジュン - この投稿者のレビュー一覧を見る
外国語を学ぶとき、ともすれば会話力の涵養ばかりに重きが置かれるが、言葉の学習の本質から言えば、その方向性は誤りである。言葉ができる、ということは、読解力がある、ということである。しっかり読めて初めて、「あ、自分は外国語ができるんだ」と感じることができる。そして何よりもまず、自己の母国語、日本語を正しく使いこなせる能力が求められる。外国語を学べば学ぶほど、母国語能力の大切さを実感する。母国語を高いレベルで使いこなせない人に、外国語を流暢に操れる人はいない。
外国語を学習している人すべてに読んでいただきたい書といえる。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:okumotohira2 - この投稿者のレビュー一覧を見る
単行本発刊時からこの本の存在は知っていたが、増補文庫化されたので読んでみた。
著者の、該博な知識、深い洞察力、日本語に対する深い愛情に驚嘆し、敬意を表する。
英語が他の言語より圧倒的な影響力を持ち、将来その傾向が更に増すと思われる状況で日本語が生き残るにはどうするかを真剣に考えた書である。
そこに著者の“選良主義”をみる人もいるだろうが、客観的に見て著者の主張は極めて効率的、現実的で示唆に富む。
学校での限られた英語学習時間の中で、優先すべきは“読み書き”なかでも“読み”で、決して“会話”ではないという著者の主張は、私もずっと思っていた事で全面的に賛成する。
ちょっといかめしい言葉になるが、著者は“国士”だと思う。
この先、幾十年、百年と読み継がれるべき良書、名著。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:H2A - この投稿者のレビュー一覧を見る
文庫版に寄せて長い後書きが追加されている。英語が他を圧して「普遍語」になる世紀。著者は大変に悲観的な未来を予感している。その徴候はいたる所にあるという。「国語」は「現地語」と化し、叡智を求める者は普遍語で書き読むという言語の二重化。著者は日本近代文学を奇跡として顕揚する一方で、この国ほど自国の文学に価値を置こうとしないものはないと言う。そこに共感できるかどうかはさておいて、著者の指摘の多くは鋭く慄然とさせられることが多く、歴史的な洞察には感心させられる。日本語がGHQによる戦後政策の一環でもう少しでローマ字表記になっていたかもしれないという事実には多くの人が驚くのではないか。イエール大学に学び、ポール・ド・マンや、当時渡米していた柄谷行人に遭っていたという回想もよくあるトリビア程度に見える。文庫にもなったので多くの人に読んでもらいたい名著。この人の小説も読まないと。
いつ本題になるの?
2015/10/26 13:48
4人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ゆうすげびと - この投稿者のレビュー一覧を見る
タイトルにひかれて読み始めたが、いつになったら日本語が滅びる話になるのか、いいかげん疲れてしまって、途中でやめた。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
日本語が滅びる……というタイトルは衝撃的です。しかし、始めの方は、全然そんなお話ではなくて。タイトルが、ややずれている感じでした。もう少し、この点、書いてほしかったです
投稿元:
レビューを見る
単行本が出た当時、かなり話題になっていた1冊。
かなり限定された読者層を思い描いていたそうで、ここまで話題になるとは著者も思っていなかったとか。それを念頭にパラパラと読み返してみると、当初考えられていた読者層の片鱗は随所に見られる。
投稿元:
レビューを見る
第七章 英語教育と日本語教育 より
p364
思えば、日本人は日本語を実に粗末に扱ってきた。
日本に日本語があるのは、今まで日本に水があるのがあたりまえであったように、あたりまえのことだとしか思ってこなかった。
(中略)
「西洋の衝撃」を受けるとは、西洋人こそが人間の規範に見え、それと連動し、西洋語こそが人間が使う言葉の規範に見えるということにほかならない。
(中略)
ISETANやらKeioやらSEIBU。西洋語のカタカナ表記の氾濫は、ああ、もしもこの日本語が西洋語であったら……という、西洋語への変身願望の表れでしかない。
そもそも政府からして、翻訳語を考え出すこともせず、西洋語のカタカナ表記を公文書に使って平気である。
恥ずべきコンプライアンス(=屈従)。
(中略)
(日本語が漢字、ひらがな、カタカナの三種類の文字を使い分けることに言及し)表記法を使い分けることによって生まれる意味の違いとは、(中略)明朝体が使われていようと、ゴシック体が使われていようと、そのような視覚的な差とはまったく関係のないところから生まれる、意味の違いである。
ふらんすへ行きたしと思へども
ふらんすはあまりに遠し
せめては新しき背広をきて
きままなる旅にいでてみん。
という例の萩原朔太郎の詩も、最初の二行を
仏蘭西へ行きたしと思へども
仏蘭西はあまりに遠し
に変えてしまうと、朔太郎の詩のなよなよと頼りなげな詩情が消えてしまう。
フランス行きたしと思へども
フランスはあまりに遠し
となると、あたりまえの心情をあたりまえに訴えているだけになってしまう。
だが右のような差は、日本語を知らない人にはわかりえない。
▼「日本語とはどういう言語か」
(石川九楊、講談社学術文庫)p22、204
漢字とひらがなとカタカナという三種類の文字をもつという点において、日本語は世界に特異な言語である。この特異性と比較すれば、日本語の文法的な特徴なるものは微々たる差でしかない。
投稿元:
レビューを見る
寡作ながら日本近代文学の系統を唯一現代において引き継いでいると言っても過言ではない作家、水村美苗による言語論。
言語を巡る歴史を紐解きながら<普遍語>・<現地語>・<国語>という3つのカテゴリの関係性を明示した後、インターネットの台頭などの社会変化により、英語が<普遍語>として一極化する現代において、日本語という世界でも稀有な文法性質を持ち、世界に名高い近代文学の系譜を持つ言語が消失しようとすることへの警鐘を鳴らす。決してここで述べられているのは、回顧主義的な議論ではないし、英語の世紀においてはむしろ自国語を適切に操れるようになること、そしてそのために国語教育を強化すべきという議論の流れは納得度が高い。
専攻研究としては、ベネディクト・アンダーソンの「想像の共同体」や柄谷行人の「日本近代文学の起源」などに依っており、国民国家と文学の関係性を現代風にアップデートとした議論としても読むことができると思う。
投稿元:
レビューを見る
JMOOC OpenLearning, Japan「グローバルマネジメント(入門)」Week3参考文献。
投稿元:
レビューを見る
正直、〝日本語が亡びる〟とまでは思わないが、英語中心の世界に一石投じたものとして興味深く読んだ。単行本が発表された当時、良くも悪くも話題になった。今回増補版として当時の反応に対する〝返答〟もあるので読んでみることにした。
投稿元:
レビューを見る
単行本(2008年)が話題になったときにめずらしく買って読んだが、このたびの文庫化に際してその後の文章もずいぶん追加で入ったらしいので改めて購入。
刊行当時「日本語が亡びるとき」というタイトルがこうもセンセーショナルに話題になるとは著者も思いもよらないことだったらしい。
2020年11月、受験を控えた高3長女が読んでいる。
投稿元:
レビューを見る
面白いけど読むのに時間がかかる本でした。
日本語について示唆に富む内容の本で、様々な視点を与えてくれました。
図書館で働いていると、「夏目漱石の『こころ』の現代語訳ないですか?」とか「中島敦の『山月記』の現代語訳ないですか?」は一年に必ず一度は聞かれる質問で。そのたびに「現代語訳に訳したら世界観変わるやん!なに考えてんねん」と心の中で思っていたのですが。第7章「英語教育と日本語教育」を読んで、なぜ自分がそう思うのかが分かりました。アルファベットだけで表せる英語と違って、カタカナ・漢字・平仮名・ローマ字などを持つ日本語においては「どう表すか」も大事な点なんだなと。そしてなぜ「読みにくいから現代語訳で読みたい」と思うのかも。(日本の国語教育は「日本近代文学を読み継ぐこと」を大事にしていないからだと思われる)
投稿元:
レビューを見る
刊行当初からおおいに反響を呼び、第8回小林秀雄賞も受賞した話題作だが、読んでみて正直ガッカリした。たしかに、示唆的な内容も多く含まれているし、たとえば「社内英語公用語化」や近年の教育改革などにおいて、まるで英語さえできればすべて良しとするような傾向は眼に余る。それよりはまず日本語や日本文学をシッカリ学ぶべきであるという著者の主張には頷けるものがある。しかし、だからといって、日本近代文学こそ至高であるというような考えかたはいかがなものか。夏目漱石が国民的で模範的な作家であることは否定しないが、近代文学といっても玉石混淆である。文法などがまだ確立していないために、今日の規範でいえばどうかという箇所もままある。とうてい絶対的なものとは呼べないであろう。著者はけっきょく、漱石や鷗外など、もともとすばらしいものを同語反復的にすばらしいといっているだけなのではないか。全篇にわたってこういう著者の思い込みにも似た主観ばかりが登場するので、読んでいて疲れてしまう。曽野綾子にはわたしはまったく共感しないが、文章の感じは似ているように思う。曽野は近ごろ話題の「反知性主義」を代表するような人物だが、この本もまた「なんちゃって知性」で色づけしただけで、内容的には曽野と同レヴェルではないか。この作品しか読んでいないので、著者を全否定するつもりもないが、文章もまったくおなじ文末表現の文章を無意味に重ねるなど、ハッキリいってぜんぜんうまくない。文学賞を受賞しまくっている作家が書いている文章とは思えない。こういう作品を自信満満で上梓されると、問題提起以前の問題であるという気がする。
投稿元:
レビューを見る
センセーショナルなタイトルだが、本書を読むと、現実のものとして日本語が亡びる日が来てしまうようにも思えてくる。
日本語だけでなく、言語についての考察はとても素晴らしかった。
国語と現地語。今まで考えてもみなかった。
そしてまた、現在の普遍語である英語を母語とする人々の自らのアドバンテージへの無自覚さ。
英語で書くことの重要性。英語の図書館に出入りするのは、アカデミックの世界だけの話ではない。
私自身、編物をするようになって英語でパターンを書くことの重要性を痛感している。
過去に英語公用語論や、漢字を廃してアルファベット表記にする案など、日本語が危機に瀕していたことは驚きだった。
そのような状況下にありながら、今現在、漢字仮名交じり文や世界唯一の表意文字である漢字を使用していることは、それらが理にかなった素晴らしい言語だということを証明しているのではないだろうか。
本書のタイトルは、漱石の「三四郎」の中の台詞から取っただけで、人を驚かせようと思って付けたわけでないそうだ。
投稿元:
レビューを見る
「読まれるべき言葉」真に優秀な二重言語者は日本語を捨て、英語を選択する。それはインターネット社会になり英語の有用性が確実となったからだ。そこでは、有益な情報を得るためには英語で読まなければならず、自分の意見を広く知らしめるためには英語で書かなければならない。