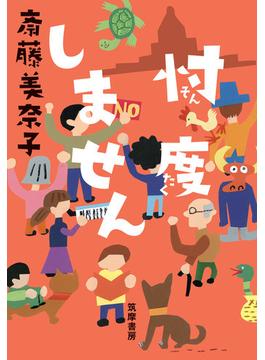0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
今の日本で、忖度しないで生きていくのは、社会に出ると、キツいものがあります。学生時代でも、友人関係や、部活の先輩などなど……。読んでいて、良いのですが……出来るかは……ですねー。
投稿元:
レビューを見る
「世の中ラボ」をまとめたこのシリーズは、正直、日本の現代史を当事者としての生活感とともに記してくれる。歴史の書である。
いつも思うが、要点を確実にまとめてくれる、斎藤さんの技量の高さは何より尊敬する。
投稿元:
レビューを見る
3冊の本を元にテーマごとに現代社会を論じる。ブックガイドであり、社会評論。
切れ味よくて読みやすい。
投稿元:
レビューを見る
斎藤美奈子の新刊は、本屋で見かけたら買うことにしている。
で、数年放置してしまう。
絶対読むのだから、今でなくてもいい。
『月夜にランタン』も『ニッポン沈没』も数年放置した結果、第二次安倍政権が発足したタイミングで第一次安倍政権の突然の終焉と総括について読んだのだった。
それはそれで面白かったけど。
今回はひと月も寝かせず、すぐ読んだ。(当社比)
テーマごとに3冊の本を紹介し、世相を斬る。
私が彼女を好きな理由は、知識の(彼女の興味)の幅の広さと、上下左右どこにも忖度しない語り口の鋭さにある。
今作も、目からうろこがドバドバ落ちた。
「バカが世の中を悪くする、とか言ってる場合じゃない」
「戦後日本の転換点はいつだったのか」
「わかったつもりになっちゃいけない、地方の現在地」
「文学はいつも現実の半歩先を行っている」
「当事者が声を上げれば、やっぱり事態は変わるのだ」
上記5つのテーマの他に、「新型コロナウイルスが来た!」を番外編として収録。
「オール沖縄」についてとか、司馬史観やアイヌ民族についてなど、個別に語りだすとキリがないので、2つだけ。
私は官僚が忖度をするようになったのは、安倍政権が「内閣人事局」を作ってからだと思う。
それまで官僚と言われる人たちは、独善的なところはあったとしても、行政のプロとしてのプライドと自信があった。
省の推薦を、「これで総理が納得すると思いますか」と突き返す菅官房長官。(当時)
これを繰り返して、官僚は骨抜きにされた…というか、骨のない人しか上がっていけなくなった。
結果、やる気と能力のある若手が大勢霞ヶ関を去った。(霞ヶ関ではないけれど、うちの職場も若手の流出が止まらない)
今度は学問の世界を骨抜きにするつもりなんだ、とニュースを見て思っている。
もうひとつは田中角栄について。
「ロッキード事件で金をもらった悪いやつ」というイメージしかなかった田中角栄だけど、「小粒なタカ派」しかいない今の政治家の中で、「大物ハト派」という存在がどれだけ大きなものだったかと知った。
そして、脱アメリカ依存、全世界を視野に置いた「資源外交」等が、キッシンジャーとCIAの逆鱗に触れて陥れられたという陰謀説は、どうも荒唐無稽とばかりは言えないらしいのだ、
ちょっとそのあたりの本でも読んでみたくなる。
投稿元:
レビューを見る
PR誌「ちくま」の「世の中ラボ」2015.7-2020.7の連載をまとめたもの
2018.4 老境を描く「玄冬小説」って?
青春小説が「上京~東京へ」なら老境を描く小説は「地方回帰~脱東京」 「おらおらでひとりいぐも」
2020.9.20初版第1刷 購入
Web版もある
http://www.webchikuma.jp/category/saitouminako
投稿元:
レビューを見る
「月夜にランタン」「ニッポン沈没」に続くシリーズ三作目。「ニッポン沈没」が暗めのトーンだったのに比べて、今回は、「政治も世の中も相変わらずひどいもんだけど、それでも希望はある」という前向きな思いを感じる一冊だった。タイトルにもそれが表れていると思う。
いつもながら取り上げられる本の幅広さに感嘆する。不愉快になるに決まっている安部ヨイショ本とか嫌韓本とかもしっかり読んで、自分の意見をはっきり述べる姿勢がすがすがしくカッコイイ。あとがきがとても良かったので、以下その抜粋。
「言論空間が『敵と味方』『内と外』『ホームとアウェイ』に二分され、仲間うちでしか通じない言葉が増殖していく。いわば思想のタコツボ化です。
左派リベラル陣営においても、タコツボ化は急激に進行しています。なぜ野党は選挙で負け続けているのか。なぜ市民運動の現場には、高齢者しかいないのか。
それは日本人が劣化したからだ。若者の意識が低いからだ。
と、もしかしてあなた、思ってません?だからダメなんですってば。リベラルが後退戦を強いられているのは、相手がバカだからではなく、こちら側に魅力がないからです。
自分はぜったい正しくて、自分以外はみんなバカ。愚かな大衆諸君に、賢い私が正しいことを教えてあげる。そんな不遜な人たちに、だれが与したいと思います?民主主義の危機をいいつのる人々のやり方は、ぜんぜん民主的じゃないんだよね。」
「『バカが世の中を悪くする、とか言ってる場合じゃない』ってことです。
忖度とは、コミュニケーションの回路を閉じて、腹のさぐりあいをすることです。ろくなもんじゃありません。『当事者が声を上げれば、やっぱり事態は変わるのだ』なんです。みんな、つまんない忖度はやめて、いいたいことはいったほうがいいんだよ。意見の表明の仕方も、既存のスタイルに忖度する必要なんかない。人それぞれでいいんです。」
「『倦怠』『停滞』と申しましたが、歴史というのは、いつどんな形で動きだすかわかりません。希望は捨てない。どんなときでも。」
投稿元:
レビューを見る
政治の話からLGBT、反知性主義、現代進行中のコロナについてまで。時事について、三冊の本を読みながら考える。真面目に考え込むところと、クスっと笑えるところの振幅が魅力的。静かに淡々と説明したかと思うと、「でもさ」といきなり切り返す。そのあたりの動きになんかしびれるね。読んでいて楽しかった。楽しかったでおわるのではなく、あぁ自分にはもっとできること、やらなければいけないことがあったんじゃないかな、と振り返ることができるし、その元気が出てくるんだ。
「忖度とは、コミュニケーションの回路を閉じて、腹のさぐりあいをすることです。ろくなもんじゃありません。「当事者が声を上げれば、やっぱり事態はかわるのだ」なんです。みんな、つまんない忖度はやめて、いいたいことはいったほうがいいんだよ。」
あとがきのことばが、なんか、いろんなことへ背中を押してくれているような気がしたな。
年末年始に読んでいたんだけど、2021年の読書を本書で始められたことは、良かったなぁと思う。
投稿元:
レビューを見る
見返しの「続・裸の王様」から笑ってしまった。で、次にまたいきなり、内田先生編の「日本の反知性主義」に厳しいご意見。確かに「日本の知識人はバカの悲しみに鈍感なところがあるからな」っていうの常々私も感じる。
やっぱり斎藤美奈子さんいいわ、と思って最後まで読み続ける。
次に読みたい本がたくさん見つかった。読むのが追いつかない。
投稿元:
レビューを見る
ちゃんと読んで
ちゃんと考えて
ちゃんと自分の言葉で発信
斎藤美奈子さんの「書評集」
PR誌「ちくま」に連載中の「世の中ラボ」
から出来上がった一冊
初めから読んでも
後から読んでも
どこから読んでも
すっきり はっきり
こりゃ面白い
自分だったら絶対に買わない本も
(批評のために)ちゃんと取り上げてくださっているのが
また嬉しい
〽「本」は世に連れ 世は「本」に連れ
「世間」を眺め渡している視点が
さすが 斎藤美奈子流ですね
投稿元:
レビューを見る
相変わらず切れ味バツグンの書評、というより今を切り取る時事放談。大好きです斎藤美奈子。世の中気になることがあったら、関連書籍をなんでも読んでみよう!という姿勢、見習いたい。書評家じゃないからどうしたってチョイスが偏るもんねえ。自分の言葉で語るには、他人の言葉を知らなければ。知らないことは書物で知っていかなくては。
投稿元:
レビューを見る
どこかで『災間の唄』と並び称されているのを読んで、同作に痛く感じ入った身としては、本作も是非と手に取ったもの。期待通り、存分に味わわせて頂きました。それにしても幅広く読んでいらっしゃって、小説、ノンフのみならず、新書やら専門書にまで、その読書対象は広がってるんですね。凄い。その上で提示される、現体制への危機感だけに、説得力もいや増すというもの。これを読みながら、またちょっと新書への読書欲が湧いてきました。という訳で、今手元にある中で、特に気になるものをピックアップして読み始めることになった訳です。
投稿元:
レビューを見る
2021年3月13日読了。世相に関連した3冊の良書・ダメ本を各回で取り上げ、主にアベ政権に駄目だししながら世相を切る本。忖度しない、ということでが安倍政権批判、れいわ新選組称賛など確信犯的に著者の偏見混じりではあるが言いたい放題な内容を興味深く読んだ。理解が難しい事態が発生したとき、「歴史に学ぼう!過去の類書を参照しよう!」という態度は正しいと思うのだが、それはこの先の世界でも有効なのだろうか…?自分の生きている世界で現在進行形で起きている出来事に対して自分の知識は圧倒的に足りず、気分や世間の雰囲気・マスコミやTwitterでなんとなく言われている風潮に流されているとも思えるが好奇心と「自分の考え」は常に持ち続け、アップデートを心がけていきたいもの。
投稿元:
レビューを見る
現代日本のさまざまな問題点を読み解くためにどんな本を読んだかという、ブックガイドも兼ねた時評集、というところがいかにも興味深い。その選書も、一方的にならず、対立する側の意見についても目配りが行き届いている。
北朝鮮による拉致問題では、「家族会」とは別に「救う会」があるとは、この本を読むまで知らなかった。自らの不明を恥じたい。
投稿元:
レビューを見る
自分が経験できることはたかが知れているから、せめて沢山の本を読んで、いろんな事実や考え方を知りたいものだと思います。
投稿元:
レビューを見る
斎藤美奈子の本の読み方は、私の手法とは全く違って面白い。そして、問題意識もいまの時代にフォーカスして、実に巧みな解説をする。
6つのテーマの選定がうまい。時代の核心に触れる。とにかく、「忖度しません」と言う題名さえも素晴らしい。現在の官僚やマスコミも忖度しすぎの時代に、これまで言えるのはいい。
6つのテーマは、①「バカが世の中を悪くする、とか言ってる場合じゃない」ー反知性主義とは何か?を追いかける。またなぜ反知性主義が台頭したのだろうか?
②「戦後日本の転換点はいつだったのか」ー60年安保。田中角栄をどう評価するか?1985年阪神タイガースが優勝。くつろいすぎの司馬史観。坂の上の雲はもう見終わった。ネットウヨのアイデンティティ。
③「わかったつもりになっちゃいけない、地方の現在地」ー観光でも基地でもない、沖縄の実像、沖縄の革新は琉大という階層の中で構築される。「オール沖縄」を育てた翁長雄志、沖縄の保守本流がなぜ辺野古基地反対を掲げるのか?長崎の隠れキリシタン。天皇が象徴であることから、なろうとした。君たちはどう生きるかが?なぜはやるのか?
④「文学はいつも現実の半歩先を行っている」ー認知症が文学になる。老人たちの玄冬小説。そもそも源氏物語って?
⑤「当事者が声を上げれば、やっぱり事態は変わるのだ」ー教授やジャーナリストのセクハラ。セクハラ当事者が自覚していない現実。フェミニズム、フェミニスト、LBGTと時代の変遷の中で、METOOと声を上げる。⑥「新型コロナが来た」ーペスト文学を読む。
問題意識が鮮明だと、本のセレクションも鮮明だ。面白い本がたくさんあったけど、それより面白い本があるので、それを読もう。