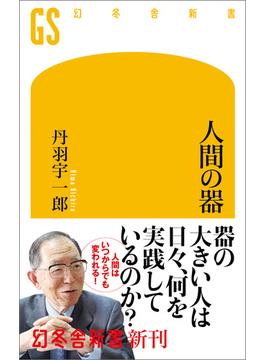0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:おどおどさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
大きい人には、なりたいと思ってもなかなかなれないように思う。自分は、すぐイライラしたり、それが言葉に出るので、器を大きく…というより、まずはいつも穏やかな人を見習いたい。
所々ハッとする言葉がある
2021/05/29 14:40
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:makiko - この投稿者のレビュー一覧を見る
人間の器を大きくするために、どういう思考・態度で人生を過ごせばよいのか著者の考えがつづられている本。器というのは生まれ持ったもので変えられないと思っていましたが、著者はいくつになっても器を大きくできるというお考えのよう。ほとんど著者の独断と独自説ですが、「生活は雑事の連続。仕事も半分くらいは雑事。しかし、雑事だからといって雑にすませていると、本筋の仕事も生き方そのものも雑になってくるから、一つひとつを丁寧に、ある程度の速さを持ってこなしていく姿勢は大事なことだ」という部分は、なるほどと思いました。
投稿元:
レビューを見る
財界人きっての読書家である著者が、人間の器を大きくする心の在り様についてまとめたもの。
心に留めておきたい箴言至言が数多。
第1章「人間力」を高める
多様性を求められる現代では「人は人と違うからこそ、生きる意味があります」
人間としての成長を求める時は「まずは『自分は何も知らない』ということを自覚する」
第2章「人間の器」は仕事で変わる
リーダーの条件の一つとして「忘れるからこそ新しい発想も生まれるし、現在をベストに生きることもできるのだと思います」
困難に直面し考えられる方策が尽きた時も「『始まりがあれば、終わりが必ずある』と思うことです。終わりのない始まりはないのです」
第3章老年をいかに生きるか
余命宣告を受けた時も「自らの人生を振り返って悔いることよりも、その日その日を自分なりに精一杯生きる。それで、十分ではないでしょうか」
「モノを丁寧に使い切るように、人生も丁寧に使い切るという姿勢こそが、器の大きな生き方に繋がるのではないかと思います」
「これからの人生においては”今”が一番若いのですから、『歳だから…』という暇があれば、アンテナを張って行動を起こしてみましょう」
アフガニスタンに生涯を捧げた中村哲さんの項では
「現在、日本の国内では平和憲法をめぐっていろいろな軋みが生じていますが、少なくとも海外諸国にとって日本が持つ平和憲法は畏敬の対象であり、日本はそのような器を持つブランド国家として期待されていることを忘れたはならないと思います」
現在の憲法論議に一考を促す言葉と言えるのではないでしょうか。
投稿元:
レビューを見る
中国大使時代の言動に疑問を持ったことがあるが、本を読んだら底の浅さがよく分かった。ここに書かれている程度のことは普通の常識人なら承知していること。
お金をドブに捨てた気になった。
投稿元:
レビューを見る
「たまたまの運」は自力ではどうにもならないが、必然の運は自分で作り出せる。
いくつになっても好奇心を持ってアンテナを張っている人には、次々と面白そうな運や縁が舞い込んでくる。
面白そうなことはとりあえずやってみる。
投稿元:
レビューを見る
仕事、生き方について非常に納得感がある。但し、これを実行できるかどうかは別問題。出来たから筆者はここまでになっている。
投稿元:
レビューを見る
■題名がちょっと大上段だが、内容は身近な話題で読みやすかった。
■大きく4章の構成。目次を読むとなかなかキャッチーではある。
■「人間の器」と聞いて一般的に何が頭に思い浮かぶだろうか。自分でそれを考えながら読むと面白い。
投稿元:
レビューを見る
・読んだ理由
歴代で一番器の大きかったテラスハウスのメンバーは誰か、という議論になり、「器の大きさ」とは何かについて考えたことがキッカケで本書を手に取った。
自身も器の大きな人間になりたいと思い、何かヒントが書かれていることを期待して読んだ。
・感想
本書における「器が大きい人」の定義は、他人のために自分を捨てられる人、損得抜きで行動できる人、だということが序盤に語られている。
それ以降の話は、期待したようなものでは無かった。
大半は著者の社会人人生から得られた仕事術が語られるのみである。
「常にベストを尽くして振り返るな」「答えは常に現場にある」「目標は低めに設定する」など、途中から「器」の話はどこに行った?と思わざるを得ない内容が続く。
著者は伊藤忠で社長にまで上り詰めたエリートであり、他にも多くの書籍を出版しているようだが、全て同じ内容を書いており、本の題だけ変えているのでは?と思ってしまった。
投稿元:
レビューを見る
著者が取り上げているどの項目も大事であり、簡単なようであり、当たり前であり、それができないから悩むのだ、というものである。
多分自分の置かれている環境や時期によって刺さるものは異なるのだろうけど、今は、お金が不安。そんな今だから、お金に執着すると人は逃げていくという言葉は戒めとして胸に刻んでおきたい。
人のためにお金を使えばいずれ回ってくるということを肝に銘じ、自分のためでなく、よのため人のため、家族のために使いたいと思う。
投稿元:
レビューを見る
昨年購入。たった今読了。
何冊か前に【20代で得た知見】を読んでからの
80歳の著者の内容は目新しさには欠けた。
そもそも器の大小を分析したところで無意味。
何か起きている時に取り乱さず口を出さなければ一見器の大きい人に映るが、人間には動物の血が色濃く流れているため如何に自分を律するか?
自尊心を捨てた矢先の自分には
【三つ子の魂百まで】の方がしっくり来る。
上記の【人間には動物の血が流れている(後略)】のくだりは4回も登場している。
∴如何に理性でコントロールするかが筆者の1番言いたいことなのではないか?
絶体絶命な出来事を目の当たりにした場合は
理屈ではわかっても感情を抑えきれない。
筆者も「悪い感情は無理に打ち消す必要はない。
無理やりなくそうとすると自分を偽っていることになる」と書かれている。
でも「『まだ自分はこの程度だな』と自分に対する認識をすれば多少なりとも【人間の器】を大きくすることにつながるのではないか」とも。
甚だ難しい。
2022,11,6〜11 3時間56分
投稿元:
レビューを見る
器の大きな人間になろうと思うが、なかなか難しい。しかし、努力することにも意味があると思うので、自分は何も知らないということを自覚する、アウトプットも行う、読書で知識を得て、経験を加えて、知恵を得る、部下を褒める場合は、人前で、叱る時は、個別に叱ることを実践したいと思う。
投稿元:
レビューを見る
読もうと思った理由
人間の器という言語化しにくいものをどういう風に書かれているのか知りたかったため
気づき
・撤退する勇気や決断はギリシャ・ローマ時代からリー
ダーにとっての重要な要素である
・真のリーダーはいつでも自分を捨てる覚悟をもってい
る必要がある
・仕事で新しいことを構想するときは、考えられること
をすべてアウトプットしてみるとよい
・仕事において大事なことはいかなる立場にあろうと、
現場をよく知ることである
・悪い心でいるときは、つい目をそらしたくなります
が、そういうときこそ、なぜそんな心の状態になって
いるのか意識して向き合ってみる
・必然の運は自分の努力や工夫によってもたらされる
一見、当たり前のこともあるような気がしますが、自分がいつも実践できるとは限らないし、なかなかできないことだと思います。現場を知るということは自分で確信するために必要と思います。心構え、考え方は意識していきたいです。
投稿元:
レビューを見る
●何が起きてもそれがベストと考える。
最善の状態という意味ではなく、その時点ではそれしかなかったという意味のベスト。
●ベストを尽くすが反省しない。
結果は自分の実力と受け入れ、気持ちを切り替えて清々しい気持ちでいること。
●時に積極的に諦める=いい身切りを。
時間は生命。時間を無駄にするのは自分の生命を無駄に消費することになる。
投稿元:
レビューを見る
お金は手段。
自分を捨てる覚悟を持つ。
現場が命。第一情報が1番。
力の抜き方が大事だけど、量をこなさなきゃ質は増えない。
雑務を大事にする。
投稿元:
レビューを見る
この本を読んで、毎日を大事に生きていくことを大事にしたいと思いました。
仕事をする上での、モチベーションにもなっています。