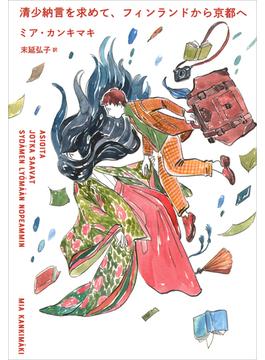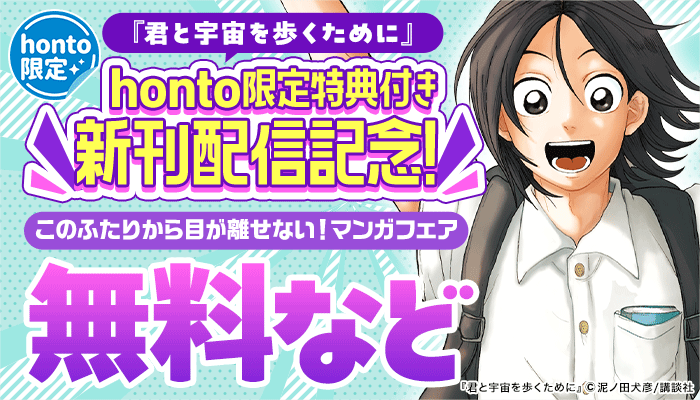彼女の鋭すぎる考察
2022/01/18 21:55
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
平安時代の女官・セイ(清少納言)とフィンランド人の私(ミア)、二人の物語。ミアは清少納言についての本を出版したいと、日本にやってくる、そして吉田神社の近くのゲストハウスに下宿することとなる、その間に東北大震災が起こって、一時、タイへ避難するなどの紆余曲折をへて、無事、本は出版されることとなった。フィンランドの、しかも日本語も片言しか話せない人が清少納言なんか理解できるのかと侮りながら読み進んだのだが、それは大間違い。彼女の紫式部が清少納言を芳しく彼女の日記に書かなかったことも、清少納言が道隆の死や定子の晩年の苦境を枕草子に描かず、宮廷の華やかな様子の描写に終始したので、すべて依頼者からの要望があったからという指摘は鋭すぎる、これが正解のような気がしてきた
憧れを自分の手に。
2021/12/24 16:30
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:名取の姫小松 - この投稿者のレビュー一覧を見る
職場での環境が変わる。そんな時著者はフィンランドの長期休暇制度を利用して、日本へ行こうと思い立った。『枕草子』の作者清少納言について詳しく知りたい、そしてその結果を本にできないかと、故郷を飛び立った。
著者は日本語ができないし、『枕草子』は英訳で読んだ。それでも焦がれる気持ちは行動に移さずにいられなかった。
紫式部より知名度が低い、英語にされた文献が少ない。世界文学での『枕草子』の知名度にぶつかりながら、セイを求める旅が綴られる。
なぜフィンランドから?
2023/09/06 00:17
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
それが、はじめの疑問でした。でも読み進めるにつれて、ミアさんすごい。本当に清少納言に魅せられて、日本にはるばる渡って来られたのね~。愛にあふれてます。
投稿元:
レビューを見る
ミアさんの清少納言にたいする情熱がすごい!!
京都や平安時代や清少納言がとても身近にかんじられ、すぐにでも京都やどこか好奇心のおもむくままに旅に行きたくなるような本でした。大満足!
投稿元:
レビューを見る
清少納言に憧れるあまり、長期休暇を申請して京都にやってきたアラフォーシングル女性の著者。異国の風景の中に「セイ」の手がかりを探す旅は、彼女自身の人生をも変えていく…。2021年のマイベストブック候補。
本名すら不明な「セイ」の残した文章に、時空も言葉や文化の違いも超えて魅かれた著者。鋭い感性や好奇心、新しい世界に飛び込む冒険心を共に持つ二人の出会いはまるで奇跡のよう。原題が枕草子の章段からとった『心ときめくもの』というのもまた、いとをかし。
投稿元:
レビューを見る
セイ(清少納言)を求める日本紀行、約500ページ
日本語は全くできないのに、あっという間に京都での極貧生活(個室冷暖房なし、共同キッチンにはゴキブリが頻出!)を受け入れて、自転車で市内を縦横無尽に走り回り、セイを熱く語るフィンランド女性。
(枕草子はフィンランド語訳はなく、英語で読破)
そのバイタリティに脱帽です。
投稿元:
レビューを見る
フィンランド人で日本古典研究者なんて、すごいなあ。私は日本人なのにくずし字も読めないのに。と思って手に取ったら、著者は研究者ではなく広告編集者。さらに、なんと著者は9月来日なのに7月に大学公開講座の日本語入門クラスでひらがなの勉強から始めるのである。えー、どうやって研究するの!?と驚いた。
でも、財団の助成金は支給されるのだ。長期休暇制度などフィンランド社会は羨ましいことがまだまだありそうだ。
本書はいわゆるお堅い学問的「清少納言研究」ではなく、いうなれば「清少納言のをかしを体感したい」という旅行随筆だろうか。そのため、古典文学玄人にはもの足りないかもしれない。
私は、清少納言を求めて試行錯誤する著者が少しずつ彼女のつかめそうでつかめない影に近づこうとする過程を共感しながら読むことができた。
さて、著者は清少納言のをかしにたどり着けたのか。ぜひ、著者の感じ取ったもののあわれについてを読んでほしい。
私はフィンランドのクロウタドリの歌を聴いてみたい。
投稿元:
レビューを見る
清少納言が好きすぎて、京都にやってきた作者の好き好きエネルギーの激流。身体ごと押し流されるようになって最後まで読み切りました。
時々、狂の領域にイッてると感じる彼女の清少納言への入れ込み。少し怖いけど、すごく惹かれます。
こんなに好きにのめり込むと、2010年の京都にいても、平安時代の清少納言の世界を妄想することができるんだな、すごすぎる!
一緒に京都を歩きたい、一緒に清少納言を探したい気持ちになりました。
投稿元:
レビューを見る
こういう形式?の本を読んだことがなかったので、いいな、こういうの、と思った。筆者は「文学的な趣のある自伝紀行文学」のようなもの、とおっしゃってるようだ。
日本人が日本の古典本を携えて旅する紀行文なら別に普通。外国人が日本の古典文学を携えて旅する紀行文、というだけではないんだな、この本。
セイとの対話がいいのかな。日本人でも清少納言と対話しながらのエッセイとか、ない。あるのかな。
そこまで自分に引き寄せられない、隣にいるようには書けない。「枕草子」の内容は現代の私たちにも共感できる部分がたくさんあるのだけれど、「セイ」と言えるような関係など考えたことはなかった。
「セイ」っていう呼び名、呼びかけが斬新で、グッと惹きつけられたように思う。その部分とご本人の日記、エッセイ部分の親しみやすさ、面白さ。京都だけではなく、プーケットやフィンランドやロンドンの紀行文的面白さ。東日本大震災時の描写。
仕事を休み、複数の財団からの助成金を集め、現地に飛んで調査、研究する逞しさ。行動力と勇気にとても元気をもらえる。
投稿元:
レビューを見る
ほとばしる清少納言愛と京都愛。
作者の「ものづくし」の章段もおもしろい。
作者が、仕事を長期で休んで京都に来て、調べ、考え、悩む。人生の転換点にたち、歩き出す不安、楽しみ、エネルギー、悪戦苦闘を鮮やかに描く。「好き」はすごいパワーを生む。
震災のとき、彼女も日本にいたとは…
投稿元:
レビューを見る
清少納言 (「セイ」) にシンパシーを感じ、彼女のことを知ろうと日本語もわからないまま単身フィンランドから京都に移り住む著者にパワーをもらえる本。
日本人より平安京に詳しくてその熱意に感動する。
小説のようにドラマチックなノンフィクション。
投稿元:
レビューを見る
ミアとセイに感謝します。彼女たちも、わたしも、同じように"生きた"女性なのだということに励まされました。幸せな読書時間でした。
投稿元:
レビューを見る
枕草子に惹かれて京都に来てこの本を書くことになるまでのの話。なんだが、めっぽう面白い。311の話が身につまされる。2022初ブクログ。
投稿元:
レビューを見る
フィンランドから、休職願いを出して、自宅を貸して、日本語が全くできなかったにもかかわらず、京都に枕草子を書いた清少納言を求めてやってきた作者ミア・カンキマキ。
この本は彼女がセイと呼ぶ清少納言の真実を探し求めて、ゴキブリが我が物顔で這い回る京都吉田山近くのシェアハウスで過ごしたノンフィクションでもある。
源氏物語と違い、バラバラになってしまった枕草子は、それが本物か?さえ異論が錯綜する作品。
元版は無く、どんな配列で編集され綴じられたのかさえわからない。
私は読みながら思い出した。
中学生の私は源氏物語の男性主導の物語を嫌い、腹立ち、この古い時代に自分の意見を通し自分の美意識を貫いた清少納言の枕草子が好きだったことを。
だが、教科書くらいの知識では宮中から政変で追い出された後のことは何もわからなかった。
今回この本を読んで、いろいろなことがわかった。
これがフィンランドでベストセラーになり、日本ブームの火付け役になった所以がわかる本!
投稿元:
レビューを見る
長期休暇を取り、清少納言について調べるために京都へやってきたカンキマキさん。フィンランド語に訳された枕草子を読んで、清少納言について知りたいと思いたち、日本語はできないものの、夏の京都ヘやったてきた。その滞在記が本書。
清少納言にセイと呼びかけながら、セイを真似た書き方をしたり、セイの言葉を挟んだり。はじめのうちは、なかなか清少納言研究にならず、普通の日本滞在記かしらと思わせるが、徐々にカンキマキが理解したセイについてを自由に描いていく。日本でもよく知られていない清少納言という人物を、親しみを込めてまとめている。そして、カンキマキ自身の新しいチャレンジとなったようだ。