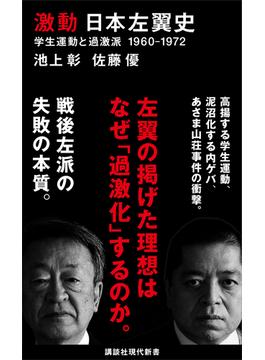なぜ殺人を正当化する思想に変化したのか?
2022/01/16 13:03
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:つばめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、おなじみの元NHK記者と元外務省職員による対談により構成され、1960年から1972年までの日本の学生運動と過激派の動向を柱にして論じられた内容である。本書執筆の目的について、<人間を最終的に殺し合いに駆り立てる思想にしても、その始まりにおいては殺人とは無縁の、むしろこの世の中を良くしたいと真剣に考えた人たちが生み出したものではあるわけで、だからこそそれが、どういう回路を通ることで殺人を正当化する思想に変わってしまうのかを示したいのです。>と、著者の一人が述べている。学生運動の章で印象に残った例を挙げると、次のとおりである。◆1969年の東大安田講堂事件で逮捕された学生は、ほとんどが他大学の学生であった。これにより人生を棒に振ってしまった学生も多かった一方、東大生はほんの数人を残して直前に逃走。◆東大紛争と同時期に日大紛争も勃発。20億円の使途不明金がこの紛争の引き金であり、取り締まる警察も当初は学生に同情的であったらしい。蛇足ながら、日大は最近も附属病院の建替え工事を巡る背任事件に端を発した一連の不祥事が世間を賑わしている。政治家の不祥事には舌鋒鋭く追及している日大法学部教授は、学内の不祥事には黙して語らず・・・。◆当時の学生運動のリーダーたちの知的水準は今考えると驚くほど高かった。
閉ざされた空間、人間関係の中で同じ理論集団が議論していれば、より過激な意見が優位に立つ。これが、殺人を正当化する回路であると結論づけている。
殺し合いに至るロマン主義?
2022/03/24 16:01
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:魚太郎 - この投稿者のレビュー一覧を見る
新左翼は、哲学・思想の面で優れたものを持っていたにもかかわらず、政治的には全く無意味な運動に終わったという。後世に残したものがない。内ゲバの陥穽に嵌り込み、互いに真剣に殺し合いまでして自滅した。そのエネルギーはいったい何に向かい、結局は何だったのだろうか。自分は1977年の大学入学だったが、当時は7~8年前の激しい学生運動の残渣すら見当たらず、自分も含めて周囲は無気力なノンポリ学生ばかりだった。そういえば、「安田講堂」や「あさま山荘」の映像をテレビで観て、「あんなふうになってはいけないね」と言われて育ったのだった。それにしても何故、哲学・思想的に優れた知性を持っていた彼らが、暴力革命が可能だと盲信して社会から逸脱して行くことになったのか。それは「ロマン主義だった」とのことだが、殺し合いを肯定するロマン主義というのはあるか。まだどうも、納得できない。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:たか - この投稿者のレビュー一覧を見る
冷静な立場で、冷静に左翼を評価。安心して読める一冊。
投稿元:
レビューを見る
共産党の独特の立場については、よく分かった。
また、学生運動が、若者が政治について考えてなくても良いという言い訳を蔓延させたという点もなるほどと思った。
ただ、戦後の政治史の中で、表面に浮かぶような右翼史は成り立つのか?(そこをギリギリ隠してきたから、どこかの政党は長期化しているのか?)
投稿元:
レビューを見る
60年安保から学生運動の高揚、新左翼の衰退まで。左翼内の意見相違から内ゲバ化していく経緯が語られているのだが、当時の雰囲気ってそんなものだったのだろうか。
投稿元:
レビューを見る
日本共産党の考え方。福祉国家とは国民の選択を社会主義に向かわせないため、社会保障や所得配分を部分的に改善し、国民を資本主義体制の枠内に留め置くための、資本主義延命策。共産党の党内序列は獄中生活が長い者順であったが、造反議員を排除する目的で、更に完全黙秘を貫いた者が偉いとなり、宮本顕治が№1となった。
しかし以前と比べ、ストライキ闘争はめっきり減った。公立の学校でも以前は毎年のようにストライキが行われていたが、当時から公務員のストライキは法律で禁止されていた。つまり処分覚悟で実施していた。で、クビになったり、幹部だと逮捕されたりしたが、そのような教師は日教組等の専従となり働けた。だから違法なストライキも覚悟をもって貫くことが出来た。
共産党と社会党の争い。共産党は労働者が社会党に引き寄せられるのを嫌がり、大規模ストなど派手な闘争を総評主導で進めてきた社会党を「一揆主義」(国家にかなわない一揆を起こしても、権力に叩き潰されるだけで効果が無い)として批判しだした。共産党にとって真の敵はアメリカ帝国主義であるため、国内問題である日本の差別問題(部落や沖縄)までも無い事としてきた。
新左翼。彼らにとって60年安保闘争の敗北は巨大な挫折。もう何をやっても無駄という無力感に襲われた。当時大学の自治は非常に重視されており、今と違い大学側が学内に警察を招き入れ学生を排除するなど言語道断という意識は、広く一般学生においても当然の考えであった。民青(共産党系)と全共闘の内ゲバは凄惨。日大は当時から裏金・使途不明金のオンパレード。裏金を応援団や柔道部に配り、全共闘学生を襲撃させる。YouTubeで「日大闘争の記録」を見られる。早稲田では法学部以外を革マル派が制圧。他のセクト学生に対し、鉄パイプで膝の皿を割ったり、目をタバコの火でつぶすなど、再起不能にし学校に出てこられないようにしてしまう。警察も捜査しない。京都の左翼系書店には公安がいて、本を探す学生に声がけし、親しくなり公安の内定者に仕立て上げる。全共闘指導部も三島由紀夫事件に衝撃を受け、あそこまで体を張れる人間を我々は一人も持っていないと嘆く。そして赤軍派、大菩薩峠事件と、よど号事件、更にはテルアビブ空港乱射事件。実行犯の岡本らは最初から生還できないことは判っており、その覚悟はパレスチナで称賛され、難民キャンプでは「オカモト」や「コウゾウ」という名を付けるのが流行した。
しかし結局新左翼はその過激さゆえに日本人を総ノンポリ化させてしまう。著者も暴力の対象を権力だけにしていれば存在感は示せたかもしれないと述べている。そしてそれが個としての自立にはこだわるが、目の前の利益をひたすら追求する経済成長型サラリーマンを量産することとなる。新左翼の連中は信頼していた仲間に裏切られ、党も何も信用できなくなり、頼れるのは自分だけという会社員に育ち、新自由主義の母体を作った。日本赤軍幹部の重信房子は今年5月28日に刑期を終え出所する。
投稿元:
レビューを見る
今や死語になりつつある「左翼」。しかし、その思想は、かつては、「いざとなれば自分だけでなく他人を殺すことも躊躇うまい」と人に決意させてしまうほどの力をもった。何が、若き知的エリート達の心をとらえたのか、なぜその思想は力を失ってしまったのか…。
「左翼というのは始まりの地点では非常に知的でありながらも、ある地点まで行ってしまうと思考が止まる仕組みがどこかに内包されていると思います」。
「人間には理屈では割り切れないドロドロした部分が絶対にあるのに、それらをすべて捨象しても社会は構築しうると考えてしまうこと、そしてその不完全さを自覚できないことが左翼の弱さの根本部分だと思うのです」。
池上彰と佐藤優が対談で歴史を解き明かす。新書だけれど、中身は濃い。
投稿元:
レビューを見る
左翼はなぜ過激になるのか。(右翼にもあてはまりますが)豊富な事例を分析しながら解き明かす。現代への示唆もしっかりあります。おすすめです。
投稿元:
レビューを見る
今の70代はこういうことをしていたと知っていた方がよいですね。
血の気の多い方もたくさんいますので。
投稿元:
レビューを見る
「左翼」のことが大嫌いな人がいる理由や、「左翼」とレッテルを貼ることが相手に対する悪口だと考えている人がいる理由が分かるかと思って前巻から読み始める
60〜70年代の過激な学生運動や過激派の活動が共産党とは無関係であることは前巻から説明されていたので分かっていたが、逆に共産党がストライキに反対していたことは知らなかった 総評→連合が労働組合が共産党から距離を置くのはそういうことだったのね
かといって、報道されている芳野友子の言動からは、芳野友子が共産党を嫌う理由がそこにあるようにも思えず。。。
新左翼が過激化した原因を全然共産党のせいにするのは論理が飛躍してないか
組織を過激化させないように組織にダラ幹を置いて官僚化せよと、社会党をぬるま湯体質と批判した同じ口で元公務員が主張するのは、自分の怠慢を正当化する屁理屈にも思えるし、今の野党が官僚化しても自民党に対抗する力を持つことができるようになるとも思えない
結局、佐藤優も長いものに巻かれてる人なのね
投稿元:
レビューを見る
感想
戦後の日本を語る上で左翼の変遷を避けることはできない。左翼史を学ぶことは日本を学び直すことにつながる。
学生運動は過去の記憶として、戦後日本の黒歴史のように扱われるが、今こそしっかりと見つめ直し、なぜ学生運動が残酷な内ゲバやテロリズムに発展したのか考えておく必要がある。
本書を読めば時代的背景も相まって当時の知識人が左翼思想に辿り着くことは自然のことであったし、その活動が過熱することも運命だったのだと分かる。
この本を読むと、一つ一つの派閥の変遷や傾向も生々しく分かる。
最初は主に政党への失望から派生した学年運動も、少しずつ本来の思想を失い、最後は内ゲバやテロリズムに発展して崩壊していく。
個人的には学生運動や左翼には少なからず嫌悪感や違和感があったが、本書はそういった部分は抜きにして、左翼という軸で昭和の日本の世相や価値観を感じることができた。
投稿元:
レビューを見る
昔も今もセンスがないという一点において左派は一貫してるなーと思った。
政治的なものの見方で突拍子もないこといったり暴力を肯定して大衆に見放されたり。とにかく大衆意識との乖離を自覚しない点で常に地に足ついてない。
過去の左派では「エライ」の基準は獄中暦とか非転向とかだったそう。本書で描かれた時代にはこの基準が先鋭性に移り変わったと見える。現代では「正しさ」。より正しく誤謬のない理論や価値観を提示できた人がエライ。そうなってしまう理由が理論への過信にあるという佐藤の見方には同意する。
現代において見られるのは、理論に惹きつけられるのはエモーションの働きが弱い人、つまり性欲や金銭欲などの俗っぽい欲望が希薄な若者が左派に引き寄せられる傾向。欲望が希薄なので基本的に欲望に従って生きている大衆の気持ちがわからない。理論を学べば学んだ自分達が正しく学んでいない大衆が遅れているという意識になるので、平気で「保守化する若者は想像力が足りない」みたいなことを言い出す。誰がより正しいかという競争は大衆からどれだけ乖離できるかという競争でもあるのだけど、それと同じ構図の競争の到達点が浅間山荘だったことは他人事としか思ってないのかな?
現代の左派の人たちこそ読まなければならない本。
投稿元:
レビューを見る
家に持っておきたい本ですが、
左翼史の中で最も吐き気がする部分であり、
個人的には思想として資本主義に疑問を感じていても、一緒にされなくないという思いが湧いてしまうのはこういう暗い歴史に対する活動家の捉え方に触れた時だと率直に思う。
投稿元:
レビューを見る
1.この本を一言で表すと?
学生運動がなぜ起こり、何故終息したのか振り返った本。
2.よかった点を3~5つ
・「敵の出方」論をめぐる志位和夫の嘘(p60)
→共産党の民主集中制の異常さがよくわかる内容だと思う。佐藤氏が言う「矛盾や詭弁を平気で口にできてしまう体質」の問題点もよく分かった。
・日本人を「総ノンポリ化」した新左翼運動(p245)
→現代に思想の面で何も残せなかったが、それでよかったのかもしれない。
浅間山荘事件の犯人の1人加藤倫教が2/28NHKラジオに電話出演していたが、今事件をどう捉えているかの質問に「事件後、政府に対して反対する市民運動自体が悪いことになってしまった」と語っていた。
・人間には理屈では割り切れないドロドロした部分が絶対にあるのに、それらをすべて捨象しても社会は構築しうると考えてしまうこと、そしてその不完全さを自覚できないことが左翼の弱さの根本部分だと思うのです。(p209)
→この文が左翼の失敗の本質ではないかと思う。
・2019年の慶應三田祭で卒業生が昔の学生生活について在校生に教えるという企画があり、私のところにもある現役学生が話を聞くために訪ねてきたのですが、この学費値上げ反対ストの話をすると不思議そうな顔をしているんですよ。彼らからすると「だってこれから入ってくる学生の授業料を値上げするんでしょう? 在校生には関係ないのに、何で反対するんですか?」というわけです。
それを聞いて私はつい語気を強めて「おい! 君は自分さえよければいいのか!」と言ってしまいました。(p114)
→私はこの学生と同じ考えです。個人主義が広がったということか。
2.参考にならなかった所(つっこみ所)
・左翼思想家はなぜ別名(ペンネーム)をつける人が多いのか?
3.実践してみようとおもうこと
・主義主張には反対の主張の両面からチェックするべきだと思う。
・今後左翼思想が主流になった時、戦後左翼史の失敗を繰り返さないために何をすれば良いか?
5.全体の感想・その他
・細かい解釈の違いみたいなもので彼らは殺し合いをしていたのかと唖然としてしまう。
・思想というのは、革命を成し遂げるためには人を殺してもいい、という考えにさせる非常に怖いものだと思う。
投稿元:
レビューを見る
1巻目もそうだったが、理論家の登場人物が多すぎて頭こんがらがる。
そして事実の解説部分と佐藤優さんの自説開陳部分の区別をもう少し明瞭にしてもらいたい。
60年安保→その後空白期間→68年東大闘争→ますます過激化し70年よど号ハイジャック事件など
という流れは改めて理解できた。
それからこれは次の巻で語られるのかもしれないが、新左翼が世間から見放されたことはわかるがそれがどう社会党と共産党の凋落に結びつくのかをもう少し詳しく解説してほしい。
だって流石に規制政党は新左翼みたいな内ゲバやらないでしょ、と普通考えると思うので世間が左翼全体を見放すにはもう少しいくつかの要素がいるんじゃないか。と思ったりした。
今を生きる私たちにとって重要なのは、佐藤優が何度か言及している「左翼とリベラルは違う」という点を理解することなのでは?
リベラル=左翼と思われてるし当事者もそう思ってると思うので、次の巻ではその点をもっと語ってほしい。