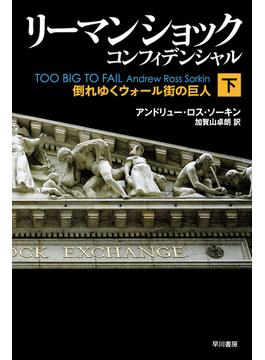リーマンは倒れた、そしてAIGが焦点になる
2015/10/25 00:14
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:okadata - この投稿者のレビュー一覧を見る
2008年9月12日CNBCにテロップが流れた。「関係筋によると、リーマンの問題解決に公的救済はない模様」13日土曜日、ポールソンがウォール街の全CEOを招集し冒頭でポールソンはこう言った。「週があける前に、何らかの解決策を見いださねばならない。公的資金注入はその答えではない。あなた達だけで解決してもらう。」買い手の2社は支援なしでは資金は出さない。その片方のバンカメCEOのケン・スミスもここにおり、参加者は全て状況を知っている。もしリーマンが倒れたら次はメリルリンチ、そしてモルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス(GS)と破綻は連鎖する。この日のメンバーではないがAIGやGEも危ない。メリルもバンカメとの合併に意欲を見せておりもしバンカメがリーマンを助けたら今度はメリルが窮地に陥る番だ。7月にGS出身の財務次官ロバート・スティールがCEOに就任したワコビアも危ない。AIGの方は新たな損失が見つかり資金は600億ドル必要と見積もられた。
14日朝、イギリスのバークレイズはリーマンのバッドバンクに他の銀行が330億$融資すれば残りを買収することを表明していた。CEO達は拠出を決意しリーマンは救われるかに見えた。しかしイギリス政府はアメリカの金融危機を持ち込むのを嫌い許可しなかった。なぜアメリカ政府が何もしないのにイギリス政府がリスクをとる必要が有るのか・・・
ついにプランBがスタート、連銀は貸し出し枠を拡大する準備を始めたがそれをリーマンに利用させるとモラル・ハザードが拡がるためその日の内にリーマンに破産申請させる必要が有った。政府に破産を強制する権限はないのだが。もはや時間も策も残されていないリーマンの取締役会はこの日の夜遅く破産を決定し、15日にチャプター11を申請した。その裏では1株29$と言う金融業界市場最高のプレミアでのバンカメのメリル買収が決まった。
16日午後1時連銀の繋ぎ融資が受けられなければAIGは後数分でキャッシュ不足で破産するところまで追いつめられていた。AIGは世界的な金融システムの事実上の要であり、もし破綻すると世界中の金融機関のレバレッジを支えたCDSの保証が消えあらゆる銀行が資金調達の必要に迫られる。さらにAIGは世界中で8100万件の生命保険を発行しその総額は1.9兆$を越える。AIGの破綻は大恐慌を再来させかねない、まさしくTOO BIG TO FAILだ。連銀はAIGにLIBOR+8.5%と言う高金利で850億$を貸し付けたがその後のAIGのモラル・ハザードはオバマ大統領のボーナス奪還宣言によく知られている。
ポールソンは9月19日に不良資産救済プログラム(TARP)を発表し、10月3日下院の再審議でようやく可決された。とにかく各銀行に先ず資金援助を受け入れてもらう、そうしておかないとTARPを利用する銀行は危ないと狙われるためだ。TARPの準備金は7000億$(70兆円)。2008年9月24日に成立した麻生内閣の景気対策が75兆円、09年度の当初一般会計予算が88.5兆円だ。
のちにポールソンはリーマンを救済しなかった理由を定期的に修正している。最初は警告のため、そして後にはその権限がなかったと。それでもバークレイズをつなぎ止める手は残っていたしモラル・ハザードがなくなったわけでもない。このように批判される部分はあるにせよよくこれだけの手を打ったものだ。ブッシュ大統領が全く金融システムを理解しておらず、ポールソン、ガイトナー、バーナンキ達に丸投げだったことは幸運だったのかもしれない。麻生政権の景気対策も使い道はともかく非常時の対策としてはもっと評価されるべきなのだろう。鳩山内閣のぐだぐだ進行が1年前に始まっていればと考えるとちょっと怖い。
わかっていても止められない
2022/02/19 16:45
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:いて座O型 - この投稿者のレビュー一覧を見る
「リーマン・ショック」の裏側で何が起こっていたかを、詳細にリポートした歴史に残るであろう名著。
名だたる大金融機関が、次々と危機に直面するものの、様々なしがらみや、政治的問題に翻弄され、立ち往生寸前に陥っていく状況は、まさに迫真の内容で、リーマン・ブラザースの倒産でその自体が極に達する。
最後のほうで東京三菱が重要な役どころで登場するのも面白い。
投稿元:
レビューを見る
日本の小泉政権時代を一気に解決するために
アメリカの利害関係者がおのおのの立場でどう
動いたかが分かる本でした。
良くも悪くも民主主義・資本主義がわかるが
功罪はおいても決断してきめるリーダーが
いるかいないかは大事。
投稿元:
レビューを見る
米国だけでなく、英国、中国、そして日本からも金融エリートが集い、打開策を昼夜を問わず議論し試みるがついにその日がやってくる。100年以上の歴史を誇るリーマン・ブラザーズの破綻である。これに前後して、AIG、モルガンスタンレーなど連鎖倒産の危機が現実的なものとなる。ついに政府が乗り込んで・・・。自由経済を信じ、自由経済を守るために政府が乗り込むという皮肉。上巻に続き、各社のCEO、弁護士、州知事や大統領、財務長官、連銀総裁などの生々しいやり取りが一層加熱する。またじっくり読みたい一冊。
投稿元:
レビューを見る
素晴らしい。朝起きても仕事をしてても常に続きが気になった。金融知識がないので結構タフな読書だったが、濃密な体験だった。
鬼のように複雑で、スパゲティのように絡み合った依存構造の中で、リーマン・ブラザーズの破綻、メリルリンチの売却、AIGの危機…分単位で数百万ドルの金がなくなり、経済崩壊が広がっていく中で不眠不休で終末から救おうと闘った人たちの話。彼らが何を考え、どう行動したか、凄まじい取材力に圧倒。
投稿元:
レビューを見る
原書名:TOO BIG TO FAIL
第13章 誰がリーマンを救うのか?(承前)
第14章 全CEO招集
第15章 リーマンの最期
第16章 AIG倒れる
第17章 モルガン・スタンレー絶体絶命
第18章 三菱UFJからの電話
第19章 揺らぐゴールドマン・サックス
第20章 ワシントンDCへの最終招集
著者:アンドリュー・ロス・ソーキン(Sorkin, Andrew Ross、ジャーナリスト)
訳者:加賀山卓朗(1962-、愛媛県)
投稿元:
レビューを見る
「時間があると言うときには足りないものだ。」
誰がリーマンを救うのか、から始まる後編。
後編でも、各会社の生き残りをかけた画策が見られる。そして、”株主のため”というスタンスを重視している姿は、やはり日本の起業人とは違う考えなのだと感じた。株式会社である以上は、他社を顧みずに自社利益を追求するのが第一に正しい考え方なのだとは思う。
リーマンショックを通して、金融は貪欲で危険なものだという認識がそれまで以上に広がった。その結果、お金からお金を生み出す行為は不潔で非人間的だという侮蔑が一般化している。そのような考え方は一理あるかもしれないが、人が成功してお金持ちになることを妬んではいけない。
投稿元:
レビューを見る
(上下巻共通)
結果としてどんなことがおこったかはわかっていたけれど、どんな経緯で事態が推移していったのかがわかって興味深く読めました。
何が正しい選択だったのかはわかりませんが、政治家がメンツにこだわらなければもう少し軟着陸の可能性が有ったんじゃないかと思います。
あと、経営者が事態をちゃんと把握できないのもおっかない感じでしたね。
投稿元:
レビューを見る
2008年9月12日午前9時15分、CNBCにテロップが流れた。「関係筋によると、リーマンの問題解決に公的救済はない模様」市場が開くとリーマン株は3.84$に下げる。6月頭に韓国産業銀行(KDB)からの出資受け入れを交渉していた時点ではまだ株価は30$でリーマンCEOのファルドは33%増の40$を主張した。7月21日にバンカメに持ちかけた際には株価は18.32$で少なくとも25$欲しいと主張したがバンカメにとってはただ同然で買えるのでなければ意味がなかった。リーマンの資産にはあまりにも不透明なものが多すぎたのだ。
9月4日にはポールソン財務長官はファニー・メイとフレディ・マックの救済を決め、その終末に両社はこれを受け入れ7日の日曜日に発表された。次はリーマンだ。この時点でファルドはこう言っている「ベア・スターンズですら1株10$だ。この会社はそれより安い値段では絶対売らないぞ!」。1株6.4$を提示していたKDBは手を引いた。9日にはJPモルガンがリーマンの一部を買いたたく可能性をほのめかす。この日の終値は45%安の7.79$。
10日リーマンは前倒しで第3四半期の決算発表を行った。改善計画では資産運用部門の55%を売却し、不良資産をスピンオフさせる。しかし、売却資産のポートフォリオは時価を反映させず新会社は時価評価の圧力を受けることなく、”みずから”が実態価値とかけ離れると考える価格以下での資産売却を強いられませんと続けた。リーマンを批判し続けてきたヘッジファンドマネージャーのアインホーンから見れば事態はもっとはっきりしている。リーマンは有害なゴミ資産の評価源を避けようとしている、いかようにも数字をでっち上げられるということだと。リーマン株は少し戻したがまだ解決していない問題がある。新会社には資金が必要だ。この時点でJPモルガンは手を引き最後に残った資金の出し手はバンカメかイギリスのバークレーズとなった。
13日土曜日、ポールソンがウォール街の全CEOを招集した。午後6時45分から始まった会議の冒頭でポールソンはこう言った。「週があける前に、何らかの解決策を見いださねばならない。公的資金注入はその答えではない。あなた達だけで解決してもらう。」買い手の2社は支援なしでは資金は出さない。その片方のバンカメCEOのケン・スミスもここにおり、参加者は全て状況を知っている。もしリーマンが倒れたら次はメリルリンチ、そしてモルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス(GS)と破綻は連鎖する。この日のメンバーではないがAIGやGEも危ない。日本の銀行に対する公的資金投入は評判が悪かったがアメリカでも同様だ。共和党は納税者の負担が増えることに、民主党は企業の高給取りと経営者の救済に反対している。メリルもバンカメとの合併に意欲を見せておりもしバンカメがリーマンを助けたら今度はメリルが窮地に陥る番だ。7月にGS出身の財務次官ロバート・スティールがCEOに就任したワコビアも危ない。AIGの方は新たな損失が見つかり資金は600億ドル必要と見積もられた。
14日朝、イギリスのバークレイズはリーマンのバッドバンクに他の銀行が330億$融資すれば残りを買収することを表明していた。CEO達は拠出を決意しリーマンは救���れるかに見えた。またメリルもGSから1株1桁価格なら買収される見込みがついた。しかしここで認識されてはいたが重視されていなかったイギリスの上場基準が待ったをかける。正式に取引が完了するまでの間リーマンに債務保証するには株主投票が必要であり、今日中に買収を決めるためにはイギリス政府から免除の承認がいる。しかしイギリス政府はアメリカの金融危機を持ち込むのを嫌い許可しなかった。なぜアメリカ政府が何もしないのにイギリス政府がリスクをとる必要が有るのか・・・
ついにプランBがスタート、連銀は貸し出し枠を拡大する準備を始めたがそれをリーマンに利用させるとモラル・ハザードが拡がるためその日の内にリーマンに破産申請させる必要が有った。政府に破産を強制する権限はないのだが。もはや時間も策も残されていないリーマンの取締役会はこの日の夜遅く破産を決定し、15日にチャプター11を申請した。その裏では1株29$と言う金融業界市場最高のプレミアでのバンカメのメリル買収が決まった。15日の記者会見では予想されたようにポールソンが返答に困る質問が来た。「ベア・スターンズは救済したのに、リーマンは救済しなかった理由は?」「連銀がAIGにつなぎ融資を行う理由は?」
16日午後1時連銀の繋ぎ融資が受けられなければAIGは後数分でキャッシュ不足で破産するところまで追いつめられていた。AIGは世界的な金融システムの事実上の要であり、もし破綻すると世界中の金融機関のレバレッジを支えたCDSの保証が消えあらゆる銀行が資金調達の必要に迫られる。さらにAIGは世界中で8100万件の生命保険を発行しその総額は1.9兆$を越える。AIGの破綻は大恐慌を再来させかねない、まさしくTOO BIG TO FAILだ。連銀はAIGにLIBOR+8.5%と言う高金利で850億$を貸し付けたがその後のAIGのモラル・ハザードはオバマ大統領のボーナス奪還宣言によく知られている。22日には子会社の幹部が44万$を費やした高級リゾートでの会合を催し、翌年3月には幹部社員に対し1億6500万$のボーナス支給が発表された。
モルガン・スタンレーは東京三菱UFJからの資金提供で生き延びたがそれは90億$の小切手で10月13日午前7時53分に契約が締結され手渡された。偶々この日は日米ともに休日で電子送金が出来なかったのだ。19章の終わりにおそらく2度と現れない高額小切手のコピーが載っている。
ポールソンは9月19日に不良資産救済プログラム(TARP)を発表し、10月3日下院の再審議でようやく可決された。さらに銀行に直接投資できるようにウォーレン・バフェットのアイデアを取り入れて修正し10月13日午後3時に再びCEO達を招集した。とにかく各銀行に先ず資金援助を受け入れてもらう、そうしておかないとTARPを利用する銀行は危ないと狙われるためだ。午後6時23分までに各CEOは電話での取締役会を開きこの案を受け入れた。TARPの準備金は7000億$(70兆円)。2008年9月24日に成立した麻生内閣の景気対策が75兆円、09年度の当初一般会計予算が88.5兆円だ。
のちにポールソンはリーマンを救済しなかった理由を定期的に修正している。最初は警告のため、そして後にはその権限がなかったと。それでもバークレイズをつなぎ止める手は残っていたしモラル・ハザードがなくなったわけでもない。このように批判される部分はあるにせ��よくこれだけの手を打ったものだ。ブッシュ大統領が全く金融システムを理解しておらず、ポールソン、ガイトナー、バーナンキ達に丸投げだったことは幸運だったのかもしれない。麻生政権の景気対策も使い道はともかく非常時の対策としてはもっと評価されるべきなのだろう。鳩山内閣のぐだぐだ進行が1年前に始まっていればと考えるとちょっと怖い。
投稿元:
レビューを見る
リーマン、AIG破綻に至るには多くの利害関係者の欲望、保身、プライド、合理的な判断とそうではないもの等が様々絡み合っていることが良く描かれている。血なまぐさいに人間ドラマの帰結。
投稿元:
レビューを見る
「よくここ迄詳細に人物の発言や会議内の様子を含めて調べきれたな」というのが素直な感想。
話は、ベアスタンズ合併後のリーマンが破綻に向かう一部始終、その後市場は更に下がり続け、モルガンスタンレー、ゴールドマン・サックスにまで経営危機が及んでいく。
まさにリーマン・ショックの裏側。当時の実在のトップ投資銀行のCEOたちや財務省連銀の役員たちが史上最大の金融危機に対し、どのような行動を取っていなのかが詳細に記してあり、読み応えがあった。
金融危機のさなかのせいか、投資銀行が自社の保有資産価値を全然把握できていないのは何とも間抜けであり、適切な対策を施したとしも、市場は違う反応を示せば結局は危機を脱しないのはなんとも無力だなってという感じがした。また、困ったときはバフェットに支援を頼むことが多いのでやはり信頼が厚いんだなと思った。
また、モルガン・スタンレーと三菱からの支援を受ける話が出た時に、ポールソンが「日本の銀行は行動が遅く、何も決めれられない。よってその話は信用出来ない」と却下されたのが、まあ一般的な日本の企業に対する印象なのかなと何とも悲しくなった。
登場人物が多く、全部英語名なので混乱しそうになるが、親切にも巻末に人物表が載っているので、助けになる。
投稿元:
レビューを見る
リーマン・ブラザース、AIG、モルガン・スタンレー、そしてゴールドマン・サックスと立て続けに押し寄せる危機の波の中で、なんとか時間を稼いで、資金調達や担保を探して...と金融危機の中で必死にもがく様が伝わって来る。上巻は今一つだったが、下巻がスピード感もあって面白い。
投稿元:
レビューを見る
最初にエピローグを読めばよかった。登場人物が多いので、全体像把握してから読むべきであった。それにしても、リーマンショックと言えば、日本でも仕事面・生活面でも身の回りで影響があったように記憶しているが、アメリカ本土ではリーマンだけでなく大手金融機関が軒並み大変になっていたことは恥ずかしながら知らなかった。エピローグに簡潔にまとめられている。
「わからない、まったく」ポールソンは疲れた声で言った。頭のなかはまだリーマン・ブラザーズとメリルリンチの運命のことでいっぱいだというのに、AIGのための解決策も考えなければならないのか?
ミラーは一刻も早く会社を売却する方法を探っていた。この業界は取引先の信頼や信用で成り立っている。リーマンは単独で運営されている時間が長引くほど価値を失っていく。
マックは言った。「わが社はクリーンだ。利益も出ている。過去八日間でさえ大幅な利益をあげている。しかし、そんなことはなんの慰めにもならない。今日の市場では、実際の業績よりも財務に関するデマ、噂、中傷のほうがはるかに影響力を持つ」
ペック判事は、一世紀以上の歴史を持つ企業に残されたものを救うことの重大さに心を震わせながら、バークレイズとの取引を承認した。
「ミスター・ミラーに圧力をかけられたから、承認したのではありません」判事は説明した。
「これが考えられるなかで最適な取引だとわかっているから、承認するのでもありません。私がこの取引を認めなければならないのは、これが唯一残されている取引だからです」
以下、エピローグより
たった数カ月のあいだに、ウォール街とグローバル金融システムは、すっかり様変わりした。かつての五大投資銀行は、それぞれ破産したり、身売りしたり、銀行持株会社に変わったりした。住宅ローン二大企業と、世界最大の保険会社が政府の管理下に置かれた。そして10月初めには、大統領のペンが動き、財務省―ひいてはアメリカの納税者が―かつて国の誇りだった金融機関の一部を所有することになった。ほんの数カ月前には、想定することすらむずかしかった救済策だった。
ゴールドマンの成功に関する真の疑問は―ほかの会社にも言えるが―次のようなことだ。政府と納税者が、少なくとも暗黙のうちに彼らのビジネスを保証している場合、莫大な利益を生み出すリスク負担に規制当局はどう対応すべきか。実際、2009年下半期におけるゴールドマンの想定最大損失額は、どの日をとっても史上最高の2億4500万ドルに達していた(前年の数字は1億8400万ドル)。ゴールドマンのビジネスはこれまでのところ好調だが、これがまちがった方向へ進んでいたら、どうなっていたのか。好むと好まざるとにかかわらず、ゴールドマンは、国内最大級のほかの金融機関と同様、大きすぎてつぶせないまま残っている。
たしかに、もし政府が何もせず、破産申請をする金融の巨人たちのパレードを眺めていたとしたら、実際よりはるかにひどい市場の大変動が起きたことだろう。一方で、連邦政府の官僚―ポールソンやバーナンキやガイトナーたち―の一貫性のない決断が、市場の混乱になったことは否めない。ベア・スターンズにはセイフティネットを提供し、ファニーとフレディも救い、リーマンは破産させておいて、結局あとでAIGを救済した。定型はあるのだろうか。規則は何なのか。何かあるようには思えず、投資家が混乱したとき―この会社は救済されるのか、そのまま破綻させられるのか、それとも国有化されるのか―当然ながらパニックが生じた。
救済措置の後、まださまざまな議論が噴出していたころに、ジェイミー・ダイモンがヘンリー・ポールソンに短い手紙を送った。セオドア・ルーズベルト大統領が、1910年4月にソルボンヌ大学でおこなった”共和国における市民権について”という演説を引用したもので、次のような内容だった。
重要なのは批評家ではない―力ある者がどうつまずいたか、偉業をなしとげた人間がどこでもっとうまくやれたかを指摘する人間ではない。名声は、現に競技場に立つ男のものだ。果敢に闘い、判断を誤って、何度も何度もあと一歩という結末に終わり―なぜなら、まちがいも欠点もない努力など存在しないから―顔はほこりと汗と血にまみれている。しかしその男は、真の熱意、真の献身を知っており、価値ある理念のために全力を尽くす。結果、うまくいえば優れた業績という勝利を得る。しかし、万一失敗に終わっても、それは少なくとも雄々しく挑戦したうえでの失敗である。だから彼の立場が、薄情で臆病な、勝利も敗北も知らない者たちと同じになることはありえない。
投稿元:
レビューを見る
Too Big To Fail
リーマンショックの最中は学生ということで、さわりしか知らなかったけど、勉強になった。三菱の小切手のくだりには痺れた。
この本に出てくるCEOの中に未だ現役がいるというのもなかなか感慨深い。
投稿元:
レビューを見る
一般人には知り得ない舞台裏が丹念に描かれていておもしろい。あの頃のジェットコースター相場が思い出されます。