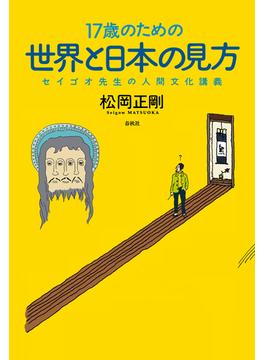電子書籍
17歳のための世界と日本の見方
著者 松岡正剛
ワクワクする世の中の秘密、教えます。世界の文化・宗教・思想をクロニクルにまとめ、日本とのつながりを明らかにする。流れるようにドンドン読める人間と文化の教科書!
17歳のための世界と日本の見方
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
17歳のための世界と日本の見方 セイゴオ先生の人間文化講義
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
「編集」という方法
2009/05/17 20:22
10人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:GTO - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者の専門である編集工学をベースとした方法論を学ぶための本である。帯には「大人は」とあるが、著者があとがきで述べているように、いかなる年齢層が読んでも得るところがある内容である。いやむしろ、17歳ではやや基礎知識が足らず、充分に理解できないとさえ思われる。とは言うものの、大学初年生向けに講義されたものなので、大変に親しみやすい口調(文体)となっている。
「編集」というキーワードを挙げるだけでは分かりにくいと思うので、もう少し私なりの言葉で説明を加えると、この世界がいかに紡がれてきたかの分析であり、我々が現在どのような物語の中で生きているかの講義である。人類の歴史を作ってきた数多くの物語、その物語の中にはどんどんと補強され、現在にいたるも強大な影響力を持っているものもあれば、消えていったあるいは消えつつある物語もある。それぞれの物語がどのような変遷を辿って現在にいたっているかを語ることで、現状のより深い理解を与えてくれる。そして、さらには物語はどのような変遷を辿る傾向があるかを話すことにより、未来を見通す視差を示してくれている。
著者は最後を「今後のサミットや国際会議や企業のミーティングでは、たらこスパゲッティに味噌バター味のポテトが出ることをおおいに期待して」(p.356)と締めくくっている。アメリカ社会を表現する言葉で言えば、「るつぼ」より「サラダボール」のような世界を想起していると思うが、ユダヤ・キリスト・イスラムの一神教が合い並び立つとは考えにくい。それでも、一神教かた多神多仏まで、人類全体を包み込む新たなる物語の創設(編集)が可能なのだろうか。人類はそこまで進化しているのだろうか。アーサー.C.クラークの『幼年期の終わり』が頭に浮かんだ。
紙の本
冷静に日本と世界を見ると。
2020/09/24 14:26
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:タオミチル - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、かつて著者の松岡氏が大阪の帝塚山学院大学・人間文化学部にて教鞭をとり、その際の1年生用予備講義を書籍化したものなのだとか。
世界の歴史に登場した「人間文化」...どうしても話題の中心は「宗教」などの話になるが、それらを今まで誰もしなかったようなクールな視点で切り口を設定し、整理してみせた。松岡正剛流の歴史編集とでも言ったらいいか。
ざっと読んでしまったが、ノートをとりながら再読したい感じで、さらに、この内容を概論代わりに、枝葉を広げて勉強したいとも思った。
各講座の詳細テーマはそれぞれ、1.人間と文化の大事な関係 2.物語のしくみ・宗教のしくみ 3.キリスト教の神の謎 4.日本について考えてみよう 5.ヨーロッパと日本をつなげる...となるが、「私は日本人」と思うあなたなら、とりあえず「4.日本について考えてみよう」だけでも読んでみよう!ともかく面白い!
紙の本
学力テストの数字だけが文化じゃあない
2008/09/21 22:40
8人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:栗山光司 - この投稿者のレビュー一覧を見る
博覧強記で蘊蓄の人と言えば、松岡正剛大先生でしょう。まあ、なかには異論の人もありますが、僕なんか同年なのに、あまりにも文化的リソースの広さ、深さにいつも感嘆してしまう。そんなセイゴオ先生が17歳の少年・少女のために「人間文化講義」を紙上で行うとなると、ジジィなのに気になって店頭で衝動買いしてしまった。
講義は第一講:人間と文化の大事な関係、第二講:物語のしくみ・宗教のしくみ、第三講:キリスト教の神の謎、第四講:日本について考えてみよう、第五講:ヨーロッパと日本をつなげるで、原テキストは大阪の帝塚山学院大学で一年生向けに行った「人間と文化」という講義録から、増補改訂して新たに著者のイラストレーションを加えたもの。
17歳の大学生っていないんじゃあないかと思うけれど、17歳というのは大学生に話す以前に高校生にこそ話しかけたかったという思いをこめてであって、特に年齢にこだわったわけではないとあとがきに書いているから、僕のような「ジジィ買い」でも問題ない。
世界と日本はどうつながっているのか、此岸と彼岸、マクロとミクロの連関、あいだ、歴史を横断し、縦横無尽に大きな問題を取り上げながら、入り口となる出来事、人、ものなど網羅的にキーワードを配して的確な考えるヒントを与えてくれる。
後は読者がそれぞれの思考の流れによって、原典にあたり自分なりの世界観を身につけるということでしょう。そんな思考のマッピングとして最適なものだと思う。
僕も、かような本に40年ぐらい前に巡り逢っていたら少しはましな大人になっていたかもしれない。せめて、少年・少女に本書を贈呈したいと思っているが、子ども達に本をプレゼントして読んでもらうなんて、これほど難しいことはない。
本書は結構店頭では売れているみたいだけど、実際に購入した人は僕のような高齢者ではないかと、そんな穿った見方をしています。「孫のために」と手に取ったんではないかと思ってしまう。
だって、本書に書かれていることに子ども達のセンサーが感応したら年寄り達はうるうるするにちがいない。こんな語りがあります。
《では、「もののあはれ」の「もの」ってなんだかわかりますか。/もともと日本では「もの」という言葉に、二つの意味をこめていたんです。ひとつは「物」という意味。もうひとつは「霊的なもの」という意味。スピリットのことも「もの」と呼んでいたんです。「霊」という字も「もの」と読みました。「ものあはれ」の「もの」がまさにそれだったんですね。「ものすごい」「ものがなしい」「ものさびしい」とか、関西弁で「ものごっつう」とかいうときの「もの」もそうです。/古代の日本では、目に見えないけれどもこういった霊的なるものが、巷にあふれ飛び交っていると信じられていたんですね。何かをふいに思いついたり、誰かから音信が届いたりするときには、このような「もの」がそこに媒体しているのだと考えられていた。魂や心にくっついていると感じられていたんです。「ものおと」というのも、たんなる物の音ではなく、そういう気配の音のことなんです。/そういった「もの」の気配を感じていきながら、「もの」を語る、あるいは「もの」になりかわって出来事を語っていくことを、「もの・かたり」=「物語」と言った。だから当時の物語を読むときは、「もの」にひそむ意味を大事にしたほうがいいわけです。(p234)》
僕のような年寄りはこういう文章に接すると、そうか、「フィギュア萌え」の萌えは「もの」としての「霊」ではないかと思ったりするが、若者たちは萌えから、『源氏物語』、『古事記』にリンクすることはないのであろうか。
玩物喪志っていう言葉があるが、そもそも大きな物語=志が不在な時代にあっては、せめてフェチ萌えでも、萌えであるかぎり、霊的なものにつながり、世界につながって、それなりに「生きる力」になればいいかなぁとは思う。
本書で言及している定家の《見渡せば花ももみじもなかりけり 浦の苫屋の秋の夕暮れ》の歌に萌える力が多分、文化の力だと思うし、数値化できない学力だと思う。教育は見えるものではなく、見えないものにアクセス力をつけることでもあると思う。本書はそのような気づきになる啓蒙の書である。単に数値化された学力に偏すれば国を滅ぼす。それこそ、玩物喪志っていうことでしょう。
葉っぱの歩行と記憶