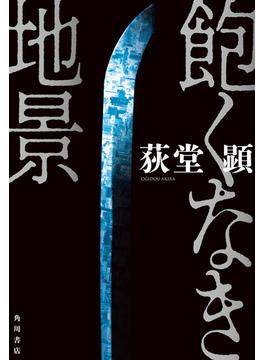じゃない人の物語。
2025/02/09 12:01
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:はぐらうり - この投稿者のレビュー一覧を見る
『不夜島』以来の荻堂さん。直木賞次点といわれている作品。
一般的には恵まれている人生にもかかわらず、思うようにことが運んでおらず、報われないなぁと思いつつ、この人にも責任の一端があるような気がする。生涯主役になることがなかったしそう描かれない人の話って、意外と珍しいのではないか。
面影橋や関口パンなど自分にとって懐かしい固有名詞も多く、親近感を持って読んだ。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:hid - この投稿者のレビュー一覧を見る
他に直木賞候補にふさわしい作品はあったよね。
本屋大賞にはノミネートもされてないわけで。
選考委員の感性だから仕方ないか。
投稿元:
レビューを見る
家宝の刀と反目し合う元華族家内の軋轢、烏丸治道は刀と父親の建設会社での都市開発への反発。
長い話を目一杯に書き綴ってはいるのだが、元華族様たち上流階級のいざこざが延々と続き読み続けていくのが辛かった。
端的に言えば、努力は認めるが面白く無い小説だった。
投稿元:
レビューを見る
序盤に主人公烏丸治道が、父が無法組長に一族の守り神でもある粟田口久国の「無銘」を渡したと知って、物騒な方法で奪い返そうとした物語を読み、このあとが読み切れるだろうかと不安になりました。
その後治道も社会人となり、父親の会社に入社して時代に即した生き方をしていく様子が描かれると、今度はこの作品のテーマが見えなくなりました。
あらすじにある「刀に隠された一族の秘密と愛憎を描く美と血のノワール」とは一人のマラソンランナーや、治道の異母兄と刀との関係でもあり、主人公との苦悩を描いているようでもあり、とふらふらしつつ読み終えました。
私にとって著者の作品は初。出会いは大切です。今回は可もなく不可もなくといったところでした
投稿元:
レビューを見る
とにかく面白かったです。
改行の少なさ?から、文字が多く感じて冒頭読みにくいかなと思いましたが、
物語が始まると引き込まれていきドキドキしながらあっという間に読了しました、
表現が的確かつ文体も美しいので、こんな風に捉える事ができる才能に羨ましく感じました。
投稿元:
レビューを見る
第172回直木賞候補作。
戦後まもない時期から平成の末期まで、長い時間を舞台にしたゼネコン社長一族の歴史をつづった物語です。
主人公の御曹司は、父がつくった異母兄との確執や、母をないがしろにする父への怒り、自分の審美眼を養ってくれた祖父への敬愛など様々な心情に振り回されながら生きてゆきます。
早稲田大学が舞台で、私自身が在学中に通っていた(そしてまだ現存している)店が出てくるのは懐かしく感じましたし、当時の早稲田生の息遣いを感じることができました。
社会人となってからの、東京オリンピック(1964年)をめぐる主人公の活躍などは手に汗を握るような部分もありましたが、直木賞候補作としては主人公の内省や葛藤、自己分析に描写が多く割かれていて、すこし読みづらさを感じる部分もありました。
投稿元:
レビューを見る
172回直木賞候補 R6
戦後史×刀剣×都市開発
結局、意味わかんねーって本
自分には合わない作風で、義務的に読了
投稿元:
レビューを見る
直木賞候補作ということで読んでみました。
今年は昭和100年。
(ここでこの内容をぶつけてきたか~)
出版社の戦略がちらつきます。
今、私の手元にある帯にはこのように書かれています。
”僕は憎んだ
父が築く東京の景色を”
この一文を読んだときに、スターウォーズ的なストーリー(息子が父を倒す話)を想像したのですが、読んでみると、そこまでではない感じでした。
主人公・浩道のぼんくらっぷりがずっと続いていく感じだったなぁ。
恵まれた環境でぬくぬくと育ってきた感じが、どこまでも続いていく・・・。
彼には欲望ってものはないのか?
私が読む限り、感じなかった・・・。
彼自らが動いて、何かを成すということがないのですよ。
むしろ、彼の兄貴(腹違いの)・直生の方が、欲望だの野望だのギラギラとしたものが前面に出ていて、ここまで欲望丸出しだとすがすがしささえ、感じられました。
(帯の内容から兄貴寄りの話かと思っていたのだが)
それは置いておいて、昭和生まれ(後半ね)の私は、昭和の懐かしさを感じることもできました。
ゼネコン業界の裏側が赤裸々に描かれている点が興味深かったです。
「大型案件の受注の仕方」
「土地買収のリアル」
「ゴシップの収束方法」
どれも想像できそうな内容ではあるけれど、文章としてリアルに突きつけられると妙に生々しい。
企業がスポーツ選手のスポンサーになるメリットや、そのための社内稟議の通し方なんかも書かれていて、「企業って、こうやって裏で動いているんだな…」としみじみさせられました。
スポーツ選手が企業からのプレッシャーを受けながらも、命がけで戦っている姿も描かれています。
「好きなことを仕事にするって、綺麗事だけじゃない」
大人になるって、こういうことだよな…と実感せざるを得ませんでした。
大人になってやりたい事をやり続けるためには、子どものように無邪気なままではいられないのが実情なのでしょう。
個人的に驚いたのは、途中出てくる刀のストーリー。
「え?これどうつながるの?」と思っていたら、最後に見事に回収されて、思わず唸りました。
全体を通して、「昭和という時代の空気」と「ゼネコンという世界」が巧妙に描かれた読み応えのある一冊でした。
「あの頃の日本」「バブルの残り香」を感じながら、昭和100年を迎えた今、もう一度「父と子」「企業と個人」というテーマについて考えさせられる、そんな物語でした。
投稿元:
レビューを見る
モヤモヤするなぁ。どうにも芯のない治道が、粟田口久国の無銘一振を介して真に背筋の伸びた男へと変じるのを期待していた。その妨げとなるのか救いとなるのか、愚連隊の藤永はどちらかの役割を担うと思いきや知らぬ間に撲殺された。マラソンランナー高橋も、円谷さんをモデルにしただけでなんだったんだろう?無二の親友である重森にせよ、おとぼけながら味のある上司の多部さんにせよ、蠱惑的であそこまで進展した飯嶋さんにせよ、誰も彼も関係が深まらない。そして烏丸家の面々のいずれもが、年取って衰えるだけで人として成長しないのが悲しい。
投稿元:
レビューを見る
●読前#飽くなき地景
第172回直木賞候補作なので、なにはともあれ読む。読んだことない作家さんなので相性いいかはわからないが、芥川賞候補作でないのと、現実的なストーリー性がありそうな内容なので、その点では多少不安感が薄められる
https://mnkt.jp/blogm/b241002b/
●読後#飽くなき地景
読み始めは引き込まれることもなく、ページ数も多いので途中断念かと思われた。しかし、こらえて読み進めたら、気持ちを高揚させられるほどではなかったが徐々に面白さを感じて読了できた。結果的には、僕には可も不可もない一冊
https://mnkt.jp/blogm/b241002b/
投稿元:
レビューを見る
第172回直木賞候補作。無銘の刀ひとふりと、主人公の一代記のような感じ。帯の「戦後史✕刀剣✕都市開発」という言葉の通り、でも、息苦しく重苦しく、切ない話だった。
投稿元:
レビューを見る
不動産やビルといった都市開発事業を営む一族の中で、祖父が残した刀に尋常ではない執着をみせる主人公の葛藤と愛憎、そして刀をめぐる事件などが昭和の長いスパンの中で描かれており、一種の大河小説のような趣のある作品になっている。
が、結論から書いてしまうと私の苦手なタイプの小説で、文章そのものがダメというわけではないんだけど、読者が場面や風景を自由に想像する余地を与えないほど地の文で細かく書き込まれているので、書かれたままをただ頭の中でリフレインするだけの読書になってしまい、読み終えるのにかなり時間がかかり、疲れた。
舞台の大半は昭和なんだけど、文章も同様で完全に一昔前のもの。これは当時の空気をそのまま描きたかったという著者の意向らしいんだけど、私のようにその知識が無い状態で読んじゃったりすると、令和の時代にここまで押しつけまがしい話ってどうなの、といった感じでかなり困惑したというのが正直なところ。
これで登場人物が魅力的であればまだ救われたんだけど、主人公は刀に対する執着以外はパッとしないし、周囲の人物造詣も想像の域を出ないかなあ。
帯に「美と血のノワール」ってあるけど、そもそもノワールってこういうものなんだっけ?という点も疑問が残る。
それでも美点を挙げるとすれば、前述した主人公の刀に対する執着が全く論理的でない点で、これは現代日本で保守や平和主義者を自称している言論人や政治家たちの精神性と完全にオーバーラップして読めたので、そのあたりは結構面白かった。
なんだかんだ筆力はある作者だとは思うけど、今回は相性が悪かったようで。次作に期待します。
投稿元:
レビューを見る
昭和の高度経済成長期から世紀末あたりまでの世の中の価値観/空気感みたいなものが込められていることはわかるし、先が知りたくなるストーリー展開でなんとか読了することができましたが、直木賞候補作な”ワクワク感”に乏しいところがなんとも言えず。。
実在の政治家がいっぱい出てくる割には、円谷幸吉を”モデル”にしたと思われる五輪マラソンランナーをやっぱり自決させてしまったり、とちょっとちぐはぐな感じも。
文字も多いし、やや読みにくい箇所もあるので、その分、読了の達成感はアリ!
投稿元:
レビューを見る
天邪鬼かな。
ページの割に文の多い本で読むのが大変でした。
読む限り、兄を嫌っていたと書いていますがそれ程嫌っているように感じられなかった、読みきれなかった。
父を軽蔑していながら、父に愛されているところを読むとそんなに嫌ってないじゃん、って思ったり。
天邪鬼なのかなって思いました。
重森さんが一番辛かったね。
投稿元:
レビューを見る
1944年~2002年間、時代と共に移り変わる大都市東京と人を描く。膨大な資料を読み込み、当時の象徴を物語に融合させる著者の技量に唸る。戦後の復興、旧華族の没落、骨肉の争い、親子の愛憎…急所満載。第172回直木賞候補作。