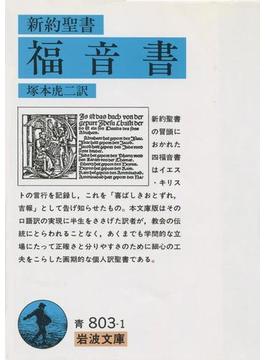0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:藤和 - この投稿者のレビュー一覧を見る
新約聖書の中の福音書だけを抜き出して日本語訳したもの。
訳自体はだいぶ古いものみたいだけれども、そこまで読みにくい訳ではない。
福音書ははじめて読んだけれども、手を変え品を変え同じようなことを言っていたんだなという感じ。
微妙に内容が違ったりするので、その差を比べてみるのもいいかもしれない。
逐語訳と意訳の間みたいな翻訳
2023/12/31 21:56
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オタク。 - この投稿者のレビュー一覧を見る
本文を敷衍した個所を小さな活字で本文に組み込まれているが括弧付けしてくれなかっただろうか。リビングバイブルや現代訳聖書といったバンバン意訳した翻訳のような文体にした方がかえって読みやすかったかもしれない。
マルコ伝が最初に執筆されたという通説に従ってマルコ伝がマタイ伝より先に収録されたりナザレのイエスの発言に「アーメン」を取り入れた福音書の日本語の翻訳はこれが初めて?
新教出版社が塚本虎二訳新約聖書を出していたが絶版のようなので岩波文庫に移籍しないだろうか?
キリストは神なのか
2023/09/25 22:01
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:伊達直人 - この投稿者のレビュー一覧を見る
パンと魚 パンを三つ 魚を二つ
5000人の前に分け与える
それは 真実か虚構か本当に分け与えたら
くず しかいきわたらない どのようにこの
状況をとらえるのか 神は 等しく分け与えたまい
みな満足している
そのような 教えが いくつも書かれている
神は本当に奇跡を呼び起こすのか
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:中堅 - この投稿者のレビュー一覧を見る
キリスト教徒でない人間が、聖書やそれに類する本を読む場合を
想像してみると、下の4つが考えられる。
(1).衒学的な、それなりに強い関心(自負心?)がある場合
(とりあえず新約聖書は押さえておくか、といったような)
(2).宗教社会学的な関心がある場合
(キリスト教徒は一体何をそんなに拝んでいるのだろうか?)
(3).単純に物語的な観点から読む場合
(イエス-キリストの話って、外国の本で良く出てくるけど、
どんな物語なんだろう?)
(4).何かしらの実存的な危機意識を持っている場合
(悩みを抱えている人。前-キリスト教徒?)
書評を書き始めてまず「読者像」を考えてみたら、私自身の心理を解剖したのが、上記(1)(2)(3)(4)になっただけ、ということがはっきりしました(苦笑)。独断的読者像の分類に従って、この本の読者の反応を予想すると、単純に(1)(2)の動機の人には、「知的満足」が得られるだろうし(当たり前ですが)、bk1の書評ポータルのにぎわいからして、手法を凝らした小説が量産されている今日の読者が、(3)の単純に物語的な観点から読むと、多分、がっかりすることが予測されます。当然ですが、「読者を楽しませてやろう」という考えが書き手にはないので。
(4)の動機の人は、特にアナウンスがなくても、読み込んでいくことが想像できます。現状に満足している人間は、骨を折って、こんな本に挑もう、という気は起こしませんから。
(以下雑感)
変に先入観をもっている人がいるかもしれませんが、ニーチェのような道を行った人もいるぐらいなので、福音書を読むこととキリスト教徒になることは全然違う、ということはあらかじめ言っておきます。それと、宗教をもつ人間に対する無宗教者の優越感は戦争を知らないことを誇る子供と同じぐらい無意味だと思います。まぁ逆の場合も然りですが。
・戒律を守ることに汲汲とし、神とのつながりを忘れ/俗化させる祭祀たちの宮殿に現れ、「羊も牛も宮殿から追い出し」「両替屋の」「その台をひっくり返」すイエスは、「誰かが右の頬を打ったら、左の頬を差し出せ」というだけの、唾棄すべき敗残者ではない、ことが明らかです。ルサンチマンでは無いでしょうが、「反逆」、「怒り」、そういうパトスも持ち合わせているようです(特にマタイ)。
・永遠の命を得たい金持ちの青年に対して、イエスは財産を売り貧乏な人に施すようにいう。もともと現実の資本主義社会と相容れるはずのないイエスの思想が示されているように思えて興味深かったです。
・イエスのする例え話もいろいろとありますが、放蕩息子の帰郷する話が一番実感があり、面白かったです。
イメージと福音書内のイエスの姿のギャップに気づくだけでも、意味のある読書になるのではないでしょうか。
------
この岩波文庫の聖書以外にも、新共同訳の新約聖書があります。
そちらが定番とも思えますが、入手が簡単なこちらをまず、お勧めします。
新共同訳の方には、「手紙」「詩篇」も載っているので興味があればどうぞ……。
投稿元:
レビューを見る
ヨーロッパに住むとキリスト教文化と付き合わないわけには行かない。彼等の生活と文化は多かれ少なかれ聖書と結びついてしまう。ヨーロッパ居住予定の人には一読をお勧めする。
投稿元:
レビューを見る
聖書は無料でもらったりもするんですがこれが一番理解しやすい。信仰心とかそんなのは残念ながら無いけど純粋に興味はあるって方には読みやすいのでおすすめ。
訳によって印象がだいぶ違うので、本格的に学ぶ方はこれ以外も読んだほうがいいです。私はこれで十分。
投稿元:
レビューを見る
福音書。
新約聖書中にある4つの福音書。
多くは日本聖書教会発行の、新共同訳という訳のものが聖書のメインとなっている。
しかし、これは「個人」が訳した福音書なのである。
また、訳の仕方…というか表記の仕方が独特で、適時解釈を読みやすいように、流れが切れないように挿入し、より親しみやすいように試みが行われている。
また、新約聖書の解説などの付録もよい。
これと、新共同訳の聖書を合わせて読むと奥が深くなるかも。
ただ…イエスが話すたとえ話とか意味がわからないものがある(それはこの本に限らず)ので、聖書は勉強書が必要だなぁと思っている。
投稿元:
レビューを見る
「パンセ」を読んでいて、やたらと聖書の引用が多いのに驚き、読んでみたくなったので購入しました。いままで本格的に読んだことが無かったので、普通の聖書は高いということもあり岩波文庫版を取りましたが、なかなか読みやすいものでした。
イエスの足跡をもっとも簡潔に記したマルコ伝、それをさらに詳細に描いたマタイ伝とルカ伝、前3書とは違う角度から、神の言葉の代弁者としてのイエスを描くヨハネ伝。4つから構成される福音書にはそれぞれに特徴があります。私が思うところ、マルコ伝はイエスの人間からの超越性、マタイ伝は12使徒を導くイエスの姿、ルカ伝は病者や弱者に手を差し伸べる姿、そしてヨハネ伝はイエスの抱く世界観や神と人間との関係性が、それぞれ記されていると捉えたのですが、こんな一面的な理解で合っているでしょうか。
その中で私が興味深いと感じたのは後半の2書です。ルカ伝はイエスの譬え話やエピソードがとても感性豊かに書かれており、よく構成された1人の男性の伝記を読んでいるかのようです。「善きサマリア人の話」や「刑場まで運ばれるイエス」「十字架上での2人の泥棒との会話」など、巷に流布する聖書のエピソードがもっとも多くあり、それだけ親しみやすいものであることが容易に想像できました。弱者への施しは「神の国」に自分が入るために必要なことと説く教説は、なにやら「情けは人のためならず」という諺を連想させますが、「神」こそが唯一の価値であるとする立場を端的に表しているようで、そこに一神教の強みと弱みとの両方が内包されているように思えます。
他方、ヨハネ伝では、自らを神の子だとするイエスと、ユダヤ教の律法学者やバリサイ派の人々との討論が中心内容となります。高度に教義理論化されたその内容は、教会専門家向けのもののように感じられました。ただし、両者の主張はどこまでも平行線です。それどころか、イエスを律法違反だと糾弾するバリサイ派と、彼らが引き合いに出す旧約聖書に書かれた神こそ自らの父だとするイエスとの間には、そもそも議論が成り立ってすらいません。第三者的立場で読んでいる私には、ただ互いに互いへの不信を増幅させるだけの不毛なものに映り、暗澹たる気持ちになりました。自分の内側で起こる宗教体験を他者と共有することは、世間が考えているよりもはるかに困難だということでしょうか。他人の主観を自分の主観で捉えることができない以上、それは当然の帰結だといえます。
長々と感想を書いてきましたが、そもそも回心するつもりもなく、且つ興味本位だけで一宗教の経典を読むことは、禁忌とは言えなくてもあまり褒められたことでないという感覚が離れません。とはいえ、私の読書経験上、本書は貴重なものになりました。アウグスティヌスやトマス・アクィナスなどに興味を持ち始めたいまは、よい予備知識になったと思います。
(2008年8月 読了)
投稿元:
レビューを見る
塚本虎二による口語訳の福音書。日頃は新共同訳で触れていたが、これはこれでとても読みやすくてよかった。史的イエスの勉強をしていると、日本語訳の聖書はどれも意訳、解訳が多くて参考にならないと口をそろえて言われていますが、それをふまえたうえで読んでいると新しいことにもたくさん気づけます。巻末でそれぞれの福音書に対する説明や共感福音書について触れていて、それも参考になるし、各福音書の対応している事件には共通箇所の章節が記されているのがとてもわかりやすかったです。内村鑑三に師事した著者が晩年の30年以上をかけて新約聖書の口語訳をなしました。その偉業の一部。巻末にその当時の決心がうかがえるあとがきがあるのもグッド。
09/5/11
投稿元:
レビューを見る
私はキリスト教徒ではないが、マタイ伝が好きで複数回読んでいます。イエスの言葉は強く、弾丸のようです。ラビへの非難はとても厳しい。それは将来大教団となって本質を見失ってゆくであろう人々への極めて強い非難にも思えます。近親憎悪のような憎しみ、宗教の原則、愛情、教団の堕落、現世との対立、論争・・・。現代においても、古くならない本質的な問題に溢れています。
投稿元:
レビューを見る
いわゆる新約聖書の福音書。
聖書には、福音書の他にも旧約聖書や黙示録・~への手紙などがあるが、現在のキリスト教の基本は福音書であす。
この福音書では、キリストが生まれてから死ぬまでを4人の人が語っている。それぞれ微妙に異なっていて面白いです。
口語訳でとてもわかりやすく書かれており、キリストの教えが一番よくわかる。
私は、キリスト教徒ではないが、キリスト教の良い部分を積極的に取り入れるため読んでいる。
精神的に安定した生活を送るために学ぶことが多いです。
投稿元:
レビューを見る
何はともあれ、兎にも角にも、読 み 終 わ っ た !
私、がんばった!
「何を、何故信じるのか?」が知りたくてここまで読んできました。
…やっぱり、分かんなかった。
予備知識ナシ、テキストのみ、ではやっぱり無謀だったか…。
歴史等含めた解説書を読みつつ、再トライ決定。
ひとつ、分かったコト。
私は、クリスチャンにはなれない。
投稿元:
レビューを見る
全てを読み終えてはいないのですが「マタイ伝」に感銘を受けました。
弟子の裏切りが展開されていく辺りは人間の業みたいなものを表していて怖いです。
投稿元:
レビューを見る
「異教徒のために祈る」って凄いことですよね。すばらしい教義です。「自分や家族のために祈ることは異教徒にもできる。」確かに。
マルコ伝あたりは本当にあったことなんだろうなあ、という気がします。超能力持ってる人はいますし。
投稿元:
レビューを見る
(2014.10.10読了)(2014.10.02借入)
新約聖書の入門書やキリストの伝記的なものは、何冊か読んだのですが、『新約聖書』そのものは、読んだことがありませんでした。『聖書』が手元にないわけではないのですが、分厚いし、読みにくいので、岩波文庫版を借りてきました。借りると、返却期限までに読まないといけないというメリットもあるし。
四つの福音書が収録されています。イエス・キリストの生涯と事績・教えという感じのものです。似たようなことが書いてあるので、ひとつにまとめてもいいようなものですが、まとめずに残したのですね。
マルコの福音書は、洗礼者ヨハネが、イエスに洗礼を授ける話から始まります。受胎告知やらキリスト生誕やらの話はありません。
マタイの福音書は、イエスの母・マリアの夫ヨセフの祖先の系図から始まります。最初は、アブラハムだったようです。系図の途中にダビデやソロモンが登場します。
不思議なのは、イエスは、マリアの子ではあっても、ヨセフの血は受け継いでいないのだから、ヨセフの系図を述べてもあまり意味がなさそうなことです。
マリアに対する受胎告知の話はありません。キリストの誕生、四博士の礼拝、エジプト逃避、のあとは、ヨハネによる洗礼と続きます。
ルカの福音書は、「はしがき」があり、「イエス・キリストの福音の発端から、それがローマにまで伸びていいったことの顛末を」「一切の事の次第を始めから精密に取り調べ」テオピロ閣下に報告するといっています。
ルカの福音書では、洗礼者ヨハネの誕生のお告げから始まり、イエスの誕生のお告げが続きます。受胎告知の話は、ルカの福音書で初めて出てきます。
エジプト逃避やヘロデ王による幼時虐殺の話はありません。イエス十二歳のときの教師たちとの問答のエピソードは、ルカの福音書に入っています。
洗礼者ヨハネによってイエスが洗礼を受けた話の後にイエスの系図の話が入っていますが、始まりは、神の子アダムになっており途中にノア、アブラハム、ダビデ、が登場します。
系図は、マリアの夫ヨセフまでのものです。
ヨハネの福音書は、マルコの福音書と同様洗礼者ヨハネがイエスに洗礼を授けるところから始まります。
いずれも、イエスが処刑され、三日後に復活を遂げたというところで終わっています。
復活したのなら、そのまま地上に留まって、伝道を続ければよさそうなものなのですが、天上に戻っていった、となっています。
イエスは、死んだのか、復活したのだから、まだ生きているのか。天上へ行ったということは、やはり、死んだということなのか。
【目次】
凡例
本文
マルコ福音書
マタイ福音書
ルカ福音書
ヨハネ福音書
附録
各書の標題
旧約聖書の引用
ネストレとの異同、その他
解説
新約聖書について・共観福音書問題
四福音書の内容と成立
あとがき―翻訳の決心
●体の外から(29頁)
人の体の外から入って、人をけがし得るものは何もない。人から出るものが、人をけがすのである。
すべて外から人の体に入るものは、人をけがし得ないことが解らないのか。心に入らず、腹に入って、便所に出て行くからだ。
人から出るもの、そちらが人をけがす。内から、つまり、人の心からは、邪念が出るからである。
●預言者(33頁)
「世間の人は私のことをなんと言っているか。」
「洗礼者ヨハネ。あるいはエリヤ、あるいは昔の普通の預言者と言う者もあります。」
●夫婦(40頁)
神は彼らを男と女とに造られた。それゆえに人はその父と母とを捨てて、二人は一体となるとモーセは書いている。従って、もはや二人ではない、一体である。だから夫婦は皆神が一つの軛におつなぎになったものである。人間がこれを引き離してはならない。
●掟(50頁)
一、あなたの神なる主を愛せよ
二、隣の人を自分のように愛せよ
●求めよ(86頁)
欲しいものはなんでも天の父上に求めよ、きっと与えられる。探せ、きっと見つかる。戸をたたけ、きっとあけていただける。誰であろうと、求めるものは受け、探す者は見つけ、戸を叩く者は開けていただけるのだから。
●神の国(141頁)
復活の折には、めとることもなく嫁ぐこともなく、ちょうど天の使のようである。
☆関連図書(既読)
「聖書物語」山形孝夫著、岩波ジュニア新書、1982.12.17
「新約聖書入門」三浦綾子著、光文社文庫、1984.11.20
「イエス・キリストの生涯」三浦綾子著、講談社文庫、1987.11.15
「新約聖書を知っていますか」阿刀田高著、新潮文庫、1996.12.01
「ナツェラットの男」山浦玄嗣著、ぷねうま舎、2013.07.24
「死海のほとり」遠藤周作著、新潮社、1973.06.25
「イエスの生涯」遠藤周作著、新潮社、1973.10.15
「キリストの誕生」遠藤周作著、新潮社、1978.09.25
「イエスの生涯」モーリヤック著・杉捷夫薬、新潮文庫、1952.10.
「神の旅人」森本哲郎著、新潮社、1988.05.20
「サロメ」ワイルド著・福田恒存訳、岩波文庫、1959.01.05
(2014年10月13日・記)
(「BOOK」データベースより)amazon
新約聖書の冒頭におかれた四福音書はイエス・キリストの言行を記録し、これを「喜ばしきおとずれ、吉報」として告げ知らせたもの。本文庫版はその口語訳の実現に半生をささげた訳者が、教会の伝統にとらわれることなく、あくまでも学問的な立場にたって正確さと分かりやすさのために細心の工夫をこらした画期的な個人訳聖書である。