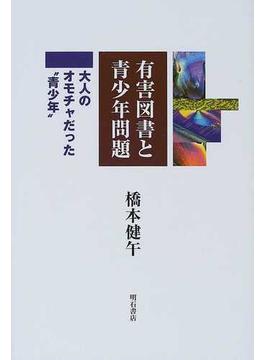「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
青少年にとって本当に「悪書」があるのか、少年非行と出版物の因果関係はあるのか、また規制する側の倫理と運動は純粋か。戦後における青少年の非行の現実と、出版物を中心とした「有害環境」との関連について検証を試みる。【「TRC MARC」の商品解説】
著者紹介
橋本 健午
- 略歴
- 〈橋本健午〉1942年中国生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。作家助手、日本雑誌協会勤務等を経て、現在日本エディタースクール講師、ノンフィクション作家。著書に「バーコードへの挑戦」他。
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
「若者論」の不毛なる歴史
2005/03/02 10:43
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:後藤和智 - この投稿者のレビュー一覧を見る
現在の我が国において、青少年が凶悪犯罪を起こしたり、あるいは何か問題があったりすると、決まってあるメディアを標的にして、「こんなものがあるから犯罪が起こった!」などという論理を振りかざす自称「識者」が現れるのはもはや日常茶飯事である。しかし、そのような論理が、往々にしてメディアの抱える問題の本質を衝くことはほとんどなく、大抵はスケープゴートとして一時的に採り上げられ、そして時間の経過(あるいは次の事件が起こったとき)と共に忘れ去られる。
しかし、我が国において、敗戦直後からたびたび青少年問題が採り上げられて、その「原因」として特定のメディアをスケープゴートにしてしまうような論理がまかり通ってきた、ということを知ったら、皆様はどう思われるだろうか。
本書では、敗戦直後から現在に至るまでの青少年問題と、そのたびに起こってきた出版物規制の歴史をたどりつつ、現在議論されている「有害メディア」規制の不毛さが衝かれている。最初に「有害メディア」規制論が生まれたのは昭和21年、敗戦直後であり、その頃は性風俗雑誌や「低俗な」タブロイド版の新聞が幅を利かせていた時代であった。これらの「有害メディア」への規制を推し進めたGHQは、映画に関しても検閲を行なった。
GHQによる占領政策が終わってから、最初に「悪書追放運動」が加熱したのは昭和30年である。この時期は、中高生の家出や寄り道、あるいは薬物乱用が深刻化していた時期なのだが(ここで紹介されている「東京防犯協会」と「東京母の会連合会」による「“悪への第一歩”」は噴飯ものだ。現在でもこれと同じような内容を語る人はたくさんいるけど)、世の中の母親たちは児童雑誌の「残酷さ」をしきりに槍玉に挙げ、子供たちには悪影響がほとんどないにもかかわらずメディア規制を主張した。「子供」がイデオロギー化されるのは、現在でも変わらない。そして、同じようなメディア規制は、昭和32年、33年、40年、53年、58年、59年、そして平成2年にも繰り返されてきた。「子供」をイデオロギー化したいという「善良な」大人たちの欲望が長く続いてきた証だろう。
また、いつの時代にも青少年の「問題行動」が喧伝されている。凶悪犯罪や窃盗罪(万引き)、及び青少年の売春や妊娠中絶や薬物乱用は、これらの「メディア規制」が盛り上がる時期とほとんど重なって問題視された。また、いわゆる「家庭崩壊」「ひきこもり」「学力低下」なんかも、かなり前から問題視されてきたということが、新聞記事の引用によって明らかにされている。まるで青少年問題をめぐる感情論的な言説(俗流若者論!) から時代が見えるようだ。残念なのは、著者が現在の青少年に向ける視線が「メディア規制」を支える俗流若者論とあまり変わらないことだろう。
さて、現在の我が国はどうか。マスコミに代表されるような「善良な」大人たちは、現在起こっている青少年問題に狼狽することしか知らず、安易なスケープゴート合戦に腐心している。このような「善良な」大人たちの態度こそが問題なのである。青少年問題に関する言説は、その言説とイメージばかりが盛り上がって、当の青少年はほとんど無視、さらには「善良な」大人たちに限りなくイデオロギー化される。しかし、それでいいのか。本書を読んで考えてほしいものだ。
評者のブログはこちら