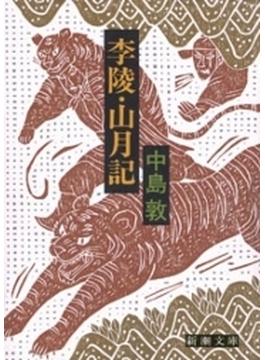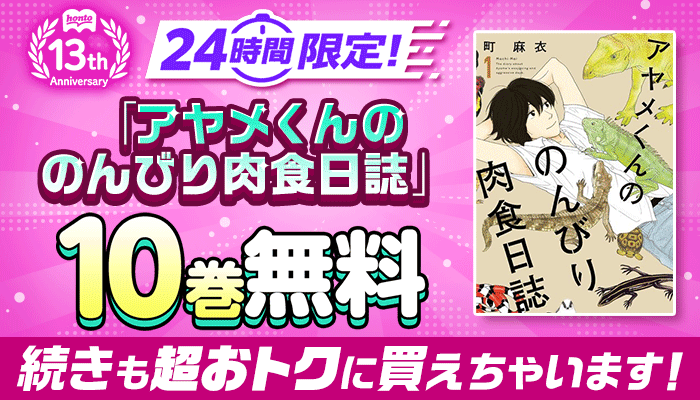- 販売開始日: 2013/06/25
- 出版社: 新潮社
- ISBN:978-4-10-107701-7
李陵・山月記
著者 中島敦 (著)
人はいかなる時に、人を捨てて畜生に成り下がるのか。中国の古典に想を得て、人間の心の深奥を描き出した「山月記」。母国に忠誠を誓う李陵、孤独な文人・司馬遷、不屈の行動人・蘇武...
李陵・山月記
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
人はいかなる時に、人を捨てて畜生に成り下がるのか。中国の古典に想を得て、人間の心の深奥を描き出した「山月記」。母国に忠誠を誓う李陵、孤独な文人・司馬遷、不屈の行動人・蘇武、三者三様の苦難と運命を描く「李陵」など、三十三歳の若さでなくなるまで、わずか二編の中編と十数編の短編しか残さなかった著者の、短かった生を凝縮させたような緊張感がみなぎる名作四編を収める。
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
夭折 ということ
2008/02/21 06:34
11人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:くにたち蟄居日記 - この投稿者のレビュー一覧を見る
中島敦という作家は薄命な方だった。
33歳という没年は 昭和初期の作家の中で飛びぬけて短命であったわけではない。しかし残した作品を読むにつけて「薄命」という言葉が似合うお方だと思わざるを得ない。
本短編集を読むと 中島という作家は本当に剃刀のような方だと思う。似ている作家として思いつくのは芥川龍之介ぐらいだが 切れ味の鋭さと 一種の香気は 中島の方が一枚上ではないかと 芥川ファンの僕にしても 感じざるを得ない。
村上春樹は 芥川の小説は「使っている漢字がビジュアルに美しい」という趣旨の発言をどこかで行っていた。漢文の素養を駆使して 短編を書いた中島にも その言葉はそのまま通用する。例えば 本書に収められた山月記の冒頭を読んで見れば それははっきりしている。
「隴西の李徴は博学才穎、天宝の末年、若くして名を虎榜に連ね、ついで江南尉に補せられたが、性、狷介、自ら恃むところ頗る厚く、賤吏に甘んずるを潔しとしなかった。」
絢爛たる漢字としかいいようがない。
そういう剃刀のような作品を書き上げて 33歳で亡くなったのが中島だ。やはり 剃刀のイメージは「薄命」としか表現できない。
孤立を恐れず、信念に殉ず。
2010/05/26 17:08
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:風紋 - この投稿者のレビュー一覧を見る
収録作品の一、『弟子』の子路は、まず遊侠の徒として登場する。孔丘を似非賢者と目して喧嘩を売る。ところが、問答をかわすうちにたちまち信服し、弟子入りする。
これが発端である。
孔丘は、子路の頑固さ、礼楽の形に対する無関心に手こずるが、その没利害的な一途さを愛した。
師弟のこうした相互信頼が『弟子』の魅力のひとつである。
晩年、子路は衛の孔家に仕えた。遠く魯にあって衛の政変を聞いた孔丘は、即座に預言した。
「弟子の一人は帰ってくるだろう、子路は死ぬだろう」
はたして、子路は、単身簒奪者のもとへ乗りこんだ。
向背に迷う群衆に対して、火をかけて台を焼き我らが主人を救え、と教唆扇動した。
簒奪者はおおいに恐れ、二人の剣士をさし向けた。子路は二人を相手に激しく斬りむすんだが、往年の勇者も齢には勝てない。
子路の旗色が悪いのを見てとった群衆は、ついに旗幟を鮮明にした。罵声に加えて石や棒をぶつけた。
かくて子路は、「全身膾の如くに切り刻まれて」死んだ。
『弟子』は、稲妻の一閃のように昭和文学を駆け抜けた中島敦の代表作の一。
漢文脈の即物的な簡潔さが、行動的な子路の特徴をきわだたせる。
ことに、結末では、正邪ではなくて物理的に強い側に敏感になびく群衆心理をあざやかに浮き彫りにし、読む者を慄然とさせる。現代日本におけるいじめ、差別のグループ・ダイナミックスもかくのごときか。
根源的な切なさと人への愛しさ
2010/04/15 12:20
5人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みどりのひかり - この投稿者のレビュー一覧を見る
・
山月記のあらすじは次の通りである。
***
博学才英の李徴は官吏任用試験に合格し役人となったが、性格が狷介(自分の意思をまげず、人と和合しない)で、賤吏に甘んずるを潔しとしなかつた。ほどなく李徴は官吏をやめ、故郷に帰り自然を友とし静かな生活にはいり、ひたすら詩作に耽った。下吏となつて長く膝を俗悪な大官の前に屈するよりは、詩家としての名を死後百年に遺そうとしたのである。
しかし、文名は容易に揚らず、生活は日を逐うて苦しくなる。数年の後、貧窮に堪へず、妻子の衣食のために遂に節を屈して、再び東へ赴き、一地方官吏の職を奉ずることになつた。
一方、之は、おのれの詩業に半ば絶望したためでもある。曾ての同輩は既に遙か高位に進み、彼が昔、鈍物として歯牙にもかけなかつた其の連中の下命を拜さねばならぬことが、往年の秀才李徴の自尊心を如何に傷つけたかは、想像に難くない。
一年の後、公用で旅に出、汝水のほとりに宿つた時、遂に発狂した。或夜半、急に顏色を変へて寢床から起上ると、何か訳の分らぬことを叫びつつ其のまま下にとび下りて、闇の中へ駈出した。彼は二度と戻つて来なかつた。その後李徴がどうなつたかを知る者は、誰もなかつた。
翌年、監察御史、陳郡の袁サン(サンは人偏に参の旧字体)といふ者、勅命を奉じて嶺南に使し、途中に商於の地で宿をとった。次の朝未だ暗い中に出発しようとした。駅吏が、これから先の道に人喰虎が出る故、夜が明けてからの方が宜しいでしょうと言ったのだが、袁サンは、供廻りの多勢なのを恃み、出発した。
残月の光をたよりに林中の草地を通つて行つた時、果して一匹の猛虎が叢の中から躍り出た。虎は、あはや袁サンに躍りかかるかと見えたが、忽ち身を飜して、元の叢に隱れた。叢の中から人間の声で「あぶない所だつた」と繰返し呟くのが聞えた。其の声に袁サンは聞き憶えがあつた。驚懼の中にも、彼は咄嗟に思ひあたつて、叫んだ。「其の声は、我が友、李徴子ではないか?」袁サンは李徴と同年に官吏任用試験に合格し、友人の少かつた李徴にとつては、最も親しい友であつた。温和な袁サンの性格が、峻峭な李徴の性情と衝突しなかつたためであらう。
叢の中からは、暫く返事が無かつた。しのび泣きかと思はれる微かな声が時々洩れるばかりである。ややあつて、低い声が答へた。「如何にも自分は隴西の李徴である」と。
袁サンは恐怖を忘れ、馬から下りて叢に近づき、懐かしげに久濶を叙した。そして、何故叢から出て来ないのかと問うた。李徴の声が答へて言ふ。自分は今や異類の身となつてゐる。どうして、おめおめと旧友の前にあさましい姿をさらせようか。
しかし、その恥ずかしさがあってもなお、懐かしい友と暫くでいいから話をしたいと李徴は言う。
今から一年程前、自分が旅に出て汝水のほとりに泊つた夜のこと、一睡してから、ふと眼を覚ますと、戸外で誰かが我が名を呼んでゐる。声に応じて外へ出て見ると、声は闇の中から頻りに自分を招く。覚えず、自分は声を追うて走り出した。無我夢中で駈けて行く中に、何時しか途は山林に入り、しかも、知らぬ間に自分は左右の手で地をつかんで走つてゐた。何か身体中に力が充ち満ちたやうな感じで、軽々と岩石を跳び越えて行つた。気が付くと、手先や肱のあたりに毛を生じてゐるらしい。少し明るくなつてから、谷川に臨んで姿を映して見ると、既に虎となつてゐた。
しかし、何故こんな事になつたのだらう。分らぬ。全く何事も我々には判らぬ。理由も分らずに押付けられたものを大人しく受取つて、理由も分らずに生きて行くのが、我々生きもののさだめだ。
自分は直ぐに死を想うた。しかし、其の時、眼の前を一匹の兎が駈け過ぎるのを見た途端に、自分の中の人間は忽ち姿を消し、兎を食ってしまった。
それ以来今迄にどんな所行をし続けて来たか、それは到底語るに忍びない。
ただ、一日の中に必ず数時間は、人間の心が還つて来る。さういふ時には、曾ての日と同じく、人語も操れれば、複雜な思考にも堪へ得るし、経書の章句をも誦ずることも出来る。その人間の心で、虎としての己の残虐な行のあとを見、己の運命をふりかへる時が、最も情なく、恐しく、憤ろしい。
虎になった李徴は、このあと、何故、虎になったか判らぬと先刻言ったが、考えてみると思い当たることが無いでもないという。
人間であつた時、己は努めて人との交を避けた。人々は己を倨傲だ、尊大だといつた。實は、それが殆ど羞恥心に近いものであることを、人々は知らなかつた。自分に、自尊心が無かつたとは云はない。しかし、それは臆病な自尊心とでもいふべきものであつた。己は詩によつて名を成さうと思ひながら、進んで師に就いたり、求めて詩友と交つて切磋琢磨に努めたりすることをしなかつた。かといつて、又、己は俗物の間に伍することも潔しとしなかつた。共に、我が臆病な自尊心と、尊大な羞恥心との所爲である。己の珠(たま)に非ざることをおそれるが故に、敢て刻苦して磨かうともせず、又、己の珠なるべきを半ば信ずるが故に、碌々として瓦に伍することも出来なかつた。己は次第に世と離れ、人と遠ざかり、憤悶と慙恚(ざんい)とによつて益々己の内なる臆病な自尊心を飼ひふとらせる結果になつた。人間は誰でも猛獣使であり、その猛獣に当るのが、各人の性情だといふ。己の場合、この尊大な羞恥心が猛獣だつた。虎だつたのだ。之が己を損ひ、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、果ては、己の外形を斯くの如く、内心にふさはしいものに変へて了つたのだ。
***
切ない物語なのだが、李徴の言葉に、思わず慟哭してしまう。何故か判らぬが慟哭させられてしまう。
中島敦の作品に、「憐れみ讚ふるの歌」というのがある。
「憐れむ」というのは、「かわいそうに思う、気の毒に思う」という意味もあるが、中島敦が言う憐れみは、おそらくは「いじらしく思う、愛すべく思う」の意味の方だろう。
その一部を次に掲げます。
***
みづからの運命(さだめ)知りつゝなほ高く上(のぼ)らむとする人間(ひと)よ切なし
弱き蘆弱きがまゝに美しく伸びんとするを見れば切なしや
人類の滅亡(ほろび)の前に凝然と懼れはせねど哀しかりけり
しかすがになほ我はこの生を愛す喘息の夜の苦しかりとも(※しかすがに:そうはいうものの)
あるがまゝ醜きがまゝに人生を愛せむと思ふ他(ほか)に途(みち)なし
ありのまゝこの人生を愛し行かむこの心よしと頷きにけり
***
中島敦のこころはこれらの歌が示す通り、宇宙の根源的な切なさと人への愛しさがあったのだと思う。山月記には直接的にはこれらの歌の中に表現されたことは出て来ないのだが、わけもわからず慟哭させられるのは、知らぬ間に、この切なさと愛しさが伝わってくるからかもしれぬ。
こちらと
こちらも
ご覧下さい。
『山月記』もいいけど『弟子』が好き
2025/04/13 23:17
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みずくらげ - この投稿者のレビュー一覧を見る
『山月記』を読んだことがある人は多いだろう。わずか十数頁に満たないこの作品は、滔々と流れるように語られる漢文調の文体が小気味よく、中島作品の真骨頂を表している。もちろん私も好きな作品の一つだ。だけれども、中島作品で一番心に響くのは、やはり『弟子』である。
『弟子』は古代中国の思想家・孔子とその弟子の子路の物語だ。物事の分別を悟り何物にも動じない孔子と、勇猛果敢・猪突猛進、一度決めたらどこまでも突っ走る子路。その対比が両者の魅力を際立たせる。やんちゃとは言わないが、やや手のかかる弟子である子路に対して、慈愛の眼差しでそれを見守る孔子の姿。その孔子に対しまっすぐな敬慕でどこまでもついていく子路。師弟を描いた作品で、これ以上の師弟愛はないのではないだろうか。
子路の最後を聞いた孔子の行動に、私は何度読んでも涙する。『山月記』ばかり取り上げられるのは、中島敦が好きな私としては、いささか不平がないでもない。早逝した天才・中島敦。彼の短い生涯で生み出された珠玉の名作が、私だけでない誰かの心を、今日も揺り動かす。
音読するのにもオススメな作品
2020/04/23 20:28
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:North Shin - この投稿者のレビュー一覧を見る
山月記は高等学校の教科書などで一度読んだことのある人も多いのではないでしょうか。
もういちど読みたい人にお勧めです。
音読するのにもオススメな作品です。
何者でもない自分を受け入れ、現実世界を生きることを考える10ページ
2019/04/21 23:29
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:sio1 - この投稿者のレビュー一覧を見る
作者中島敦は南洋庁国語教科書編集書記としてパラオに赴任中この作品をおさめた「古譚」を刊行・・・33歳で南洋庁を辞し、創作に専念しようとしたが、急逝。・・・代表作の多くは死後に発表され、その格調高い芸術性が遅まきながら脚光を浴びた。とある。
「隴西の李徴は博学才穎、天宝の末年、若くして名を虎榜に連ね、ついで江南尉に補せられたが、性、狷介、自ら恃むところ頗る厚く、賤吏に甘んずるを潔しとしなかった。いくばくもなく官を退いた後は、故山、かく略に帰臥し、人と交わりを絶って、ひたすら詩作に耽った。」
この作品と出会ったのは高校の時。国語の教科書に載ったさきの一文は暗記が必須だった。後年就職後、職場の先輩が偶然にも同じ高校出身だとわかり、飲み屋で「高校時代にこの作品の冒頭を覚えさせられたのが印象的だ」という話になった。夏目漱石や太宰治の作品も教科書には載っていたが、一番印象に残っているのはなぜかこの中島敦の作品である。
なぜ、李徴は虎になったのか?
「臆病な自尊心」と「尊大な羞恥心」こそが理由だと李徴は言う。
プライドの高さが邪魔をして人に教えてもらったりすることができず、現実世界では行き場がなくなり、逃避として人間でなくなる以外なかったのだろう。李徴はもっと早く気づくべきだったと後悔する。
ただ、李徴にとっては虎になって良かったのではないか。
元々人と関わることが苦手な人がそんなに簡単に心を開いて人と交われるかというとそううまくはいかない。現実逃避の手段としてますます人と関わらなくてもよい状況に逃げ込めたのだと解釈できる。
会社でなかなか昇進できず、年下の優秀な人材がどんどん出世していく。
異動の時期になると、自分を卑下して、自分だけが取り残されている状況を恥じる。会社に期待されていないという現実を突きつけられた時に、現実をどう受け止めるか?という課題に直面することは、一般的に起こりうることだ。
何者でもない自分を受け入れ、本質的な結果を残すために自分を変えるか?はたまた虎になって現実世界から逃避するか?
「 才能の不足を暴露するかもしれないとの卑怯な危惧と、刻苦を厭う怠惰とが己の凡てだったのだ。己よりも遥かに乏しい才能でありながら、それを専一に磨いたがために、堂々たる詩家となった者がいくらでもいるのだ。虎と成り果てた今、己は漸くそれに気が付いた。」
こう書かれても、虎になる方がよほどマシなのではないかと思うし、モームの「月と6ペンス」の主人公ストリックランドのようにすべてを捨てて自分のやりたい道を追求したくなる。
虎になるか?現実を受け入れるか?
やはり虎になってしまいそうだ!
山月記/李徴の思い
2002/06/10 21:20
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:おろち - この投稿者のレビュー一覧を見る
エリート、社会的挫折、詩への激しい執着。その結果、虎になってしまった主人公、李徴。「尊大な羞恥心」「臆病な自尊心」「人は誰でも猛獣使いであり、その猛獣にあたるのが各人の性情」というキーワードは、現代人にも通じるものがある。自らのこころをいかに制御していくのか、あるいは解放していくのか。自らのアイデンティティの問題についても考えさせられる名作。
文章の美しさ
2002/02/14 17:26
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ピエロ - この投稿者のレビュー一覧を見る
学生のころ、国語の授業ではじめて読んだ(読まされた)山月記、いつもは教科書なんてあまり真剣に読んだこともなく、どんな作品が載っていたかなんて今ではコロッと忘れてしまっているのに、なぜかこれだけは心に残って、その後何度も読み返しています。
漢文調、普段見ないような漢字が使われていると、ちょっととっつきにくい感じがしますが、とても調子のよい文章で、声に出して読んでみたくなってきます。言葉の美しさ、文章の美しさということをはじめて気づかせてくれた、私にとってとても大切な作家・小説です。
読み易い
2022/05/25 11:21
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ないものねだり - この投稿者のレビュー一覧を見る
生物の自意識はとても強い。プライドの高い人は多い。あまりに高く、周囲を観察し状況を認識し客観的に判断したものとプライドがつり合わない時、傷つく事を恐れて表面に別の自分を作る人を多く見てきた。皮を被るという言葉をある(想定している状況は違う気もするけど)。筆者は正直に丁寧に描写しようとしていると思う。好感が持てる作品。
自分のなかにひそむなにかと出会う時
2001/12/12 00:00
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:しっぽ - この投稿者のレビュー一覧を見る
この人の作品は、古典的なものから題材をとっているものが多い。一番多いのは古代中国(あまりにもアバウトな区切り方だが)の伝承や史実に基づいたもの。で「山月記」の舞台は唐代の中国です。
李徴という、頭はきれるんだけどちょっと偏屈な男が役人になったものの、まわりといまいちうまくいかなくて、役人をやめて詩で身を立てようとするんだけど、それもどうもうまく行かない。しかたなくもう一度役人になるのだが、ある日出張の途中、突然気が狂って宿を飛び出しそのまま行方不明になる。
その翌年、李徴の友人だった袁惨(字がでない!)という役人が、やはり出張で李徴がいなくなったあたりを通りかかって、一匹の人喰虎に行き当たります。ところがこの虎、人間の言葉をしゃべります。袁惨はその声に聞き覚えが。その虎こそ李徴の変わりはてた姿だったのです。う〜ん、ファンタジーだったんだなあ。
国語の授業でこの作品を取り上げたのですが、うちの先生が、この「山月記」の下敷きになった中国の伝承を持ってきました。もちろんそっちは漢文なのですが、当時は今よりも漢文は読めたので(ううっ)ざっと目を通してみると、ストーリーまるっきりいっしょ。でも、中島敦の方が、「虎になった理由」についてより詳しく語っています。理由は正確にはわかりません。あたりまえだけどね。
でも、李徴は人間だった頃の自分を振り返って思うの。詩によって身を立てようとしながらも、師匠についたり同好の仲間と交わったりすることをしなかった。それでいながら、身近な人たちを才能の乏しい俗物だと軽蔑してつきあうことができなかった。「己の珠にあらざるをおそれるがゆえに、あえて刻苦して磨こうともせず、また、己の珠なるべきを半ば信ずるがゆえに、碌々として瓦に伍することもできなかった」と李徴は思う。そうやって自分の中に「臆病な自尊心」と「尊大な羞恥心」を飼いふとらせ、友人や妻子や自分自身を裏切り傷つけてきたがゆえに、外見までも虎のようなみにくいものになってしまったのではないか。ここんところでぼくは参ってしまいました。なんか、自分のことをいわれてるみたいで。
物語の最後で、草むらに身を潜めていた李徴は遠ざかる袁惨の一向にその身をさらします。もう二度と袁惨が自分に会おうという気を起こさないために、あえて凶暴で醜悪な虎の姿で朝の空に浮かぶ月に向かって咆哮するの。
ずっと昔に読んだ本です。ぼくにはその時から分かってたはずです。自分の中にも李徴と同じ虎がいることに。でも「臆病な自尊心」は今でもぼくの心の中で眠っています。自分を変えるというのは、なんて難しいことなんだろうか。
リズム感
2000/08/16 03:49
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:katokt - この投稿者のレビュー一覧を見る
山月記の文章は、特に最初の「性、狷介、自ら恃むところ頗る厚く、 賤吏に甘んずるを潔しとしなかった。」から漢文独特のリズムにのり、流れるように進んでいく。特に虎になった主人公の独白部分は一気に読ませる。詳しくは
山月記
2025/02/01 11:38
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みみりん - この投稿者のレビュー一覧を見る
存じ中島敦のお話です。虎になった李徴が、親しい友人袁さんと会って、自分が虎になったいきさつを語るというもの。私もいつか虎になってしまうかもしれない。
読了
2019/12/29 11:50
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ムギ - この投稿者のレビュー一覧を見る
学生時代に山月記を読んだときには、トラが出てくる変な話としか思っていなかったけど、改めて読むと違う印象を受けた。
注がついているため、手間ではあったが、中国の話でも読むことができた。