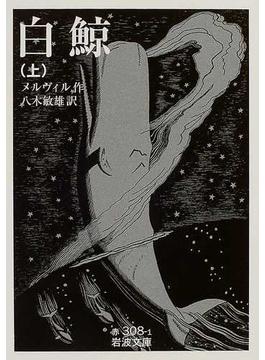「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
白鯨 上 (岩波文庫)
白鯨 上
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
紙の本 |
セット商品 |
- 税込価格:4,004円(36pt)
- 発送可能日:1~3日
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
目次
- 語 源
- 抜 粋
- 第一章 まぼろし
- 第二章 カーペット・バッグ
- 第三章 潮吹き亭
- 第四章 掛けぶとん
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
電子書籍
クジラについての解説書でもあります
2019/01/27 18:45
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
グレゴリーペック主演の「白鯨」をテレビで初めて見たのは、遠く中学生のころだったか、ひょっとしたら小学生高学年だったかもしれない。とにかく乗組員の迷惑顧みずただひたすら白鯨に復讐を誓っている男の汗臭い映画だったと記憶している。この小説は上中下3冊に別れている長編で、「わあ、延々と執念深いエイハブ船長とお付き合いしていかねばならないのか」と覚悟をしていたのだが、中にクジラの豆知識コーナーに留まらないクジラの生態から処理方法、甲板の掃除のことまで網羅されている捕鯨のあらゆる知識が挿入されていて、船長の汗臭さを中和してくれている。また日本の開国まで予想しているメルヴィルの博識に脱帽する
電子書籍
新訳だとこんなにも読みやすいのか
2023/12/24 19:10
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:H2A - この投稿者のレビュー一覧を見る
かつて新潮文庫版で挫折したのを新訳で再挑戦。最初のクジラについての文献拾遺からして読みやすく、丁寧な解説にくだけた訳文まで加われば面白くないはずがない。エイハブの狂気の片鱗とモビー・ディックの神秘的な獰猛さにぞくぞくする。
紙の本
日本が幕末のころ、アメリカ人が見ていた世界。捕鯨民族史としても面白い。
2008/12/22 11:44
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本をきちんと読んでみようか、と思った動機をまず書いておきたい。たいしたことではない、大河ドラマで「幕末」を扱っていたから、である。どなたかも書評に書いておられたが、「歴史に興味を持つきっかけ」としてはなかなか役立ってくれたのではないだろうか。そのころ世界は、ということでこの本を読む気になった。
日本があのようにざわついていた頃、アメリカではこの「白鯨」が書かれていた。ほんの数行だが、「日本ももうじき開国するだろう」というようなことに触れている部分もある。捕鯨船は随分日本の近くまで来ていたのだ。
恥ずかしながら、いつの間にか子供の頃に読んだピーターパンのフック船長とエイハブ船長が融合してしまっていた「白鯨」のイメージは、読んでみると随分違ったものだった。
とりあえず岩波文庫で読んだのだが深い理由はない。わりに最近の訳であることと、航路や船の構造図などが載っていること、掲載されている挿絵の不気味さが想像力を引きつけたからという程度である。
文庫3冊を積み上げれば5,6センチにはなる長い物語ではあるが、記憶にあるようなストーリーはところどころに挟まっているような感じで、白鯨との実際の戦いは最後の3章分、10%にも満たないのではないだろうか。よく引用される、「私のことはイシュマエルと呼んでくれ」という、唯一人生還した乗組員の語り始めの言葉の前にも、数十ページ「鯨関係の句集」みたいなものがあるし、途中にも「鯨学」なる分類的な章、挿話などが沢山ある。鯨を見つけ、追いかけ、解体し油をとる作業なども詳しく書かれている。著者自身も捕鯨船に乗った事があるとのことだから、この時代の捕鯨事情として読むのもなかなか面白かった。
ピークォッド号には、さまざまな人種が乗り込んでいる。「蛮人」とかの差別語もぽんぽん出てくる一方、語り手はそんな蛮人にも高貴なものを感じる、などという。差別なく皆雑多に混じっている、という「アメリカ的」を象徴している、というのはごく一般的なこの本の読み取り方であるらしい。( そういえば、9.11の後、アメリカ大統領がなにやら「白鯨」を引用していたらしいのだが、小説では最後にピークォッド号が沈んでしまうのはどう解釈していたのだろうか。)途中で出会う船もさまざまな国民性のカリカチュアのようだ。エイハブ船長がこっそり連れてきた自分専用の「こぎ手」である怪しげな「異教徒」が、オリエンタル、と評しているが「しわくちゃの黒木綿のシナ服にだぶだぶズホン。白いターバン」と、その頃の「オリエンタル」のイメージはそんなものか、と思わせる部分もある。
記載的な文章や、戯曲風の部分もあり、全体像がわかりにくい作品ではある。いったい著者は何を書きたかったのか。ひとそれぞれ、の読み方ができるので、さまざまな議論も時代を経て続いているのもうなづける気がする。
最初に書いた「読んだ動機」に戻っておこう。日本の中が「攘夷」だ、「開国」だと騒いでいた頃、アメリカ人はこんな風に世界を見ていたかもと思って読むのも一興、の作品である。世界の流れと日本の流れをこうやって「同時期」という視点でみてみるのも、いろいろと新しい考えを触発してくれるのではないだろうか。
紙の本
歯応えのある本の代表格
2023/06/01 13:40
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:あき - この投稿者のレビュー一覧を見る
歯応えのある本で、挫折者多数の本と知りながら気合を入れて読み始めた。
ネット上の情報によると、上巻を読む前に下巻の翻訳者解説を読んだ方が挫折しにくいとのことだったので、下巻の解説を読んでから読み始めた。
描写が非常に細かく、読んでも読んでも先に進まない、、読みながら、「いったいいつになったらこいつは捕鯨船に乗るのだろうか?」と何度も思った。そして、いつまでたっても、船は出航しない。
でも不思議なことに読んでいることに苦痛を感じないし、むしろ、どんどん引き込まれる。
読んで価値のある本ですので、ぜひ勇気を出して読んでみてほしいです。