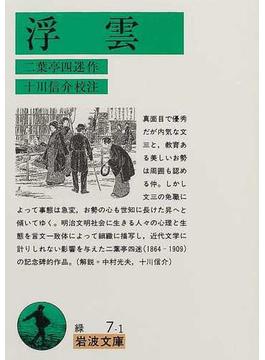0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:雄ヤギ - この投稿者のレビュー一覧を見る
様々に評価できる作品。日本近代文学の嚆矢、二葉亭の日本文学における「余計者」の表現、21世紀の読者でも感情移入できるリアルな人物描写、明治20年代当時の文明批判、言文一致運動、これら以外にも私が気づかなかっただけで様々な評価が出来ると思う。
解説にあるように、明治初期は「学問のすすめ」に代表されるような、学問による立身出世が肯定され、「明治の御世」は世襲の封建制と違い、「新しい素晴らしい時代」とされてきた。そして同じようなイメージは今日でも受け継がれている。しかし、この小説では、学問よりも上司へのおべっかと奴隷的忠誠が出世の条件とされ、それができない主人公・文三は免職になってしまう。
免職以前は文三に娘をやってもいいと考えていた叔母や、心惹かれていた従妹も免職以降冷たく当たるようになり、同僚で上司に取り入って出世する本田昇に心を寄せていく。この3人が文三に手を変え品を変え、馬鹿にし、嘲笑い、軽蔑し、笑い話の種にするのが話の大半なのだが、これを読んでいくのが非常に心苦しい。
文三も反撃したり、従妹を教化しようとしたり、叔母に言い訳したりするのだが、これが悉く空振りに終わり、途中まで文三の内面を描写していたのが、文三が部屋に引きこもってから少なくなり、文三の内面というものが無くなってしまったのではないかと心配するくらいである。なお、作品は未完で終わっているが、作者の案によると、最後は文三が母の死、実家の焼失などによりアル中になり、精神病院に入院する予定だったらしい。
また、日本の言文一致運動という面からも面白く、作者の技術が変化していくさまが面白い。最初は近世文学の読み物みたいだったものが、「近代文学らしく」なっていく。
紙の本
男の片思いも立派な小説になる
2019/01/27 18:57
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
”くたばっていしめい”からペンネームをとったということしか知らなかった二葉亭四迷の「浮雲」を読んだ。お勢の一挙手一投足に惑わされて右往左往する主人公・文三の姿に若いころの自分を重ね合わせて苦笑いしながら読み進んだ。社交的な本田にお勢が心移りしてしまったのではないかと心配する様子は、明治中期も今も変わらない男心だろう。作者本人は「失敗作だ」と言っていたという話はありますが、私の心には響いた
紙の本
文三の免職から
2019/01/19 18:09
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Otto - この投稿者のレビュー一覧を見る
文三の免職から始まった、様々な出来事が文三や昇、お政、お勢の思考を浮き上がらせていきながら物語は進んでいきます。そんな彼らの言動が、私たちにも多くの考えを与えてくれる作品です。
投稿元:
レビューを見る
秀才だが要領の悪い文三と、ミーハーな従妹・お勢、要領はいいが軽薄な昇の三角関係を中心に、官僚腐敗を批判した、近代リアリズム小説。言文一致を成し遂げた未完小説でもある。
文三と昇、お勢とお政、四者が各々の果たすべき役割をきっちり守り、歯がゆい人間関係を寧ろ整然と見えるほどに演出している。まさに出来すぎた物語だが、不自然ではない。ありがちな男女関係・上下関係を無駄なくさらりと書き上げている。
韻を踏んだ調子のいい文章、諸所に散りばめられる洒落冗談、その奥に含まれた痛烈な社会風刺。処世術を知らない者は惨めな思いをするばかりで、正しいことをしているのに報われない。文三は男としては意気地なしだが、人のいい青年であるがゆえに私は最後まで彼を憎むことはできなかった。
投稿元:
レビューを見る
坪内逍遥の提唱した近代小説のあり方を履行したのはこの小説じゃないでしょうか。一度ロシア語で書いたものを和訳したんですよね(二葉亭四迷はロシア語学校で学んでいた)未完なのが残念です。
投稿元:
レビューを見る
初の言文一致体小説だということで、読んでみました。内容自体は物凄くつまらないので、近代小説が好きな方にはオススメできない本です。小説を「言文一致体」でどのように表現したらいいのか、当時のその苦悩がわかります。
投稿元:
レビューを見る
面白い。近代文学でこんなにおもしろかったのは初めてかもしれない。現代にも言えることですね、これは。未完なのは残念だけど。
投稿元:
レビューを見る
何てことない話といえばそれまでだけれど、こういう素朴な日常を描いたものって好きです。
恋の淡さも、今の時代から考えると奥手すぎるほど控えめな様子も、
恋心を抑えきれずに右往左往してしまう様子も、じれったいけれど、何か共感できちゃいます。
そして何より、言葉回しがすごく面白かったです。
駄洒落みたいな掛詞や、ひとつの言葉を引き出すための飾り言葉や枕詞(っていうのかしら)が散りばめられていて、
日本語って、すごく茶目っ気があって楽しい・面白い文化だなと思いました。
投稿元:
レビューを見る
二十三歳の青年が失職したり、家の中で一緒に住んでいた従姉妹への恋や同僚への嫉妬、憎悪や叔母との関係など、人間の仔細な描写の極めて卓越に描かれた作品。明治十九年(出版二十年)、二葉亭四迷が齢わずか二十三にして完成させた作品である。大変おもしろく、夢中になって読んだ。こういった昔の小説で、自分と歳が近い青年の物語というのは、非常に身にしみておもしろく感じられる。2008-11.17.
投稿元:
レビューを見る
2008/11/22,23,26
必読書150に掲載。
作品自体はとてもいいものだと思うし、読みやすくて面白い作品だった。
しかし、私は主要登場人物3人がそれぞれ好めない特性をもっているため、どうもだめだった。
特に主人公・文三の友人(友人と呼べるのか?)の本田昇がみていて腹が立つ。
んでもってお勢も腹が立つ。
解説いわく、この本は当時の若者を見事に描かれているというが、
当時はこんなにひどかったのか!と思わされた。
まあ、今現在のほうがひどいのかもしれないが、、、
投稿元:
レビューを見る
まるで今の日本人だ、って妙に親近感。
言う事考えは立派だけどヘタレな文三はまるで自分みたいだって思った。(だから妙にイライラするの)明治の時代というものはきっと長い日本歴史の中で一番揺れ動き楽しい時代だったんだろうなぁって。
それにしたって変な文章の書き方で読みずらいけど、これが凄い新鮮だったんだろうなぁってよく分かる作品でした。
投稿元:
レビューを見る
言文一致体によって、日本の近代文学に多大な影響を与えた(らしい)記念碑的作品。
軽妙な文体で読みやすく、登場人物もステレオタイプであると同時に、生き生きとしている。
投稿元:
レビューを見る
言文一致体の始まりでもあり、いま読み返すと文章はかなり独特。
ストーリーは特に凝ったものではないからか、内容のほうはほとんど覚えていない。
投稿元:
レビューを見る
思っているよりカタクない!! 言文一致しすぎて面白いです。「へーそう」なんて台詞があったり、明治人のおしゃべりを感じるにはもってこい。音読したくなるような調子の良い文章も魅力。
投稿元:
レビューを見る
あれ?わたしが読んだのとこの画像のカヴァーの絵が違う…これは観菊の場面だな。
言文一致運動とかは置いておいて、普通に面白かった。語り手(作者)がときどき剽軽者だ。最後の方のお勢が不可解。作者はもっと書くつもりだったんじゃないだろうか?
お勢「デモあれは品(ヒン)が悪いもの」
お政「品(シン)が悪(ワリ)いてッたッて」「覚えがないならないでいいゃアネ」
教養がある娘は標準語でお母さんが江戸弁!