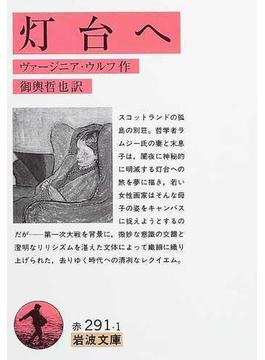紙の本
「時の流れ」を「意識の流れ」に対置して、移ろい行くすべてのものを詩情に満ちた文体で封印した——美しい、それはそれは美しい文学作品。
2005/02/02 22:24
11人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:中村びわ - この投稿者のレビュー一覧を見る
「英国文学」「モダニズム文学」「フェミニズム文学」、あるいは「意識の流れ」「精神病のセラピー」「ブルームズベリー・グループ」「実験性」といった属性や特徴でヴァージニア・ウルフ作品を文学的に論じることは、いずれも有効的で興味引かれる分析ではある。
だが、そうした研究のための概念でなく、たとえばロード・ダンセイニ『エルフランドの王女』、記憶の文学ナボコフ、三島由紀夫の「豊饒の海」4部作、そして誰が良いのだろう、SF作家は…。そう、ジョン・クロウリーあたりをウルフ作品の横に並べてみると、誰もがみなそれぞれに「時間の流れ」に特別なこだわりを持って虚構世界を築いているということ、独自の世界観を誇っているということが読書テーマとなり、1つのきらびやかなコレクションができる。
最近の物理学界では、過去から未来へ向かう時間の流れは決して一様なのではなく、揺らぎが存在するという説もあるそうだ。だが、今現在、時間は世界各地でメトロノームや時計で計り得るという前提を元に話を進めるとすれば、その「時間の流れ」という普遍的概念にウルフが対置させたのが、内面描写の一技法である「意識の流れ」ではないか。誰にとっても公平な時間経過の呪縛から逃れることに、小説という実験で挑んだ。本書『灯台へ』は、彼女のほかの長篇代表作『ダロウェイ夫人』『オーランドー』とともに、時間の扱いにおいて際立ったものがある。
父母をモデルにし、家族と彼らを巡る友人たちの物語という一見普通小説の体裁を打ち出して始まる『灯台へ』は、3部構成になっている。最初のパートでは、スコットランドの孤島の別荘で過ごす、哲学者一家と客人たちの1日が描かれる。翌日になったら対岸に見える灯台へピクニックに出かけたいと6歳の末息子が心待ちにしているのに、父親はどうせ荒天だとくさす。母親は、子どもの夢をつなごうとフォローをし、夫の態度についてあれこれ来し方の体験から思いを巡らせる。
文章は各人の意識の流れのなかに潜り込みながら、家族を見守り、密かに夫人に憧れを抱く女性画家の意識をも映し出す。
圧巻は「時はゆく」という第2部だ。ここには、宇宙にまで突き抜けていくような時間観が提示されており、10年の時が巻かれていくのであるが、ウルフの大きな資質のひとつである「詩情」がまた素晴らしい。
——夏が近づき、日暮れ時が長くなる頃、夜中に目覚めて浜辺をさ迷う人たち、希望を求めて潮溜りをかき回す人たちの心に、奇妙な想像が訪れるようになった——たとえば肉体が風に舞い散る原子の群れと化し、無数の星が彼らの心にきらめき、崖も海も雲も空も、心の中の断片的なヴィジョンを目に見える形にまとめ上げるべく、互いに寄り添うように結ばれ合う——そんな不思議なイメージだった。(252-253P)
紙幅が限られているので途中で切るが、時間や空間への広がりを詩情に満ちた言葉に留めることこそが、文芸や小説の本質だと教えてくれる表現である。
「灯台へ」は目的地を指し示す言葉ではあるが、10年を経たのち、改めてそこへ向かうメンバー、それを見守る人の内部に、時の行く末を示す言葉としての響きも持たせている。移ろい行く現実も移ろい行く意識も、ともにウルフの言葉の魔法に封印されている。
紙の本
世界を予兆する感性
2018/08/23 22:53
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:SlowBird - この投稿者のレビュー一覧を見る
主な登場人物の一人が当時の著名な哲学者ということなのだが、中心になっているのは彼の夫人であり、その夫人を取り巻く様々な人たちの皆が主人公とも言える。その家族や、家に集ってくる親しい知人たちと、明日は灯台までハイキングに行こうという何もない一日における、一人一人の内面の独白が延々と語られる。
それがまったく退屈ではないのは、それらが平凡なようで非凡なところ。非凡の人の平凡な心理、平凡な人の非凡な発想が、入り混じって、共感と新鮮さを交互にもたらすことにあるようだ。特に夫人は古風な、つまりヴィクトリア朝風の理想的な女性となっているのだが、美しく、男を惑わす恋愛の対象としてではなく、主婦として夫や家族、それから地域コミュニティを支える存在としての才能を指している。天才学者も必ずしも生活の達人ではなく、むしろ突出した能力ゆえに俗悪な社会と折り合いをつけていくための技法が必要であって、だがそれを彼のために提供できる人は数少ない。そういう才能こそが理想の女性であり、産業革命や科学の時代を、あるいは大英帝国を支えているのだという着眼点は、女性作家にしか到底持ち得ないものだったろう。
そして第一次世界大戦が一家を離れ離れにしてしまう。再び集った友人たちの中に画家志望の若い女性がいて、彼女は夫人の美しさにも言動についても思慮をめぐらせているが、自分の夢を追うことに精一杯で、じゃあ夫人のように結婚して一家の女主人となろうとはかけらも思いはせず、これは作者自身の姿の意図的な投影かもしれない。そういう女性の時代は終わり、夫人のような美徳の価値に気づいて、受け継いでいこうとした者はいなかった。その結果ロンドンは魔都と化し、帝国は崩れ落ち、科学者は悪魔の兵器を作った。この作者だけが透徹した観察力により、家庭というミクロな場を通して、世界の行く末をを予感していた。
紙の本
そんなに難解ではありません
2022/07/02 22:32
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
まさに、映画のタイトルではないけれど「ヴァージニア・ウルフなんて怖くない」なのだ、彼女の作品は「ダロウェイ夫人」「オーランド」に続いて3作目、難解だ、何を言いたいのかよくわからない、という声があるのは知っているが、本当にそうだろうか、この作品の前半は主人公ラムジー夫人、彼女の心の動きが話の主軸となっていく、彼女の心のうちは複雑ではない、8人もいる子どもを眺めながら「大きくなってほしくない、どうぞ今のままで」と願っている姿は私たち子どもを持つ身にとっても身につまされることだ、そして頑固な夫(どうやらモデルは作者の父?)の存在、食事中のつまらない会話を何とか面白い会話にしたてて盛り上げようとする企みとか、いけすかない客の存在(タンズリー)とか、彼女を私たちに置き換えれば、あるあるだらけで理解できるのだ
投稿元:
レビューを見る
ヴァージニア・ウルフなんて怖くない?そんなことはあるまい。著者はブルームズベリーグループに属し、フェミニストとしても有名。ウルフの小説は、短編(名前は忘れたが兎の出てくる話)が微妙で読まなかったのだが、再考せねばなるまい。 本作品はまず、第一部が思わず引き込まれる魅力があって一番好き。夫人が強烈な印象を与える。第二部は全体がリリシズムを湛えるといっていいこの作品でも、特に抒情的。その中にも戦争への反感が根強く見受けられる。この部があることで「怒りの葡萄」の構成を考えさせられた。第三部はリリーと灯台行きに夫人への哀悼を感じる。 蓋し、第一部の1を読みきった時は、ここで短編として終わってもよいと思ったくらいに完成度が高く、ジョイスの「ダブリン市民」を想起した。だが、全体の印象としてはよりプルーストを思わせる。意識の流れは無論のこと、風景描写や詩的な雰囲気まで似ていると思った。プロットは前述のスタインベックと共に、福永武彦氏の「風土」が近いと考える。全体に、流麗という言葉がふさわしかろう。
投稿元:
レビューを見る
風のように流れる“意識の流れ”にのって世界を見ると、日々のあいまいさに気づきます。そんぐらい、すごく繊細に精密に文章がつづられてる。
投稿元:
レビューを見る
とにかく描写が繊細。精神描写も情景描写も、繊細すぎて粘着質に感じるくらい。ウルフの言葉へのこだわりを感じるなあ。と言ってもウルフについてはほとんど無知で、精神を病んでいたとか自殺で亡くなっているとか、巻末の解説等を読んで知ったんだけど。
二章の時間経過の表現はすごく好きだ。なんとなくガルシア・マルケスの「百年の孤独」を思い出した。
「われらは滅びぬ、おのおの一人にて」後半から最後まで何度か繰り返されるけど、繰り返されるうちにこの一節が段々胸に響いて切ない気持ちになってくる。
投稿元:
レビューを見る
ツイッターから引用:
2011年01月17日(月) 1 tweets
小説:灯台へ:時間の推移をユニークに捉えている小説って好きだ。時間の経過によって見捨てられた別荘はどんどん崩壊していくけど、そこに人の手が加わることによって再び蘇っていく。別荘が蘇ったとき、全ての自然音がリンケージして「意味を持った音」響き合うシーンが美しい。
posted at 21:58:14
2011年01月18日(火) 1 tweets
小説:灯台へ:慌ただしく読み終えてしまった。本当は各登場人物の意識のパートを細かく区分けして、注意深く読まないといけないんだろうな。ディテールがものすごく詩的に描き込まれていることと、全体の構成と、両方考えつつ読まないと辛い。また機会を見つけて読み返すか…。
posted at 23:49:14
投稿元:
レビューを見る
比喩暗喩が多くてちょっと消化不良気味。
読みづらくてすごく長く感じたし、長い割には自分が何か学んだとも思えない。
「意識の流れ、変化」が評価される作品だと聞いて期待したけど、思ったようなものじゃなかった。
投稿元:
レビューを見る
死によって生を浮かび上がらせるコントラスト。迷いながらも、独立して生きようとするリリーに共感を覚えた。
投稿元:
レビューを見る
読み終わった後、自分がなにを読んだのかよくわからなくなってまた繰り返し読んでしまうような本。
文章の力のせいかどんどん読めてしまう。書いている内容はある意味ほんとうに生々しいのに、どことなく清潔ですらすらと読める。
投稿元:
レビューを見る
何だかところどころ泣きたくなるのはなぜだろうか。
人と人との間に流れる感情のゆらぎだとか、風景と自分との折り合いだとか、荒廃してゆく家のすさまじさだとか。ときどき共感できてしまうからか。
繊細、の評が多いようですが、物事の芯をきちんと捉えて、なるべく、正確に、表現してくれようとしているのだと思わされました。
とくに難しい言葉を使っているわけではないのに、言いまわしが多様で飽きさせない。
読み終わったあとに冒頭を読み返して、ああそうか、そうだったんだと納得。
何年ものあいだ待ちつづけ、一晩の闇と、一日の航海をくぐり抜けて、灯台へ。
投稿元:
レビューを見る
1章読むのにやたら時間がかかったけど、そこからさきはするりと読めた。
つかみかけたと思ったら終わってしまったので、もう一度読み返そう。
あえて言うならバンクス氏に萌えた。
投稿元:
レビューを見る
読み終えるのになかなか時間がかかった。
登場人物の間に張りつめた糸を手繰っていくような感覚。
あるひとりの思考を辿っていると、それがいつの間にか他の人の思考につながっていて…時間の流れにそって漂う意識を言葉によってなぞっていく、不思議な体験だった。
オールドミスのリリーが良妻賢母の権化ともいえるラムジー夫人に抱く複雑な感覚はわかるなぁ、と思いながら読んでいた。ぼんやりとした憧れと、お節介を少し疎ましく思う心と、愛し愛される人を「自分とは違う人種だ」と思いつつも羨む気持ち。
二章の時間の流れの描写がとても好き。
投稿元:
レビューを見る
なんて美しい小説なのだろう。波の満ち引きの様に押しては返す内面の機微、それを優れた知性と洞察力によって掬い取り、繊細に言葉を紡ぐ事によって日常に寄り添う幸福や憂鬱を情景豊かに描き出す。家族と友人たちの一日の風景と瞬く間に過ぎる10年という歳月、そして再び描かれる一日の風景。内面描写の主体を次々と移しながら表象には出てこない感情のひだまで丁寧に描き出すその文章は、雪の結晶の微細な美しさに触れた時の感覚に似ている。だからこそそれはどこか儚く、触れてしまえば粉々になってしまいそうな危うさも感じさせてしまうのだ。
投稿元:
レビューを見る
1927年発表、ヴァージニア・ウルフ著。孤島に住む夫人とその一家、彼らを取り巻く画家ら数人。第一部「窓」:明日灯台へ行くことを思いながら日が暮れ、夕餉の席で頂点に達する各人の心理的緊張を描写する。第二部「時はゆく」:擬人化した風や闇などに視点を据えつつ、それらに家が侵食されて廃墟と化していく過程を描く。第三部「灯台」:十年後、再び家に戻ってきたラムジー氏と子供達がようやく灯台に向かう。
濃密な心理の流れだった。
第一部:主観人物はころころと入れ替わり、特に夫人の存在感が他の登場人物の心理に及ぼす影響を精密に、詩的に、哲学的に描いている。静かな池に石を投げ入れて波紋が広がっていく様を眺めているような印象を受ける。ストーリー自体はほぼ動いていないのだが、微妙な精神の揺れを介して、各人の関係や思想が浮かび上がり、物語に深みを与えている。
第二部:この部が一番面白かった。風の小隊など、自然現象に関するユニークな表現が目を引く。それに比べて、主要人物のストーリーは非常に簡潔に語られている。生き生きとした自然と無機的な人間。全てが朽ちていく、という事実がひしひしと伝わってくる。
第三部:つくづく人の死というものは、肉体としての死だけでなく、心理的な内面の世界(それは他の人の心にも食い込んでいる)をも含むのだと痛感した。そしてようやく灯台に到着したシーンでは深い解放感を覚えた。特別取り立てて言うことのない本小説のストーリーなのだが、たったそれだけの行為に膨大な心理が詰まっているのかと思うと、感慨深いものがある。こうして一旦は灯台に流れ着いた精神の流れは、これからも、永久に、主観人物を変えつつどこかへ流れ続けていくのだろう。
解説によると、本小説は著者自身の両親に対するレクイエムらしい。永久に続く流れに身を委ねること、委ねられると納得できたこと、その穏やかさを著者はきっと感じたことだろう。