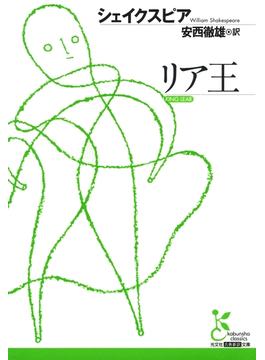怒りや悲しみで狂気を帯びていく主人公リア王の迫力
2006/12/25 17:21
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る
シェークスピアの悲劇の一つ、「リア王」。表向きの愛情表現に惑わされて姉娘二人に財産を譲ったものの、たらいまわしにされる姿は現代の家族像にも投影され、そういった演出もされる劇である。安西訳は言葉使いも現代風であり、すらすらと読み進める。舞台上の動きまでが想像できる活き活きとした文章である。「傍白」という言葉にまで注釈がついている親切さは、そこまでしなくてもとも思ったが、シェークスピアを難しいと思わずに読んで欲しい、という心遣いが感じられる。
怒りや悲しみで狂気を帯びていく主人公リア王は何度読んでも迫力がある。それぞれの思惑で行動する姉娘たち、エドガーやケントの身分を隠した行動の二重性が生み出す複雑な設定など、楽しめる要素がもりだくさんなのは、やはりさすがシェークスピア。これまで難しい、と思った方も、もう一度読んでみてはどうだろうか。諧謔やひねりの利いた道化の台詞も、わかりやすくなっている。
巻末には劇作家で研究者でもある著者の「シェイクスピア小伝」「解題」「年譜」つき。当時の演劇事情も良くわかる。訳者あとがきも「タネ本」や「悪名高いケイト版」に言及し、この作品の特徴をよく伝えてくれる。
光文社の古典新訳文庫シリーズは、どの訳者も力をいれて良いものにしようとしている姿勢が感じられる。古典に限らず、良い訳本をこれからも期待したい。
投稿元:
レビューを見る
舞台の台本のまま、ほぼ会話文で進んでゆくので途中若干眠くなりましたが、やはりこの人間劇は色々考えさせられますね。
投稿元:
レビューを見る
衝撃のクライマックス!ってやつですか。
読者は思いっきり放り出される感じですな。
途方にくれます。
面白かったっす。
戯曲とか全然読んだことなかったから最初は抵抗があったけど、よかったよかった。
それにしてもこの作品が関が原の戦いの時代に書かれたってのが信じられないぐらい新しい。
それが訳者の力量なのか、それとも作品自体の力なのかは分かりませんが。
解題も勉強になったし、よし、次もシェイクスピアでいきますか。
投稿元:
レビューを見る
「だって、おっちゃん、諺にもいうじゃァねえか、うっかりカッコウの雛を孵したヒバリは、育てた子供に首を食いちぎられるってさ。
こうしてロウソクの灯は消えて、おいらもあんたも、みーんな闇ン中を、ウロウロうろつくことになるってわけよ」
投稿元:
レビューを見る
言うまでもなくシェークスピアの名作。
王が突然引退を決め、その後継として、3人の娘に対し自分への愛情をテストする。
しかし、王の期待はもろくも崩れ去り、気がふれてしまった王は全てを失い、絶望の中、森をさまよう。
愛情と憎悪、忠誠と謀反、期待と絶望、栄華と零落。まさに悲劇。
訳も、実際に話しているような言葉。話しかける相手も括弧書きで示されていて、読む一役となる。
投稿元:
レビューを見る
うーん、よく分からなかった……。
リア王の気持ちもよく分からないし、末娘がどうしたいのかもいまいち分からない。
難しいわ〜。
ただ、「三人」の娘という登場人物に対しては思うところあり。
三兄弟のモチーフは物語によく出てくるわけで。
ハリーポッターだって、最後の肝心な神話で三兄弟が出てきた。
三人いると、キャラクターが対比しやすいのか、構造として三人というのが良いのか。
「起承承承転結」で、承を3パターン書くことの面白さを説いている人がいたのを思い出しました。
3は変化の数か。
投稿元:
レビューを見る
リア王、結末に、悲しむ。さすが四大悲劇のひとつ。
実際に劇場で見てみたい!
色々と研究書を読んでみたくなる。どういう解釈がなされているのか。
投稿元:
レビューを見る
この作品、KiKi はこれが何度目の読書か、正直なところよく覚えていません。 もちろん原典も学生時代には読んだし、福田恆存の訳本(当時のスタンダード)でも読んだし、当時注目を集め始めていた小田島雄志の訳本でも読んでいます。 もっとも今回の読書でそれらを比較検討できるほどには記憶に残っているわけじゃないんですけどね(苦笑)
ただ漠然と覚えているのは「福田訳」がかなり詩的だったのに対し「小田島訳」はかなり口語調になっていたことと、それと比較しても今回の「安西訳」はそれに輪をかけて言葉としてひっかかるところがなかったこと・・・・・ぐらいでしょうか?? スンナリと目や耳に入ってくるというのはある意味では「わかりやすさ」に通じて素晴らしいことだと感じるのも事実なんですけど、逆に言えば特に読書の場合、「あれ?」と思って読み返して咀嚼するというプロセスがなくなってしまうため、その分読み飛ばしてしまうリスクがあるなぁと感じました。
シェイクスピアが書く言葉には物事を2面からとらえる言葉とか2つの事象・概念を並べて語る言葉がよく出てくるんだけど(例えば有名なところでは「きれいはきたない、きたないはきれい」というような)こういう言葉って「あれ?」と躓き、何度も読み返して咀嚼するプロセスがあるからこそ何を言わんとしているのかが伝わってくるとか記憶に残るというようなところがあると思うんですよね。 でも、少なくとも今回の読書で KiKi はこれに類するような「あれ?と思って読み返してみる」という行為をほとんどしなかったなぁ・・・・と。
これを既にストーリーを知っている物語ゆえ・・・・と捉えるべきか、読み方が雑になった・・・・・と捉えるべきか微妙なところだなぁ・・・・・と感じました。
さて、それはさておき、読後感です。 今感じている読後感が今回の読書だけによるものなのか、はたまた学生時代に感じていたものそのまんまなのかは自分でもよくわからないし、今となっては学生時代にこの物語から何を感じていたのか?はよく覚えていません(苦笑)
この物語、シェイクスピアの4大悲劇の筆頭として語られることが多いんですけど、個人的にはこちらの物語よりも「マクベス」や「オセロー」の方が好きだったりします。 それは恐らくリア王の狂気よりもマクベスやオセローの狂気(というよりは錯乱と言うべきか?)の方が KiKi には理解しやすいし、特に「マクベス」あたりはコンパクトな纏まり具合という点からしてみても、素晴らしいとしか言いようがないと感じられるからです。 リア王ってどことなく因果応報な感じもするし、途中でグロスター伯と二人の息子の話まででてきちゃって悲惨さと言えばリア王その人の悲劇よりもグロスター伯の悲劇(リアを助けようとして迫害を受け、両目をつぶされたうえで追放される)の方が悲劇的に過ぎる部分もあるように感じちゃうし・・・・・。
KiKi はね、リア王って恐らく暴君と言ってもいいほどの専制君主だったと思うんですよね。 で、権力の座にある間は彼の言葉が絶対で、臣下も娘も決して彼の言葉に異を唱えるようなことはなかったし、仮に唱えたとしてもそれをすぐに打ち消さざるを得ないような空気を漂わせた人物だったんだろうと思うんですよ。 で、恐らくそんな暴君でありつつも彼なりの方法で3人の娘たちを愛してはいたんだと思うんです。
老境に達してそろそろその「絶対性」にも疲れてきちゃっていた王様は、後世の憂いを絶つためにも彼の領土・権力を3人の娘たちに等分に分配し、「みんなで仲良く」治めて欲しいな~んていう夢みたいなことを思い描き、さらには「絶対君主としての責任は放棄(彼としては委譲)するけれど、王という称号と名誉だけは手元に残す」な~んていう都合のいいことを画策したのがあの冒頭の「愛情テスト」の場面。 まだ権力を手元に置いた状態での「愛情テスト」に上の二人の娘は耳触りの良い言葉で答え、どこか抜けたところのある末娘はそんな姉たちの上っ面に反感を抱きます。
この悲劇の根本にあるのは、リア王が絶対だと考えていたある種の「価値観」を娘たちの誰一人として共有していないことにあり、その価値観が権力と密接に結びついていたことを肝心のリア王自身が理解していなかったことにあると KiKi は思うんですよ。 ・・・・・と同時に、この物語の背景にある時代が恐らくは結構群雄割拠な時代だったんじゃないかと思うんです。 リア王に勘当されたコーディリアはフランス王に嫁ぐわけだけど、これだってその裏にあるのはどんな思惑やら・・・・・。 だいたいにおいてイギリスとフランスが仲が良かったな~んていう話はほとんど聞いたことがないし・・・・・。
恐らく本来ならフランスをはじめとする外敵と対峙するためにも王権を3分割するな~んていうのは当時の国家君主としては間違った判断だったんじゃないかと KiKi は思うんです。 でもリアはそんなことさえ考えられず自分の安逸な老後のため(& 姉妹仲良くという夢想のため)に冒頭の「愛のテスト」に臨む段階では「きれいに三等分すること」を心の中で決めていた節があるように感じられます。
コーディリアが勘当されることにより三等分だったはずのものが二等分されたことにより、少しはマシではあったかもしれないけれど、もともとあった力を半分ずつに分けられてしまったうえに、引退老人が100人からなる軍隊を言ってみれば自分の遊興のために(そして万が一の時には戦力として)手放さないという状況が2人の娘にとっては面白いはずもなく、彼女たちはリアから戦力を奪ったうえで追放します。
2人の姉妹が極悪非道・冷血人間のように見えなくもないけれど、だいたいにおいて「姉妹仲良く分割統治」な~んていうのが理想(夢物語)に過ぎないわけで、彼女たちがリアを説得しようとする言葉の中にもある種の真実が含まれているところが目を引きます。
そしてそんな父親の苦境を知ったコーディリアは善意からフランス軍を率いてドーヴァーに上陸するわけだけど、この段階での彼女はリアの娘である以上にフランス王妃なわけです。 これはブリテン側にしてみれば侵略と呼んでもいいような振る舞いでもあるわけで、ここでもコーディリアのやっていることはどこか間が抜けています。 そうであるだけにリアの長女、ゴネリルの夫であるオルバニー公は心の中ではリアに対する娘(≒自��の妻)の仕打ちを許せないと思いつつも戦に赴かないわけにはいきません。 こうしてブリテン側が勝利することによりコーディリア & リアは捕えられ、その後あれこれあって、結局みんな死んじゃった・・・・・と。
考えてみるとこの物語、絶対権力者が陥ったある種の時代錯誤・傲慢さの為せる業とも見えるわけで、そこにこそ悲劇性があるように KiKi には感じられました。 狂人となったリアが嵐の中で彷徨う姿は確かに悲劇的だけど、道化の存在やらグロスター伯に迫害された長男、エドガーとの出会い等々があり、悲劇的でありつつもどこか喜劇的なように感じられました。
投稿元:
レビューを見る
沈黙は、金ではない。コーディリアは心優しいお姫様かもしれないが、それでも高慢だ。道化の秀逸な用いられ方は現代小説にはなく、興味深い。
投稿元:
レビューを見る
超資産家の老人が「もうそろそろ資産をすべて譲渡し、子どもたちに面倒を見てもらおうと思う。そのために子どもの君達が資産を譲る対象にふさわしいかテストします。資産を譲るから私は私で好き勝手に生活させてもらう」、と言ったら現代のリア王ができあがりますよね、たぶん。(家族全員が死ぬかどうかは別にして)それは別にして、読んでいると劇を見てみたくなります。
マクベスは魔女、ハムレットは親父の亡霊という、ふつう現代社会にはない想像しにくく、言ってみれば突然に悲劇がふって湧いてきます。しかし、リア王は身から出た錆というか、自分自身のふるまいが原因で悲劇が始まります。ふつうに現代社会にも似たような話が起こり得る話で、子どもの心情もかなり理解しやすい話だと思います。王様は「老いては子に従え」の真逆を突っ走っており、老後を悠々自適に暮らしていこうと、王の尊厳を保持してわがままに生きていけるような「余計な一手」を指してしまったがために、子どもにそっぽを向かれます。(というか自分も子供らも死ぬことになります)ほんと、自分も気を付けないと~。
投稿元:
レビューを見る
良識と思慮にかけた王様と、狡猾で身持の軽い長女次女。そして不器用で天然の入った三女。
この親子の中で誰に感情移入するかに寄って、善悪が入れ替わってしまう作品だと思う。最初は王様のあまりの放埒ぶりに、長女次女の方に利があるように見える。しかし正しさを身につけると人は残酷になってしまうもので、王様への仕打ちは悪役のすることに変わってしまう。
最終的に親子の誰も幸せになれなかったできなかったけれど、彼らの誰もが問題を抱えていたので、どうにも同情しきれない。むしろ振り回されたあげくに、両目を失い死に絶えた家臣の方に、落涙を禁じえない。忠誠心溢れる彼の物語はサブプロットでもメインを喰うほど輝いている。
投稿元:
レビューを見る
p.173「なんだ、気違いか、お前?目なぞなくとも、世間は見える。耳で見ろ。あそこにいる、あの裁判官め、あのコソ泥を叱りつけておるのが見えようが。いいか、よく聞けよ。あっちとこっちと取っ換えてみろ。どっちが裁判官でどっちが泥棒か、誰に分る?百姓の犬が乞食に吠えかかるのを、お前、見たことがあろうが?」
とか、人間が単に皮をかぶった存在でしかないみたいな記述が頭に残る。最も弱い存在でしかないのに最も強欲な存在の人間。
リア王はただの気違いかと思っていたらどうやらそうではないらしいと思える。でもなんとも言えない。後半はだんだん王に同情するようになる不思議な劇作品だと思えた。
投稿元:
レビューを見る
リア王が世界を呪う場面がすごいなぁ。全体的に、張りつめて、積み上げて、一気に崩れる。
非常に現代語で読みやすい、わかりやすい。それだけに何でリア王こんな老害なん?とか、二人の王女はケチくさい。とか、わかりやすく感想が出てくる。エドガーとグロスター親子のエピソードが泣きそうになる。
舞台とかでも見てみたいなぁ。
投稿元:
レビューを見る
理性あるが故の悲しみというか狂気は時代や環境が違っても変わらないものだなぁと自分と環境を省みてなんとも暗い心持ちになってしまった(..;)嵐の中の独白や地獄の裁判のシーンはきっと原語で読んだらもっと凄いんだろうな。
投稿元:
レビューを見る
『老いた王・リアは引退を宣言し、三人の愛娘に王座を明け渡そうとしていた。しかし、その結果は彼の心を打ち砕く。失意の果てに、老王は嵐の荒野をさまよう。一方、リアの臣下の次男・エドマンドは権力を求めてある画策を練る。策略と裏切りが交錯し、そして悲劇が訪れる……』
戯曲なので、地の文は一切なく、会話だけで進みます。堂々と謳い上げられた台詞のインパクトが凄まじいです。会話の節々に悪意と野心がにじみ出ていて、その毒を噛みしめるほどに物語にのめり込んでいくのを感じました。
グロスター伯がもう哀れすぎて……泣くかと思った。