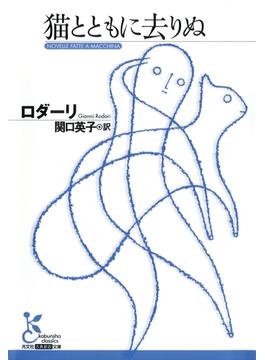猫とともに去りぬ
猫の半分が〈元・人間〉だって、ご存知でしたか。家族も会社も、何もかもがいやになったら、ローマの遺跡の境界線をまたいで猫になってしまおう……。ほかにも、魚になってヴェネツィ...
猫とともに去りぬ
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
猫の半分が〈元・人間〉だって、ご存知でしたか。家族も会社も、何もかもがいやになったら、ローマの遺跡の境界線をまたいで猫になってしまおう……。ほかにも、魚になってヴェネツィアを水没の危機から救う一家、ピアノを武器にするカウボーイ、ピサの斜塔を略奪しようとした宇宙人、家々を占拠する捨てられた容器たちなどが活躍! 現代社会への痛烈なアイロニーを織り込んだ、ユーモアあふれる知的ファンタジー短編集。
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
軽くて上質なくつろぎの味
2006/12/20 09:36
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る
どの話も突飛な展開をするのだが、登場するものはみな俗世間の考えで行動をする。そのギャップがどれも軽妙なユーモアを感じさせる短編集である。
著者はイタリアの児童文学作家。国際アンデルセン賞も受賞しているそうであるが、作品は初めて読んだ。毎日の生活に疲れてしまったとき、ちょっと口直しに味わうと良いような、辛さも苦さもあるが、重たく残りはしない上質の口どけの作品である。軽焼きの、高尚なユーモアを味わう一口サイズのお菓子、といったところ。
たまたま手にとって、表題作「猫とともに去りぬ」の設定がユアグローの「鯉」(「ケータイ・ストーリーズ」に収録)と同じ設定だな、どう違うのかな、と思って読んでみた。こちらはローマ廃墟の猫になってしまうおじいさんの話であるが、あちらは鯉。人生が嫌になってこんな風に考えることは結構ある、ということなのだろう。ここではなかなか楽しい、ほのぼのとした展開になっている。
他には白雪姫を題材にした作品もある。シンデレラはSF仕立てになっている。イタリアらしく、ヴェネツィアの水没や、ピサの斜塔を扱った作品がある。いろいろあって楽しい。最後に納められている作品が運命や友情の無情観をひんやりとした後口として残すのも、一冊のまとめ方として洒落ている。
なかなかお買い得感のある一冊で、子供向けでない著者の作品にも手を出してみたくなった。
楽しい本
2015/09/12 15:26
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:けy - この投稿者のレビュー一覧を見る
ぶっとんだ展開が多く、ファンタジーであるといえる。しかし、ブラックジョークを散りばめ、ユーモアたっぷりに言ったりとめちゃくちゃな作品。社会風刺しながら説教臭くなく、むしろ笑わせに来るのは凄い。
幼稚園や学校の子どもたちとの交わりのなかから、子ども向けファンタジーの創作にこだわった作家ロダーリ。大人向けファンタジーのカルヴィーノとイタリア・ファンタジー界を支えた。
2007/06/20 23:32
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:中村びわ - この投稿者のレビュー一覧を見る
ファンタジーについての評論がまだほとんどなかった30年も前に、武井武雄画伯の愛らしい装画・装丁で『ファンタジーの文法』(筑摩書房)というファンタジーの教科書とも言うべき本の邦訳が出ていて、それを書いたののがロダーリ。イタリアを代表する児童文学者である彼は、どの国の児童文学者もそうであるように、「民話」「おとぎ話」というものの大切さを強調し、それを創作の源泉としている旨を『ファンタジーの文法』に書いている。「おとぎ話に耳をすます子ども」という章に、次のような「おとぎ話」賛美がある。
——(前略)おとぎ話は、人間性への、つまり人間の宿命の世界への、イタロ・カルヴィーノが『イタリア民話集』の序文で述べているように、歴史の世界への、有益な手引きの役を果たしているのである。(P207)
おとぎ話が提供する人間や運命の豊富なレパートリーに、子どもは未知の現実や未来への手がかりを発見するというのである。子どもがおとぎ話で自分の想像力の構造を見つめ、同時に想像力を作り上げるのだとも言っている。
「民話」賛美のほかに、「子どもたちの反応重視」という点がロダーリのこだわりである。幼稚園や学校に出向き、話をして、自作の作品を読みきかせ、反応により手直しを重ねた——児童文学の本来的作られ方を大切に、常に創作を行っていたという。それによって作られた作品が奇想天外であることに対し、大人である自分が「こういうナンセンスでいいのか、ご都合主義的に取れなくもないのだが……」というように言い訳を求めながら読み進め、違和感を持たざるを得ないのも、子ども時代からこちらの世界へ移行してしまったときに「鉄柵」を越えてきてしまったせいかもしれない。
最初に所収された表題作「猫とともに去りぬ」はまさに柵越えの話で、年金生活者のおじいさんは柵を越えるだけで猫になってしまう。そして、「行きて帰りし物語」の子ども物語の約束に従い、おじいさんは再び柵を越える。この他愛なさが「深読み可能なファンタジー」を求める類いの大人には、正直いささか物足りなくはある。
しかし、水没しつつあるヴェネツィアで暮らして行く対策として、いきなり魚になろうとして変身してしまったり、マシンが好きだからとバイクとの結婚を考えたり、この世にあるものすべてを箱詰めしようとしたりといった制限や縛りのない着想のかけめぐりには、「こうであれれば……」と思わせる伸びやかさがある。
したがって、そのような伸びやかさを受け止める余裕があればこのファンタジー集は楽しい読み物であるし、めぐり逢わせ悪く、受け止める余裕がない場合には、楽しさも半分なのだと思える。それでも、ここにあるすべてのファンタジーが伸びやかという特徴で片付けられるものではない。釣りの獲物を得たいがために、何度も何度も長大な人生の時をやり直す男を描いた「ガリバルディ橋の釣り人」や、エイリアンにさらわれそうになった観光名所を土産物売りが機転で救う「ピサの斜塔をめぐるおかしな出来事」などは、おとぎ話的な風刺が色濃く出ており、日頃の自分の愚かさに気づかされながら、子どもにそれを指摘されたような居心地の悪さすら感じながら読むことができる。
ファンタジーを通しての「人間性」「宿命世界」「歴史世界」への案内は、子どもならより直感的なレベルで、大人ならより論理的なレベルでスムースに行くということなのだと思う。ロダーリは教訓的表現と詩的表現、伝統的要素と新奇な要素の両義性を意識したと共に、子どものなかの「子どもらしさ」「大人びた部分」、そして大人のなかの「大人らしさ」「子どもじみた部分」に響くものを抱えながら物語作りに励んだのではあるまいか。