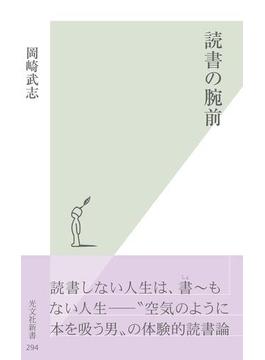読書の腕前
著者 岡崎武志 (著)
寝床で読む、喫茶店で読む、電車で読む、バスで読む、食事中に読む、トイレで読む、風呂で読む、目が覚めている間ずっと読む……。“空気のように本を吸う男”の書いた体験的読書論。
読書の腕前
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
著者紹介
岡崎武志 (著)
- 略歴
- 1957年大阪府生まれ。ライター、書評家。書評を中心に執筆活動を続ける。著書に「気まぐれ古書店紀行」「古本生活読本」「文庫本雑学ノート」など。
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
ツン読は立派な読書なのです。
2007/03/31 17:21
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:栗山光司 - この投稿者のレビュー一覧を見る
僕は岡崎武志ブログを時々訪問しますが、著者の本をこれまで、ちゃんと読んだことがなかったのです。雑誌や新聞の記事をつまみ食いした程度で、図書館や本屋で偶にめくっても、購入することがなかった。今回初めて買ってしまったわけは、恐らく、書名に『古本〜』という冠がなかったことが第一だと思う。
だからと言って僕は古本に拒否反応を示しているわけではない。古本屋を覗くのは好きだし、ネットで日本の古本屋さんもクリックする。でも、かって、古本を冠した書籍、雑誌を愛読したことがありましたが、古書の分野は申すまでもなく、チラシ、紙くず、日記の類もアンテナを伸ばして、底なし沼に彷徨う世界にいささか恐れをなしたのでしょうか、知らぬ間に古本屋さんの世界に近づかないようになりました。
その代わりと言ってはなんですが、本書で著者が「ブ」と表示している新中古書店には足繁く通うようになりましたね、そこで、思わぬ本と巡り会う。
実は僕は最近、近所の「ブ」で、百五円の佐藤泰志の『きみの鳥はうたえる』を見つけたのですが、その翌日、本屋で、本書を立ち読みしたら、161頁に何と「本の熱病は伝染する−佐藤泰志を求めて」がありました。まさに鳥の声で、「買いなさい」なのか、それで、持ち帰ったわけです。
見事に感染しましたよ。著者のファンは殆ど古本狂に近い方々だと思いますが、僕のように成る可く古本に感染しないように気をつけている、むしろ、新刊が大好きなオヤジにとっても愉しい『本の本』になっている。
著者の読書を通した自分史にもなっており、16歳の時、旅行中に不慮の事故でお亡くなりになった父親とのエピソードや、娘さんに仮託して朝日新聞に書評『かいけつゾロリの大どろぼう』を書いたくだり、学校での担任との本にまつわる悲しい思い出、著者を勇気づけた担任の一言などは力のこもったエッセイです。
寺山修司、高橋源一郎、色川武大、植草甚一、丸谷才一、川本三郎、吉田健一、開高健、長田弘、エリック・ホッファー、田中小実昌、保坂和志、小林信彦、荒川洋治と僕の好きな作家について語ってくれるのも嬉しいのですが、著者は山本健吉が命名したとされる「第三の新人」達に最も感化されているみたいです。
特に庄野潤三の思い入れは尋常ではない。著者が最も好きな読書空間は乗り合いバスの運転席のすぐ後ろ、「一人掛の席」ですが、バスの揺れに任せて庄野潤三の『夕べの雲』を読んでいる姿が目に飛び込んでくるのです。
本書は大文字で語るくだりは全くないけれど、暮らし、生身の著者の日常が本を飲み込んで立ち上がってくる。強い読後の印象が残ります。古本と言う限定した分野だけではなくて、本書のような「本の本」についての本をどんどん書いて欲しいと思いました。
歩行と記憶
泣かせてやろう、っていうお話は読みたくないんですが、人間には慟哭することがあります。ドキュメントを読んだ時の涙は、許せます
2007/06/06 21:14
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みーちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
これが岡崎武志初の新書、というとウッソーと思いません?ま、岡崎の本と言えばソフトカバーなので、新書と勘違いされやすいのかもしれませんね。しかも出したのが光文社。筑摩あたりから出た印象ですが、それって先入観です。でも、積読を評価する、っていうのは、ある意味、常識の破壊です。
そんな言葉は、カバー折り返しに出ています。
「人間の土台は「読書」がつくる
よく見ると、「ツン読」には、ちゃんと「読む」という文字が入っている。現
物が部屋にあることで、いつも少しずつ「読まれている」のだ。プロ野球の
ピッチャーが、投げないまでも、いつもボールをそばに置き、ときどき触る
ことでその感触を確かめるようなものだ。だから「ツン読」を避けようとす
る者は、いつまでたっても「読書の腕前」は上がらない。これ、たしか。
(本文より抜粋)」
うーむ、自虐的に「積読」状態を反省していた私には、嬉しい一言。で、目次を見れば、そんな先入観をぶち壊すタイトルがいっぱい。まずはご覧下さい。
はじめに
第一章 本は積んで、破って、歩きながら読むもの
第二章 ベストセラーは十年後、二十年後に読んだほうがおもしろい
第三章 年に3千冊増えていく本との闘い
第四章 私の「ブ」攻略法
第五章 旅もテレビの読書の栄養
第六章 国語の教科書はアンソロジー
第六章(ママ。目次の間違い。本文は第七章、と表記) 蔵書のなかから「蔵出し」おすすめ本
ささやかなあとがき
おお、本を破って読むか・・・図書館の本が傷むはずよ。でも、自前の本だって私には破れない。でも積読ならば、得意。たしかにベストセラーを読まない、っていうのは見識なんでしょうが、読んだ本があとでベストセラーになるのは私の責任じゃあない。時代を膚で感じるには軽薄も一手ではあります。
でも、年3000冊増える蔵書、っていうのは恐怖ですね。実家から移動した本が3000冊くらいですが、もうお手上げですから。それに私、ブックオフに入ったことないし・・・。でも、教科書をアンソロジーとして楽しむという発想には驚きでした。もし装丁がもっと良くて、文庫にでもなったら私も買うかも。
で、読みたくなったのは第七章 蔵書のなかから「蔵出し」おすすめ本 の「詩は「別腹」」にあげられている高階杞一『早く家へ帰りたい』偕成社。息子さんを三歳で失った親の慟哭を綴った詩集ですが、想像しただけでも目がウルウルしてきます。お涙は嫌いなんですが、二児(もう大学生と高二ですが)の母としては、気になる・・・