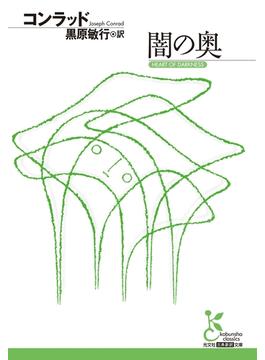善悪定まらないものの 魔力を感じながら
2010/01/04 18:29
11人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:くにたち蟄居日記 - この投稿者のレビュー一覧を見る
新訳で「闇の奥」を読んだ。
中野良夫の旧訳の「闇の奥」は幾分読みづらい本であったが 本書でも その読みづらさは ある意味で変わらない。となると これはやはり原作自体の難しさにあると考えるしかないと思った。
僕にとっての 本書の難しさは 結局主人公であるクルツの善悪が定まらない点にある。これは僕自身が「善悪がはっきりしないと物事の理解が難しい」という「考える力の弱さ」を露呈したと謙虚に受け止めるべきだ。
僕らにとって 何かを考えることは 「それらを区別し 何らかのラベルを貼る」という作業で終わってしまうことが多い。「分かるとは分けることだ」という言い方もあるし それは一面真理なのだろうが それだけだと「分けようとしても分けられないもの」への理解が不可能になる。その一例が 本書であり 本書の主人公であるクルツではないかと事が今回読んだ印象だ。
文化人類学を学べば 「すばらしく崇高なもの」と 「おそろしく俗物なもの」は一人の中に共存することがある点が分かる。クルツを理解するには そのような手法を取っていくしかないに違いない。
本書には救いもないし 結論も無い。どこか尻切れトンボで居心地も悪い。クルツの許嫁の大いなる誤解も滑稽だ。あるべき「悲劇」にもなっていない。それがコンラッドの 結局言いたかったことなのだろうか。ただし 結末を作者が提示していないことで 本書の読み方が自由になったことも確かだ。本書から 村上春樹が「羊をめぐる冒険」を書いたと言われるし コッポラは「地獄の黙示録」を撮った。「善悪定まらないもの」への本能的な嗜好が人間にはあるのかもしれない。
闇のさらに奥とは?
2017/07/29 01:03
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Ottoさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
映画「地獄の黙示録」のイメージの元になったといわれる。
コンラッドは、ポーランドの没落した小地主の息子で、家族はシベリヤに送られ強制労働に処せられた。その後イギリスへ船乗りになるために渡り、後年船乗り時代の経験を語る形式で、物語は始まる。
19世紀、暗黒大陸と呼ばれたアフリカ、そのコンゴ川をさかのぼるのだが、当時アフリカからの輸出品は象牙だった、それを奥地から送り出してくるクルツという得体のしれない、まさに闇の男がいることを知る。どうやって大量の象牙を集めているのか、鎖につながれた奴隷たち、クルツに心酔する白人青年、髑髏の突き刺さった杭、船に向かって雨のように降る弓矢、闇の奥はさらに深い心の奥。
投稿元:
レビューを見る
植民地時代のコンゴの奥地に深く分け入って行くと同時に、人間性の闇の奥に迷い込んで行く重層的な語りの物語。
ストーリーや思想を読むのではなく、感覚を味わう物語。
イメージに迷い込んで、宇宙の深淵に放り出されるよう。
植民地時代や文化を描いた物語では全く無い。
投稿元:
レビューを見る
単なるアフリカ冒険小説かなと思っていたのですが、なかなか難しい小説です。かといって読みにくくはないのですが、話がきれいにまとまらない所が難しい。そういうタイプの難しさです。作者はもとポーランド貴族で、船員をやり、小説家に転身した人物で、英文学と東欧文学の血脈をひいているそうです。語り手マーロウ、コンゴでやりたい放題をしていた象牙の略奪者クルツ、彼のことを何もしらないのに、全てを知っていると豪語する「幸せな」婚約者、道化のようなロシア人、狡そうな支配人、下劣な社員「巡礼たち」などが織りなす、文明と野蛮、植民地の悲惨、物語を消費する読者の内なる野蛮を考えさせられる作品です。解説も秀逸です。
投稿元:
レビューを見る
難解な小説と言われてましたが、「リーダブルな新訳」という帯の言葉につられて購入した。物語は、面白く、あっというまに読み終えました。昔見た「地獄の黙示録」の映像がちらつきます。
投稿元:
レビューを見る
19世紀イギリスの作家、ジョゼフ・コンラッドの代表作。
船上の場面から始まり、これから大航海が幕を開けるのかと思いきや、そうではなくて男の独白の海に飲みこまれる。印象主義的な描写が難解で、ときどき立ち止まりそうになるが、船の上でマーロウの語りを聞いている一員になったつもりで、その圧倒的な語りのフローに身を委ねた。
コンゴへ赴いた当時のクルツは、高く見積もったところで「普通の天才」でしかなかっただろう。残された婚約者の心の中にいるクルツの姿はまさにそれだ。そんなクルツがコンゴ体験、すなわち「魔境 wilderness 」での体験を経て、例の最期の言葉、「恐ろしい!」に示されるような実存的真実を発見するに至る。この変化こそが「闇の奥 heart of darkness 」に潜んでいるものに他ならない。このドラマティックな変化を、マーロウの語りを通じてわれわれは追体験する。もちろんその衝撃の度合い、アクチュアリティは、クルツ自身のもの、マーロウが感じたもの、そしてわれわれ読者の順に小さくなってしまう。残念なことであるが、われわれも自ら「闇の奥」に足を踏み入れなければならない。
訳者が真摯に取り組んだ仕事なのだというのがよく分かる好訳。黒原敏行は信頼できる訳者である。
投稿元:
レビューを見る
西洋植民地主義の「闇」を描いたジョセフ・コンラッドの代表作。
よくこの本の感想で「結局一番怖いのは人だよね」なんていう安易な結論を見るが、実際に読めば「闇の奥」のさらに奥に広がる先が見えない奥深さがわかる。
ゴールディングの「蠅の王」もあわせて読むと相互に作用し合うものが多い。
誰が読んでも長いレポートが書ける、知的欲求を刺激する本。
光文社の古典新約じゃないと読むのしんどいと思う。
投稿元:
レビューを見る
20世紀の植民地支配・虐殺の歴史を知らないと、話の筋がつかめない。本書の解説を読んで、初めて理解できた部分も多かった。そのうえで本書の内容を思い返すと、かなり考えさせられる。というか、人間の心の奥の闇が垣間見えて、自分にも同じ闇があるかと思うと空恐ろしくなった。新訳版は、やはり読みやすかったように思う。
投稿元:
レビューを見る
未開の河を遡上して、文明から外れかけた西洋人の支配する混沌とした世界に入って行く物語。
『地獄の黙示録』の原案(?)だけあって、手探りで河を進む息苦しさがよく描かれています。
投稿元:
レビューを見る
書評や広告で見かけて気になった本は”いつか読む本リスト”に残すようにしていて、読み終わると削除していくんだが、「闇の奥」は書店で見かけることがなく、かれこれ5年はリストに載ったまま。やっと手に取ったものの、どうしてこの本を読みたいと思ったのか、今では記憶も定かではなく、なにしろ怖い本らしい、という印象だけ。作品が書かれたのは1899年。当時の人たちがアフリカをどう見ていたのか、現実にアフリカで何が起こっていたのか、を考えさせられる一冊。情報化が進む現代に生きる私でさえ、アフリカというのがどんなところなのか、実はあまりイメージできないけれど、「13(古川日出男)」を読んだ後に、この本にめぐりあったというのもきっと何かの縁に違いない。多少は、イメージを膨らませる助けになってくれた気がする。
投稿元:
レビューを見る
船乗りマーロウがコンゴの奥地で見たもの・感じたことを語る話。
のっぺりした密度の濃い闇に足を踏み入れていくような感覚を覚えた。
緩やかな語りに耳を傾けていると、気付いたら足を取られ飲み込まれたら戻っては来られないような、粘度の高い質感に包まれているような感じがした。
黒原氏の訳文が大変読みやすい。
期間を置いてから再読したい一冊。
投稿元:
レビューを見る
橋本図書館にて借出。初コンラッド。『地獄の黙示録』の原作とのことで読んでみたかった一冊。時間をおいて読んでみると違った味わいがありそう。
投稿元:
レビューを見る
初コンラッド。「闇」の中に包み込まれていく語り手が描く人々は、「意味」を持っていない。クルツの婚約者が語ることばすらなんだか偽善的なニュアンスを持って響いてくる。
投稿元:
レビューを見る
たまたま家にあったので読んだ。帯に20世紀最大の問題作とあったが・・・自分的にはそこまでぴんとこなかった。
投稿元:
レビューを見る
コンラッドはポーランドの良家出身で、解説にあるように伝統的な多声楽(ポリフォニー)を受け継いでいるという観点に賛成。驚くべき構成で、終始マーロウの語りの中で展開し続ける。「分かりづらい」原文や訳で有名な古典らしいが、一介の船員が語る物語なのだから、オーラルでしか伝えられないニュアンスがあって自然だし、それを含め表現したとしたら恐るべし。それを差し引いても、語り得ないもの、闇自身を語るような何回も読み返すべき含蓄と深みのある名著。