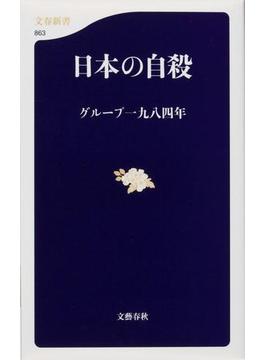紙の本
自殺は何が何でも避けるべし、いわんや自然死など・・・
2012/08/27 00:17
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Fukusuke55 - この投稿者のレビュー一覧を見る
1975年、そう今から37年前。「文藝春秋」に掲載された論文が、昨年あたりから注目され始め、今年の5月に新書として補論、解説とともに再版されたのが本書。
バブルもバブル崩壊も、阪神淡路大震災も、オウム事件も、インターネットも、政権交代も、東日本大震災も・・・これらがすべて起きる前。ここで繰り広げられている議論は、不思議なくらい色褪せていない。
「自殺」とは何を意味しているか、それはすなわち自らが命を絶つ「内側からの崩壊」のことです。
「危機は実は資源の制約、環境の制約などのなかにあるのではなくて、日本人の魂と社会制約の深部にこそあるのである。」(p.47)
私が、これこそ至言と思ったのはオランダの文化史家ホイジンガのピュアリズムについて触れたところで、ちょっと長いですが引用します。「思考力、判断力の全般的衰弱と幼稚化傾向」についてです。読めばハッとするはず。
(幼稚化した精神状況を特徴づけるものは)「適切なことと適切ではないことを見分ける感情の欠落、他人および他人の意見を尊重する配慮の欠如、個人の尊厳の無視、自分自身のことに対する過大な関心である。判断力と批判意欲の衰弱がその基礎にある。このなかば自ら選びとった昏迷の状態に、大衆は非常な居心地のよさを感じている。ひとたび倫理的確信のブレーキがゆるむや、いついかなる瞬間にも危険きわまりないものとなりうる状況がここにある」。(p.78-79)
ローマの衰退を例にとりながら、社会の中に自壊作用のメカニズムが働いており、このメカニズムを除去しないかぎりは、ローマ同様自殺してしまうであろうという著者たちの「予言」が、37年後の今、私たちの目の前で顕在化し始めています。
巻末に、中野剛志さん、福田和也さん、山内昌之さんという論客たちの解説が載っており、同時代を生きてい読者たちに、厳しい問いを突き付けます。
中野さんは、これまでの著作で繰り返し語ってきた「大衆化社会化状況」について、相変わらず厳しい論調で警告を発し、福田さんは「今の日本は「自殺」するだけの勢いもなく、衰えた末に「自然死」してしまうのではないか」と諦観の念さえ滲ませているのでした。
このような日本にしたわれわれ大人は、今、なにをなすべきか!
ここ数か月、私にとっての大きなテーマであるのです・・・。
紙の本
日本の自殺
2015/08/28 09:30
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:パパママ香港 - この投稿者のレビュー一覧を見る
過去に栄えた文明が滅んでいく過程を、日本の現状に照らし合わせ、いかにそれが、日本の現状と類似しているかを詳細に分かり易く説明している。特にローマの盛衰との比較が秀逸である。
投稿元:
レビューを見る
1970年代の論文のリバイバル。ローマ帝国の衰亡を教訓に、1980年代の日本の没落を予想。大衆迎合主義が、文明を滅ぼす。どうも、1970年代から今日にいたるまで、日本は衰亡の過程をたどっているようだ。
投稿元:
レビューを見る
1975年、既に現在の政治の低迷、衆愚政治を予言。
『失敗の本質』も合わせ読み、日本は良いリーダーを育まないのか!
投稿元:
レビューを見る
P162
「グループ一九八四」の論文をはじめて読んだのは、1974(昭和49)年の春、関西から東京に帰る東海道新幹線の車中でした。大阪で会った山崎正和さん(大阪大学名誉教授)から、「これ、ちょっと面白いですよ」と渡されたものが、「日本共産党『民主連合政府綱領』批判」というまがまがしいタイトルの第論文だったのです。執筆者は「共同執筆グループ一九八四」とある。ジョージ・オーエルの近未来小説『一九八四』をもじったものだということはすぐわかりました。(田中)
P163
当時、私は月刊誌『文芸春秋』の編集長をしてましたので、早速その年の6月号に掲載しました。論文が論争を挑んだ「民主連合政府綱領」とは今風にいえば日本共産党の「マニフェスト」です。それまで、野党の中でも独自路線を歩んできた同党が、1973年、他の野党と連携して連合政府を模索することを提案したのがこの綱領でした。(田中)
P165
有史以来、多くの文明において、国民が利己的な欲求の追及に没頭し、難局をみずからの力で解決することを放棄するようになり、しかも指導者たちが大衆迎合主義に走った時、国家が自殺する。ローマが滅んだのはこれだった。いまの日本もローマが歩んだ道を歩んでいはしないか。──というのが「日本の自殺」の発表時の趣旨でしたが、事態はまったく変わらないのではないか。あいかわらず日本人はかつてのローマ人のように「パンとサーカス」に酔いしれてはいないか。(田中)
目次
はじめに
第一章 衰退ムード
第二章 巨大化した世界国家“日本”
第三章 カタストロフの可能性
第四章 豊かさの代償
第五章 幼稚化と野蛮化のメカニズム
第六章 情報汚染の拡大
第七章 自殺のイデオロギー
エピローグ 歴史の教訓
補論 ローマの没落に関する技術史的考察
「グループ一九八四」との出会い(田中健五)
「グループ一九八四」の執筆者(大野敏明)
「日本の自殺」その後(中野剛志)
「自殺」か、「自然死」か(福田和也)
二一世紀の「パンとサーカス」に抗して(山内昌之)
投稿元:
レビューを見る
1975年に書かれたとは思えないほど的確に日本が死に至る要因が書かれている。それは失われた20年を経て現代日本がたどり着いた場所にあまりにも似ている。1975年にはすでに種は蒔かれていたのだろうと思うが、それを見つける目、どうなっていくかを見据える目を持っていた人がいた事実に鳥肌が立った
投稿元:
レビューを見る
グループ1984という大学教授らが集まって1970年代後半にまとめた論文(+当時を知る人たちによる書き下ろしの解説)。
勉強になった点は社会が野蛮化したり幼稚化したり、
政府が大衆迎合化してしまった国家というものは
国外からの攻撃がなくても内部崩壊を起こし、
国家が滅亡(自殺)しまうという事。
本書は将来の日本経済にも言及しているが、
解説者も触れているように、
現在の日本ではインフレが起こっていない。
しかしローマ史を通しての衰亡論はとてもわかりやすかった。
野蛮化はしていないまでも、
現在の日本は幼稚化、政府による大衆の迎合化等
国家が崩壊するポイントが当てはまってしまう・・・。
歴史を通じて国家が崩壊するプロセスを学びたい方におススメです!
投稿元:
レビューを見る
【読書その81】1975年の文芸春秋に掲載された匿名のグループ「グループ1984」の論文「日本の自殺」。発表から47年経過した今年、朝日新聞の主筆である若宮啓文氏が朝刊でとりあげられ、再度注目されている。この論文では、ローマ帝国をはじめとする多くの文明で、国民が利己的な欲求の追及に没頭し、難局を自らの力で解決することを放棄し、しかも指導者たちが大衆迎合主義に走ったときに国家が自殺するという。つまり、あらゆる文明が外からの攻撃ではなく、内部からの社会的崩壊によって破滅するというものである。47年たっても、この論文で書かれるものは示唆に富むものである。
投稿元:
レビューを見る
「自殺者」の話かと思いましたが、読んでみると「社会の自殺」というテーマでした。
この本は、一九七五年に社会に出された論文を基調としており、それに補論と解説を付け加えたものです。
古代ローマが当時たどった国家の社会的崩壊による没落=自殺をとりあげ、現代日本にもあてはめることで警告を発している。
中野さんも解説で言うている通り、この本の主題は、外敵の征服などではなく、国家内部からの人間性の堕落などによる崩壊に焦点を当てていることにある。
よくあるような話やけど、うまくまとまっていて、読んで損はなかったです。
投稿元:
レビューを見る
役員の朝会講話で紹介されたので、読んでみる。
1975年(昭和50年)、文芸春秋に掲載された「日本の自殺」という論文が、37年もたった今年3月の文芸春秋に再掲載されて話題に。
戦後急成長した日本経済が、1970年代にゼロ成長に停滞した。その頃の日本をローマ帝国の衰亡期になぞらえ、「パンとサーカス」を求めて働かなくなった国民の堕落が、帝国を内部から没落させると警告する。
ひどく悲観的にみているが、1975年から先の20年間で日本のGDPは50兆から500兆円に10倍に成長した。
日本の強さは、いつも悲観的に考えて、警鐘しつづけていること、なのかもしれません。
投稿元:
レビューを見る
衝撃的なタイトルに惹かれて購入。
本書は、1975年に「文芸春秋」紙上に掲載された論文である。
2012年5月に新書として出版した文芸春秋社の決断の素晴らしさもさることながら、本書の内容が全く色あせていないことに驚いた。
まず、冒頭の諸文明の没落の原因についてであるが、
『諸文明の没落の原因を探り求めて、われわれの到達した結論は、あらゆる文明が外からの攻撃によってではなく、内部からの社会的崩壊によって破滅するという基本命題であった。〜中略〜それは根本的には魂の分裂と社会の崩壊による自己決定能力の喪失にこそある』
鋭い右ストレートをまともに喰らった 様な衝撃を受けた。
この論点を補足する意味で、古代のローマ帝国やギリシャについてその没落過程を解説する。
そして、日本の未来を予言的に言い当てる一文。
『やがては日本の国民大衆を遊民化し、その家族や伝統的共同体を解体して大衆社会化状況を作り出し、エゴ、悪平等主義、活力なき福祉、怠慢そして画一的な全体主義のなかに社会を解体させていくことになるかもしれないのである。』
続いて、戦後の民主主義を「疑似民主主義」として、本来の民主主義と異質な者としての理論展開を行う。
疑似民主主義の兆候は、その画一的、一元的、全体主義的性向であるとし、その徴候が、多数決原理の誤った認識の仕方に示されているという。
本書では、
『真の民主主義の本質のひとつは、多元主義の承認である。ところが、疑似民主主義は本来、多元主義のための一時的、かつきわめて限定された調整のための手段、便法として工夫された多数決を一元主義、画一主義、全体主義のための武器に巧妙に転用するのである。こうして多数決の決定は、疑似民主主義の支配する集団のなかでしばしば村八分のための踏み絵のような役割すら果たし、多様なものの見方の存在を否定する方向で作用することになる。』
といったように、世論調査などの多数の支持を得たような正義をふりかざして一元的な考え方を強引に押し進めるやりかたへの警鐘ともとれる。
そして、最後には歴史から得られる教訓として、
「国際的にせよ、国内的にせよ、国民みずからのことはみずからの力で解決するという自立の精神と気概を失うとき、その国家社会は滅亡するほかはないということである。福祉の代償の恐ろしさはこの点にある。」
と締めくくる。
2012時点でのホットな話題を1975年に展開していたのは驚きであった。
また、ローマ帝国の崩壊につながった「主食を海外へ依存」については、TPPで揺れる現在に対して、圧倒的な説得力をもってその愚策を否定している。
読んでいる最中、何度も現代に書かれた論文のような錯覚にとらわれるほど、現代性に富んでおり、今読むべき新書といった感想を持ちました。
国内の政治的混乱や政策的な欠陥に憤慨されている方にはオススメの一冊です。
投稿元:
レビューを見る
『日本の自殺』は「グループ一九八四年」と呼ばれる匿名の学者集団が、1975年『文芸春秋』に発表した論文の一つ(香山健一氏単独での執筆との指摘もある)。
文明は内部から崩壊するという基本的命題を提示した上で、ローマ文明の崩壊のプロセスになぞらえて日本社会の崩壊を指摘している。
「豊かさの代償」「幼稚化と野蛮化」「情報汚染」などの自壊作用はどれも示唆に富んでいて、むしろ現在問題とされるであろうトピックばかりだ。
人々が自分で考え判断していく力を失ったとき、社会は生命力を失い自壊に進んでいく。自己決定する力を奪われてはいけないと改めて認識させられる内容だった。
投稿元:
レビューを見る
何となく抱く危機感、それは大小あるとは思うけれど読み手が属する組織で何らかの形で感じている問題意識が可視化されており紛糾間違いなし。
一方、30年経っても変わらぬ課題が存在していることが、時代は繰り返すのだということが、その危機感が諦めや楽観になる。
投稿元:
レビューを見る
ローマ帝国の「自壊」のプロセス。キーワードは「パンとサーカス」。
豊かな暮らしを享受している国民が、「目の前の刹那的な快楽にばかり目を引かれて自分の頭で考えることができなくなった」結果、勤労などの義務も果たさずに、ただその権利(パンをくれ、サーカスを見せろ)だけを主張するようになる。為政者側もエリート意識を失い「衆愚政治」に陥って、大衆化した国民を諌めることも無く、ただ彼らの要求に応え人気を得ることだけにまい進する。結果、経済的にはスタグフレーション(不況下のインフレーション)が「賃金コスト上昇×生産性低下=付加価値を伴わないコスト上昇」により発生する。
翻って、日本でも同様のことが?
筆者の指摘する日本における「スタグフレーションの兆候」は、①資源エネルギーの輸入依存、②環境コスト上昇、③賃金コストの上昇であり、当然現在の日本にも同様の課題はあるのだが、現在の日本は「インフレ」ではなく「デフレ」となっている。今の日本はお金もあふれているが、それ以上にモノがあふれている。この本の想定と現状が異なっている大きなポイントが「グローバル化」であり「円高」、その結果として産まれた「海外製品の大量流入」だろう。
それはさておき、日本の社会は、いや地球全体の社会は、先人たちの活躍によって、豊かになり、便利になり、快適になった。それはそれで悪い事ではないのだが、それを「当たり前のもの」と勘違いしてしまうと、「それらが一体何によって実現されているのか」、或いは「それらを維持するために何が必要なのか」「もっと進展させるにはどうしたらいいか」といったことを考えが至らなくなってしまう。「インプット」(原因)を忘れて「アウトプット」(結果)だけを求める(例えば「ひきこもり」や「アダルトチルドレン」になって、ただ親の家に寄生し続ける、或いは「原発は嫌だ嫌だ」と言って、一方で「増税にも反対」する)ようになってしまう。この「甘えの構造」的な精神状態が、諸悪の根源だ、というのが本書の主張の幹たる部分である。
とは言え、現実には、世の中には豊かさが溢れている。「押しボタン式」な機能製品で溢れている。この状況に於いては、誰もが「これが当たり前」という精神状態に陥ってしまうのだろうか。過去から、人間は豊かさや便利さを求めてきたし、それはいつの時代でも基本的に前進してきた。その時代の人にとってみれば「今が一番便利」だったはずだが、それでも「当たり前だからもういいや」とはならず、「もっともっと」と、進化は止まなかった。人間の欲望の凄まじさである。その点は、悲観する必要はないように思う。****
要は、いつの時代も現状を当たり前なものと受け入れて親世代の惰性でしか生きられないダメな子供やダメな国民はいるものだか、ダメな子供には厳しい親が、ダメな国民には厳しいエリートが、現実をきちんと認識させる必要がある、ということなのだろう。親が子に、為政者が国民に迎合してしまうと、そのサイクルが崩れて社会は自壊へと向かってしまう。
但し、今の日本に言える事は、「この国がなくなるかもしれない」という危機感に乏しいこと���ある。或いは、そういう危機感もとに立ちあがる人材に乏しい事である。現代の日本人には、精神的には何処か「鎖国」したような心持があって、国際的なニュースを「おれたちには関係ないや」と、どこか「蚊帳の外」から眺めている風情がある。それはまさしくあの第二次世界大戦と、その後の「平和主義」を掲げ、日米同盟の下で「骨抜き」にされた「戦後日本」の産物なのだと思う。
祖父の世代は世界大戦に兵士として赴いた。父の世代は、その厳格な祖父の世代、「国体」から敗戦後瞬時に「転向」した祖父の世代に反発し、安全保障や外交面、要は「戦争の記憶」からは一定の距離を置いた中で、結果的に経済的な成長を第一に求めて必死に頑張って来た。そして彼らは、「おれたちは頑張った。子供の世代には少し楽をさせてやりたいものだ。父のような厳格な家長像など真っ平だ。おれたちは父から何もしてもらえなくてもここまで自分の力でやって来たのだから、あえて子供に教育を施す必要もないだろう」という態度で子供に接した。「やさしい父」であり、「仕事優先の父」像であった。そして、その社会での厳しさをあえて子に教えることはしなかった。戦争や外交、安全保障などについては、話題にすらしなかった。
子の世代に起こったのは、「歴史の終わり」だった。自らがよってたつ社会構造そのものは「元からあったもの」「誰かが提供してくれるもの」であり、「批判」や「愚痴」の対象であっても「自らが作っていくもの」ではない。政治や社会には無関心或いは「何でもかんでも批判的」で、ただ経済的には(親ほどではないにしても)、「相対的に悪くない」ポジションを保つことばかりを考えている。
こういう「甘えた日本人」「アダルトチルドレンな日本人」の再生産を少しでも減らしていかなくてはいけない。ただでさえ人口が減少している中で、歩留まりを上げていかなくてはいけない。
もう一点、大きな潮流の原因となっているのが「ソーシャルネットワークサービス」である。「レジャー化」する人間は「無駄だけど楽しい体験」(つまりは「平日体験」ではなく「休日体験」)ばかりを追い求めるわけだが、SNS(特にmixyやfacebook)はまさに「休日体験」の「発表と共有」の場であり、自分の体験だけでなく、他人の体験をも(‘いいね!’や‘RT’によって)「追体験」することで「レジャーの波」は加速度的に高まっていく。つぶやくために休日体験を積み上げ、他人の体験を「追体験」するのにも忙しく、まじめに「平日体験」を考え進める時間すら失われていく。
匿名のtwitterに関しては「平日体験」に関する議論を架空の場ではあるが行えるという点ではまだマシで、実名で「当たり障りのない」休日体験を雪だるま式に共有化していくfaceboookはとても危ないツールだと考えている。
投稿元:
レビューを見る
確かにバブル期以前からこれだけの予言をするのはすごいけれども、全くといっていいほど根拠と解決策が語られていない。