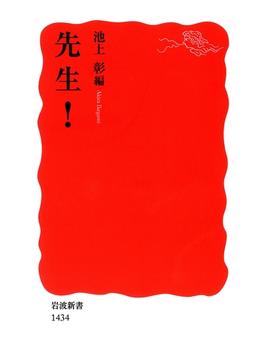先生だけで本を作った
2023/09/30 14:41
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:a - この投稿者のレビュー一覧を見る
池上彰さんが呼びかけたとてもゴジャースな27名による先生についてのエッセイ集です。27名の名前を聞いただけで、買ってしまいそうになります。それが岩波赤版であればなおさらです。
切れ味さまざまに鋭くて。
2016/12/04 18:10
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:うりゃ。 - この投稿者のレビュー一覧を見る
池上氏が編者となったエッセイ集。
「教育はきわめて社会的事象である」とはデュルケムの言葉だったか。
教える人間にならずとも、教えられる人間にならないことは難しい現代日本において、教育、もっというと学校教育とのかかわりというのは個々人のアイデンティティの大きな部分を占めているだろう。
そこをざっくりと切り取る27人の切れ味はメスやカッターだけでなくのこぎりやナタにも似ていて、どれもこれも鋭い。
投稿元:
レビューを見る
≪目次≫
はじめに
センセイの最期(しりあがり寿)
西日の渡り廊下で(天野篤)
想像力は無限だ(岡野雅行)
「歌の時間」(稲泉連)
先生がくれた 光(押切もえ)
先生は…(関口光太郎)
大切な「症状」(田中茂樹)
手紙(増田ユリヤ)
柔道とは?(山口香)
中学・高校生に願うこと(柳沢幸雄)
巨大な疑問符を与えてくれた(鈴木邦男)
実はすごい、日本の教育(パックン)
「抗う」こと(安田奈津紀)
学びの同志おっちゃん(市川力)
八十歳を超えた中学生(太田直子)
紅茶の味(李相日)
ことばの裏にある子どもの声を聞く(渡辺恵津子)
「消費者感覚」に立ち向かう(武富健治)
作る、壊す、作る(武田美穂)
人生最初の「先生!」は…(姉小路祐)
逃げろ!逃げろ!(石井志昂)
先生と子どもの関係(鈴木翔)
色えんぴつ(乙武洋匡)
詩が開いた心の扉(寮美千子)
自分の物差し(山口絵理子)
とらわれちゃだめだ(平田オリザ)
(インタビュー)学問を武器にして生徒とわかりあう(太田光)
≪内容≫
”先生”をキーワードにしたエッセイ集。教師の私が読んでいて、応援になるもの、批判になるもの、指摘、共感、感動、勉強…いろいろなことを考えさせられました。生徒・児童の「学ぶ」ことを如何に手伝うかが先生(教師)の役目だと思います。このエッセイ集は、そうしたことに日々努力している"真面目"な教師への応援メッセージだと思います。
投稿元:
レビューを見る
池上彰さんの名前だけ見て、ぱっと買ってしまったんだけど、池上彰さんが編集した、いろんな方のエッセイ集+対談です。
厳しい状況と言われる日本の教育。高いレベルをかろうじて維持するのは現場の先生たちの頑張り。先生への期待の高いが故、批判も高まる。
そんな先生たちわ励ます本を世の中に出したい、
と、呼び掛けられてできた本だそうです。
私自身は教員ではないし、子供もいない。軽い気持ちで読んだのだけど。
でも、安田菜津紀氏の「今の教育現場では、なにかに『抗う』ことはほとんど教えてくれない」という言葉には、はっとした。
寮美千子氏の、奈良少年刑務所の少年が書いた詩の話では、少しふるえた。
投稿元:
レビューを見る
自分にこのテーマがあたえらえたら、はたしてどんなエッセイを書くのだろうか。書く人の年代によって大きくトーンが変わるのではないだろうか・?「先生」という存在自体がとても微妙にむずかしい時代なのですね。
投稿元:
レビューを見る
・読もうと思ったキッカケ
先生の役割って?教師の役割って?
ふと、疑問に思った。自分自身の経験と照らし合わせてみても良さそうだと思い、購入。
・メモ
誰にとっても良い先生、悪い先生というのはいるだろう。
何を以って良い/悪いとするのか、一概に決めてしまうのは、あまりにも乱暴であり、勿体無い。
先生の言葉がいつまでも残る、気になる、その結果として人を創る。いつも自覚していかねばと思う。
投稿元:
レビューを見る
先生というお題でそれぞれがそれぞれの視点で書いている。教育に対して消費者的な姿勢で向き合う感覚に浸食されている社会の話や、学びに対して主体的に臨む話などが印象的だった。
投稿元:
レビューを見る
涙腺を緩ませる話がちらほらあった。
全体として心に残る「先生」の話。
うまく構成されてると思う。
池上さんがただ集めただけでないことがわかる。
投稿元:
レビューを見る
良書。教育の根幹問題を考える教師論の一冊。教師にとっては聖職の再確認が、読者には教育の消費でなく創造の覚悟、先生応援する気持ちが湧いてくる。少年刑務所の詩の授業、涙が。
投稿元:
レビューを見る
「先生!」というテーマで作家、映画監督、研究者、教師など27名が書くエッセイ集。
稲泉連(ノンフィクション作家)が紹介しているスギセンはとっても魅力的。とくにテストに点数をつけず、丸か花丸のみ。保護者からの抗議には「子どもたちは花丸が大好きなんです!」と言い放つ。「小学校を卒業すれば、ずっと厳しい競争の中を生きていくことになります。せめて今のうちだけでも、そうではない世界に触れさせてあげるべきだと僕は思います(p.23)」というスギセンはかっこいい。
増田ユリア(ジャーナリスト)の体験談も興味深い。いじめられているA子を会議で話題に出しても「自分の指導力がないことを公にしていることだ」と一蹴されてしまう。ある日、A子と修学旅行に行きたくない生徒がA子を囲んでいた。著者はA子の「修学旅行に行きたい」という思いに次のようなこという。「だったら絶対に行かなきゃダメ!あなたたちも軽井沢じゃなくて一緒に行かなきゃダメ!みんなで行かなきゃ日本史の単位出さないからね!(p.62)」
安田菜津子(フォトジャーナリスト)は高校生の時にストリートチルドレンやトラフィックチルドレン(人身売買さられた子ども)に取材しに行く派遣プログラムの経験を語る。その経験から学んだことを次のように記す。
カンボジアで学んだことの一つ。それは「無知」が人を傷つけるということだった。相手の抱える問題を知らないが故に、言葉で、行動で、その人のトラウマに触れてしまう。また知らない人がたくさんいるが故に大きな問題が黙殺される(p.106)。
乙武洋匡(作家)は教員時代子どもたちに「みんなちがってみんないいんだ」ということを伝えていた。教師の仕事は成果が見えにくい。勉強面はテストで結果がわかる。だが道徳や生徒指導などは効果がわからない。「みんなちがってみんないい」も後者に値するだろう。ある日著者のクラスで文集をつくるという話になった。そのタイトルは「色えんぴつ」だという。理由を聞くと「色えんぴつって何十色もあるのに、全部ちがう色でしょ。このクラスもいろんな人がいて面白いから、『色えんぴつ』がいいかなと思って……(p.191)」.。こういうときに「やっててよかったなー」と思うんだろうなー。
(まっちー)
投稿元:
レビューを見る
いろんな人の先生論。
先生に期待する人が多い。先生は特別な人間でないと思いつつも特別を期待する複雑な気持ちか・・・エライ人というのを身近に感じていたいという欲求があるのかも?
投稿元:
レビューを見る
ジャーナリスト・池上彰が呼びかけ人となり、「先生!」のひと言で思い出すエピソードを各界の著名人27人が語ったもの。
教員だけではなく、漫画家・外科医・町工場のおやじさん・作家・モデル・アーティスト・柔道家・映画監督などなど、多様な経歴を持つ人が集まっている。
まずはこの人選がおもしろい。
多彩な人々を集めたことで、通り一遍ではない、さまざまな角度から「先生」と呼ばれる職業にライトが当たるエッセイ群になっている。
縛りは文中に「先生!」という呼びかけの言葉を入れることのみ。
1編1編は短いので、空き時間にも読める。
そして自分にとって「先生」というのはどういう存在だったかな・・・と考えるきっかけにもなる。
個人的に印象に残ったのは、町工場の岡野雅行、一水会の鈴木邦男、詩人・作家の寮美千子の三氏のエピソードだろうか。特に寮氏の『空が青いから白をえらんだのです―奈良少年刑務所詩集』(新潮文庫版もあり)はちょっと心に留めておきたいと思う。
1編は漫画、25編はエッセイだが、最後の太田光(爆笑問題)のみ池上彰がインタビューする形になっている。太田さんという人は、何を語っても太田さんだなぁ・・・。非常に好きであるとか共鳴するとかいうわけではないが、このブレない個性はなかなかすごいと思う。
投稿元:
レビューを見る
池上彰の呼びかけに27名が『先生』について書いたエッセイ集。
本書の中で池上さんは、教育とは自分が自分であること、社会の中の一員であることを認識できる力を身につけてもらうことだと思う、と語っている。
ネルソン•マンデラは、「教育は世界を変える最強の武器です」と語ったそうだ。
27名の中で印象的だったのは、柔道の山口香さんが学んだこと。東京の有名私立•開成の校長が開成で教えている教育の根本のこと。フォトジャーナリストの安田菜津紀が語る「抗うこと」。
『鈴木先生』の武富健治さんの消費者的感覚に立ち向かう考え方。少年刑務所で詩を教えている人の話。
『先生』と名のつく職業の人はぜひ読んでみて下さい^_^
投稿元:
レビューを見る
いろんな人たちがそれぞれの先生観を綴っているので興味深かった。短くて読みやすいが、もう少し読みたかったという話もあった。
投稿元:
レビューを見る
「先生」ということばから喚起されるエピソードを押切もえ、山口香など作家、タレントたち27人が書き綴っている。担任のことを書く人もあれば、教えた経験のことを書く人もある。まとまりはないが、読みやすい。