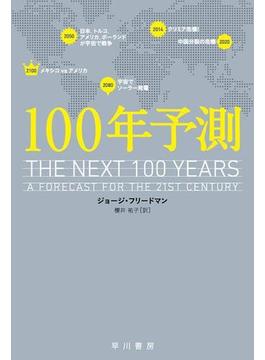1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:たろう - この投稿者のレビュー一覧を見る
これからの百年の歴史を予想するが感覚で想像するわけではもちろんなく、筋道立って論を進めていく
この本はその予想が当たっているかどうかではなく、もちろんそれは興味深いが、その予想にいたるまでの論理に焦点がある
その論理というのが地勢学。人間の価値観、政治家の気まぐれでなく、国家の置かれた地勢的環境、そこから導かれる戦略こそが百年変わらない、動かしようのない事実、世界観である
アメリカが弱体化していると言われて久しいけれど、それは非常に表面的なことだとこの本を読むと考えるようになる
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:k - この投稿者のレビュー一覧を見る
ウクライナ情勢、中近東情勢を見るとあたっている。東アジア情勢もあたるかもしれない。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:papajunny - この投稿者のレビュー一覧を見る
100年先のことなどわからない。著者もそれを百も承知で書いています。
この本は100年先までの見通しを学ぶためのものではないと思うのです。地政的な知見に現世界の動きを加味して将来を構想するという新しい手法を展開しています。そして描かれた将来の世界の在りようは他では見られない斬新な視点を提供していると思います。50年後に日本がアメリカを相手に再度戦争を仕掛けるなどと考えている日本人は今はいませんが、それを可能性としてまじめに論じています。考えたことがないことを考えさせられる、それがこの本が提示するダイナミズムです。
終盤で、100年後、アメリカはメキシコとの戦争を行うがその戦いには勝てないという部分など、誠に納得させられる話も多く、固定観念に凝り固まってしまっていた私にはとても刺激となる本でした。
ここに書かれていることを覚えるのではなく、この本から学ぶことが大事
2017/05/09 21:37
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コスモス - この投稿者のレビュー一覧を見る
一部の著名人が述べるように、インターネットの普及により国民国家という意識は薄れ、国民国家間の戦争というよりは、国家対テロというような構図にシフトしてきていると思います。
そのため、この先100年の国家間のパワーバランスを地政学的に分析することが、果たして役に立つのかは正直疑問に感じています。
しかし、依然として国民国家というものが世界を動かしている事は事実であるので、少なくとも近い将来については、地政学的に物事を考える必要があると思います。
本書に書かれていることが必ず当たるとは思っていませんが、この先、世界がどのように動くのかを考える方法を学ぶことはできると思います。
未来予測の例として
2019/02/06 01:13
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:H2A - この投稿者のレビュー一覧を見る
アメリカで有名なシンクタンクの代表が地政学に依拠して今後起こりそうな未来を予想していく。それによると、アメリカの時代は実はまだ始まったばかりで、21世紀こそアメリカ時代が続く。中国は張子の虎でいずれ地方の軍閥に分裂し、ロシアも一旦は復活しヨーロッパに挑戦はするが結局は没落する。台頭するのは日本、トルコ、ポーランド。日本とトルコは同盟を結んで宣戦するが、結局は宇宙を制したアメリカにはかなわず、地域大国に甘んじることになる。勝者のポーランドもアメリカのパワーバランス政策によって勢をそがれる。次の世紀にアメリカを脅かす存在になるのはメキシコである。後半は未来予測というよりSF小説のようだ。予測する著者の方法論そのものが非常に刺激的でおもしろく、予測の当否などそんなに気にならない。
投稿元:
レビューを見る
非常に興味深いです。
当然ながら、細かいところまで予測できるわけではありませんが、それでも、おおまかに「こんな風に推移するだろう」と言う予測が述べられています。
どのくらい、その予測が当たるかは、未来の人々の評価に依存するしか無いですが、大体のところは、当たりそうな気はしますねぇ。
気になるのは、日本の件。この予想のようなことにならないと良いんですが、何となく、この予想に近づいていくような気がしてなりません。
投稿元:
レビューを見る
地政学の視点で今後の世界情勢を鋭く分析した本。2014年のクリミア紛争的中!と帯や表紙に書いてあるので、人によってはA・トフラー系の未来予測本だと誤読する可能性がある。しかし、この本の本質は、欧米人がどのような考えに基づいて、どのように振舞うのか、その思考回路を把握することにある。アメリカが世界をどのようにとらえ、どのように考えているのか、その一端を知るのにふさわしい本。
投稿元:
レビューを見る
題名道理の内容の本だった。地政学に基づいて語られる未来の予測は説得力のあるものだった。特に近い未来、2020年代についての内容は過去から現在への時の流れを考えると、とても説得力があった。
読んでいて興味深く、面白かった。今後、新聞やニュースで国際情勢を知る時、この本のアでプローチの仕方で考えたり、この本の予測と比較していきたいと思う。
投稿元:
レビューを見る
思ったより面白かった。
21世紀の100年間がどのようになるのかを
地政学的見地(これがよくわかりませんでしたが)
から予測する内容。
21世紀はアメリカの時代。第2次世界大戦やEUまでは
ヨーロッパの時代で、アメリカはまだ若くて粗暴な国。
そのアメリカに挑戦する国。挑戦させられる国が
かわるがわるでてくる。
まずはイスラム、まとまりがなく自壊していく。
その次はロシアと中国。現状の経済や技術に固執し
アメリカの技術にまけてしまう。また民族問題や
それを統制している機能が弱体しロシアと中国は
分裂する。
その分裂した中国とロシアの周辺を力に変えていく
日本とトルコとポーランドがアメリカとの関係の
なかで日本とトルコと(ドイツ)がまたアメリカと
戦争をおこす。その開戦の仕方や結末は第2次世界大戦
とほぼ同じ流れが起こっていて。。
最後には、アメリカのひざ元であるメキシコと
アメリカの対決になる。
投稿元:
レビューを見る
表題の通り、今後100年の世界史を予測している。
本作の冒頭でも著者が記載している通り、Detailの部分は正確ではないかもしれないが、大筋では悪くない予測を与えると考えているという。
未来に発生する事象が何の制約条件もないのであれば、科学的な予測は不可能に思えるが、未来は過去という極めて強い拘束を受けるため、注意深く考察することにより、大筋は予測できるのであろう。
ちょうど、チェスの名手同士が対戦した時に、コマが盤上全て動くことはできても、最善手という意味では実はありうる手数はそれほど多くは無いという比喩が成り立つように。
ただし、どんな科学でも100年後は眉唾ものであると思われる。
例えば、日本のエネルギー予測を良く見受けられる(特に原子力!)。が、100年後となると誤差の影響が強く伝搬するためもはや何でもありになってしまう。
とすると、重要なのは直近の数十年(~50年)の挙動予測であると思う。
筆者は、ずば地政学的な意味では、アメリカが相変らずヘゲモニー的な地位を維持すると予測している。
ただし、対抗馬がありそれは(ロシアや中国ではなく)トルコと日本、時点でメキシコであると予想する。
なぜの核心部分は本書を読んでもらうとして、トルコはわかるとして、日本が出てくるのは日本人として誇らしいようで、ホントか。と自虐的になってしまう。
長期的な不況、歪んだエネルギー構造による国際的な競争力のなさ、人口減少、年齢構造による労働力の減少等、マイナス要素を挙げればキリがないが、プラス要素はパッと思いつかないし。
筆者のロジックは、アメリカは南米、ヨーロッパを軍事的に制圧できるがアジアまでは手をのばすことができない。かつ、中国、ロシアは歪んだ資本主義により自然と解体するので、そのスキに日本とトルコが台頭するしかないじゃん、というもの。
その後は、日本がアメリカに戦争をしかけるというシナリオを紹介しているが、なかなかあり得なさそうなシナリオだと思う。
日本の安全保障はどこの国にしてもらっているのだろうか。それを振りきって、自国で軍事力を持つ勇気がこの国にあるのだろうか。。集団的自衛権の憲法解釈でこんなに騒がれているのに。
いずれにせよ、将来の予測をするのは大変な努力をしなければならないし、将来、本書の正解がはっきりとわかるという点で著者のリスクは大きい。
それを承知で、このような大胆な本書を書き上げたのはやはり作者の力量があってこそなのだろう。
50年後にまた本書を読むとしよう。
投稿元:
レビューを見る
おもろい。ぶっとんでるけど、ありえなくない範囲と思ってしまった。
主題は未来予測だけど、やはり過去の分析から立ててるだけあって、いちアメリカ人から見た●●人観みたいなものもうかがい知れてすごく良かった。
投稿元:
レビューを見る
地政学と経済予測の本ではあるが、とても読みやすい。アメリカびいきな部分も多いような気もするが、作者曰く”こういう予測は当たらない”らしい。読み物としては、未来から近未来100年を振り返った書き方になっているのでSF的な読み方もできる。ロシアのウクライナ侵攻は必ずあってその後ロシアは衰退するとの記述があった。読んでいるときに実際に起こったのでびっくり。
投稿元:
レビューを見る
アメリカは若い国で繁栄はこれから。筆者はこの本を臆面もなく書けることで、はからずも母国が若い国であることを実証している。また若さ故に大胆な予測も。この単純さにこそ学ぶべきか。
投稿元:
レビューを見る
地政学的に極合理的に考えれば、2050年頃にはアメリカ・ポーランド・日本・トルコは戦争をする。日本は武器を持つことを避けられない。21世紀は相変わらずアメリカ中心の世界である。海を支配しているから。のちにアメリカは宇宙を支配することで世界を支配する。21世紀後半には発電は宇宙で行われる。そんな、マクロの、ありそうなシナリオを描いている本。そしてそれはちっとも非現実的な話でもなさそう。そこでわたしはどう生きていこう。
投稿元:
レビューを見る
地政学的な予測本。
序章に書いてある手法の説明がわかりやすく、この本が単なるSF本ではない、信頼性の高い本であることを教えてくれる。そこには、
地政学的な予測はチェスに似ており、国家の行動はチェスの指し手と同じように非常に合理的である。無限の選択肢がありそうで、実は打てる手はかなり限定されている。
「統治行為とは、ほとんどの場合必要かつ論理的な次の一手を実行に移すことに過ぎない。」つまり、誰が指導者になるとか、指導者が何をするとかではない。戦前の日本は、資源の問題から海外へ行くしかなかったし、ヒトラーのドイツはベルサイユ条約の賠償金の問題からフランスなどに出ていくしかなかった。日本にヒトラー的な指導者がいなかったのは、そういうことだろう。
こういう手法で21世紀を描く。
面白い。そうなりそう。
ウクライナ問題はその通りになったし。
日本は宇宙で「真珠湾攻撃」をして、また負けるって。