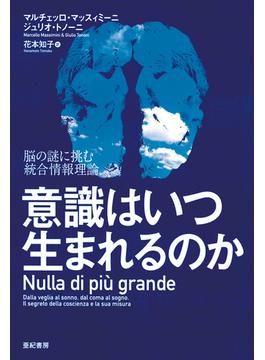意識研究の最前線であり、現在の科学で最も有力な仮説
2018/05/10 09:30
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:病身の孤独な読者 - この投稿者のレビュー一覧を見る
人間の意識の謎に科学的に取り組む世界的に有名な神経科学者のトノーニらの研究をわかりやすく解説した書籍。トノーニらの研究は、Science誌などをはじめとした一級の学術ジャーナルにも掲載されているくらい現在の意識研究を引っ張っていると言っても過言ではない。人間の心(意識)の有無を情報学の知見を取り入れて客観的指標を作成しようとするトノーニらの研究を一冊で知ることができる名著だと思われる。科学に興味を持つ読者と心や意識について語る人にとっては、必須の書籍である。
意識について探るサイエンス・エンターテインメント
2015/11/04 02:20
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:nori*tama - この投稿者のレビュー一覧を見る
意識とはどのように生まれるのか、意識があるものとないものの違いは何かなどの疑問について総合情報理論を基に解明していくサイエンス・エンターテインメント。
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:7013 - この投稿者のレビュー一覧を見る
まだまだ知らないことも多いことに気が付かされた。様々なことについてこれまで以上に知識がふえることだろう。シンプルに書かれている点もよかった。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:L療法 - この投稿者のレビュー一覧を見る
大変読みやすい、意識と、脳についての本。
中国語の部屋のはずが、日本語の部屋とか、日本未公開映画のタイトルが、日本語に訳されてて原題がわからないとか、本題と関係ないところが気になるものの、大変読みやすくわかりやすい。
意識を確認することの困難さなど、様々な謎を、追求していく、謎解き作品。未解明なことは謎として残るので、ミステリよりは、SFに近いと思われる。
投稿元:
レビューを見る
意識の存在について科学的にアプローチした作品。
誰でも一度くらいは、緊張で頭が真っ白になってしまったり、前触れもなく恋人から別れを告げられたり、意識を失いそうになった経験はあるハズだ。でも本作はそんなメンタルな意味ではなく、もっと生理学的な意味合いでの「意識」がテーマである。
不幸にも大きな事故に遭い昏睡状態となってしまう人がいるが、実のところ本当に意識がないのか、それとも外部からの刺激に反応出来ないために、意識がないと診断されてしまうのか、そもそも意識があるというのはどのような状態を示すのか、という疑問にも迫っている。
本作では「統合情報理論」という、意識の謎を解くカギとなる理論に関して、TMS脳波計という新しい測定装置を使用した、今まで不明瞭だった意識レベルの研究成果が紹介されている。今まで脳科学がテーマの書籍はわりとよく読んだが、ここまで生物の意識という事象に特化している作品は、意外と少ないのかもしれない。
人間の意識を解明するという行為は、人類が今まで歩んできた道を再び辿るような、気が遠くなるほど地道な営みであると思う。このような研究が、回復の見込みがなかった重篤な患者たちを、再び社会に復帰させるための大きな一歩につながることを期待したい。
投稿元:
レビューを見る
統合情報理論と聞いてもピンとこないかもしれないけれど、人にあってコンピュータにはないと言われる「意識」について、わかりやすく解説している。
「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」
この本を読むと自分なりの答えが見つかるかも。
投稿元:
レビューを見る
医学的な臨床事例などから意識を考察し、数々の臨床における脳波の動きと情報理論を結びつけ、意識とは「多様性があって、統合のある」として考察を続けるも結論的には哲学なども引用し、やや曖昧な形で終わる。脳の謎が完全に解明されるのはまだまだ先のようです。
投稿元:
レビューを見る
素人には難解な内容を『潜水服は蝶の夢を見る』での閉じ込め症候群や、ネーゲルの『コウモリであるとはどのようなことか』などを例にあげるなど、人文学的アプローチで著者は軽快に解説してくれている。訳の日本語は柔らかくて優しい。どうやら翻訳者はタブッキの研究者のようだ。
投稿元:
レビューを見る
冒頭に「『意識とは何か』という哲学的な問いには答えない」とあるように、「意識」が発生するための必要条件について考察する本。なぜその条件が整うと「意識」が発生するのか、や「意識」が発生する過程といった内容については触れられないため、「意識」の持つ神秘性に興味を持ってこの本を手に取ったとすれば、肩すかしを食うかも知れない。
しかしこれまでは可視化できなかった「意識があるかないか」を外部から観察できるようにする手法は見事というほかなく、この方向で研究が進めば今回この本で触れられなかった上記の内容についてもいずれ明らかになるのではないか、という希望は充分に持てる内容だった。
著者の今後の著作にも注目していきたい。
投稿元:
レビューを見る
「意識」とは何か。何が「意識」をつくるのか。「意識」と「無意識」の違いは何か。世界的な脳科学者が「意識」の正体を解き明かすサイエンス・ノンフィクション。
著者が提唱する「統合情報理論」によると、「意識」とは、主に大脳において、高度に専門化したニューロンが相互作用により無数の選択肢を組み合わせたり排除したりして、最終的には統合された情報として認識することをいう。例えば暗闇にいる人は、「明るい」だけでなく、「赤い」「星空」「音」など、膨大な数の「闇ではないもの」を情報処理している。逆に小脳のニューロンは連携せず、単独で特定の処理のみを行う。これにより、例えば瞬きなどの習慣化された「無意識の行動」が可能となる。
200億個のニューロンによる「多様な相互作用と統合」の「奇跡的なバランス」がもたらす「選択肢の広さ」を「φ(ファイ)」という情報量の単位であらわし、この値が大きければ、たとえ「植物状態」で身体反応がない人であっても、「意識がある」可能性が高いことが実証されている。専門書ではなく、一般読者向けに平易に書かれており、読み物として純粋に楽しめる。何より、脳というシステムが、極めて優れた組織行動によって機能していることに驚かされる。知的好奇心が刺激される一冊。
投稿元:
レビューを見る
用語も平易で、文章もこなれていて、かつ構成もミステリー小説を意識して書いたと著者が言うように、疑問とその回答を対置する形で書かれていて、この種の科学読み物の中ではずば抜けた読みやすさだと思う。
ただ、結局のところ本題の意識が何かということに関してはよく理解できなかった。
構造的な話、情報量の話、情報の統合の話というヒントは提示されているが、結局結論としては解明されていないわけで、その点がちょっと読んでいて歯がゆいというか、物足りない気がした。
まあしょうがないと言えばしょうがないが。
投稿元:
レビューを見る
意識を説明する理論として、統合情報理論というものが提唱される。
「ある身体システムは、情報を統合する能力があれば、意識がある」というもので、これ自体は目新しいものではなく、前半はやや退屈。
後半はとたんに面白くなってくる。
この理論の一つ、重要な点は定量化を可能にしている点で、系の複雑さがΦ(ファイ)として測られる。Φの具体的な計算法は「難しすぎるから」ということで説明されていないが、経路の情報を含んだ組み合わせの數のようだ。なので、小脳のようにニューロンの数こそ多いが、小脳皮質間の連絡線維というものはなく、独立したモジュールが集まったような系では低くなる。また、モジュール間の連結が多ければいいというものではなく、全てのモジュールが同じように繋がった系では、結局はどのモジュールが興奮しても全てのモジュールにそれが伝播するだけなのでやはりΦは小さくなる。ある程度のランダムさをもった結合の系でΦは大きくなるようで、脳のように層化していたり半球にわかれている方が値が大きくなる。
もう一つは、実際に理論を確かめているところで、TMSによる刺激後の脳波をとり、意識がある場合はその棘波が脳全体に複雑な形で広がるのに対し、意識がない(睡眠、昏睡)の場合は同じ波形が広がっていくだけであることを確認している。これもΦの値が小さい系(睡眠・昏睡)では同じ波形が伝播するだけで、理論とよく合っている。
また、われわれがコンピューターに意識がないと考える根拠は、われわれ自身がそれを組み立てたから、ということにすぎない。その動作の秘密を知り尽くしているからだ、というのもナルホド、という感じ。やはり意識は何らかの創発性によって生み出されるもので、そのためにはよく分からない部分が残っていないとダメなんだろう
投稿元:
レビューを見る
分割脳に芽生える二つの意識、小脳よりも少ない細胞数で意識を生じさせている大脳の謎、それらの事実から導かれる結論に納得させられた。
投稿元:
レビューを見る
シナプスの量からいえば小脳のほうに多いのに、なぜ意識は大脳にしか生じないのか。重要なのはたんなる複雑さではなく「システムが抱え持つ潜在的なレパートリーの大きさ」なのだと説く。人間が部屋を「暗い」と言うとき、そこには「明るくない」だけではなく「赤くない」「星空ではない」「音がしない」といったあらゆる「ではない」が含まれている。意識とは、こうしたありとあらゆる情報が統合されたものでありるのだという主張だ。
大脳は左右の半球に分かれていて、その間で対話をすることで複雑性が高められている。あらゆる情報からひとつのものを取り出すことと平行して、わずかな情報から多様な可能性を引き出すことが、「意識」の条件であり、結果でもあるということだろうか。
視聴覚器官からの情報が脳みそをぐるっとまわって、いろんな可能性のなかからひとつを取り出してくるには、0.3~0.5秒ほどかかるそうだ。「自由意志」仮説への疑いとして、「手を伸ばしてアレをとろう」と考える0.3秒前にはすでに手には信号が発せられているというものがあるが、最初のピン!という信号から「意識」のほうが遅れて形成されるとすれば、頷ける話だと思う。
投稿元:
レビューを見る
意識や自由意思とは一体なんなのだろうか。こういった脳科学系の本は好きで色々読むが研究や実験が進めば進むほどに答えが近くなるというより遠ざかるような気さえする。それでも非常に惹かれる分野である。睡眠時の意識についても詳しく書かれているが興味深い。そもそもなぜ人間は寝なくてはいけないのだろうか。なんとなく読みながらレインボーマンのヨガの眠りを思い出した(レインボーマンは力を使い果たすと身体が石化して5時間仮死状態になる)。面白い本でした。