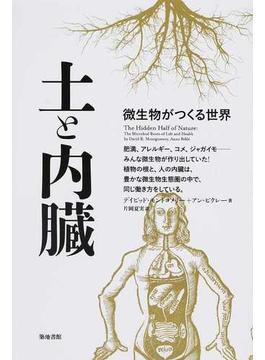紙の本
菌(微生物)と、我らとの関係を知ったら、イヤな人に「〜菌」なんて言うイジメはしなくなるかも。
2017/01/26 03:13
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オカメ八目 - この投稿者のレビュー一覧を見る
菌(微生物)と、我らとの関係を知ったら、イヤな人に「〜菌」なんて言うイジメはしなく成るかもしれない。 その位、微生物と我らとは、関係が深い事を示してくれる本。 目には見えず、その存在もなかなか感じ難いが、その微生物が発する「言葉」に耳を傾ければ、我らに、「花粉症」とか「アレルギー」とか、下手すりゃ「自閉症」とか「癌」とかと言う重たいメッセージを厳しく伝えてたりする。 我ら人間を含む動物は、皮膚と腹の中に、植物は自分の根と、その根の周りの土とに、それぞれ「菌」を、それとは気付こうが、気付くまいが「飼って」いる!
本書を読んでいて、かつて庭で「泥遊び」をしてて、木の近くの土を掘った時に嗅いだ、なんとも言えぬ、いい匂いを思い出した。 あれは「根圏」の「菌」の活動によるものだったんだと判った。 「微生物」の活動は実に静かだが、それを知ると、なかなか終わらない、静かなワクワク感のようなものが、染み込んで来る。 どっから読んでも面白い。 それらは、「悪い菌を無くす事」に熱中してる人達には、なかなか判って来ない事のようだ。 「微生物」は一筋縄では、判らない、奥の深い存在だ。 なお、「腸内革命」と言う本も合わせて読むと、異口同音の事を言っている所があって、興味が尽きない。
紙の本
微生物パワー
2024/02/18 01:00
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:DB - この投稿者のレビュー一覧を見る
地質学者の夫デイブと生物学者の妻アンが微生物について書いた本です。
まずは彼らが手に入れたシアトルの新居の荒れはてた庭を植物の生い茂る庭へと変える話で始まります。
ガーデニングの夢を持っていたアンが木を植えようと苗を取り寄せて穴を掘ると、庭の土は氷礫土という岩のように固い土だった。
表面をすべてはがして新しい土を入れるのは予算的に難しく、臭いの問題で鶏糞を撒くプランは却下された。
そこでアンがはじめたのは、木くずや落ち葉をマルチにして土中の水分を保つようにすること、そしてただでもらってきたウッドチップや落ち葉、コーヒーかす、草食動物の糞を堆肥化したものを庭に撒いて有機物を足していった。
さらに堆肥中の有益な微生物を培養して撒くことで、庭の土は濃いチョコレート色に変わりミミズや甲虫、昆虫、鳥たちと庭の住人がどんどん種類を増していく。
五年の努力が実って庭には植物が生い茂り、夏には野菜がたくさん採れるようになったそうですが、その原因となったのは微生物の働きだった。
ここで微生物の歴史をおさらいしてリンネやレーウェンフックの業績が語られる。
コッホやパスツール、ジェンナーの話も出てきて、クライフ著『微生物の狩人』を復習できました。
興味深いのは微生物が遺伝子情報を種を超えて容易に受け渡しするという性質だ。
そして化学肥料は一時的に生産性をあげることはできるが、土壌はむしろ痩せていくため長期的には有機物による肥沃化の方がよいということも知った。
まあベランダのプランターに応用できるかは別問題ですが。
後半ではアンがHPVの感染による子宮頸癌にかかり手術する話で始まります。
病気をきっかけに食生活の見直しを迫られたそうで、砂糖やカフェイン、アルコールを控えて野菜が半分、精白されていない穀物を少しと豆のような植物性のタンパクをメインに肉はなるべく控えめに、そして一日三食をきちんと取ること。
わかってはいてもなかなか難しいのが食生活の改善ですが、実行したら血糖値や血圧、コレステロールが下がって肥満が改善されるそうです。
人間はもちろん生物の内部も環境にも微生物があふれているが、本書では特に大腸に住む細菌群に注目している。
慢性の腸疾患の患者に健康な人の便を移植すると疾患が改善するという話は十年くらい前から聞いていたが、腸内フローラ移植と言葉を変えても抵抗感がぬぐえない。
微生物が主体なら必要な微生物だけ培養すればいいとも思うのですが、複雑で多種類の腸内フローラを再現するのはまだ難しいようです。
大腸に住む菌のためにもプレバイオティクスとプロバイオティクスを取ることの有用性が説明されていた。
微生物は身体を守ることもあれば病気の原因となることもある。
そんなミクロの世界にもっと目を向けて、うまく付き合っていけるようになればと思います。
投稿元:
レビューを見る
思い切った邦題だが、原題は"The Hidden Half of Nature- - - The Microbial Roots of Life and Health"。「自然の隠された裏側。微生物が担う生命と健康の根幹」といったあたりか。
土にも生物にも元来、多くの微生物が住み着き、「共同体」としてバランスを取りながら存在してきたのに、近年、前者は抗生物質や食習慣、後者は化学肥料や単一作物の連続栽培などで、微生物叢が破壊され、あるいは単純化されてきている。現代病の頻発や収穫量の減少はそこから来ているのではないかというのが全体としての趣旨である。
これにプラスして、微生物学の歴史も記載される。
微生物学は専門外である学者夫妻が、専門用語や専門的すぎる言い回しを排して、わかりやすく解説するというのがミソで、読みやすく、興味深い読み物となっている。
執筆のきっかけは妻がガンになったこと。
宣告後、自らの食生活を見直し、また趣味の庭いじりに奮闘する中で、世界の中で微生物が果たす役割の大きさに気付いていく。
幸いにも治療は功を奏し、著者らの食生活も改善されて、夫は減量にも成功したようである。
治療や食事、園芸を通し、現代社会に考察を加える間に、レーウェンフックから始まる、微生物学の発展史があり、これがなかなかおもしろい。コッホとパスツールが実はあまり仲良くなかったとか、レーウェンフックの小さな珍しい生き物を見るためにロシア大帝やイングランド女王もデルフトを訪れたなど、小ネタも適度に混ぜ込まれている。糞便移植療法などの新しい話もあり、人と微生物との関わりをざっくり俯瞰するにはよさそうだ。
肝は、「土」も「内臓」も、実は複雑であるのに、過度に単純化されてしまったことで、さまざまな不具合が表出しているという問題提起である。
化学肥料も抗生物質も登場したときには、世紀の発明・発見だった。これさえあれば、安価に健康で豊かな暮らしが手に入ると思われた。
だがそれは目に見えない複雑さを切り捨て、バックグラウンドを痩せ衰えさせることにつながっていった。このあたり、多分に微生物が培養できるものばかりでなく、そして人は培養できるものにばかり目を奪われて、見えないものになかなか気が付かなかったことが関連している。
主張としては、非常にわかりやすく、説得力があるのだが、一面、ガンを初めとする現代病を避けるために推奨される食生活というあたりは、ちょっと根拠が薄いようにも思われる。いずれにしろ、アメリカ流の大容量のコーヒーと甘いスコーン、肉をがっつり、野菜はちょっぴりという食事はよいとは思わないし、スローフードもよいのではあろうが、精製糖や精製炭水化物が即悪というのもいささかヒステリックで短絡的に聞こえる。
野菜をたっぷり食べて、食物繊維を取り、ふすま入りの穀物を食べるのは悪くはないのだろうけど、それで直ちに現代病が予防できるかというと個人的には少々疑問だ。
厚さもそれなりにあるので、一見、取っつきにくい本に見えそうだが、いろいろ考えさせてなかなかの掘り出し物であった。
*学名の表記で1つ。ラクトバキラス(=Lactobacillus?)、バキラス(=Bacillus?)とい���表記があるが、ちょっと違和感が。ラテン語の原則としてはcをkで読むものらしいが、生物学的には慣用的にバチルスかバシラスを使うと思う。本文では原語が併記されていなかったので、新しい細菌なのかとちょっと驚いたが、文脈的にはバチルスっぽい。
*こぼれ話的におもしろかったのは、種痘で知られるジェンナーがカッコウの託卵の研究もしていたという話。あとはミトコンドリア共生説で論争を巻き起こしたリン・マーギュリスが天文学者のカール・セーガンの最初の妻だったという話か。
投稿元:
レビューを見る
★土は半ば鉱物で半ば有機物、砕けた岩と死んだ生物からなる風化した層という奇妙なもの。
★土の色が濃くなったのは、有機物が分解されてフミン酸になったから。
★植物に必要なのは炭素多い目、窒素少な目の配合の有機物。
★D・ラディオデュランスは人間を殺すのに必要な放射線の千倍に耐え、極度の高温低温、さんへの暴露にも無傷。原子力発電所の冷却槽の中で繁殖出来る。
★リンネ→植物と動物の分類法を考えた。
★レーウェンフック→自作の高精度顕微鏡で微生物を発見。
★全ての多細胞生物を一緒くたにする発想は我々は特別だとしがみつく脳の一部を動揺させる。
★細胞の一部でありながら一部でない→ミトコンドリアと葉緑体。マーギュリス
★化学肥料はその場凌ぎの一時的な代用品。継続して使用すると作物の収量が低下する。
★植物が栄養豊富な浸出液を土壌に放出している。自分で光合成した炭水化物の40%を土壌浸出液が占めていた。敵となる微生物を追い払い、食い止め、滅ぼす微生物のボディガードを呼び寄せて群集を形成する為に炭水化物を根から放出する。勧誘された微生物は地下で仕事に就き、盟友である植物を守る衛兵の役目を務める。
★人は食べた物でできている。ガンの予防。皿の半分を植物性の食品、とくにアブラナ科の野菜、その他の野菜、果物で埋める。1/4は精米していない全粒の穀物。残りは豆類や動物性のタンパク質を入れる。多すぎてはいけない。
★免疫系の約80%は腸、特に大腸に関係している。GALT腸管関連リンパ組織。大腸内微生物。
★共生微生物の一部は母から子へ受け渡しされる。虫垂は共生菌の隠れ家。
★免疫系は微生物を殺す為に進化したのではなく、微生物が免疫系の働きを助けている。マイクロバイオーム。
★抗生物質は細胞1つ1つにある発電所ミトコンドリアにダメージを与える。抗生物質過多が炎症性の疾患の根本的原因。
★微生物が肥満と関係している。かつて飢餓の時役立っていたメカニズム。食事性脂肪は体脂肪を増やさず、単純糖質を食べすぎると脂肪に変わり予備プランの備蓄を増やす。
★プレバイオティクスの価値は食物繊維の消化しにくさにある。セルロース。ジャガイモ人参玉葱。プロバイオティクスヨーグルト、ケフィア、発酵食品。
★精白された穀物は単位量あたり全粒より多くのグルテンを含む。
★肥沃な土地で育った作物や家畜を原材料にする食事は栄養素が全て揃っている。根底には土壌生物がある。ハワード
★腸内細菌バランス異常が数々の病気の主な原因。肥満、喘息、アレルギー、鬱など
投稿元:
レビューを見る
この本は化学・生物・歴史・医学といった様々な切り口から微生物について書かれた本です。
特にタイトルの通り、土-地中-と内臓-腸内-における微生物の働きについては興味深い内容が目白押しです。
どうやら著者らはガーデニング及び闘病の過程で微生物への関心を得たようで、こうした経験が一見何のつながりもない”土”と”内臓”を微生物という観点から上手に結び付けることにつながったようです。
本書を通じて、土や内臓に対して抗生物質や窒素肥料を使い過ぎると微生物に逆効果を生むこと、そして微生物とうまく共生することが重要であるということを再認識できました。
”敵を飢えさせ味方に食べさせよ。敵を抑えてくれる見方を滅ぼすな。”
本書に出てくるこのフレーズは著者の伝えたいことをうまくまとめていると思います。
専門用語の注釈や索引、参考文献も充実しており、微生物やガーデニング、健康に興味・関心がある方はそこに該当する部分を読むだけでも価値のある1冊だと感じました。
PS
本書の冒頭に出てくる有機肥料を用いたガーデニングの話は興味深かったです。ガーデニングや家庭菜園をする機会があったら試してみようと思います。
投稿元:
レビューを見る
『土と内臓』は、科学者である夫婦が引越しをして
庭を掘り返し植物を植えようとすることから、
土の中の微生物が植物の健康な成長に
大きな役割を持つこと、強いては人間の体の中には
数え切れないほどの微生物がその健康にやくだっていることを
化学の歴史も紐解きながら、新しい科学データに
照らし合わせて説明。読み物としても楽しい一冊。
投稿元:
レビューを見る
デイビッド・モンゴメリーら「土と内臓」原題The hidden half of nature読了。終盤13章のタイトルに納得。
投稿元:
レビューを見る
夫婦の著者たちが、シアトル北部の荒れ果てた敷地に庭付きの古家を買ったことから始まる。土壌の再生物語と検証が適当に配分されていて、とても読みやすい。
夫の著した、アルバート・ハワードの有機農業についての第5章・第6章と、妻のガンとの闘うでもなく阿るでもない付き合い方(第7章)。
後半は一転して、ジェンナー、パスツール、コッホにペニシリン、ポリオワクチン、ストレプトマイシン…と、科学史じみてくる。でも薬物耐性の抗生物質の話はやっぱり怖い。
投稿元:
レビューを見る
本を一目見て驚くに違いありません!!
重厚ですぞ、分厚いですぞ!
そして、専門用語も出ますぞ!!
そんな本が伝えてくれることは
菌類がいかに大事かということ。
そして、菌類をなくす、ということが
おっそろしいことを招くかという
警鐘も促しています。
抵抗力がなくなる…
それは体にある大事な菌が
ある種補給されないのも
原因かもしれませんね。
それがない食習慣は
太ります。
(ン?うちはなんでなんだろう
ストレスの線が強いかも)
それとロカボと言われていますが
精製されたそれは
人は分解に適さないようです。
菌類を補充している人は
ある程度耐えうるのですが
そういった人が、率先しては、ありえないですよね。
菌類を消すだけの農業は
いずれ、ひどいつけを見ます。
健康も、栄養もそう。
楽はやっぱりだめみたいですね。
投稿元:
レビューを見る
大腸をひっくり返すと、植物の根と同じ
それがおもしろい
畑をやりたくなった
化学肥料をあまり使わない母の畑をのぞきにいきたくなった
発酵食品をこれからも摂っていこう!
投稿元:
レビューを見る
そこ(大腸)では数多くの微生物が生態系を築き、人体と共生して、食物を分解し人間に必要な栄養素や化学物質を作り、病原体から守っている。それと同じことが、土壌環境でも起きている。腸では内側が環境だったが、根では裏返って外部が環境となる。そこに棲息する微生物は植物の根と共生して、病原体を撃退したり栄養分を吸収できる形に変えたりしている。
病原体としての微生物という考え(細菌論)にもとづいてさまざまなワクチンや抗生物質耐性遺伝子が作られ、おかげで多くの人の命が救われたことも確かだ。しかし抗生物質の乱用は薬剤耐性菌を生み、また体内の微生物相を改変して免疫系を乱して、慢性疾患の原因になっている。
同じことは土壌でも起きている。人類は有機物と土壌の肥沃度の関係に気づき、農地に堆肥や作物残滓などを与えてきた。科学者が、有機物に含まれる栄養分は植物の成長に寄与していないことを発見すると、化学肥料がそれに取って代わった。当初、化学肥料の使用で爆発的に収穫が増大したが、やがて収量は低下し、病気や害虫に悩まされるようになった。実は、土壌中の有機物は植物そのものではなく土壌生物の栄養となり、こうした生物が栄養の取り込みを助けて、病害虫を予防していたのだ。
訳者あとがきより抜粋。
いいけどちょと長い。
投稿元:
レビューを見る
「微生物の目から見れば、わたしは生きている丈夫な格子垣で、そこに無数の微生物がからみつき、はい上がり、生長する。(略)わたしは彼らの故国だ。わたしは自分で思っていたようなものではなかった。読者もそうだ。
わたしたちはみんな、別の生物の生態系の寄せ集めなのだ。」
近年健康へ及ぼす影響などが解明され始め、注目を集めるヒトマイクロバイオームについて、少し掘り下げて知りたい人に大変お勧めです。
原文の著述を損ねない素晴らしい訳で、引き込まれるように読み進められました。
投稿元:
レビューを見る
原題は The Hidden Half of Nature
非常に面白い切り口。
微生物学の歴史を辿りつつ、新しい知見が得られる読書になりました。
生物学は、まだまだ新発見がありそうです。
投稿元:
レビューを見る
ながらく人々は、農地に堆肥などの有機物を与えることでその肥沃さを保ってきた。しかし近年、その有機物の栄養が、実は作物の成長にあまり寄与していないことが分かった。そこで代わりに与えられるようになったのが、化学肥料であった。作物の成長に必要な栄養を直接まく効果は絶大であり、収穫量は増大した。ところが、それは一時的だった。やがて、作物は病気や害虫に悩まされることになったのだ。あらためて分かったのは、堆肥の有機物の栄養は、農地に住む小動物、微生物の栄養となっていたことだった。そして、その小動物、微生物が、作物の栄養の吸収を助け、病気の発症や害虫の繁殖を防いでいたのだった。また、作物の方も、光合成した炭水化物を、そんな小動物、微生物に与えていた。植物はただ土壌から、直接に栄養や水を吸収していたのではなかったのだ。植物と土壌との間には、これまで知られていなかった生態系「根圏」が存在していたのである。さて、実はそれと同じものが人間の内側にもあるという。植物の根の外側を内側にひっくり返してやると、それは人間の腸に対応する。人間の細胞の数は、およそ37兆だが、人間の身体に棲む微生物の数はゆうに100兆を越える。とくに、大腸はその多様性のもっとも豊かであるという。「根圏」がそうであったように、人間の腸内細菌叢「マイクロバイオーム」もまた、自分たちの消化吸収を助け、免疫に多大な影響を与えている。いや、それだけではない。今日では、そんな腸内微生物のバランス異常が、増加している生活習慣病、肥満、糖尿病他、アレルギー、うつや自閉症などにも影響している可能性が示されているという。筆者は、昨今の人間の食生活の変化をあげたうえで、自分たちもそろそろ微生物の恩恵に与るだけでなく、その声に耳を傾ける必要性を説く。自分たちは一個の人間であるまえに、幾多の生態系の寄せ集めでしかない。食べることとは、己が腹を満たすことよりも、自らを耕して微生物とともにある営みなのだ。
「微生物の目から見れば、私は生きている丈夫な格子垣――が裏返しになったもの――で、そこに無数の微生物がからみつき、はい上がり、成長する。細胞の一つひとつに、少なくとも三個の最近細胞が棲んでいる。それは私の身体の内外いたるところ——皮膚、肺、膣、爪先、ひじ、耳、目、腸――にいる。私は彼らの故国だ。」
「私は自分で思っていたようなものではなかった。読者もそうだ。私たちはみんな、別の生物の生態系の寄せ集めなのだ。しかし、私たちの身体に加わるのは微生物そのものだけではない。微生物は人間の遺伝子レパートリーを増やしているのだ。細菌だけで約二〇〇万個の遺伝子を人間の体内に持ち込んでいる。ヒトゲノムにあるおよそ二万のタンパク質コード遺伝子の一〇〇倍だ。マイクロバイオームのほかの構成品――ウイルス、古細菌、菌類――のゲノムを合わせると、私たちの体内にある微生物の遺伝子は六〇〇万にものぼる。たいていの場合これはいいことだ。微生物の遺伝子のおかげで、人間は免疫、消化、神経系の健康に重要な何十種類もの必須栄養を吸収できるのだ。」
「私たちの身体にあるすべての生物生息地で、量と多様性において���っとも豊かなのは、長さ七メートルの消化管だ。特に最後の一.五メートル――大腸――には、腸内マイクロバイオームの四分の三、何兆個もの住人が入っている。腸の最下部に棲む顕微鏡サイズの生物が、地球そのものの目に見える生物多様性に匹敵するなどと誰が思うだろう?
さらに驚くべきことに、私たちの腸内に棲む微生物の大多数は、培養されたことがない。人間の身体の外では生きられないのだ。」
「免疫系の約八〇パーセントは腸、特に大腸に関係していることを知って、私はやはり驚いた。免疫学者は免疫系のもっとも大きな部分に、あまり面白みのない名前――「腸管関連リンパ組織」あるいはGALT――をつけている。」
「人間が微生物のまったくいない無菌の身体を持ったことはない。もしそんな状態が実現したとすれば、不健康この上ないことになるだろう。人体内部に棲む微生物群衆は、敵の撃退を助けることから、人間の健康維持に役立つ代謝副産物の供給まで、数知れぬ役割を果たしている。たとえば私たちは、神経系が正しく機能するために必要なビタミンB12、血液凝固と骨の健康に関係するビタミンKといった、健康に欠かせないビタミンを作る腸内細菌相に支配されている。だがそれらは、人間が生きるために必要な数ある分子や化合物の中の二つに過ぎない。微生物は、私たちの血液中にある代謝産物の三分の一までも作りだしているのだ。」
投稿元:
レビューを見る
前作の土の文明史と比べると、エッセイ的な要素も多くて、彼ら夫婦の経験談を楽しく読めます。
や病気と治療の歴史、食など、について、科学者的な雰囲気も保ちつつ、エッセイ風に平易な言葉で語っており、一気に読み終えてしまいました。