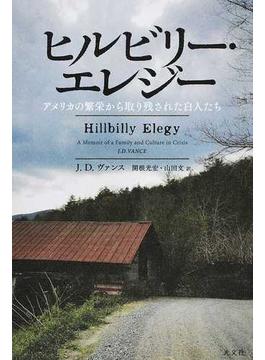紙の本
アメリカの白人貧困層を知る
2017/05/12 21:13
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Takeshita - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書はアメリカでベストセラーになっていると言う。著者はまだ33歳だが、波瀾万丈の少年時代、家庭環境を経て、イェール大学ロースクールを卒業して成功した。その著者の自伝であり、出身階級であるヒルビリー(田舎者)という白人貧困労働者の社会をよく描いている。トランプが大統領になったのも白人労働者層の支持のためだと言われているが、その実際の情報に触れられる大変有益な本である。それにしても著者は書きにくい自分史をよく書いた。その努力と誠実さに心から拍手を送りたい。萬人の胸に響く快著である。
電子書籍
ロールモデル
2018/03/03 16:02
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:中性脂肪 - この投稿者のレビュー一覧を見る
どん底から抜け出せない状態が代々サイクルする環境。
どこの国、地域にも同様の問題は存在する。
著者が触れているようにどん底から抜け出すには、身近にロールモデルとなる人物がいるかいないかが大いに影響すると思う。
若手白人ラッパーのNFはミシガン州出身。著者と似たような環境で育ったようだ。
この本を読んでから「Let You Down」ミュージックビデオを見ると少し感情移入できる。
追記
エミネムもスコットランド移民の子孫でミシガンなどで育ったようだ。著者のような環境で育っている。
紙の本
ヒルビリーの
2017/09/11 14:13
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:igashy - この投稿者のレビュー一覧を見る
イメージは笑える系だと山出し田舎者、怖い系は映画「脱出」の現地住人とのこと(これは怖い)。 親世代は大工場城下町の労働者としてそこそこの生活をして、子供は更に上を目指すはずだったのに、その工場が(日本等の外資の侵略で)撤退し、寂れきった町の残骸(ラストベルト)で暮らしている。出て行こうにも、値下がりした不動産が足枷となって動けない。「世界一偉大な国」アメリカの国民、しかも白人であるプライドと現状の矛盾にぐちゃぐちゃになっている。
紙の本
ああ、田舎者の哀歌
2021/01/04 11:13
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:2502 - この投稿者のレビュー一覧を見る
全体を通じて陰鬱(depressing)ながらも、非常に読み応えのある本でした。著者が「はじめに」で書いている通り、「上院議員でもなければ、州知事でも、政府機関の元長官でもない」アメリカの「市井の人」の半生を、その本人が出来る限り忠実・真摯に書き記すことで、日ごろ私たちが触れることの出来ないアメリカの「ヒルビリー(田舎者)」と呼ばれる人たちの実態を描き出した本書は、まさに巻末の解説で渡辺由佳里氏が書いている通り「50年後のアメリカ人たちが2016年のアメリカを振り返るとき、本書は必ず参考文献として残っていることだろう。」
紙の本
どん底から立ち上がる
2020/05/22 22:30
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Todoslo - この投稿者のレビュー一覧を見る
無力感が漂う貧困層から成功を掴んだ、著者の言葉には説得力があります。トランプ大統領誕生の陰にある、負のスパイラルについても考えさせられました。
投稿元:
レビューを見る
トランプ大統領誕生の原動力となったヒルビリー、その米国の繁栄から取り残されたヒルビリー出身でイェール大学を卒業して投資会社の社長を務めるまで上り詰めた著者が自らのルーツや生い立ちに遡り、赤裸々にその実態を描いています。日本も格差社会が問題として取りざたされているが、ある意味上も下もとても極端な米国には驚かされます。
また、両親の離婚で別れ別れになっていた実父と、その後一緒に暮らすことになります。そこで、敬虔なプロテスタントである実父と共に教会に通うようになると、自ら悪魔的なブラックサバスのCDを捨てることになるのですが、実父にレッドツェッペリンが嫌いと言われると居心地の悪さを感じで、祖母を頼って家を出るなど、微笑ましいエピソートもあります。
著者はヒルビリーなのかでは、とても勤勉な性格ですが、出身を越えて人生を変えたのは海兵隊に入隊してからです。そこで心身ともに鍛えられ、更に軍隊任期満了の奨学金も得て進学することが容易になったと描かれています。穿った見方をすると、海兵隊(軍隊)の新兵募集のマーケティングとも思えます。なにせ戦意高揚映画で「カサブランカ」を制作する国ですからねぇ。。。
投稿元:
レビューを見る
著者自身の複雑な家庭環境、ヒルビリーの社会全体が抱える問題、政府が白人労働者階級にどういう姿勢をとってきたのか、それが今どういう結果を生んでいるか、いろいろなことがとてもわかりやすく書いてあって、ヒルビリーをほとんど何も知らない(映画「ウィンターズボーン」で彼らの存在を知った)状態から読み始めた私にとっては勉強になった。
副題の通り、アメリカの繁栄から取り残され、仕事もなければ学もなく、かといってこれといった努力もせず(そもそも彼らは努力をする、ということを教わらずに育っている。努力せずただ怒っているだけ。それを著者も問題視している)ただただ未来に悲観的になるだけだったヒルビリーたちに、わかりやすい希望を与えたのがトランプだったのかと知って、妙に納得してしまった。
本作の中である高校教師が著者に言ったというセリフ
「みんな現実をわかってない。野球選手になりたいといいながら、コーチが厳しいといって高校の野球チームにも入らない」
が妙に印象に残った。
こういう人、いるいる。
この深刻な「生まれつき頑張れない、頑張ったことがない」という負の遺産、日本も他人事じゃない。
投稿元:
レビューを見る
トランプ推し界隈ってなんなん?が少しだけみえたかも。(余談。婆、母が強烈すぎて「赤朽葉家の伝説」を思い出す。ファミリーヒストリー、強い女性陣てとこしか共通点はないのに!)
自分の怠け心には目をそらし、チャンスに恵まれないのは人が多いから、他の人種が邪魔するから、という発想。それが支持の理由だとしたら。貧困が伝統、という皮肉。
投稿元:
レビューを見る
20170606〜0616。米国の繁栄から取り残された白人達。それでもこの本の著者は、底辺から這い上がっていく。やはり、支えてくれる人が身近にいるのが大きかったのかな。
投稿元:
レビューを見る
各所で話題になっている本書は、その前評判に違わず、非常に面白い。「トランプ支持者の実態がここに!」という時流に乗ったコピーの妥当性はともかくとして、本書で書かれているのが、日本に暮らしているとほぼ見えない別のアメリカの姿であるのは間違いがない。
本書は、オハイオ州の田舎町で”ヒルビリー”と呼ばれた階級で育ち、海兵隊での経験と大学での懸命な学生生活を経て社会的に成功した著者が、その半生をリアリスティックにまとめたノンフィクションである。暴力とセックスとドラッグが蔓延するヒルビリーの生活の生々しさに驚きつつ、その中で必死に孫である著者らを守り続けた祖母のたくましさと愛情には感動を覚える。
著者は自らが育った”ヒルビリー”達の社会に対して、愛惜のこもった眼差しを持ちながら、その問題点を明らかにする。例えば、彼らの中には極めて不真面目な勤務態度で仕事に臨み、いざ仕事を失う段階になった際には困難を他人のせいにする傾向が見られるという。また、昨今では貧困と家庭状況に強い相関が見られることがほぼ明らかになっている中、貧困対策としての家庭支援策は、「両親+子供」という枠組みを基本にしている。しかし、著者の生活がそうであったように、シングルマザーでかつその母親も頻繁に新しい夫との結婚を繰り返すような状況では、祖父母の存在が大きな役割を占める。にも関わらず、両親以外の存在や家族の構成員としては公的に認められず、様々な公的扶助の対象にならないというのは、短期的に解決すべき一つの問題なのだろう。そして、それはアメリカに限らず、日本を始め、他の国・地域でも応用可能な示唆であるはずである。
見えているようで見えていないアメリカの実態を知るのに、非常に適切な一冊。多くの人にお勧めしたい。
投稿元:
レビューを見る
白人労働者階層は米国のポリティカル・コレクトネスという考え方の中で、もっとも割を食っているということがよくわかる。トランプ支持が今後も続くのか?
投稿元:
レビューを見る
[切なさと強情さと]「ヒルビリー」と呼ばれるアメリカの白人労働者階層で育った著者のJ. D. ヴァンスが,自身の生い立ち,そしてコミュニティの危機について記した作品。文化や社会,そして心理の分野にまで及ぶ問題はどこに端を発し,その処方箋はどこにあるのか......。訳者は,関根光宏と山田文。原題は,『Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis』。
今年のトップテンに間違いなく入るであろう一冊。トランプ現象と組み合わせて本書について語る書評が多いのですが,その現象にとどまらず,アメリカという国の根っこの1つを覗くためにも間違いなく参考となる作品です。経済的困難を抱える人々のためのアメリカの福祉政策が,なぜまさにその人々から毛嫌いされるかを理解する一助にもなるかと。
〜白人労働者階層のどこを一番変えたいかと問われるたびに,私はこう答えてきた。「自分の選択なんて意味がないという思い込みを変えたいです」〜
本書が語る世界は狭いですが,それが収める世界は広い☆5つ
投稿元:
レビューを見る
アメリカのラズベルトの街で生まれ育った筆者が、逆境や環境に打ち勝ち、弁護士になるまでのサクセスストーリー、なんだけど…
環境がどーしょもない(家庭内暴力、ヤク中、度重なる離婚et cetera)という家庭は多いらしく、そのような貧困の世帯がワシントンや都市部のエリートに反感を持ち、真実でなくとも分かりやすい言葉で訴えたトランプを支持した、という話は複雑である。で、そのトランプがそのような人の頼みの綱であるオバマケアを廃止しようとしてるのは、うーーーーん…。
ともかく、アメリカで起きてる分断について知りたい、アメリカの貧困に陥っている「白人」について知りたい場合、本書に当たることを強く勧めたい。
投稿元:
レビューを見る
いやあ、読むのがつらく苦戦した。
筆者の曾祖父母の代〜筆者の幼少期〜高校までの前半が、殺伐、無法、堕落、荒涼で、読むのに気が乗らず苦労した。
激情家で、つまらぬ意地が大事で、向上心を持たないのは母親のみならず、祖父母、曾祖父母、地域すべての空気になってしまっている。
かつてこういう空気の地域(日本で)に少し関わったことがあり、それも思い出されて余計につらかった。貧困というだけでなく、親が次々と恋人を変え、家庭は安定せず、言い争いや罵りばかりの毎日は、子どもにとってあまりにもつらい。祖母が銃器を持って人を脅すこともある始末。心は落ち着くはずもない。
戦争や歴史の激動と違って、貧困や教育は、巻き返す糸口が個人にもまだあるはずなのに、向上の意欲のない人々はどうすればいいのか。
努力すれば必ず報われるというものないし、個人の努力だけを強要するものでもないと思うけれど、この諦め切ったこの荒涼。。。
せっかく仕事に就いてもさぼったり遅刻したりで解雇されてしまうのを、どう止めたらいいのか。
失業、犯罪、低所得、飲酒、ドラッグへと転落していくのはあっという間だ。転落というより、浸り切って出てくることがない。それも子どもの頃から浸かり切ってしまうから、それ以外の目標や価値観を見いだせない。。。
サクセスストーリーは(後付けの正当化になっていることが多いので)普段ほとんど読まないのだが、これに関しては、後半の大学以降自分の人生を立て直せて本当によかったね、と思ってしまう。。。
投稿元:
レビューを見る
ヒルビリー、つまり田舎者と呼ばれるラストベルトのスコッツアイリッシュの人達の実態を赤裸々に描写した佳作。アメリカにはマイノリティがいくつかあって、アフリカ系、ヒスパニック、アジア系が、よく言われる被差別層だが、実はもっと大きな塊であるヒルビリーという白人被差別層にスポットライトを当てて、当選したのがトランプ大統領だという。解説者曰く、『50年後のアメリカ人が2016年のアメリカを振り返る時、本書は必ず参考文献として残っているだろう』と述べたごとく、それだけ本書は白人労働者階級社会を的確に描写しているということだと思う