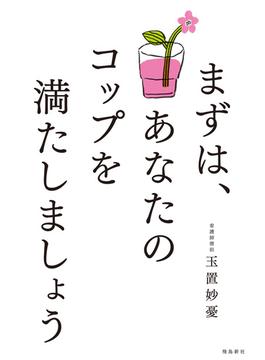こころにひびきました
2018/06/24 07:38
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ひややっこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
死や介護を目前に迎えた人間がどう考えて行動すればよいのか一つの指針を教えてくれています。著者のご主人ががんに対する積極的な治療をうけず、在宅で「枯れるように」亡くなった、その姿が描かれてます。看護師としてそして僧侶として生きる著者の生き方をみると、これから自分がどう考え行動すべきなのか、がんばりすぎず、自分にまつわる決定を人任せにせず・・といったことがすっと心に入ってきます。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:たんたん - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者が看護師、僧侶であることに興味を持ちました。
図書館で借りて読んだのですが、手元に置きたくなり購入しました。
生き方、死に方、色々と考えさせられます。
辛い方におすすめ
2019/07/06 10:02
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ピーちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
介護や別れから何年も経った今、この本を読んで、もっと前に出会っていたらと残念に思った。
ご自分のつらさを乗り越えて看護師、僧侶と色々と勉強された方なので多方面からの視点を持っていらっしゃる。
皆通る介護や別れの辛さから、この本はそおっと寄り添うように、そして静かに背中に手をあてがってくれるような感じ。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:のきなみ - この投稿者のレビュー一覧を見る
読んで涙が止まりませんでした。
作者はとても強い人なんだ、と思いました。
人が生きるって事は人と関わることなんだ、と。
投稿元:
レビューを見る
まずは、あなたのコップを満たしましょう。玉置妙憂先生の著書。他人を幸せにするには、他人に優しくするには、まずは自分が幸せに、自分に優しく。他人のコップを満たすには、自分のコップも満たさないと。自分のコップを満たさないで、他人のコップを満たすことに一生懸命な人、多いと思います。それはそれで素敵なことだけれど、少しだけ自分勝手、自分中心主義になってもいい。看護師で女性僧侶でもある玉置妙憂先生ならではお言葉に救われる人も多いと思います。介護問題や家族問題に疲れている全ての人におすすめできる良書です。
投稿元:
レビューを見る
看護師僧侶、玉置妙憂 著「まずは、あなたのコップを満たしましょう」、2018.6発行です。「家族のため、生活のため、会社のため、自分のことは後回しにして頑張りすぎている人が多すぎる。まずは、あなたのコップを(少し)満たしましょう。」と。また、今の日本は、命があるうちは医師の領分、命がなくなってからは僧侶の領分と分業化されている。そのせいで生き死にの悩みが解決されない人が多いと。私が一番感銘したのは、「延命治療に良し悪しはない。風邪薬も延命治療のひとつ。すべての治療は延命治療。自分の物差しを持つのが大切」と。自分のやりたいことを書き出しておく。例えば人工呼吸器を使えば声は出せなくなる。声を出し続けたいなら、この処置は選ばなければいい。
投稿元:
レビューを見る
ともすれば「自分は後」にすることが美しいと思いがちな日常の中で、ご自身の体験をもとに「自分のコップを満たしてこそ、人を笑顔にすることができる」と勇気をもらえる一冊です。
投稿元:
レビューを見る
自分の幸せを後回しにしていませんか?延命治療とは、在宅介護とは、一体誰のためのものか。現代医療の常識をくつがえし、将来への憂いが喜びに変わる「希望の書」
現役看護師であり女性僧侶とて、生きることと死ぬことを、ひとつのものがたりとしてとられることができたからこそ、伝えることができる。
一回きりの人生を前向きに生きるヒントが本書にある。まずは、自分のコップをみたしましょう。
投稿元:
レビューを見る
#英語 First, Fill Your Cup by Myouyu Tamaoki
「あなたのコップが空っぽだったら、ほかの誰にも分けてあげられないでしょう?」
仏教でいう「二利」(自利と他利)だそうです
投稿元:
レビューを見る
「本書は人生の痛みどめ。苦味も副作用もありません。
主成分は、優しさとささやかな気づきだけ。」
★朝日新聞、毎日新聞で報じられ、日本中が感動!
「現役の看護師」でもある女性僧侶が、その波乱万丈の人生でみつけた「幸せに生きるコツ」
★「あれほど美しい死にざまを、看護師として見たことがなかった」ガンの夫を、息子2人とともに「自然死」で看取った感涙の体験記も収録! 壮絶なエピソードの数々
医療と宗教、どちらのプロでもあり、 数多くの看取りを経験してきた著者が 「幸せな生き方」「幸せな最期」について初めて語った一冊。 読むごとに将来への「憂い」
――― 「はじめに」より抜粋 ―――
夫をわが家で看取ってから、はや7年が経ちました。
夫は当時62歳、「がん」でした。自宅で夫を看病した時期は、2人の息子の母親として、また病床にある夫の妻として、 また現役の看護師として「ひとり3役」で駆け抜けた、 人生でもっとも目まぐるしい、大変な時期でした
夫の死後、やがて僧侶となって「ひとり4役」に。 以降は、 プロの看護師として、高野山真言宗の僧侶として、
多くの方々に接してきました。 そのような活動を続けるうち、 クリニックの患者さんたちから、今までになかったご相談を数多く受けるようになりました。
「妙憂(みょうゆう)さん、 幸せな人生って、どんなものでしょうか?」 「 幸せに生きるには、 幸せに最期を迎えるには、どうしたらいいでしょうか?」
出家する前は、「どんな治療法がよいのか」「どの薬が効くのか」といった、 西洋医学に関するご相談がほとんどだったのに……。はじめは不思議でしたが、徐々に理由がわかってきた。 もしかすると、私は「生きる・死ぬ」をひとつながりのものとしてとらえて お話しできるところにいる存在なのかもしれません。そしてもうひとつ、
私が「人生の最期」について相談を受ける理由があります。 それは―夫を、「 自然死(しぜんし)」というかたちで 看取ったから、でしょう‼️積極的ながん治療を選ばなかった夫は、まるで樹木がゆっくりと枯れていくようにおだやかに、美しく、旅立っていきました。
夫の看取りにまつわる体験は、 西洋医学で培った常識をガラリと覆す、稀有なものでした。 そして、私の人生もこの日を境に一変したのです ――― 【本書の構成】
【第1章】 自分の心を整える
◆まずは、あなたのコップを満たしましょう。
◆この世で一番効くお薬は、時間ぐすり、日にちぐすり
◆延命治療に、良し悪しはありません。
そこいらの「風邪薬」だって、延命治療のひとつです。
◆悲しいときは、泣けばいい。いずれお腹も空いてくる
◆あなたが選んだ道こそが、なにより美しい花道となる
◆最後にいつも、「かもしれない」をつけましょう。
◆いまは一億総「お釈迦様」時代。
◆あなたの考えは、くるくる変わっていい。
◆寝不足で、人助けはできませんよ。
【第2章】 人と上手につきあう
◆人生という火を燃やす。それができるのはあなただけ
◆他人様の悩みは、解決してあげなくてだいじょうぶ。
◆やさしくするのに、長台詞はいらない。
◆不安でソワソワするときは、「心の箱」が開いている
◆「私、イライラしてる」それに気づけば、イライラは止まります。
◆「過去」にねじれた糸は、「今」ほどけばいいんです
◆心配にはおよびません。人間は、自分で後始末ができるいきものですから。
【余話】 最愛の家族を「自然死」で看取るということ
○たとえ「看護師失格」と思われようとも……
○真夜中に起きた、摩訶不思議なできごと
○西洋医学の常識を覆す、あまりに美しい死にざま
○夫の手のぬくもりは、誰にも奪われることはない
【第3章】 あわてずに将来へ備える
◆肉体は滅びても、魂は自由になる。
◆あわてないで。最後はすべてが、うまくいきます。
◆正解は、ひとつじゃない。「何もしない」だって、立派な選択肢。
◆「書く」ことで、心の免疫力をあげましょう。
◆夢なんて、どんどん前倒しすればいいんです。
◆迷って悩んでも、いい。一度決めたら、それが「ベストアンサー」。
【第4章】 きれいに後始末をする
◆お医者さんだって、神頼みしていますよ。
◆あなただけの「幸せのものさし」は何ですか?
◆好きな物は、食べられるうちに、好きなだけ。
◆死ぬときは、生まれたときと一緒。
◆エネルギーの粒に還っていきます。
◆みんな、この世に役割をもって生まれてきています。
◆心配しなくても大丈夫です。難しく考えなくても、みんな、逝けます。
投稿元:
レビューを見る
看護師僧侶という異例の肩書きを持つ著者。
NHKのスイッチでお話は聞いたことがあったが、著書に触れるのは初めて。
夫の死を自宅で看取る。その経験から僧侶となる。どちらも簡単ではない。すごい決断力と行動力。ケツは自分で持つ、という著者の胆力を感じる。
最後はみんな逝けるという言葉は、あたりまえのようで、どこか安心感を生む言葉に感じた。
将来を考えて不安に苛まれてしまうことが多いけど、どんなに悩んでも不安に思っても、人間はみんな最後は一人で死ぬのだし、今、悩んでも仕方ないのかもしれない。どうしても不安が消せないうつ病の自分だけど、最後は逝けると思って、今を楽に生きられるようにしていければいいなぁと思う。
投稿元:
レビューを見る
個人的な死生観としては、死ぬ時に大切な人がそばにいるなかで死ねればいいなーくらいにしか思ってなかった。でも、この本を読んで他にもあるなと思った。もっと具体的に。
食物は口から摂りたい。声が出せなくなるなら延命したくないといったことだ。
投稿元:
レビューを見る
いろいろなものを犠牲にしながら疲れ果てて日々を過ごしても、好きなことをしながら穏やかに過ごしても、ゴールの日は同じかもしれない、というお話が響きました。何事も「中道」の心で、楽しみながら笑いながら“歩く”くらいでちょうどよいと。肩の力を抜いて周りを明るく照らし幸せに暮らすこと。そのために、まずは自分のコップを満たすこと。しっかり寝る、自分だけの時間をつくる、ときどき息抜きしたっていい
投稿元:
レビューを見る
同居の家族が亡くなり、葬儀がひと段落した頃に手に取りました。
悲しんでいる相手に対し「泣かないで」「早く元気になって」という言葉をかけることへの嫌悪にも似た感情と辛さを、客観的な言葉で払拭させていただけた気がします。