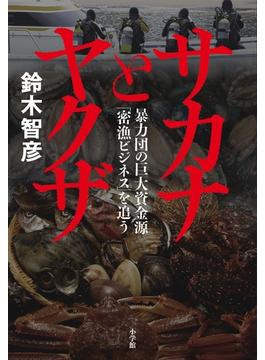「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
密漁ビジネスは、暴力団の巨大な資金源となっている。その実態を突き止めるため、築地市場への潜入労働をはじめ、北海道から九州、台湾、香港まで足を運び突撃取材した、日本の食品業界最大のタブーに迫る衝撃のルポ。【「TRC MARC」の商品解説】
築地市場から密漁団まで、決死の潜入ルポ!
アワビもウナギもカニも、日本人の口にしている大多数が実は密漁品であり、その密漁ビジネスは、暴力団の巨大な資金源となっている。その実態を突き止めるため、築地市場への潜入労働をはじめ、北海道から九州、台湾、香港まで、著者は突撃取材を敢行する。豊洲市場がスタートするいま、日本の食品業界最大のタブーに迫る衝撃のルポである。
〈密漁を求めて全国を、時に海外を回り、結果、2013年から丸5年取材することになってしまった。公然の秘密とされながら、これまでその詳細が報道されたことはほとんどなく、取材はまるでアドベンチャー・ツアーだった。
ライター仕事の醍醐味は人外魔境に突っ込み、目の前に広がる光景を切り取ってくることにある。そんな場所が生活のごく身近に、ほぼ手つかずの状態で残っていたのだ。加えて我々は毎日、そこから送られてくる海の幸を食べて暮らしている。暴力団はマスコミがいうほど闇ではないが、暴力団と我々の懸隔を架橋するものが海産物だとは思わなかった。
ようこそ、21世紀の日本に残る最後の秘境へ――。〉(「はじめに」より)
【編集担当からのおすすめ情報】
『ヤクザと原発 福島第一潜入記』『潜入ルポ ヤクザの修羅場』など、暴力団に関する潜入ルポで知られる著者が次なるテーマに選んだのは、サカナとヤクザという意外な組み合わせでした。サカナを食べるとヤクザが儲かる――ウソのような本当の話を、足かけ5年に及ぶ徹底した現場取材で明らかにしていきます。築地市場への潜入記から密漁団への突撃取材まで、緊迫感に笑いが混じる独特の現場描写こそが、本書の読みどころだと思います。
【商品解説】
著者紹介
鈴木智彦
- 略歴
- 〈鈴木智彦〉1966年北海道生まれ。日本大学芸術学部写真学科除籍。雑誌・広告カメラマン、『実話時代BULL』編集長を経てフリーに。著書に「ヤクザと原発」など。
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
魚を食べれば日本が滅びる!?
2018/11/17 06:14
10人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ももたろう - この投稿者のレビュー一覧を見る
魚食こそは周囲を完全に医務に囲まれた国・日本の食生活の特色だ。
日本人はタンパク質の多くを鳥獣の肉よりも魚介類で摂取してきて、戦後、食生活が欧米化したと言われても、依然、魚介類の消費量は多い。
魚介類に含まれる脂肪は鳥獣の脂肪よりも体に良いということで、日本人の長寿の理由ともされて、見直されている。
私も、毎日魚介類を食べているが、ここに来て、この本を読んで、大変なショックを受けた。
ヤクザが絡んだ漁業は・・・
岩手・宮城のアワビ
北海道の「黒いダイヤ」ナマコとカニ
九州・台湾・香港のウナギ
千葉や東京築地
この本にかかれているような高級魚は好まないので、滅多に食べてこなかったことだけが、僅かな救いだ。
今では、やくざは任侠の徒ではない。
それは、朝鮮人や支那人がやくざに入り込んできたからだ。
つまり、儲けは反日の朝鮮や支那に渡り、日本を滅亡させるための工作や武力になっているということだ。
日本人は真実を知って、戦わなければならない。
電子書籍
知らなかった
2018/11/16 11:21
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:AR - この投稿者のレビュー一覧を見る
漁業にヤクザが絡んでいるのは時々聞いたことがありましたが、この本で記されるような実態を知ると唖然。少なくとも近海の魚だけは漁師さんがメシを食え、私たちもその恩恵に与れるような社会であつてほしいと願う次第です。
紙の本
「魚を食べると、頭が良くなる」だけではなかった!!
2019/02/08 16:07
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オカメ八目 - この投稿者のレビュー一覧を見る
儒教の孟子の、残した言葉として、「食べ物を作ってる、台所の裏事情は知りたくない」と言うのがある。 まさに本書は、それに当たりそうだ。
全く凄い本だ。ーーーー魚をウマイ!ウマイ!と食べると、そんなところに「資金」が流れて行くとは!!!! こんな裏ビジネスがあるんだと目から、魚だけに何枚ものウロコが落ちる。ーーーー確かに渾身のルポだ。
真実は小説どころか、下手なドュメンタリーや、ミステリーを平気で越えて、まさに「奇なり」!
紙の本
そうなのか
2019/07/03 19:32
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:飛行白秋男 - この投稿者のレビュー一覧を見る
築地は仕事で少しお世話になりました。
そんなもんかなーと思いますが、資源は大切にしないと、取り返しがつかなくなりますね。