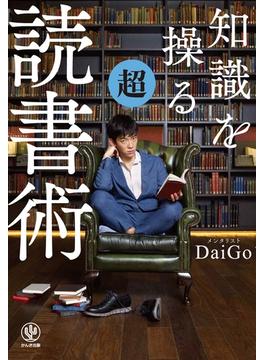0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なのはな - この投稿者のレビュー一覧を見る
さすがDaiGoさんという感じです。読書のサイクルなどに関して実にコンパクトに単純明快に解説してあります。読む前の段階がいかに大切かということがよく分かりました。また「何を読むべきか?」という点についても、確かな指針を示してくれていて助かります。本の読み方について、非常に具体的、実践的な方法を指南してくれていて、今日からでも本当にそれを実践したくなりました。「アウトプットが大事」とか「質問しながら読む」とか、今までもよく聞いてきた内容ではありますが、分かりやすさでいえばトップクラスの良書ではないでしょうか。
☆知識を操る超読書術☆
2024/04/15 23:49
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ACE - この投稿者のレビュー一覧を見る
( ..)φメモメモ
----------------------------------------------
1.本を読む準備をする
(1)メンタルマップ
→「何故この本を読もうと思ったのか」を書き出す。
→目的を見失わないようにする。
(2)キュリオシティ・ギャップ
→既知の知識と未知の内容を並記する。
→知識の差を明確化する。
(3)セルフテスト
→過去の読書挫折原因を検討し、対策を決めておく。
Ex.集中力が続かない→メンタルマップの利用
Ex.集中力が続かない→短時間だけ読む
Ex.理解できない→入門書から読む
Ex.読むべき部分が分からない→接続詞に注目して読む
2.本の読み方を知る
(1)繋げ読み
ア.Text-to-Text
→過去に読んだことがあるテキストと結びつける。
イ.Text-to-Self
→自分の経験と結びつける。
ウ.Text-to-World
→世界で起きている現象と結びつける。
3.本から得た知識をアウトプットする
(1)テクニカルタームを例え話等で説明できるようにする。
(2)思想書と科学書のダブル読み
ア.思想書:特定の考えを書いた本
→古典がおすすめ(∵長年読まれている本に真理が多い)
→知識の土台を構築できる。
イ.科学書:自然科学について書かれた本
→新作がおすすめ(∵知識は常に更新される)
→最新知識や表現を学ぶことができる。
☆知識を操る超読書術☆
2024/04/15 23:50
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ACE - この投稿者のレビュー一覧を見る
( ..)φメモメモ
----------------------------------------------
1.本を読む準備をする
(1)メンタルマップ
→「何故この本を読もうと思ったのか」を書き出す。
→目的を見失わないようにする。
(2)キュリオシティ・ギャップ
→既知の知識と未知の内容を並記する。
→知識の差を明確化する。
(3)セルフテスト
→過去の読書挫折原因を検討し、対策を決めておく。
Ex.集中力が続かない→メンタルマップの利用
Ex.集中力が続かない→短時間だけ読む
Ex.理解できない→入門書から読む
Ex.読むべき部分が分からない→接続詞に注目して読む
2.本の読み方を知る
(1)繋げ読み
ア.Text-to-Text
→過去に読んだことがあるテキストと結びつける。
イ.Text-to-Self
→自分の経験と結びつける。
ウ.Text-to-World
→世界で起きている現象と結びつける。
3.本から得た知識をアウトプットする
(1)テクニカルタームを例え話等で説明できるようにする。
(2)思想書と科学書のダブル読み
ア.思想書:特定の考えを書いた本
→古典がおすすめ(∵長年読まれている本に真理が多い)
→知識の土台を構築できる。
イ.科学書:自然科学について書かれた本
→新作がおすすめ(∵知識は常に更新される)
→最新知識や表現を学ぶことができる。
投稿元:
レビューを見る
メンタリストDaiGoさんが紹介する読書術に関する本
これまでニコニコ動画やYouTubeで紹介した内容もあり復習するつもりで読んだ。
書かれている文に上から目線を感じる人もいた。読むとそういう文が見られたが、個人的にはスキルや情報が得られれば良いので気にはならなかった。
クエスチョニングは、ニコニコ動画で紹介されていた内容だったが動画で紹介されていた項目より少なくして分かりやすく実践しやすくなっていた。
さらっと読める本で分かりやすいが、アウトプットに関しては3つ紹介されている。その内容は読書術関連の書籍を読んだことがある人なら知っている内容だった。個人的には、知識を定着させるためにノートにどうまとめているのか他の読書術との差異を見たかった。
投稿元:
レビューを見る
本の読み方が変わった。
最初から文字を順に追っていく必要はない。
また事前準備をすることでその本の価値を上げることになる。
より記憶に残りやすくなるし、効率よく本を読むことができる。
太字や図が多用されていて読みやすい。DaiGo様さまです
投稿元:
レビューを見る
「本をよく読むのに、読み終えた後に内容をイマイチ覚えていない」「効率よく本を早く読めるようになりたい」「DaiGoさんはどうやって1日に10~20冊も読書しているのだろう?」
そう思って本書を購入した。大事なのは、本を読む時に受け身にならず、目的をもってちゃんと準備すること。
テクニックのいくつかは同著者の『超効率勉強法』の応用で、西岡さんの『東大読書』で取り上げられている内容と重なるものもあった。でも、それだけ頭のいい人たちが実践する読書術なんだから、実践するしかない。
個人的に「スキミング」で内容をざっと捉える方法や、知っている内容や直ぐに理解出来た箇所は読まなくていいと教えてもらえたのは有難かった。
投稿元:
レビューを見る
・一旦、本を閉じて、目を瞑り、自分に質問する
・寝ること、目を閉じるだけでも脳の整理となる
・忘れそうになった頃に復習をする事で長期記憶となる
投稿元:
レビューを見る
ニコニコ動画の会員からすれば、やっとまとめてくれたという感じ。見てない人にはかなり新鮮な情報も多い。ノート術もまとめてくれないかな。
投稿元:
レビューを見る
ほぼ毎日本を読む習慣が定着したものの、肝心の読んだ内容が記憶に残らない、結局体系的に身につけられていないことで悩んでいた今日の頃ごろ。そんな悩みに明快な回答を示してくれた本。
目的意識を持って存分に本から学びたいことを学ぶ姿勢とノウハウが学べる。
知りたいことを身につける目的なら別にいきなり難しい本から入らずに入門書から始めても全然良いし、知っている事なら飛ばせば良い。既知と未知の判別で頭を使うから記憶に定着する、分からない所は別の情報源で明らかにしてから戻ってきても良い。要は、自らのものにする(=ビジネスや日々の生活に活かす)という目的のためなら、考えつくあらゆる方法を使って効果的効率的に知識を習得しろ、ということなんだと思う。
愚直に読んで量をこなす姿勢になりがちだった自分にとっては、手に取った本で何を得たいのか、どうすれば効率良く得られるかを意識する姿勢には目から鱗だった。
普通に本を読み慣れた人にとっては、少し考えれば当たり前の読書術なのかもしれない。ただ、その内容をきちんと分かりやすい言葉で理論的に解説されているので説得力がある。これまでで一番感銘を受けた読書術本だった。
投稿元:
レビューを見る
なぜこの本を読みたいのか目的を持って読むこと。基本的な知識があれば全部読もうとせずスキミングをし、想起しながら自分の言葉に言い換えると記憶として定着しやすい。疑問を持って読むことが大切である。
投稿元:
レビューを見る
以前よりDaiGoさんが1日に10〜20冊本を読む読書について関心を持っていたため、そのノウハウがまとめられたこの本は待ち望んでいたと思えるような内容でした。
特に自分は読んだ内容を忘れてしまうことに悩んでいます。
目次をもとにスキミングをする読み方、読書する前の目的を明確にする方法など新しい視点を得ることができました。読書の概念が変わるだけの質があります。読書について速読から読書法までいろいろ読んできましたが、この本が1番腑に落ちる内容でした。
4章の内容がガラッと変わりすぎ。
投稿元:
レビューを見る
「読書する」という事を、より深く理解する為に同じジャンルの本を読もうと思い手に取った本です。先に読んだ「高速読書」で説明されている内容と合致する部分も多く読みやすかったです。
また、著者がメンタリストDaiGoさんであるという事もあり、科学的な根拠(エビデンス)に基いたより具体的な内容で理解し易かったです。
読書をする時は、その目的を明確にして自分の苦手部分をしっかり把握するという事。その上で「本は全部読まなくていい」や「要するにどんな内容なのかを自分の言葉で説明出来ること」などの読書をする上での技術を磨くことで、より効率的な読書が出来ることを学ぶことができました。
また、作中で登場したメンタリストDaiGoさんの作成した「BND15分IQ脳トレゲーム」を実際にプレイして記憶力が上がった(記憶の仕方を自覚する兆しが見えた?)ように思います。
投稿元:
レビューを見る
読書が習慣化できておらず、1冊読み遂げることが難しい今の自分に何かしらの解答が用意されているのではなかろうかと思いチェック
結果、読んでよかった、、。
速読とはスキミングすることであり、重要なのは要点をいかに選定して読み取っていくかということとか、読書のモチベーションを保つ方法とか、、、いろいろと読書していくうえで今の自分にためになることがたくさん書かれていて、実際に活用していこうと思える点が多かった。
読書を習慣化して目指せ教養人!
投稿元:
レビューを見る
読書をする上で本から学んだことを以下に実行できるか、これから一生かけて本を読んでいく上で、いわゆる読書のための読書は絶対に必要だと思い、この本を手に取った。
自分もこの本を読んで、短時間で本をしっかりと理解した上で読み終えられたらなと思っていた。
自分のこれからの本の読み方を大きく変えさせてくれる本であることは間違いない、冒頭での速読、多読、選書はするべきではないというのは衝撃だった。速読は意味がないのか、良かった、これを見て少し安心した。自分が読むのが極端に遅いのかと思っていたが、そうではなかったのだ。そう、律儀に自分の知っている部分、読む必要のない部分まで読んでしまっているにすぎなかった。
この本を読んで、1番学ぶに値したことは、やはり読書の前の準備に関することだ。
本を読む前に勝負は決まっている。その本で得たいこと、本と同じ分野に関して自分はどれくらい知っているか、その本から何を知りたいのか、読んだあとどうなりたいか、など読む前に以下に考えるかで勝負は決まるというのだ。本当にその通りだと思った。さっそく次に読み始めた本から実践しているが、すでに効果大だ。自分のその本を読む目的も今まで以上によりクリアになり、常に目的を持ってその本を読んでいる感じがしてとても心地いい。
本を読むという行為は、テレビなどとは違い、能動的行為ではあるが、本の読み方が受動的であったかもしれない。本に自分から仕掛けていく、能動的にアウトプットに移す、この行為が読書をする上でなによりも重要なことなんだと分かった。
これからはこの本に書かれていることを1つ1つ試して行ってより質の高い読書を身につけられたらと思う。
投稿元:
レビューを見る
1日に20冊の本を読んでいるDaiGoさんの本の読み方について書かれた本。
単なる多読ではなく、戦略的に本を読む事の重要さを述べている。
大きく3つのサイクルがあり、①本を読む準備をする②本の読み方を知る③本から得た知識をアウトプットする、を繰り返すことで知識が深まるとの事。
また、速読、多読、選書は逆効果との主張もあり、当たり前と思っていたことを覆す内容で中々面白い。
①で読書の70%が決まるようなので、まずは①を優先して実践して行きたい。