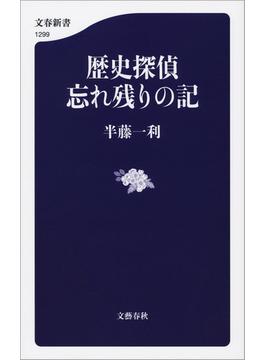0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:a - この投稿者のレビュー一覧を見る
昭和1ケタ生まれ下町育ちが感じた戦前、戦中、戦後です。その時代の風景、空気感が手に取るようにわかるような気がします。戦前、戦中の事を語る方も少なくなりましたが、読んで時代を感じるのは読書の醍醐味でもあります。
読書量に裏打ちされた洒脱さを感じます
2021/06/27 12:33
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:第一楽章 - この投稿者のレビュー一覧を見る
文藝春秋営業部が書店や取次会社に配っている「新刊のお知らせ」のフロントページに掲載されていた、半藤さんのエッセイを中心にまとめた随筆集です。膨大な読書量と好奇心のなせる技か、どのエッセイも洒脱で余裕があります。
半藤さんは、当時は銀座のみゆき通りにあった文藝春秋社に就職されたのですが、
「そして少々会社にも住み慣れて、自分でも驚くほど身綺麗になったころ、暇があれば、社の五階の窓からぼんやりと長時間、みゆき通りを行きかう人びとを見下ろすことを趣味とした。これはほんとうに楽しかった。何時間もあきることなく銀座人種を眺めていた。
女性が日を追うごとにどんどんキレイになっていった。雨の日なんかも、傘、傘、傘がまん丸く重なって、眼下の通りを右に左に流れていく。それはそれはみごとな景で、はじめのころは黒い傘ばかりであったのが、そこに赤や青や緑のあざやかな色がまじるようになったのは、たしか昭和二十九年秋ごろから。銀座の華やぎは傘の色から始まっていた。」(P.201)
春は別れの季節でもあります。今年も大変お世話になった方の何人かがまもなく定年退職を迎えられます。若い頃の武勇伝、仕事への情熱、軽妙なかけ合いが聞けなくなるのは寂しい限り。そんなことを思いながら読みました。
半藤一利さんも今年の1月に他界されました。その絶筆となったのが、本書のあとがきです。
「乱読の弊をいう人もいるようであるが、そんなことを信じない。弊なんてものはない。新しい事実を知ることにいい知れぬ楽しみがあって、むしろ脳みそのコリをほぐすのに役立つ薬と思っている。」(P.261、あとがきより)
教養が深まりました。
2021/05/31 11:49
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ら君 - この投稿者のレビュー一覧を見る
優しい語り口に引き込まれて、すいすいと読み進めました。
短い作品ばかりなので、空き時間に読みやすかったです。
語源や昔の東京の様子や俳句など、さまざまな教養が深まりました。
投稿元:
レビューを見る
私が言論人・文筆家のなかで最も敬愛する半藤一利先生の、最期の書籍となった。半藤先生の著作は昭和史ノンフィクションのほかに、『隅田川の向う側』『名言で読む日本史』といった、知的好奇心を刺激する随筆もまた魅力的であった。たとえ生きた体が消えても、その著作は残る。バカげた右翼どもの本は紙ゴミになっても、半藤先生の著作はずっと評価されるに違いない。
投稿元:
レビューを見る
【昭和史の第一人者が書き綴った随筆集】これまで書籍に収録されていなかったエッセイをテーマ別に収録。昭和史、文豪、動物、少年時代や古き良き銀座の思い出まで。
投稿元:
レビューを見る
昭和史、太平洋戦争のことが書いているとおもったら、隅田川のことや半藤さんの幼き頃(わるがき時代)戦前のこと、戦後昭和30年代の銀座のことなど江戸っ子の歯切れの良い文章で文壇のことなど多岐にわたり楽しい本でした。漢詩なども多く引用されて博識な半藤さんが色々なことを教えてくれてます。
投稿元:
レビューを見る
今年1月に91歳で亡くなった著者。文藝春秋に入社し、「週刊文春」や「文藝春秋」などの編集長を歴任し、昭和史研究の第一人者として知られていた。
本書はそんな半藤氏が遺したエッセイ集で、歴史のよもやま話からことばのウンチク、悪ガキ時代、新入社員時代の思い出などの自伝エピソードが満載されている。
氏が入社した頃の文藝春秋新社は銀座にあり、その辺りの話も出てくるが、入社試験の話や仮採用時、坂口安吾の自宅に原稿をもらいに行った際の安吾の奥さんとの会話が面白かった。
ただ、東京の地名や地理がピンとこなかったり、歴史やことばのウンチクについていけなかったり、自分にはあまりのめり込める内容ではなかった。
投稿元:
レビューを見る
今年の1月に亡くなってしまった歴史探偵のエッセイ集。
自分の父親と同級生の半藤さんは、とても豊富な歴史知識と、東京下町の情報をたくさん残してくれました。ありがとう。
投稿元:
レビューを見る
先日逝去された著者の絶筆となったあとがきが収録されたエッセイ集。
文芸春秋社の「新刊のお知らせ」に連載されたものや、「銀座百点」に綴ったものが6章で構成されている。
『昭和史おぼえ書き』では、著者らしい警句も。
「若いものがやたらにおだてられるのは、国家があらぬ方向に動き出したとき」とか。
終戦後一夜にして、軍国主義の権化たちが民主化の旗振りとなり、その厚顔無恥を思い知らされた経験から
「このぬけぬけとした自己欺瞞は今に続いているのではと。いや、もっとひどくなっているのではないかと」、憂慮する。
また、横文字まじりの略語が氾濫する現状を嘆き、「せっかくの日本語の語彙が貧しくなるのは、日本の財産が貧しくなるのと同じである」と、論破する。
『わが銀座おぼろげ史』では、著者が文芸春秋社の新入社員のころの古き良き時代の銀座の様子が綴られ、タイムスリップ出来たら、ぜひとも行ってみたくなる魅力がたっぷり。
投稿元:
レビューを見る
文藝春秋営業部が書店や取次会社に配っていたパンフ「新刊のお知らせ」に連載されていたエッセイと書籍に未掲載のものを合わせた氏の遺作。
生前に企画され、氏の逝去後に出版された一冊。多岐にわたるテーマの文をまとめたもの。20年以上の連載(1回書籍化)なので時期的にも話題的にも極めて広範囲。
江戸のご隠居さんのべらんめえ調に近い気さくな文体が良い。 [歴史探偵 忘れ残りの記 (文春新書 1299)]の感想
文藝春秋営業部が書店や取次会社に配っていたパンフ「新刊のお知らせ」に連載されていたエッセイと書籍に未掲載のものを合わせた氏の遺作。
生前に企画され、氏の逝去後に出版された一冊。多岐にわたるテーマの文をまとめたもの。20年以上の連載(1回書籍化)なので時期的にも話題的にも極めて広範囲。
江戸のご隠居さんのべらんめえ調に近い気さくな文体が良い。
投稿元:
レビューを見る
激動の昭和、平成・令和にかかる90年の生涯を振返った半藤一利氏(1930-2021) 最後のエッセイ集です。北朝鮮の水爆実験の衝撃のニュ-スに触発され、「昭和史おぼえ書き」の項では「人類は自分で制御できない魔物を造ってしまった。ヒロシマ、ナガサキ、ビキニ、そして原発事故の歴史に少しも学ぼうとしていない」と嘆いています。文藝春秋社が銀座にあった著者の青春時代の回想「わが銀座おぼろげ史」では、GHQによる日本占領時代から戦後の復興にかけての銀座の風景を、面白く読ませて戴きました。 ご冥福をお祈りします。
投稿元:
レビューを見る
昨年一月に亡くなられた著者の最後のエッセイ集
友人に借りて読みました
「昭和史」「ノモンハンの夏」
「日本のいちばん長い日」
など心にずっしりとくる著作を読ませていただいた
エッセイは軽いタッチで「悪ガキ」を彷彿とさせる
昔の銀座など東京の地理には疎いけれど
楽しく読みました。
多くの「警告」を心に留めておきたいと思います。
ありがとうございました
≪ 昭和史を 語りつくして まだ足りず ≫
投稿元:
レビューを見る
半藤氏はTV番組では太平洋戦争の話題の時に生き証人のように登場されていた。貴重な戦前戦後の語り部の逝去を惜しむ声が多い。私はあまり雑誌を読まないので、こんなに軽妙でおもしろいエッセイの方だとは知らなかった。私の祖父母はよく昔の話をしてくれて、それを聞くのが楽しみだった。思えばそんな読後感。氏は昭和20年代に文春に入社され、新人時代に坂口安吾氏のところへ原稿を取りに行ったそうです。銀座のビルの上から富士山が見えたそうです。軽く楽しい物から専門的な資料まで、有るだけ全部遺稿を出版してほしい。
投稿元:
レビューを見る
半藤一利のエッセイ集『歴史探偵 忘れ残りの記』を読みました。
半藤一利の作品は5年前に読んだ『新装版 太平洋戦争 日本軍艦戦記』以来なので久し振りですね。
-----story-------------
歴史のよもやま話から、ことばのウンチク、さらには、悪ガキ時代、新入社員時代の思い出といった自伝的作品まで。
歴史に遊び、悠々と時代を歩んだ半藤さんが遺したエッセイ集。
-----------------------
2021年(令和3年)2月に刊行された作品……2021年(令和3年)1月に亡くなった半藤一利が生前最後に出版に携わった作品のようですね、、、
文藝春秋の営業部が毎月出していた『新刊のお知らせ』というパンフレットに掲載されたコラムや、新聞、銀座のPR誌に掲載されたエッセイ等のうち未発表のものを収録した作品です。
■まえがきに代えて――生涯読書のすすめ
■第一章 昭和史おぼえ書き
■第二章 悠々閑々たる文豪たち
■第三章 うるわしの春夏秋冬
■第四章 愛すべき小動物諸君
■第五章 下町の悪ガキの船出
■第六章 わが銀座おぼろげ史
■あとがき
■編集部付記
■初出一覧
昭和史の第一人者が書き綴った随筆集……歴史のよもやま話から悪ガキ時代を描く自伝的エッセイまで、、、
昭和史最良の語り部……半藤さんの遺した「人生の愉しみ方」……。
肩の力を抜いてリラックスして読める歴史よもやまエッセイでしたね……井上ひさし直伝の文章作法の心得の条である
むずかしいことをやさしく
やさしいことをふかく
ふかいことをゆかいに
ゆかいなことをまじめに 書くこと
という秘術を使って書かれたものらしく、小難しい歴史のことが、とても読みやすく伝わってきました。
そんな中で印象に残ったのは、
・ロシアの軍港であるウラジオストックは、ウラジオ・ストックではなく、ウラジ・オストックが正しい……ウラジは支配、オストックは東方で、東方支配の拠点という意味だった、
・踏襲(トウシュウ⇒フシュウ)、頻繁(ヒンパン⇒ハンザツ)、未曾有(ミゾウ⇒ミゾウユウ)、低迷(テイメイ⇒テイマイ)、決然(ケツゼン⇒ケンゼン)、見地(ケンチ⇒カンカ)等々……これは、麻生太郎が首相時代に読み違えた言葉のメモ、
・節分の「鬼は外!福は内!」は、亭主が出雲大社に参詣に出かけた留守を守っていた女房のところに訪れてきた鬼が女房に惚れてしまい、宝物を全て女房に渡した挙句、追い出されてしまうという狂言からきているとか、
・徳川夢声の俳句「ソ連宣戦はたと止みたる蝉時雨」敗戦の夏を描いた泣かせる一句、
等かなー 面白くて勉強になる一冊でした。