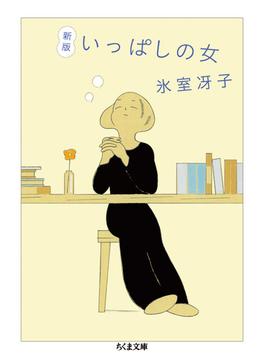紙の本
若い頃はあまりよく理解できなかった
2021/08/31 22:42
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:qima - この投稿者のレビュー一覧を見る
再読して、当時の氷室さんの年齢をかなり越えて、やっと書かれている内容が理解できた気がします。新版の出版に感謝!
紙の本
彼女がいないことがさみしい
2021/12/07 13:01
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みよし - この投稿者のレビュー一覧を見る
氷室冴子さんの少女小説を読んで育ちました。
あの輝かしい活躍の裏で、悩んだり憤ったりしていたんだなと、感慨深い気持ちになります。
今、この時代に彼女がいたらどんなエッセイを書いていたんだろうな。
カバーのイラストがすてきです。
紙の本
大人になった『ジャパネスク』世代に
2021/08/30 18:49
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:BB - この投稿者のレビュー一覧を見る
『なんて素敵にジャパネスク』シリーズを夢中で読んだ世代には、懐かしく、そして意外な感じがするかもしれない。あの氷室冴子さんも、こんな悩みを抱えていたのだと。
1992年に刊行されたエッセイ集の新版だが、#MeToo運動の高まりを受けた現代にも通ずる内容に驚いた。
男性目線のステレオタイプがはびこっていた(いる)社会で、女であるが故に生じる悩みや困難が、氷室さんらしい軽やかな言葉でつづられている。大人になったジャパネスク世代には共感できることが多いと思う。
電子書籍
なんて素敵にジャパネスク
2023/08/20 01:34
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
この漫画読んだことのある人には、すごく懐かしい名前だと思います。かくいう自分も読んでました。しかし、内容はやはり1990年代だなぁ、と思えるところがしばしば。生きづらかった女子の本音が。
投稿元:
レビューを見る
中学生の頃にまわりで大ブームだったけれど、ちょっと遅れて高校生になってからあれこれコバルト文庫で読んでいた(そのせいか、「クララ白書」や「なんて素敵にジャパネスク」シリーズのような代表作は実は読んでない。最初は「シンデレラ迷宮」だったかな?)。そのあと、愛あふれる翻訳少女小説ブックガイド「マイ・ディア」と復刊された角川マイ・ディア文庫にどっぷりはまったのは大学生のときか。
そんな少女小説のパイオニア氷室冴子さんのエッセイ。
中高生のわたしたちを夢中にさせていた80年代後半から90年代はじめ、ちょうど30代にさしかかった頃の氷室さんの考えていたこと感じていたことは、30年経った今読んでも古びないどころか、あ、わかるな、と思うことばかりで(かんたんに「わかる」ですませてはいけない、と氷室さんには叱られてしまうが)、今の自分はそのころの氷室さんよりずっと年上になってしまって読んでいるのが不思議な気がする。
引用したくなるような文章ばかりだったが、なかでも「とてもすばらしかった旅行について」が印象深く、「やっぱり評論もよみたい」には打ちのめされた。
わたしより15歳年上で、親や世間からの結婚への圧もいまに比べたらずっとずっと強かった30代独身の彼女が、あるいはいま以上にマチズモに支配されて「女」が不自由だった中で彼女が感じていた理不尽や無力感、辟易、憤懣、自戒、そしていまの言葉で言えばシスターフッドが痛いぐらい感じられて、そうしたものが当時読んでいた作品からもにじみ出ていて、自分をとりこにしていたのかもしれない…もう一度あれこれ読み直してみたくなった。
1957年生まれ、もしご存命でこの世界を見ていたらどう感じただろう…と考えずにはいられず、ちょっと調べたところ、ちょうど同じ年頃といえば、高橋留美子、柴門ふみ、そして斎藤美奈子がいるとわかった。斎藤美奈子といえば、氷室冴子も愛してやまなかった翻訳少女小説をあらためて読み解く「挑発する少女小説」をちょうどだしたところなのが奇遇。斎藤美奈子にこの本の感想を聞いてみたい。
投稿元:
レビューを見る
とてもおもしろかった。鮮やかでシニカル時に感傷的総じて聡明な…自分の知人で一番捻くれている最高な人と重ねながら全編楽しく読んだ。氷室冴子さんて、こんな人だったんだ。ご存命だったら今は何を書いたかな。好き。
投稿元:
レビューを見る
30年前のエッセイだからといって「さっぱり理解できない」なんてことは無いらしい。
時代が変わっても同様のもどかしさや面倒臭さはあるのだなあと。
特に『ミザリー』と『一番とおい他人』の章が痛い。
旅行先で一緒になった老婦人が囁いてくれた“人生の秘密”は覚えておきたいと思った。
投稿元:
レビューを見る
子供のころよく読んでたコバルト文庫。その中でも特に人気で、映像化もたくさんされているのがこの著者。久しぶりに新版が出たと知って、懐かしくなって読んでみた。
30年近く前に出版された本を、2021年に新装版で出版したもの。解説(町田そのこ)が追加されている。町田そのこと言えば、今大人気の「52ヘルツのクジラたち」の著者だ!
氷室冴子は小説以外も読んでいたので、この本ももしかしたら昔読んだのかもしれない、覚えてないけど。
30歳前後で独身、小説家という自由業、そして女であるということでの世間の風当たりの強さなどが書かれている。今では結婚しない人も多いし、当時もセクハラという言葉はあったみたいだけど、今では〇〇ハラもいっぱいできて、他人との距離感の取り方が変わってきているので、他人の生き方、趣向にずけずけ踏み込んでくる人もあまりいないけど。
「結婚なんかより大恋愛をするといいのよ。いい思い出になって、幸せなものよ。」というのが心に残った。完全に理解はできないけど、そうなのかな…
投稿元:
レビューを見る
氷室さんの作品は実は読んだことがなかったが、面白そうだと思って手に取った作品。まず、この作家さんの物事に対する視点と、語彙力、表現力に驚かされた。流れるように読めるのに、深くて、そしてすごく面白い。これが33歳で書かれたもの、ということに驚愕。自分は33歳よりも年大部年なのに、例え作者と同じようなことを感じたとしても、このように表現する言語能力を持ち合わせていない。まあ作家さんと素人の自分を比べることがおこがましいですが。。
内容としては、作者の考えていることを、実体験で起きた出来事を基に描いていく構成で、その対象となる映画やらを知らないとついていけない部分もあるが、それでもなお楽しめる。なんというか、これを読んでいると、今のあるがままを批判的な目線で見つめることもせず、ただそういうものなのだ、と受容し、ノホホンとしている自分が恥ずかしくなった。
投稿元:
レビューを見る
氷室さんのことは「海がきこえる」以外知らずになんとなく読んだのだけど、小気味良いエッセイで、元気出た。
投稿元:
レビューを見る
かつて少女だったわたしにとって、氷室冴子はある意味フィクションで実在しないかのような別世界の人だった。
少女小説を読み漁っていたあの頃、作品の登場人物と同じように、氷室冴子というのは少女小説家であって生身の肉体を伴わないものとしてわたしの中に存在していたのだ。
あれから数十年経った今、このエッセイを読んでようやくわたしの中の氷室冴子に血が通い、肉体を持ち、わたしと同じ『女』なのだと思えた。
こんなにも愛に満ちていて、シニカルかと思えば情熱的で、なんて魅力に溢れた女性だろうか。
『わかる』などと口にしてはいけないけれど、今も消えない女の生きづらさをかつてはもっと大きく感じていただろうことが、30年の時を超えてこんなにも伝わってくる。
氷室さん、2021年のこの現状をあなたならどう言葉にしてくれたのでしょうか。
今もなお残る女の生きづらさを、芸術の今の姿を、大量消費されるための安っぽいテンプレ物語の山を、あなたの目にはどう映るのか、叶うことなら聞いてみたかった。
これを書いた時の彼女の年齢を越えてしまった今、わたしは『いっぱしの女』だろうか。
わからないけれど、自信や余裕をなくしたときはわたしもおまじないのように自分に言ってみようとおもう。
もう、いっぱしの女なんだから。
しかし、少女小説を『処女でなければ書けない』とはどういう根拠というかどういう方程式なのだろう。
むかしから『処女』というものに理想とか聖性を押し付けすぎてるよな。
男を知ったからなんなんだっつーのと声を大にして言いたいね。
知って何かがかわるほど男というものが偉大な何かだとでも言いたいのだろうかと、訝しんでしまう程度に男性的な勘違いだよね。
かつて処女だったことがあるからわかるけど、人生変わるわけでも悟りが開くわけでも物語が書けなくなるわけでもねえよ。男に(あるいはセックスに)そんな大きな力はない。思いあがってんじゃねーよバァカと発言者には言ってやりたいものだ。
投稿元:
レビューを見る
読んだ理由: クララ白書が大好きだったので。
1992年発行だけれど、時代の感覚はそれほど変わっていないことに驚く。セクシャルハラスメントという言葉が出てきて、今までモヤっとしていた不愉快な出来事が、多くの女性が感じていた事なんだと気付くエピソードや、久しぶりに会った既婚の友達が夫の愚痴しか言わずがっかり、など ”あるある〜” と共感しながら読んだ。
投稿元:
レビューを見る
時を経てなお生きる言葉のひとつひとつが、呼吸を楽にしてくれる――。大人気小説家・氷室冴子の名作エッセイ、待望の復刊! 解説 町田そのこ
そんなものかなと生きてきた。
投稿元:
レビューを見る
1992年発行の単行本を新版として再刊行。
懐かしい。私にとっては『なんて素敵にジャパネスク』の原作者さん。小説は原作として読んだかな?というぐらいの記憶しかないのが申し訳ない(;'∀')
「詠嘆なんか大嫌い」…昔の女友達にたまに会うとこういう感じ(現在の愚痴をずーっと言う)になるのかなぁ。もう会ってないのでなんとも言えない。
「一番とおい他人について」…女性の「それ分かる(共感)」について。
「レズについて」…女が女にあこがれること、について。女性が「こうなりたい」と思うときの対象って女性なのが普通なのでは?
「なるほど」…セクハラについて。この時代の一部の男性は気持ち悪かったなぁ。今も一定数いるかな?ああ気持ち悪い。
「やっぱり評論も読みたい」…「ベルばら」とか「ポーの一族」とか。ベルばらからツヴァイク、一条ゆかりからサガンを読む読者たち。的外れなオジサン評論家たちから評されることに傷つきはしたけれど、評論がないと世界がどんづまりになってしまう、と思う、と。
15年ほど生まれ年が違うので少しジェネレーションギャップを感じた。でもそれは好いこと。15年でギャップがなかったら令和でも変わってなくて恐ろしいことになっていると思う。
「まえがきにかえて」や「なるほど」で女性に対して「処女かどうか」などという質問をするおっさん、私も遭遇したことあります、19歳のとき。学生なので激怒してガン無視できたけど、社会人なら受け流したんだろうなぁ~。ああいやだぁ。嫌な記憶。
投稿元:
レビューを見る
氷室冴子さんの作品を初めて読んだが、日々の鬱憤や違和感を、こんな風に自分の言葉にしていることってすごいな、と思う。元は1992年に刊行された本だが、30年経ても良くも悪くも変わらないことはたくさんあり、すんなりと読めた。