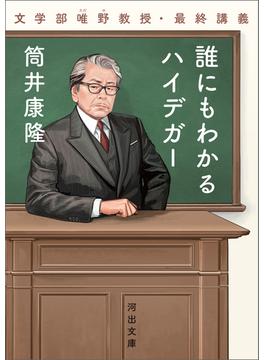1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:a - この投稿者のレビュー一覧を見る
ハイデガーの考えたことが知りたいのと、筒井康隆が哲学のことを書いてるなんて、という動機で読みました。たしかに文章は分かりやすく、読みやすいのですが、個人的には、大澤真幸さんの解説の方が興味深かったです。
確かに読みやすい一冊でしたが、正直云って食い足りない感じも
2022/05/08 01:40
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Haserumio - この投稿者のレビュー一覧を見る
サッと読めて何となくわかったような気にはなったが、(正直云って)あまり内容が頭に残らなかった一冊。個人的には、NHK「100分de名著」のテキストの方が、インパクトもあり、論旨も明快であった。(テキストからの引用も多く、焦点も明確である上に、アーレントとヨナスのハイデガー批判にも触れられているので・・・)ただ、メモっておきたい点はそれなりにあったので、幾つか摘記しておきたい。
「実存というのは人間の可能性のことです。」(41頁)
「実存というのは自分の可能性を見つめて生きる存在のしかたです。」(47頁)
「不安というのは、対象がないんです。」(77頁)
「人間の存在性というのは早く言ってしまえば、時間だというふうに言っています。」(79頁)
(死を)「先駆けて了解するんです。・・・ 自分は、つまり実存しているこの自分は、一回しか生きられないんだ。・・・ では自分は今何をすべきか。自分には何ができるか。そういったことに、これらは向かわせてくれるわけです。」(83~4頁、「先駆」の意味)
「現成化というのは、未来を見て、過去へ戻って自分の過去を振り返って、そして現在に戻ってくるというんですが、それは順番に来るのではなくて、いっぺんにやって来るというふうに言っています。これを時熟と言ってますけどね。・・・ ですからハイデガーにとっては、つまりこれが時間なんですね。これを時間だとハイデガーは言っています。ですから現存在というのは時間内存在だということも言えるんです。世界内存在であると同時に、時間内存在であるということも言えるんです。」(93頁、人生=瞬視の連続そのもの)
「ハイデガーによれば、不安という感情こそが、誰もが死を了解していることの証しである。」(143頁、大澤真幸氏解説より)
「ハイデガーは『存在と時間』で、死における絶対的な孤独、死の単独性を強調している。しかし、「死の了解」ということを媒介にして最後に見出すことができるのは、逆の、他者との連帯の可能性である。」(150頁、同)
こうやってウォーミング・アップをしつつ、後刻原典にあたりたいと思っている評者です。
投稿元:
レビューを見る
本書は、難解とされる『存在と時間』の平易な紹介として知られる。『存在と時間』には実存哲学としての読みがあり得るというが、実存哲学には、現代人に親しみやすい人生論的な語彙で置き換えてしまえるところがある。そこに本書の平易さの理由があるのだと思う。
□
『存在と時間』は、「超越者」を措定することなく飽くまで「現存在」という立脚点から「存在」への問いを解明しようとする試みである。そうした反-形而上学的志向から、「存在」への問いを、「存在的」な問い立てから「存在論的」(=自己関係的)な問い立てへと転回していくこと、則ち「存在」への問いを可能にする前提条件への問いへと遡及していくこと、が要請される。
にもかかわらず、『存在と時間』の議論は、「本来性」という観念を出発点として行き着くことになる形而上学(「非本来性批判=日常生活批判」)の典型でもある。
「現存在」が生きる「時間」は、来るべき「死」によって構造化される。「存在」への問いは、「死」へ向かう「現存在」の「時間」構造のうちに解明されていく。ここで「死」とは「可能性の全き否定」ということ。「死」という生物学的概念を「否定」という論理学的概念に読み替えてみることはできるか。
投稿元:
レビューを見る
Twitterで見かけて面白そうなので手に取りました。難解と言われるハイデガーの「存在と時間」を分かりやすく、ユーモラスな語り口で、作家の筒井康隆さんが講演。「存在と時間」の根本的なねらいは「存在の意味は時間である」というテーゼを証明するものであるそうなのだが、出版されている「存在と時間」は実は未完であるとのこと。ハイデガー特有の哲学用語がたくさん出てくるけれども、筒井さんが噛み砕いて説明しているので、躓くことなく読めました。とても面白かったです。もう少し詳しく知りたいので、また別の本も読んでみようと思います。いつか「存在と時間」のテクストに挑戦したい。
投稿元:
レビューを見る
ここまで平易にハイデガーの『存在と時間』を読み解くことができるのかという驚きの一冊。現存在が気遣いの存在であり空文を駆使して生きているが、そこから本来の生に戻してくれるのは死への不安である。一方で、死を絶対化していいのかという否定神学批判が展開されるのが、その後のポストモダンの思想であるというのが私なりの理解。
解説は大澤真幸によるキリストの二重性(生きて死んだ神)に着目したもの。頽落したキリストの弟子たちの話を書くことで『存在と時間』に話を合わせつつ、死への恐怖から神に祈りながらも結局殺されるキリストを描く。復活しては元の頽落に戻ってしまうので、あくまでも死ぬときの重要性を強調する。しかし復活するからキリストはキリストたり得たとも思うので、このあたりはもっと考えを聞きたいと思ったところ。
投稿元:
レビューを見る
平易なハイデガー解説。
非常にわかりやすい。
わかりやすいからあんまり引っかかりがない。難しければいいというわけではないけど、全体的にのぺっとしてしまう。
核になるところは、やはり死についてか。
世人、非本来性に生きている自分にとって、死への意識はまだまだ薄っぺらい。
もう若くもないから、昔よりも近しくなっているとは思うけど、まだ弱いか。
本来的に生きるとはどういうことなんだろう。
良心とは何なのだろう。
大澤氏の解説は、そこから人間の有限性に対する責苦と、それによる他者との連帯へと可能性を見出そうとしていた。
投稿元:
レビューを見る
取っつきにくい用語を日常用語に。それぞれの関係を分かりやすく、用語の使われる順番や配置に細かく気を使いながら解説。とどのつまりを大胆に。わたしは
NHKの100分で名著を見たあとに気になって読んでみた。いつか本体のハイデガー読んでみてもいいかなと思いました。誰が誰の弟子でというのがわかったのも収穫。複雑な気持ちの背景がある?ようで少し痛いかも。
投稿元:
レビューを見る
大澤真幸の解説がひどい
読めば筒井自身が《このへん、じつは僕よくわからないんです。》《このへんになるとますます、よくわからなくなってきます。》と語ってゐて誰にもわかるといふ題の惹句が嘘だとわかるし、サブタイの文学部唯野教授とは関係ない。大幅な加筆修正といってもほぼしゃべりをそのままうつしてゐて、わかりづらい箇所はある。
本の半分を占める大澤真幸の解説もキリスト教に依拠した解釈でしかなく、はいはいハイデガーは宗教なんですねと思ふし、ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』からアリストテレスの詩学第二部の箇所を引っ張ってきて笑ひの解放的な力があるんだと説明するのに至っては、そもそも詩学第二部はエーコの創作で実在しないのだからアホらしい気分になる。原発についての考へを日本人全体の考へとして敷衍させる例も適切ではない。
投稿元:
レビューを見る
難解なことで有名なハイデガーの『存在と時間』についてわかりやすく説明されている。わかりやすい説明になっても正直なところ難解ではあるのだが、外観くらいは理解できるように噛み砕いてくれているので、入門としてちょうど良いと思う。
存在と時間は「本当に難しすぎて理解しづらいことで有名である」という点を念頭に置いて読むべき。もし理解できなくても落ち込む必要なんてなく、むしろ難しすぎる点を笑い飛ばすくらいの心持ちでいるべきだろう。
投稿元:
レビューを見る
『文学部唯野教授』という小説で、小説に登場する唯野教授が授業をする場面が、都度都度登場し、ハイデガーの『存在と時間』についても第5講解釈学の授業で触れている。
この授業の補講が本書になるのかな?ハイデガーの哲学を、それはそれはとてもわかりやすく教えてくださっている。『存在と時間』を読む機会がある人は、本書及び『文学部唯野教授』の授業を受けてから取り掛かるのが良いかと思われる。全体像をなんとなく把握することが、短時間でできてしまうことがすごい。
投稿元:
レビューを見る
ハイデガーが哲学者であることすら知らない(やばい)状態で読み始めた。本編も解説も基本わかりやすいけど、時間と良心が出てきたところから意味がわからなくなった。ゴールを自覚して、もうやっちゃったことはやっちゃったからこれから軌道修正しよ!ってことでは…ないか…更に聖書とか神をを引き合いに出されてもピンと来ない…。もう一回読んでみます。
投稿元:
レビューを見る
わかった。というかわかった気にさせてくれたことと、メタ要素を保ち噛み砕いた解釈を与えてくれたことが、雛目線での親鳥に思えて筒井先生死んだら泣くやろなあと謎の感動感情感想。
投稿元:
レビューを見る
『最終講義』の名の通り、まるで中学生や高校生に戻って面白い先生の講義を受けているような気持ちになれる。
本書で指摘されている通り、ハイデガーに触れる上で大きな障壁になるのが、数々の概念(というか、言い回し?)なのだが、本書はそれらの話を最小限に抑えて解説を進めてくれている。おかげで、ハイデガーの視座は私たちが直感的に感じ取っているものと近いということが分かりやすく、説得力がある。
読書慣れ、哲学慣れしていない自分のような人に、読んでもらい、哲学の身近さを感じてほしい。
投稿元:
レビューを見る
この本じたいはとても分かり易いけど、引用されている原文は恐ろしく難解。筒井さんよくこんなの読んだな…ハイデガーで歯が立つのはこの本までな気がする…。
投稿元:
レビューを見る
これを読んでハイデガーが分かるかどうかは別にしてこう言う考えなんだねーって思う。
易しく説明なんて本当は出来ないんだろうけれど書く人の咀嚼した内容で話して貰える本書籍のようなものは大変助かる。
読んで次の段階に頑張ってみようという気にさせてくれる。
頑張って存在と時間が読めるかというと難しいかも知れないけれど、次のステップにいつか繋がる気がする。
繋がらなかったらもう一度読もうと思う。