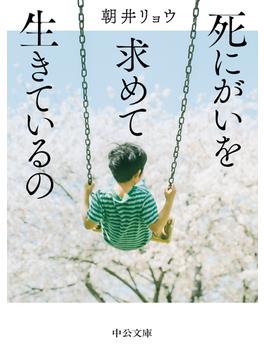絶対評価での学校生活は生きづらい
2023/12/19 18:03
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:nekodanshaku - この投稿者のレビュー一覧を見る
登場人物たちの想いを心に留めていくと、今の時代のなんとない生きづらさを言語化している気がする。ナンバーワンよりオンリーワンと歌われ、学校での相対評価から絶対評価へと変わった社会で育ってきた登場人物たちは、新たな心の苦しみ、悩みに立ち向かうことになった。世界から順位付けされるシステムを手放す代わりに、自分で自分を見つけなければならない終わりのない旅(自分探しの旅か)の始まりだった。この物語の終わりに、答えの一つが提示されているわけではない、心にしっかりとくびきを打たれた。
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:イシカミハサミ - この投稿者のレビュー一覧を見る
螺旋プロジェクト「平成」を担当する作品。
正直「共通ルール」について
これほどがっつり扱うとは思っていなかった。
朝井リョウの作品の中で
「ルール」の要素が明白に浮いていて、
読みにくさがあった。
特にエピローグにあたる
「南水智也」の章はほとんど海族山族の話でかなりだれた。
そのせいで作品全体がだれた印象になってしまった。
「ルール」要素を抜けば、
ちゃんといつもの朝井リョウ。
投稿元:
レビューを見る
今の時代、雄介や他の登場人物のような人間であふれている気がします。
他人のSNSのキラキラした投稿と自分を比較したり、何者かになるために虚栄心剥き出しにしてみたり。
普通に生きていく、ということが一番難しいんじゃないかと再認識させられました。
かくいう私も平成ど真ん中世代なので複雑な気持ちです。
投稿元:
レビューを見る
これは『螺旋プロジェクト』という競作企画の作品の平成バージョンだということを抜きにしては語れないと思います。
朝井さんの著者インタビューによると、平成では『螺旋プロジェクトで課された「対立」が個人間でも、国を挙げての「対立」も時代を象徴するものが、どちらもなかなか思い浮かばなかった。あるとき、平成はもしかしたら「対立」を排除してきた時代なのかと思ったそうです。
国が豊かになり、ナンバーワンより、オンリーワンという空気のもと、わかりやすい「対立」はなくなった。でも不思議と生きやすくなったわけではない。このあたりのアンバランス感が気になってきたそうです。
そして、インフラが整っていない国の人たちからすると「何が生きづらいの?」ということになると思うんです。だけどなぜか、人は「生きている」というだけでは満足できない…云々と続きます。
それでタイトルに『死にがいを求めて生きているの』という言葉がでてきますが、この物語の青年たちが求めているのは「生きがい」です。
『螺旋プロジェクト』で対立している海族と山族ですが、山族と思われる堀北雄介は海族と思われる植物状態にある南水智也の看病に通っています。
どうしてそういうことになったのかが、この作品の内容ですが、私がこういう作品を読み慣れていないせいか、読んでいて面白いというより非常につらかったです。
彼らは北海道大学の学生でしたが、しきりに「生きがい」を探していました。
雄介が「生きがい」について語るシーンが443Pにあるのですが(長いので端折りますが)、
一つ目は生きがいがあって、それが社会貢献につながる人。
二つ目は生きがいがあるけれどそれが社会に向いてない人。
三つ目は生きがいがない人。
に分けています。
私は自分が二つ目に属すると思います。
でも「生きがい」がまるでなかったら生きるのはつらいと想像しますが、一つ目の社会貢献につながるほどの「生きがい」がなくても程ほどで生きていけるんじゃないかな。そんな風に「生きがい」「生きがい」って毎日探すより、毎日の方が「生きがい」の中のどこかに存在していると考えられないかなと思いました。
投稿元:
レビューを見る
役割を求めて生きることしかできない雄介のいびつさは、ここまで顕著ではないにしろ平成時代の生きづらさだと感じました。
ナンバーワンではなくオンリーワンをもてはやすようになった平成は、その言葉ほど優しいものではありません。
雄介と彼を取り巻く人々の物語を通して、外からは見えづらい闇がこれでもかというほど抉られていました。
投稿元:
レビューを見る
危険な運動会の競技や成績順位の公表がなくなり、多様性とか、ナンバーワンよりオンリーワンが謳われる平成の世で、人間は自分で自分を値踏みし、自分が価値ある人間なのか問わなければならなくなった。自分には生きる価値があると認めるために必死で、そのために対立や争いや攻撃を誘引してしまう堀北雄介には、現代の若者の自意識過剰性や極端な自己否定と自己肯定を行き来する自意識が表されている。一方で、世の中をグラデーションで捉え、流されることなく自分の立ち位置を貫く南水智也は、多様性の時代の象徴そのものでありながら、父の学説を否定するという目標の元、その生きがいのために生きている点で、堀北と大差ないと自覚する。
平成の時代に生まれた、同世代の心理を鋭く描いていてとてもよかったけど、海族山族のファンタジー要素が(目が青いとか)余計で、それは異質な他者を排除するとか反目するということの象徴としてはいいのだけど、そこだけ現実離れしているのが残念だった。
投稿元:
レビューを見る
世の中の見えない対立を描いた話。
社会人の自分にも、心当たりがある感情を指摘されるような気持ちになる。
だけど、だからこそその感情と向き合おう、みんな同じ様に悩んだりしてるよねって気持ちになれるから、温かい気持ちになれたりもする。
それが、朝井リョウさんの小説の良さだと思う。
そして自分はどちらかというと南水派で、「何かを成し遂げたい」「何者かになりたい」という人を見て、生きるの大変そうだなぁ…と思ってしまう節がある。
人生なんて自己満足なのに、なんで誰かに認められたいんだろう、なんで誰かに認められなきゃいけない、成し遂げなきゃいけないって思うんだろう、と。
かと言いながら、もっと小さい視野で、やっぱり周りに認められたいと思って、仕事したり趣味をしたりしてる自分がいるわけで。
みんな、グラデーション。白黒ハッキリつけられない感情を、私たちは常に持ちながら自問自答していくんだろうな。
投稿元:
レビューを見る
タイトルに引かれて購入。
平成に生きてきた世代。この時代の持つ歪さをテーマに絡めてよく表現されていた。対立を最初から無くしてしまうのではなく(全部無くすのなんて無理だし、どうしたって比較は生まれるし)、対立からどうするのか、を考えないと人間は前に進めないのかも。
投稿元:
レビューを見る
朝井リョウさんの人の心情の書き方が本当にリアルだと思う。自分の知っている感情が沢山ある。それが本当に好きです
人は誰しも生きがいに縋り付いてないと生きていけないほど弱いし、対象の背景を見てしまうのも他者を排除していく人間の自己肯定感の作りなんだと思う
現代には限らず今までも今もこれからも雄介のように死にがいや対立を求める沢山いると思うし、自分もそういう面はあると思った
投稿元:
レビューを見る
面白かった、新幹線で集中して読むのに良かった。
朝井先生は、人の感情のあまり触れてほしくないところをえぐり出すような作家さんだな、と思う。
誰しもが幼少の頃から何処かに持っているヒーロー志向というか、誰かに認められる自分でありたいと、思っている。承認欲求。無い人もいるのかな。
それをおいてこれた人に、「痛いやつ」と思われていきるらなんとなく肩身の狭さ。
結局智也も、海山を、無意識のうちに生きがいとしてしまって、それに執着してるんだな、と、最後に思った。
記者の弓削の追いつめられようとか、怖かった。
あの人だけでスピンオフ一冊かけそうだ。
螺旋プロジェクトとは知らずに読んだがほかも読みたくなった。先生すごいな。
投稿元:
レビューを見る
「俺の中にも雄介がいる」みたいなフレーズとても刺さった、めちゃ分かる。生き甲斐なさすぎて勝敗にめちゃくちゃ拘ってしまう〜
投稿元:
レビューを見る
朝井リョウの小説は現代を生きる人の内面をうつしだしてていつも共感するがこの本もしかり読んでいて痛いところをつかれたような気持ちになった。
雄介は友達想いの人物かと最初思ったが、南水との比較の様子から、何かの役割目的がないと生きていけない、注目をあびたくてしかたない様子がなんだかさみしくなった。
目的と手段が逆転している。生きがいを探している。何してるの?は何かしていなきゃいけないってことでしょ。というようなストレートな言葉がささった。
正反対な南水と雄介の関係性が一冊を通して分かり、どのフェーズでも雄介は変わらない存在で、南水は山海の対立説に縛られて生きているのは、生きるってなんだろう、生きがいと死にがいについて考えさせられた。
投稿元:
レビューを見る
何か生きがいを持って毎日を必死に輝いて生きている人ってどれくらいいるのだろうか。
生きがい、死にがいって何だろう・・・
誰かと比べる、競うことでしか自分を証明できない雄介とそんな彼を傍で見守っている智也。
全く似ていない二人はどうして一緒にいるのか・・・
読了後にタイトルにある「死にがい」の意味が分かったような気がしました。
生きがいないなら、死にがいを求めないと自分という存在・価値を見失ってしまう。
どちらも自分の存在価値を示す指標にはなるが、
そもそもそんな大それた指標なんて必要なのだろうか。
生きていく上で大切なことは生きがいや死にがいを求めることではなく、
自分の存在は自分が認めて、自分で価値を見出すことではないのか・・・
とか綺麗事を言って自分を納得させ、結局は全て妥協や甘えなのかもしれないと思う自分もいます。
ですが、今はその不安定な現実を自分が認識している、
受け入れようとしているところまでで充分なのかのとも思います。
そんな風に思えたこの本は自分にとって大切な一冊となりました。
投稿元:
レビューを見る
朝井リョウさんの本は買う!精神でたまたま買ったら、「螺旋」シリーズとのこと。同時に買った伊坂幸太郎さんのシーソーモンスターと同シリーズという偶然☺️わくわく。平成を担当する朝井さんは平成の対立を描こうとして、平成はとことん対立を無くそうとしていることに思い当たったそう。
物語は海族山族にまつわる対立の言い伝え?を軸に小学生〜大学生まで堀北雄介に関わった人物の視点から描かれる。
どこかに対立を生もうと、諍いに首を突っ込もうとする雄介。 どこかにいそうだなあという感じがする。
朝井さんは物語の中で、平成の世の生きづらさを描いている。朝井さんは物語で伝えたいことをビシッとストレートに伝えてくるイメージ。本作も最後の章の南水智也の脳内での語りは朝井リョウのメッセージ!!感が強かった。このメッセージ感は好き嫌いが別れそうだけど、わたしはとても好ましく感じる。みんなでもやもや悩んでいこうよ。
投稿元:
レビューを見る
巻末の特別付録を読み、購入した。
今の心境にマッチする本を探して見つけた。
自分の意義や価値、内側から腐っていく痛み、自己否定の先にある「自滅」などの言葉に、胸を抉られより深く読みたいという欲求に駆られた。
他人からは理解されない感情や価値観をどのように処理すればよいか分からず、この本に一旦委ねてみた。
対立、葛藤、悩みなどと、自分がどう向き合っていくのかを考える上で、様々な登場人物の心情は参考になる。
特に気に入ったのは、安藤与志樹-後編-の「今なら生きる意味とか、生きがいとか、そういうのなくても、生きていけるかも」という場面。
非常に共感した。
また、最後の場面で、互いの〝違い“が〝対立”を生み、そこから”対話”の必要性に迫られることで〝違い”こそが、大きな繋がりをもたらすという考え方にも感銘を受けた。
生きている以上、誰かと繋がってしまう。
そんなつもりはなくても、自分が立っているだけで人間ひとり分の進路を防ぎ勢いを削いでいるかもしれない。
それがこの時代を生きる全員で何かを乗り越える一筋の光になることもあるのかもしれない。
何もわからないけど、大きな唸りのなかで、それでもただ生きていく。