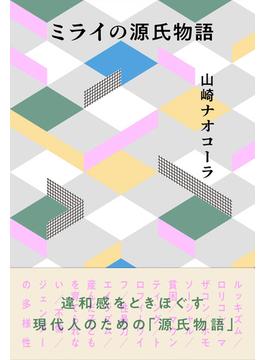紙の本
現在の視点から源氏物語を読み直す
2023/12/31 19:41
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:BB - この投稿者のレビュー一覧を見る
ロリコン?ルッキズム?
光源氏の常識は、現代の私たちから考えると、非常識なんだろうか。
現代人が違和感わ覚える倫理観の問題をときほぐし、古典の源氏物語の魅力を教えてくれる新しい視点のエッセイだ。
山崎ナオコーラさんの現代語訳も素敵でなかなか興味深い。
紙の本
現代にも通じる普遍性
2023/08/08 20:52
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:fuku - この投稿者のレビュー一覧を見る
俵万智さんがツイッターか何かで紹介していたので、手に取ってみました。
当方、源氏物語は大学受験以来、という程度の知識ですが、
現代の問題との類似性を軸とした構成となっていて、興味深く読めました。
現代語訳もかなり思い切って、今時にアレンジしてあり、硬派な人には
イマイチかもしれませんが、(私のような)知識の少ない人や高校生には
馴染みやすいかと思います。
紙の本
古典と現在
2024/01/07 14:21
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:名取の姫小松 - この投稿者のレビュー一覧を見る
フィクション、特に古典作品は倫理観が現在とかけ離れているので、現代の法律や道徳に違反しているから悪いモノ、と軽々しく切って捨ててはいけない。
それでも疑問や不快感は出てくるのだろう。その不愉快さや疑問を呈することこそ文学の役割の一つでもある。
不自由な暮らしをせざるを得ない貴族の女性の生活を現在の感覚で見てみると、また新たな古典の読み取り方が出てくるかも知れない。
電子書籍
源氏物語
2024/04/14 00:45
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
山崎ナオコーラさん独自の解釈による源氏物語です。源氏物語は、与謝野晶子を始め、浜村淳さん、そして、漫画では大和和紀さんの「あさきゆめみし」色々出てますけど、一番、現代の考え方かな~。個人的には…でしたが。
投稿元:
レビューを見る
特に目新し着眼点はなく源氏を題材にしたエッセイという感じ。各章に載った現代語訳が、角田源氏より更にラフで興味を引いた。全訳して欲しい作家さんが増えました☺️
投稿元:
レビューを見る
源氏物語に関しての知識が全然なくて、光源氏がプレイボーイだってことぐらいしか知らなくても、相関図があったり内容や登場人物がどんな人かが簡潔に書かれていて、分かりやすくておもしろかった
現代で書かれている、今自分が読んでいる物語も、1000年後にはまた今とは違う考え方や常識で違った捉え方をされるようになるのかな〜と思った
投稿元:
レビューを見る
平安時代の社会規範に合うよう書かれた源氏物語を「読みにくい」と感じる人が楽しめるよう、現代の社会規範に合わせて様々なシーンを紹介。
以前、好きだった作家の小説の中でものすごい男女差別表現があり、「登場人物にそんなことを思わせる発想を持つ著者の書くものなんて読んでたまるか!」と若かりし頃荒ぶっていた私ですが、この本のおかげで「色々な想いは感じても良くて、それでも読書を楽しむことはできる」と思えました。
投稿元:
レビューを見る
源氏物語読んだことないけど全体の話がなんとなくわかって楽しかった。登場人物の呼称は原典にはほとんど出てこなくて前の時代の読者がつけたものが現代に引き継がれているというのが面白かった。
この本を踏まえて源氏物語を読めばモヤモヤがいくらか緩和されて古い価値観の中で書かれたお話だと割り切って楽しめそう。
投稿元:
レビューを見る
「源氏物語」を今更どう読む?もう出尽くしてるのでは?と思ったのだが、なかなか潔い解釈で面白かった!
映画の「TAR」を最近見たのだが、バッハやショーペンハウアーの人格(かなり家父長的)に作品はどう影響するか、またその作品をどう扱うかについての話題が出ていた。
考えてみると、前近代の作品群はほとんど全てが、その時代の価値観に基づいて作られているわけだ。「源氏物語」もまた然り。時代の差別的な価値観はなかったことことにはできないし、ましてや、それを善きものとするわけにもいかない。それはそれとして、認めた上で、さあ、どうだ、というしかない。
「無理に進歩的な作品だと捉える必要なんてありません」「昔に差別があったのは事実です。」
そういうスタンスで読むと、著者の言うとおり、確かに、「貧乏は面白い」なんていう思いが紫式部にはあったのかもしれない。こんな視点は目から鱗だ。
そして、光源氏を裏切ったとされる女三の宮はむしろ性被害者だという視点。
女三の宮や浮舟の不当な評価はいかがなものか、という著者になるほどなと思った。そういえばそうじゃん!なんで今までそんなことに蓋をしてきたんだろ?
女三の宮が脇が甘いからと言って、レイプされていいわけはない。女三の宮は、光源氏を裏切ったわけではない。悪いのは柏木だ。女三の宮は柏木に心を許しているわけではない。
「子どもっぽいのは罪でしょうか?字が下手だったら、夫から愛されなくても仕方ないんでしょうか?異性に姿を見られたら、性暴力を受け入れないといけないんでしょうか?」
山崎ナオコーラはやさしく、公平だ。そして、その視点で、なんとなく鵜呑みにしてきた登場人物たちの評価を見直させてくれる。
LGBTQ+の人たちが先進的に見えるかもしれないが、先史時代からきっといたはず。という指摘もその通り!だと思う。むしろ自由に暮らしていたかもしれない。
十分知ってる、と思った「源氏物語」を新しく公平な視点で照らし直してくれた良書だと思う。
投稿元:
レビューを見る
感想
現代人が当時の考えや慣習を理解するには二重の隔たりがある。言葉にされ失われる鮮度。言葉も十全には理解できない。ありきたりな議論。
投稿元:
レビューを見る
いわゆる″須磨がえり″経験者の私にとって、この本を読み、著者〈ナオコーラ訳〉に早く出会っていれば、『源氏物語』を深く読めたのだ!と知ることができた。
『源氏物語』ほどではない、明治から昭和初期の作品、いや平成でも、これは今の感覚とズレているな、と思うものがある。
しかし、それが駄目なのかと言うと、その時点ではそれは普通だったのだと知ることが出来、今を考えることが出来る。
そんなことを改めて感じながら、面白く読んだ。
投稿元:
レビューを見る
実は読み終わっていない(図書館の返却期限が来た)のだが、感想を書かせて頂いても少しは良いのでは…という気がしている。日本人なら誰もが(名前だけは)知っていると思う、源氏物語、を詳しく現代的なテーマに沿って、丁寧に且つわかりやすく、また興味を引くように、読む者が想像力を働かせ易いように、解説された書籍であると思う。
私が読み終わっていない、のに「感想を…少しは良いのでは…」などと書いたのは、この書籍が勿論、長編小説などでは無く、種々のテーマに沿って解説する、というスキームの繰り返しである、と感じたからである。
現代的なテーマ(同性愛とか、ロリコンとか、普遍的ではなく人の興味を惹く愛のかたち)に沿って、源氏物語、の当時の原文を引用しながら、詳しく分かりやすく、作者の手によって解説されている、要はそのスキームに沿って読む者はそれぞれのテーマを追体験する事が出来る。かく言う私も、源氏物語などこれまで興味本意の興味すら無く、高校生時代の古典の授業など退屈を通り越して気持ち悪ささえ感じていたのだが…、流石に歳を重ねたからだろうか?、今となっては興味本意かもしれないが受け入れる事ができるようになったと思う。
先に書いたようにまだ読了してはいないが、10を超える普遍的ではないテーマに沿った源氏物語の解説、改めて全て制覇したいとは思う。屈折しているかもしれないが、ひとつひとつのテーマにある原文とその解説を読みながら、私の頭の中にあったのは、平安の時代?、或いはそれ以降?、にそれを読み、胸を熱くした、読み手のはにかんだ表情やその時代の空気、情景、であった。これを成してくれたのは、作者によるガチの源氏物語研究の成果、によるものだと思う。
投稿元:
レビューを見る
ナオコーラさん自身が好きで、トークイベントに参加するために拝読。社会規範によって読み方は変わる。だから、古典も現代文学もミライまで読み続けられる。
文学の面白さを再度感じられた本だった。
マウンティグ、エイジズムなどのパートでは、深く頷く部分が多かった。日頃考えていることに対して、アンサーしてくれたような気がする。
源氏物語自体の魅力も思い出されて、改めて読みたくなった。
投稿元:
レビューを見る
「あさきゆめみし」でではありますが、学生時代に「宇治十帖」を読んだときは、主人公(薫)と浮舟が、いわゆる現世利益的な幸せを享受しない結末に、不完全燃焼というか、もやもやした感想を抱きました。
この度、著者による浮舟についての解釈は大変興味深かったです。
私の中で浮舟は、2人の男性の間でどっちつかずになり、身動き取れずに、出家という選択をせざるを得なかったな薄幸な女性という評価でしたが、男に振り回されずに、自分を生きるという覚悟を持った自立的な女性との見方もできることは、新鮮でした。
源氏物語の奥深さを改めて感じた次第です。
源氏物語のストーリーを一通り知っている人なら、現代的な視点からはこんな読み方も可能なのだと、新たな発見ができると思います。
投稿元:
レビューを見る
私は郷に行っては郷に従え派なので、自分が源氏物語を読んでいるときは、その当時の社会規範や当たり前を知れることが面白いと思って、そこまで引っかかることはなかったなあと。
合理性とか現代的正しさはないけれど(なんなら考えられないことばかり)、なんだかそれも儚くて風流で好きだと感じてるタイプだった。
むしろ、現代のルールを当てはめて、この人はかわいそうだのひどいだの言うのは、登場人物たちも望んでないのではないかとも思ってしまう面はあった。
それでも確かに思い返すと、紫の上が源氏の奥さんにされるシーンは中学生の時に衝撃を受けた覚えがあるし、その違和感を言語化してくださってること、
また、時代が変わっているからこそ、平安時代の人とは違った感じ方で読む事ができるというのは一理あるなと思った。
キャッチーな目次とは裏腹に、淡々と論文のように、源氏物語を題材に、現代の社会問題を見ていっているような印象を受けた。