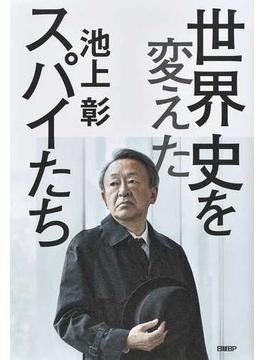紙の本
スパイ達の活動を紹介
2023/09/28 16:18
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:a - この投稿者のレビュー一覧を見る
ロシアのプーチン大統領は、何を考えているのか私にはよくわからなかったのですが、彼がKGBのスパイ出身であったことを考えるとある程度理解できたと思いました。
紙の本
大国の横暴な歴史にはうんざりさせられます
2023/09/27 09:28
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とらとら - この投稿者のレビュー一覧を見る
アメリカ、イギリス、ロシア・ソ連、中国、イスラエル、北朝鮮などのスパイの歴史が語られているのですが、それらはそのまま大国の横暴なふるまいや戦争・事件なんかと直接結びついていて、なんかうんざりさせられる感じがします。日本のことにはあまり触れられていませんが、近現代の世界の歴史をざっくりたどることができました。
紙の本
日本の現状について、もう少し詳細な解説があれば・・・
2023/05/06 17:40
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:つばめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は現代史を動かしてきたスパイについて、ウクライナをめぐる諜報戦、東西冷戦時代のスパイ合戦、サイバー空間での攻防、日本のインテリジェンスの実力など5章構成となっている。現在進行形のウクライナをめぐるアメリカの諜報能力の解説は特に興味深かった。ロシアのウクライナ侵攻について、バイデン大統領は2022年2月に、「ロシアがまもなくウクライナに軍事侵攻しようとしている」と断言した。これがはずれたら、バイデン大統領の信頼は失墜するが、情報源に自信があったのであろう。本書に記述はないが、アメリカ以外のNATO加盟国は、軍事侵攻はないと確信していた。このバイデン大統領の断言をプーチン大統領は否定。この否定により、ロシア軍は末端の兵士に直前まで軍事侵攻の計画を明らかにできなかった。ロシア軍の初期の混乱を引き起こすことに、アメリカは成功した。この情報収集の詳細は、本書を読んでのお楽しみということで。
ただし、第5章の日本のインテリジェンス能力についての解説は、少々物足りなさを感じた。例えば、2013年に「特定秘密保護法」が制定され、アメリカから来る情報の質が格段に上がったと言う政府関係者もいるとの解説がある。諸外国ではスパイ活動に死刑や無期懲役を科す法律があるが、「特定秘密保護法」の罰則は最高で10年。これは、映画泥棒(映画盗撮防止法違反)と同じと嘲笑されたらしい。日本はスパイ天国と言われているらしいが、その実態も踏まえた日本の現状についてもう少し詳細な解説があれば、本書の価値はより上がったであろうと思った。
投稿元:
レビューを見る
限られた紙面でコンパクトでありながら著者の得意とする解りやすい説明が尽くされている。イラク vs イスラエルの緊張関係も含めて「スパイ」活動だけではない世界感を持つことを助けてくれる良書。暗殺が罷り通るダークな、非民主的な国家が存在すると考えてる一方、今更ではあるが、表向きは民主国家とされる国々でそれに負けないぐらいに非合法的な行為が積み重ねられてきた歴史は正しく理解されないといけないと感じた。
投稿元:
レビューを見る
池上彰の本は基本的に好きなのだけれど、今回はスパイ活動の羅列になってしまった印象……。
スパイものは、映画か小説で楽しむのがいいのかも。
まあでも、CIAがダメダメなこととか、モサドがすごいとかは、よくわかった。
投稿元:
レビューを見る
アメリカのCIAやソ連のKGBなど、世界の諜報機関が沢山出てきて、それが歴史にどんな影響を与えてきたのか本当に詳しく書いてました。特にCIAについては20世紀に様々な国の内政に影響を与え、政権を転覆等、恐ろしい活動を沢山していたのだなと改めて思いました。それが現在の世界情勢にも繋がっていて、ニュース等から得る情報ももっと分かりやすくなったと思います!後は池上彰さんの知識の多さにはいつも驚かされます。
投稿元:
レビューを見る
池上彰氏によるスパイに焦点を当てた近現代史の解説書です。
第二次世界大戦からウクライナ戦争に至るまで、現在までに明らかになっているKGBやCIA等の活躍やその背景を分かりやすく解説してます。
スパイの活躍についての解説書ではあるものの、科学技術の発展によりスパイという情報収集手段が、サイバー空間を活用した情報収集やインターネット上のSNS等、個人が発信しているものを含む一般に公開されている情報の収集•分析に置き換わりつつあるという指摘が印象的でした。
なお、実話を元にしたスパイにまつわる映画の紹介もあったので、興味が湧いたものは見てみようと思いました。
投稿元:
レビューを見る
読み物として面白い。
007やm:iにハマってた時期、
見えていないけれども、世の中はきっとエージェント(スパイの意)で溢れているんだ!
となんとなく思っていたが、
あながち間違いでもないかもしれない 笑
投稿元:
レビューを見る
池上氏にしては珍しく分厚い。よっぽどスパイが好きなんだなー、と微笑ましい。と同時に、やっぱり現代史を考え直すきっかけを与えてくれる。わかりやすい。
投稿元:
レビューを見る
昔(約30年前)はニュースで流れない世界の出来事は落合信彦から教わった。ボスニア・ヘルツェゴヴィナ紛争、アフリカ、イスラム世界の紛争などなど。
今はその役割を池上彰がやってくれているのだろう。メディアに出過ぎるきらいはあるが(笑)、それも広範な知識を誰にでも興味を持ってもらいたいという考えによるものだと思う。
本書はスパイというよりもCIAなどの諜報機関の実績をあげながら、世界史の闇の部分を分かり易く教えてくれる良作。
投稿元:
レビューを見る
スパイを切り口にした近代~現代史のおさらい本として面白く読めた。冷戦下の頃のCIAの行ったえげつない他国政権への干渉とか、中国の国家情報法というやばい仕組みで中国の諜報活動の36%がプロではなく一般の国民の行ったスパイ活動であるとか、オープンソースで情報分析をするベリングキャットという集団が登場するとか、飲み会で話したくなるようなネタが満載。帯の池上さんのポートレートが少し諜報部員風で微笑ましい。
投稿元:
レビューを見る
表紙のコスプレ(?)からして、半ばギャグに走っているかのような印象を受ける。冗談というワケではなかろうが、どちらかというと、軽めに、楽しく「スパイ」という存在を身近に感じてもらい、理解してもらおうという、NHK「週刊こどもニュース」のお父さん役に戻ったかのようなスタンスで書いているような内容。サクサクと読めて楽しい。
記述の大半が、先の大戦から冷戦時代のスパイ暗躍の黄金時代の事例紹介が多く(ゾルゲや、CIAのダレス長官等々)、かつて30年以上前に、落合信彦本で堪能した内容が盛りだくさん。そのあたりは懐かしく拝読した。
その後の時代、冷戦終了後は、アメリカと中東地域の確執の振り返りは興味深いが、アメリカが凝りもせず世界のあちこちにチョッカイを出しては失敗している事例が炙り出される。例えばビンラディン。
アフガニスタン紛争で反ソ連の抵抗勢力に武器と教育を授け、聖戦だと戦場へ駆り立てたその中に、後年同時多発テロでアメリカ本土を攻撃するアルカイーダの親玉となるビンラディンがいた。
イランのフセイン政権を倒した後、フセイン支持のバース党(アラブ復興社会党)を解散、追放した結果、党員だった警察官、軍の将校が武器を持って職場を離脱、その中からイスラム国(IS)が誕生することになる。
ビンラディン殺害に地元の医師がCIAに協力していた事実が知れると、現地で小児麻痺ワクチン接種をする医療機関関係者=CIAとみなされ、接種が進まず、パキスタンとアフガニスタンでは、今も小児麻痺に苦しむ子どもたちがいるという。著者も、こう記す。
「CIAの罪は大きいと言わざるを得ません。」
本書タイトルの通り、“世界史を変えた”ということだが、アメリカという思い上がり国家の存在が無かったら、あるいは余計なおせっかいをしてなければ、今の世界も違ったものになっていたのだろうなという思いは強い。
そして、昨今のロシア、ウクライナ戦争だ。
現在進行形の事案ゆえに、今の時点で、スパイの暗躍といった裏事情の開陳はさすがに、ない(サイバー戦が展開されているという記述はある)。が、アフガン侵攻の経緯をこんな事例を引いて紹介していることから、現状を推察することは可能だ。
当時、アメリカのカーター政権の国家安全保障問題担当特別補佐官だったブレジンスキーの証言だ。
「アフガニスタンへの反政府勢力への秘密の援助は、ソ連の軍事侵攻より半年も早い1979年7月に始まっていた」
「我々がソ連を軍事介入に追い込んだのではない。だが意図的に力を加え、ソ連がそう出てくる蓋然性を高めていったのだ」
アフガニスタンをウクライナに、ソ連をロシアに置き換えずとも、アメリカが今なにをしているか読めてしまわないだろうか。歴史に学べ、ではないが、当然、今も同じ事が繰り返されていると推測するのは、なんら難しいことではない。歴史は繰り返されるのだろう。
その他、昨今のサイバー空間での諜報活動、あるいは市民でも行なえるOSINT(Open-Source Intelligence)の可能性など、新たな世界も垣間見れて面白かった。
投稿元:
レビューを見る
池上さんのおかげで少しずつ歴史がわかるようになってきました。
知らない、何も思いつかないというところから、
ほかの本で読んだことがある、見たことがある、
という段階を少しずつ上がっています。
スパイというと、アニメや映画の世界の印象でしたが、
各国至る所に情報収集をする人たちがいて、
さらに情報収集だけではなく、
偽情報や政治工作、煽動することも任務なんですね。
最近は至る所に防犯カメラがあるし、
(それが抑止力になることも理解してます)
アプリや通信手段がたくさんあるし、
隠そうとすることは本当に困難なのかも、と思います。
誰がどこで見聞きしていたっておかしくない。
アメリカで一般人のやり取りまですべて収集していたという告発について本書に書かれていますが、ショックでも衝撃でもなく「そうだろうなあ」が私の感想でした。
見れるとわかっていて見ない手はないし、
一度見てしまったら、見ないという行為はどうしてもできないのではないかと思うんですよね。
ただ、膨大な情報の中からピックアップしたり、関連を確認することはどのぐらいの労力なのかな、と思います。
今はAIが発達しているから、機械に頼むのかもしれないですが。
プライバシーと国を危険から守ること、どちらと言われるとなんとも言えないし、監視社会で発言に気を付けなければという気持ちもあります。
世界中でたくさんの不満が爆発していて、
あちこちで人同士が殺し合って傷つけあっていて、
当時のスパイの人たちが今の時代を見たらどう思うんでしょうか。
皆さん自身の信念をもって、自国や世界を良くする、守るために活動していたのかもしれないですが。
なので、精神を病んだり気持ちがおかしくなって
離脱する人が一定数いるのもわかる気がします。
ブレたり迷ったら、たくさんの情報たちに吞み込まれそうだから。
なかでも、プーチンが憧れていたというゾルゲは、印象的でした。
人との交流も積極的に行い、人の懐に入り込んでいく。
政治中枢にも密通者がいると思うと、怖いですね。
まだまだ歴史を知りたい、そう思いました。
投稿元:
レビューを見る
CIA, KGB, MI6をコアにして、朝鮮のスパイ戦を表しています。
日本のスパイはいないのかと思ってしまいますよね。
投稿元:
レビューを見る
物語的に読めて、スパイって実在するんだーってワクワクしながら読める。
結構エグいことやってるし、ロシアとアメリカはずっとバチバチやってるし、最近は中国もやばい、とスパイを通して各国のパワーバランスも勉強できる。