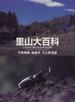- 現在お取り扱いが
できません - ほしい本に追加する
里山大百科 いちばん身近な自然の四季 みんなのレビュー
- 平野 伸明 (著), 新開 孝 (著), 大久保 茂徳 (著)
- 税込価格:5,170円(47pt)
- 出版社:TBSブリタニカ
- 発行年月:2000.4
- 発送可能日:購入できません
- 予約購入について
-
- 「予約購入する」をクリックすると予約が完了します。
- ご予約いただいた商品は発売日にダウンロード可能となります。
- ご購入金額は、発売日にお客様のクレジットカードにご請求されます。
- 商品の発売日は変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。
| 2 件中 1 件~ 2 件を表示 |
紙の本
懐かしさと新鮮な驚きの入り交じった豊潤な里山ワールド
2001/02/20 22:02
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:納高司良 - この投稿者のレビュー一覧を見る
昨今は里山ばやりであるが、本書はその里山の自然を、昆虫・鳥・小動物・植物・きのこ…といったオールスターな顔ぶれで紹介する決定版的写真集。
ページを繰るごとに、四季の移ろいをBGMにして、自然と人が巧みに調和した、美しい世界が展開していく。
大冊ではあるが、網羅的であるため、個別内容への切り込み、深みは十分とは言えない。しかし「里山ワールド」の全体像を描き出し、その魅力や大切さを伝えることには成功している。
なにげなく手にとって眺めているうちに、懐かしさと新鮮な驚きの入り交じった感覚に陥り、知らないうちにその世界に引き込まれている。そして、読み終える頃には「明日はきっと近くの野に出てみよう」という気分になっている自分に気づく、そんな一冊である。
紙の本
「里山」が死語になる前に。
2001/02/07 11:20
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:岡埜謙一 - この投稿者のレビュー一覧を見る
「里山」という言葉は昔からあったのだろうか? 手元にある古い辞書「三省堂国語辞典」には出ていない。広辞苑ではどうかと思ったが、本棚の前に本の山があり、その陰に隠れていて出すことができない。この言葉をよく目にするようになったのはここ数年のことではないだろうか。とくに、今森光彦さんの写真集「里山物語」(新潮社)が評判になって、それ以来「里山なんとか・・・」という本がちょくちょく書店に並ぶようになったのではなかろうか。それ以前は里山という言葉は聞いた覚えがない。
で、「里山」って何だ、ということになるが、とくに厳密な定義はないようだ。低い山あるいは丘陵、雑木林、谷津田、小川に水田、畑。これらの要素があれば、そこは里山だ。私はある地方都市(都市というほどの規模でもないが)出身だが、町中を少しはずれるとどこもそんな具合だった。つまり、どこの町にもある郊外の環境そのものだし、我々日本人にとってごくなじみ深いというか、あまりにも当たり前の風景でもある。東京近辺で言うなら、狭山丘陵や町田市、八王子市の郊外などがその典型だ。だが、その当たり前の存在が、段々と「以前はあった」「前はそうだったが」という言い方のほうがふさわしくなってきているのも事実だ。ゴルフ場の乱立や住宅地の開発、これらのおかげですっかり過去形になったり、土地はそのままでも農薬や河川改修なんかで生態系が変わってしまって形だけの里山が残っているところも少なくないだろう。日本のことだから、そのうち死語になる日が来るかもしれないなあ。そうした危惧があるからこその「里山ブーム」ではないだろうか。私の住む都下青梅市周辺でも徐々に里山が住宅地に姿を変えつつあり、本当にいまのうちにその姿を目に焼き付けておかなくちゃと感じている。
本書は3人の写真家による共著で、里山の自然を四季に分けて紹介した構成になっている。季節ごとの草木や昆虫、野鳥たちの生態と、里山で暮らす人の生活とを、約800点の写真と短い文章で美しく紹介している。また巻末の索引には、写真すべての撮影地が記載されているのが親切だ。中でも、野鳥や昆虫の生態を紹介した写真が見応えがある。大人のための里山図鑑というところか。価格は高いが、サイズが大きいだけに写真もインパクトがあるし、文章も「ひとつ、次の休みには近くの雑木林か谷津田にでも行ってみようか」と里山ウォッチングをそそるものがある。我が家の近くにはまだ里山の風情を残した雑木林や谷津田(谷地とも言っている)があるので、よく野鳥を見に行っている。四季それぞれに楽しめるが、いまの時期、秋から冬にかけてが一番おもしろい。木の葉が落ちて鳥も見つけやすいし、ときには美しいヤママユが拾えるし、うずたかく積もったクヌギの落ち葉を踏んで歩くだけでも楽しいのだ。本書の写真を見て、近くの里山に出かけてそうした楽しさを味わってもらえたらと思う。
著者略歴
平野 伸明(ひらの のぶあき);1959年、東京生まれ。山梨学院大学卒業。在学中から動物写真家を志す。主な著書に「チョウゲンボウ 優しき猛禽」(平凡社)など。写真集だけでなく、NKHの自然記録番組「生きもの地球紀行」の制作にも加わり、最近はハイビジョンカメラによる自然科学番組の制作にも力を入れている。
新開 孝(しんかい たかし);1958年、愛媛県生まれ。愛媛大学農学部で昆虫学を専攻。教育映画の演出助手を経てフリーの昆虫写真家として独立。主な著書は「ヤママユガ観察事典」(偕成社)など。1999年には、平野伸明氏らと「生きもの地球紀行」の「武蔵野台地の四季」を制作。
大久保 茂徳(おおくぼ しげのり);1957年、埼玉県生まれ。日本大学農獣医学部で農学を専攻。現在、私塾主宰のかたわら、園芸専門学校の講師。自治体主催の自然観察会の講師も務める。
| 2 件中 1 件~ 2 件を表示 |