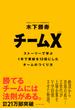0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
企業再建の実話が、詳細に紹介されていて、よかったです。現場で教訓になることが多く、参考になりそうです。
教育の大切さがよくわかる
2024/08/22 22:03
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:UMA1001 - この投稿者のレビュー一覧を見る
相反する2つの目標を同時に追わせると失敗する、片方が達成できれば満足してしまうから
きょうつうげんご、教育の大切さがよくわかる
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
同僚が、絶対読むようにというから仕方なく読み始めましたが、納得出来るところが本当にたくさんあり、なぜこんなに勧めるのか理由がわかりました。チームに必要なものは、指揮官&エース&教育係。たしかに…。
投稿元:
レビューを見る
日本中が木下さんの本を読んですごいすごい言ってるときに、いや業績どんどん下がってるよね?とおもっていたが、当著をもって改めて尊敬と畏敬の念を覚えた。
最初から最後の1ページまで無駄がなく、一気に読み切れる素晴らしい本であった。
◯強いチームに必要な5つの要素
・KPI
最重要。KPIを設定して、KPIをもとに運用し、KPIのPDCAを回して、正しいKPIにたどり着け。
KPIは数値にして見える化し、表にすることでとにかく日々数字を追う。複数のKPIを追う場合は相反してないものにする。
そして変更に次ぐ変更を自ら考えられる組織になるように導け。上層部に徐々に浸透させ、リーダーから施策を下ろすのではなく、数字をもとに日々改善できる組織風土を作っていけ。
・教育の仕組み
チームには指揮官とエース、教育係が必要。教育係がおろそかになることが多いが、拡大する場合には必須である。
教育係を設計するには、2人のトッププレイヤーが必要。2人入れば、どちらかを不断の決意で教育に専念させる。
教育係は他社を模倣せず、オリジナルの教育プログラムを作る。自社オリジナルの教育プログラムこそ、最大の強みになる。
・共通言語化(暗黙知の形式知化)
共通言語化によって暗黙知を形式知化させろ。※ファクトファインディングみたいな
社内オリジナル用語やキャッチーなフレーズを使うことで、意識統一や知見統一がしやすくなり、結果的に自社にあった文化を生み出せる。
共通言語化は、チームのスキルアップも促す。KPIや目標達成に必要な要素やスキルを共通言語化するため、皆そこに集中しやすくなる。
・風土
風土はリーダーがつくる。リーダーは他者への影響で選べ。熱狂しろ、圧倒的ポジティブに巻き込め。
数人だけが頑張るチームか、全員が頑張るチームか。全員が頑張るチームこそ、良い風土と呼べる。
・タスク管理(Do管理、進捗管理)
5つの要素を徹底しても達成に近づかない場合は、殆どの場合タスク管理に問題がある。
やるべきことをやりきれているかを追え。機会ロスがないか執着して見ろ。
戦略戦術の立案とメンバーのタスク管理はセットである。メンバーはタスクを自分ごと化出来ない場合が多く、漏れが発生する。従って、リーダーはメンバーのタスク管理することは当たり前である。
「メンバーはタスク漏れをする」ことは受け入れつつ、タスク漏れしないようにするたった1つの方法は、自分で戦術とタスクをセット導き出させること。「いつまでに、これを、このくらいやる」と上から言われてもやらないので、自分から出させるのが理想ではある。
◯新しさを生み出しにくくなる環境と脱出
・既存がマニュアル化仕組み化が整っていると、新しいコンテンツを生み出す文化・人材・スキルが失われていく。お手本依存症、フォーマット過信病を生む
・新しさを生み出すのは若手。新戦力の芽吹きを見つけたら、既存に潰されないように隔離して先輩に邪魔されないチームをつくる
・隔離すると主流から外された、、、と本人たちは思うかもしれないので��アする
◯広告について
・広告には目立つ広告と馴染む広告がある
・フェイスブックのようにじっくり見る面では、なじむように。ニュースメディアやインスタのような流し見中心メディアでは目立つようにつくる。
・市場が成長してるときやクリエイティブが枯れてないときは、即成果がでるものを模倣したほうがよい。しかし、天井には必ずぶちあたるのでコンテンツは常に発掘しつづけれないといけない。
◯クリエイティブに必要なこと
【3段階分析の実行】
・最も大切なのは、消費者目線である
・消費者目線になるのは、消費者になりきり自分のインサイトを3回深ぼる「3段階分析」が良い。このインサイト分析は研修の頃から叩き込める
例)Twitter広告
1.なぜ自分は数多くのツイートの中で、そのツイートに目をとどめたか
2.なぜ自分は目をとどめただけでなく、文章を読んだか
3.なぜ自分は文章を読んだだけでなく、クリックしようとしたのか
・当たっている広告やクリエイティブ、事業だけを分析するのではなく、自分目線で見てくことで「当たっている理由を自分ごととして考える」ことが徹底されていく
【フィールド情報の獲得】
・皆が集める情報は基本的に「オリエン情報※北の達人言語」であり、出来上がった商品や当たりクリエイティブから得られる知見。それでは本質にたどり着かない
・消費者目線(ユーザー感情)を手に入れるには「フィールド情報※北の達人言語」が必要。新商品や新サービスをつくるには欠かせない
・実際に圧倒的量の体験を得る、ユーザーに直接インタビューするなど、凝縮されていない情報を手に入れると、自分にとっては新しい価値観=ユーザー目線を発掘できる
新しい事業やコンテンツ作りする際に必要な「消費者目線」は、この2つのHowToを使うことで手に入れることができる。
◯LPの種類とエモーションリレー
・北の達人では、LPをHLP(販売LP)とBLP(ブリッジLP)に分類している※昨今LPは2重構造になっていることがある
・HLPは商品購入機能があるページで、BLPはHLPの前に表示されるページ
・BLPで記事やアンケートで啓蒙させたり、興味をもたせる。一般的に、お客様は商品を購入するまでに広告→BLP→HLPという手順を踏む
・「エモーションリレー※北の達人言語」を念頭において見ないと、広告→BLP→HLPの矛盾に気づけない。違和感なく続けているかをチェックしなければ離脱を生む
◯気をつけたい横展開漏れ。形式知化
・各チームに分断すると、暗黙知が発生し、形式知化されない
・形式知化は、全体を見れる人間が必要不可欠。当人たちでは気づきにくい
・横展開すべき要素、日頃断絶されやすい情報などがわかれば、後はそれらをまとめてマニュアル化して、みんなで横展開できるようにする
・暗黙知を形式知化する、効果的かつ手っ取り早い方法は「共通言語化」。新しくキャッチーな言葉を作り出してしまえ
◯思考アルゴリズムが強いやつこそ優秀
A.「あとでやろう」「いつかやろう」ではなく、その場ですぐにやる。あるいは、どうしてもすぐにやれない場合にはいつやるかをその場で決める※ピッパの法則
B.目標達成のために120%達成する予材管理をする。プランBを必ずもっている。「作戦をAをやります!」ではなくて、「目標達成します。そのために作戦Aでいきますが、作戦Bもっています」と当たり前に考えられる
C.多くの人は「昨日のしごとの続きをやる」。出来る人は、毎日何かしら前進させたり変化をさせる
思考アルゴリズムとは、「思考の手順」のことであり、もっと簡単な表現で言うと「考え方のクセ」。仕事の成果やスピードを大きく左右する。
投稿元:
レビューを見る
著者木下さんの体験がストーリーでそのまま読めるので自身もその会社にいて考えているような感覚になる。チーム作りについて、何が必要かのノウハウ→成功した具体例の一般的な本と違い、1つの大きな課題について試行錯誤しながらも失敗し、成功しているストーリーなので自身を投影しながら考えながら読める本。
営業工数から見た逆算、仕組みで人に気づきを与える、組織病にかからない意識、リーダーとしての役割を実践する。
投稿元:
レビューを見る
赤裸々に失敗したことも書かれているのが良かった。
業界が異なることで全く参考にならない…なんてことはなく、少なくともKPIの設定や問題に気づく能力、若手の育成や社内風土の情勢など、現在あらゆる企業で課題となっていることが書かれている。
何を学びとするか…も、この本を手に取った人、リーダーの資質にあると思う。
投稿元:
レビューを見る
「CPOを下げながら、集客人数を最大化させるKPI設定」→「集客人数成果=上限CPO以内人数-上限CPO以上人数」
ファンダメンタルズマーケティング=商品そのものやユーザーのペルソナ、インサイトを分析し、コミュニケーションを設計すること
テクニカルマーケティング=クリック率、遷移率、購入率、キーワードなどのデータから顧客とのコミュニケーションを設計すること。
投稿元:
レビューを見る
赤裸々に、奮闘した記録が書かれており、迫力があり面白かった
KPIの道具としての活用方法、成功事例が記載されています、KPIは一要素でしかなく、文化、共通言語化などを行うことが重要だと認識しました。
とても躍動感があり、羨ましいと思いました。困難、抵抗勢力はあるかと思いますが、自組織でも取り入れたいと思いました。
投稿元:
レビューを見る
同じ業界に関する本ということもあり、自分自身共感できるところが多かった。
今組織が抱えている課題と似ている部分も多かった。特に今までのあり方、今までの進め方でうまくいかさるなるというような目の前にある課題に対しては、自分の中でも理解が進んだものもあると思う。
大きな規模のことをやろうとすると自分1人ではどうしようもないことが多いと思うので、チームや組織がいかに上手く回るようになるかは考えていこうと思った。
投稿元:
レビューを見る
KPIの考え方
暗黙知を共通言語にするという考え方
が非常に参考になる
PIVOTもしくはREHAQのYouTubeを見れば内容は読まなくてもよくわかる。
投稿元:
レビューを見る
感想
チームが上手く回らない時に読むべき本、
デジマの話もあり少しイメージしづらいことはあるが、チーム達成には根本的に読むべき
スキル 思考アルゴリズム(考え方のクセ)
毎回必ず達成できる人は施策の確率を合計100%にして、運頼みや他責などを無くす
リーダーがチームに勝たせるために前線で思考と挑戦をやめなければついてきてくれる
投稿元:
レビューを見る
ミッション、ビジョン、バリューの作り方
目標とは成長のためのツールだ
現状の延長線上で頑張っている限り成長はない
背伸びしたりジャンプしたりしてようやく手の届くところに目標を、おかなければ成長ツールとして機能しない
メンバーに目標と道筋を見せ、結果を出して辻褄合わせをするのがリーダーの仕事
事業を成功させるには正しい経営戦略を作ること
経営戦略を実現できる組織を作ること
企業組織病
職務定義の刷り込み誤認
お手本依存症
職務の矯小化現状
数字万能病
フォーマット過信病
必要なのは2人のトッププレイヤー
1人はプレイヤーとして目の前の成果を上げる
もう1人は教育担当として新人を育てる
チームを作る上で重要なポイント
KPI
教育の仕組み
共通言語化
タスク管理
風土
投稿元:
レビューを見る
チームを変革するためのエッセンスが実例を用いて書かれており、読み進めると「チームで目標を達成しよう!」と、読んでいてやる気が出てくる本だった。
目標達成に向けて、「理論上可能な作戦をいかに現実に落とし込んでいくかが仕事」というメッセージは新たな視点で、自分自身が実施してメンバーに伝えようと感じた。
チームビジョンの再作成、目標達成の道筋・解決するための複数の解決方法を作り、チームでの目標を達成していく。
投稿元:
レビューを見る
AIにお任せではなく、意志と意図を持って運用すること、また目標達成に向けて何をKPIとして設定して管理するかをまだまだ考えられると気付かされた。
投稿元:
レビューを見る
配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。
https://www.cku.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=10275485